適応障害とは?症状・原因・治療法や回復までの流れを解説
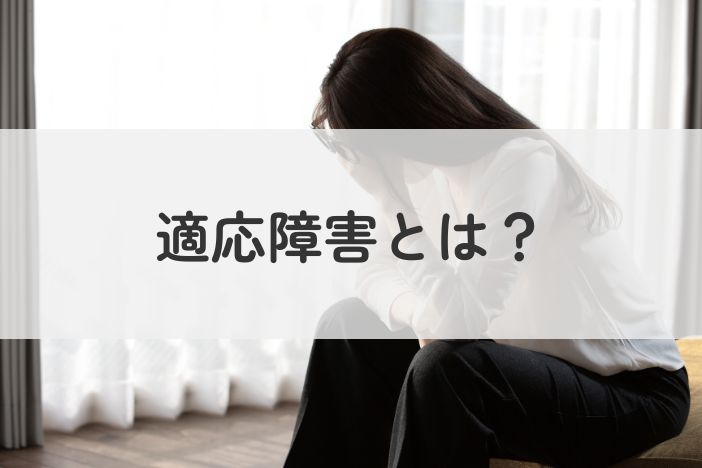
- 適応障害とは
- 適応障害とうつ病の違い
- 適応障害の原因
- 仕事・職場の悩み
- 家庭・プライベートの変化
- 災害や病気などの予期せぬ出来事
- 適応障害の代表的な症状
- 身体に現れるサイン
- 心に現れるサイン
- 適応障害になりやすい方の特徴
- 適応障害は治る?回復までの目安
- 治療の基本は「ストレスから離れること」
- その他の治療法
- 認知行動療法(CTB)
- 薬物療法
- 適応障害になったら仕事はどうする?
- 上司の相談し、業務調整をしてもらう
- 診断書があれば休職は可能
- 適応障害の方が利用できる支援制度
- 自立支援医療制度(精神通院医療)
- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
- 適応障害の方が相談できる支援先
- お住まいの役所の障害窓口
- 精神保健福祉センター
- 就職・復職に不安があるなら就労移行支援で相談も
- manabyの就労移行支援について
- まずは無理をせず、ストレス要因から離れて過ごすことが大切
最近、気分が沈んで仕事に行くのがつらい、眠れない、食欲がない…。
そんな不調が続いて病院を受診した結果、「適応障害」と診断される方は少なくありません。
でも、「適応障害ってどういう状態?」「これからどうすればいいの?」と、戸惑いや不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、適応障害とはどんなものか、うつ病との違い、治療の進め方や仕事との向き合い方、利用できる支援制度・相談先について紹介します。
適応障害とは
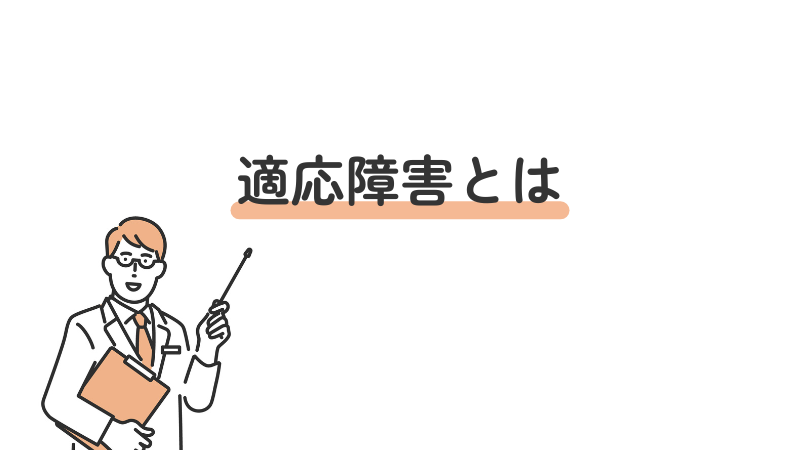
適応障害は、強いストレスがきっかけで心や体に不調があらわれる状態のことです。
具体的には、気分の落ち込み、不安、イライラ、集中できない、眠れない、食欲がないといった変化が現れ、仕事や生活環境の変化やプライベートの悩みが日常生活に影響が出ることもあります。
適応障害は、明確なストレスがあるときに、それに対して心や体が強く反応して症状が出ることが特徴です。
通常はストレスが軽減されると症状も落ち着いていきますが、6か月以上たっても改善が見られない場合は、うつ病や不安障害など別の診断が検討されたり、適応障害が長引く「慢性化」と判断されることもあります。
参考:厚生労働省(「こころの耳」)「適応障害」
適応障害とうつ病の違い
| 比較項目 | 適応障害 | うつ病 |
|---|---|---|
| 原因 | はっきりしたストレスがある(仕事・学校・人間関係など) | 原因がはっきりしないことがある |
| 症状の出方 | ストレスのあと比較的すぐに出る | ゆっくりと悪化することが多い |
| 期間 | 一時的で、ストレスがなくなるとよくなることが多い | 症状が長く続くことが多い |
| 治療方法 | ストレスの原因から離れる・自分を知り、ストレス耐性を高める | 薬とカウンセリングの組み合わせ |
適応障害と似た症状が見られる心の病気として、うつ病が挙げられます。
どちらも気分の落ち込みや意欲の低下といった点は共通していますが、原因や症状の出方、続く期間、治療法に違いがあります
適応障害は、仕事や人間関係などのはっきりとしたストレスがきっかけになり、比較的早く症状が現れます。ストレスから離れることで症状が落ち着くことが多く、治療では環境調整やカウンセリングが重視されます。症状が重い場合は薬物療法も一緒に行われる場合があります。
一方うつ病は、明確な原因がない場合もあり、少しずつ悪化して長引くことが多いのが特徴です。適応障害とは異なり、薬物療法が主軸となって治療が行われていきます。
また、診断基準にも違いがあります。適応障害は、明確なストレスに反応して不調が出ており、多くは6か月以内に回復に向かうとされていますが、うつ病は、気分の落ち込みや楽しさを感じない状態が2週間以上ほぼ毎日続いているかどうかなど、より詳細な基準で診断されます。
参考:厚生労働省(「こころの耳」)「適応障害」、「 うつ病の主な症状と原因」
適応障害の原因
適応障害は、環境の変化や人間関係の悩みなど、強いストレスがきっかけで起こります。ここでは、実際によく見られるストレスの原因について、解説します。
仕事・職場の悩み
適応障害の原因として、仕事や人間関係の悩みが挙げられます。
特に社会人として働くなかでは、「がんばりすぎること」や「自分の気持ちを後回しにしてしまうこと」が積み重なり、知らないうちに心と体に負担がかかっていることがあります。
- 業務量が多く、余裕がない
- 職場での評価や納期に強いプレッシャーを感じている
- 上司や同僚との関係がうまくいかず、常に気を張っている
- 新しい職場や役職に早く慣れようと、無理をしてがんばりすぎている
- 職場の雰囲気や価値観が自分と合わないと感じている
こうしたストレスが積み重なると、眠れなくなる・気分が落ち込む・朝起きるのがつらいなど、日常生活にも影響が出てくることがあります。
家庭・プライベートの変化
仕事だけでなく、引っ越しや転職、家族構成の変化などのプライベートの変化でも、適応障害のきっかけになることがあります。
例えば、結婚や離婚、出産、子どもの独立など、人生の節目となる出来事は、期待や責任が増す一方で、日常のリズムや人との関わりが大きく変わるため、強いストレスとなって心身に不調が現れることがあります。
特に、こうした変化の中で親しい人との関係に問題が生じた場合には、つらさを一人で抱え込みやすく、周囲に相談しづらいという傾向もあり、より深刻化しやすくなることがあります。
災害や病気などの予期せぬ出来事
自然災害や事故、病気など、突然の出来事も心に大きなショックを与え、適応障害に繋がることがあります。
急な変化にどう対応していいか分からず、不安や混乱が大きくなることで、心のバランスを崩しやすくなるためです。
例えば、災害によって住まいを失ったり、家族の安否がわからず不安が続く場合や、病気やケガによってこれまでの生活が送れなくなったときなどは、日常の大きな喪失感や、この先どうなるかわからない不安にさらされることで、心や体に不調があらわれることがあります。
適応障害の代表的な症状
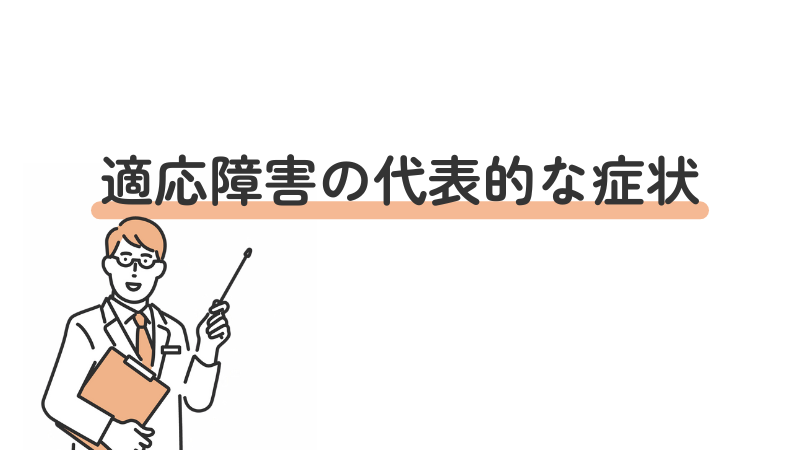
適応障害は、ストレスにうまく対応できないことで心と身体の両方に不調が現れることがあります。ここでは、よく見られる症状をご紹介します。
身体に現れるサイン
- 不眠、食欲不振
- 全身のだるさ、疲れやすさ
- 頭痛、肩こり、腹痛
- 動悸、息苦しさ(過呼吸)
- めまい、吐き気
これらの身体症状は、適応障害によるストレス反応の一部として現れることがあります。
中でも、動悸や息苦しさは、不安や緊張が高まったときに出やすく、例えば「明日の仕事を考えるだけで胸が苦しくなる」「満員電車で急に息がしづらくなる」といった場面で感じる方もいます。
放っておくと、パニックのような症状に発展することもあるため注意が必要です。
心に現れるサイン
- 不安感、焦り、恐怖感
- 落ち込み、気分の沈み
- イライラ、怒りっぽさ
- 神経が過敏になる
- 感情の波が大きくなる
このような感情の変化が続くと、日常の行動にも影響が現れることがあります。
例えば、不安や緊張が強くなると、人との関わりに敏感になったり、怒りっぽくなったり、飲みすぎや暴食、無謀な行動(けんかや危険運転など)に出てしまうこともことがあります。
その他にも遅刻や欠勤が増える・外出が億劫になる・人と会うのが辛くなるなど、行動の変化が見られるようになります。
そうした状態が続くと、人間関係のトラブルや孤立を招き、生活に支障をきたしてしまいます。
適応障害になりやすい方の特徴
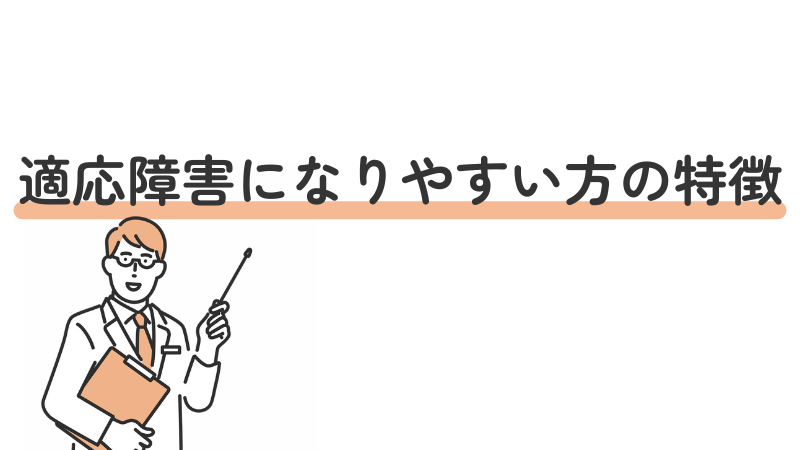
適応障害は誰にでも起こりうる心の病気です。
ですが、以下のような性格や傾向を持つ方は、ストレスを抱え込みやすく、適応障害になりやすいとされています。
- 真面目で責任感が強い
- 几帳面で完璧主義
- 他人の目や評価を気にしやすい
- 頼まれると断れない
- 心配性で傷つきやすい
- 気分の切り替えが苦手
- 人に頼るのが苦手で、何でも自分で抱え込む
- 自分よりも他人を優先しがち
こうした性格の方は、頑張りすぎてしまったり、自分の限界に気づきにくく、その結果、心や身体に不調が出ることがあります。
ただし、これらの特徴があるからといって、必ずしも適応障害になるわけではありません。
適応障害は治る?回復までの目安
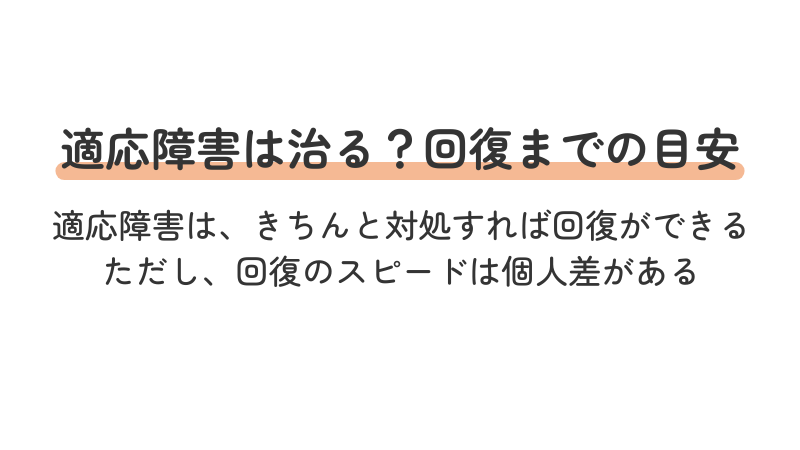
適応障害は、きちんと対処すれば回復ができる病気です。
一時的なものが多く、ストレスの原因から離れたり、必要なサポートを受けたりすることで、少しずつ回復に向うことができます。
回復までの期間は人によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月ほどでよくなるケースが多いです。
ただし、回復のスピードは個人差があり、ストレスの強さや性格などによって変わってきます。
治療の基本は「ストレスから離れること」
適応障害の治療で最も大切なのは、ストレスの原因から距離をとることです。
心や身体への負担を減らすためには、まず無理をせず、しっかりと休むことが大切です。
- 職場や家庭での負担を一時的に減らす
- 思い切って休職・休学を選ぶ
- 自分が落ち着ける環境で過ごす
また、趣味に集中する・自然の中で過ごす・軽く体を動かすなど、心がほっとできる時間を意識してつくることも回復に繋がります。
ストレスから物理的に距離をとることに加えて、「考えすぎない」「抱え込みすぎない」ようにすることも大切です。
その他の治療法
適応障害の治療には、状況に応じて、ストレスから離れる以外にも方法があります。
認知行動療法(CTB)
ストレスを感じやすい方の中には、「自分が悪い」とすぐに思ってしまったり、「完璧にやらなければ」と考えがちになるなど、思考のクセがあることがあります。
認知行動療法では、そうした思考の傾向に気づき、自分の思考のクセを見つめ直すことができます。
物事の捉え方を柔軟にしていくことで、考え方の幅が広がり、ストレスを受けにくくなるようにトレーニングしていきます。
参考:厚生労働省(「こころの耳」)「認知行動療法」
薬物療法
適応障害の症状に応じて、お薬を使うこともあります。
- 不安が強い時 → 抗不安薬
- 寝つきが悪い・眠れない時 → 睡眠薬
- 気分の落ち込みが続く時 → 抗うつ薬
ただし、薬はあくまで一時的に症状をやわらげるためのものであり、適応障害では根本的な解決にならないこともあります。
そのため、使用する場合は医師と相談しながら、自分に合った形で取り入れることが大切です。
適応障害になったら仕事はどうする?
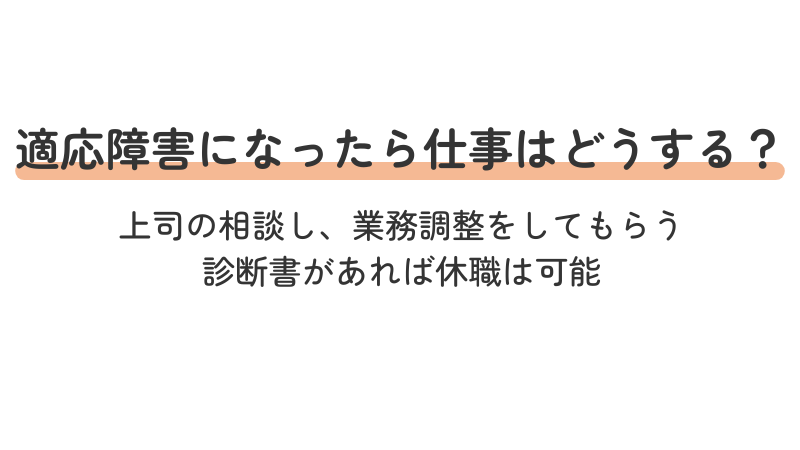
適応障害と診断された時、仕事を続けるべきか、しばらく休むべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、負担を減らしながら働くための具体的な手段を紹介します。
上司の相談し、業務調整をしてもらう
適応障害の症状があると、これまで通りの働き方が辛く感じることがあります。
そんな時は、できるだけ早い段階で上司に相談し、業務内容や働き方の調整をお願いすることが大切です。
「今どんなことがつらいのか」「どんな働き方なら無理なく続けられそうか」など、話せる範囲で伝えてみましょう。
障害名や診断内容を無理に伝える必要はありません。
自分が困っていることや、配慮してほしいことを少しずつ共有し、上司と一緒に負担を減らす方法を考えることで、ストレスが軽くなり、悪化を防げる可能性もあります。
診断書があれば休職は可能
適応障害と診断された場合は、医師の診断書があれば休職することができます。
休職の期間や復職のタイミングは医師と相談しながら、決めていくのが安心です。
また、職場によっては、少しずつ仕事に戻れるように段階的な復帰プラン(リワーク制度など)が用意されていることもあります。
こうした制度を活用することで、無理のないペースで仕事に戻りやすくなります。
適応障害の方が利用できる支援制度
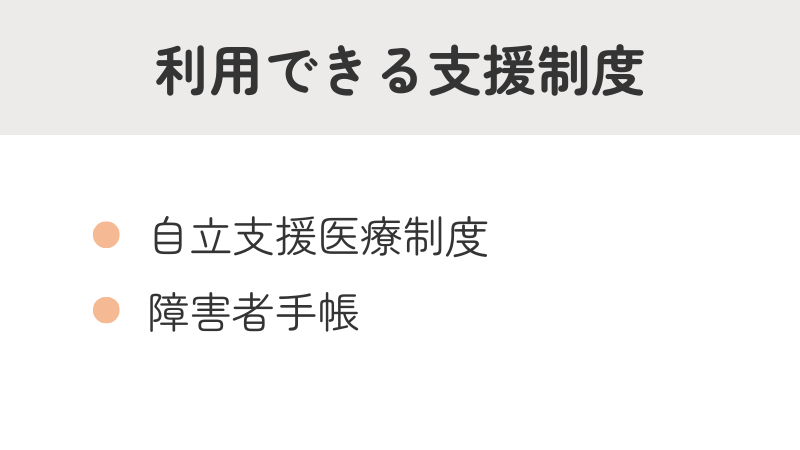
適応障害と診断された方は、医療費の負担を軽くしたり、生活や就労の支援を受けられる制度を利用できる場合があります。
自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療制度は、精神的な不調で通院治療が必要な方が、安心して医療を受けられるようにするための制度です。この制度を利用すると、通常3割の自己負担が原則1割まで軽くなり、通院やお薬にかかる費用を抑えることができます。申請は、市区町村の窓口で行います。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
「症状が6か月以上続いている」「日常生活に重大な支障をきたしている」など症状の程度によっては、障害者手帳を取得できる場合があります。この手帳があると、公共交通機関の割引、税金の控除など、さまざまなサポートが受けられます。申請は市区町村の障害福祉窓口で行い、交付までに数週間から数か月かかることもあります。
これらの制度を利用することで、医療や生活にかかる負担を少しでも軽くすることができ、安心して治療や回復に取り組める環境が整いやすくなります。手続きの内容や受けられる支援は地域によって異なるため、お住まいの自治体に事前に確認しておくと安心です。
適応障害の方が相談できる支援先
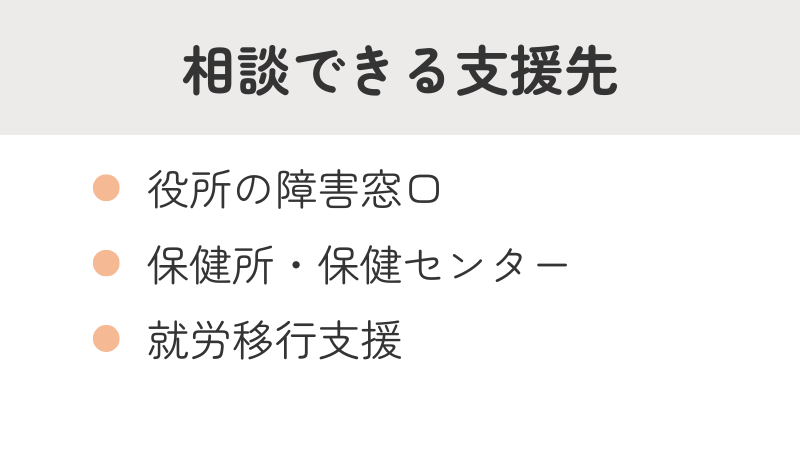
適応障害の方が相談できる代表的な支援先を紹介します。
お住まいの役所の障害窓口
市区町村にある障害福祉の窓口は、適応障害のある方やご家族が無料で利用できる、身近な相談先のひとつです。
日常生活の不安や困りごとについて話すことができ、福祉サービスの利用方法や制度の申請について相談できます。
- 適応障害に関する基本的な説明
- 診断や治療を行っている医療機関の紹介
- 利用できる福祉サービスの案内
- 障害者手帳の申請について
- 各種支援制度や手続きの流れに関する相談
どの制度を利用できるのか迷う時も、まずは市区町村にある障害福祉の窓口で相談してみるといいでしょう。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターでも、適応障害に関する相談が可能です。
地域によっては、臨床心理士や公認心理師、精神保健福祉士などの専門職が在籍しており、心のケアや生活の悩みを一緒に整理しながら、必要な支援先へ繋げてくれます。
診断を受けている方だけでなく、これから受診を検討している方やご家族も対象です。
医療機関の案内や地域の福祉サービスの紹介など、多方面からのサポートが受けられます。
就職・復職に不安があるなら就労移行支援で相談も
適応障害のある方の中には、「職場に戻れるか不安」「これから働けるか心配」と感じている方も多くいらっしゃいます。そんなときに活用できるのが、就労移行支援というサービスです。
就労移行支援では、働くための準備や生活リズムの整え方、ストレスとの付き合い方など、日常生活全体をサポートしてもらえます。ビジネスマナーやパソコンの使い方など、実践的なスキルも身につけながら、自分に合った働き方を探していくことができます。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manaby(マナビー)では、適応障害をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方が、自分らしい働き方を見つけるための訓練を行っています。
気分の波や体調の変化に不安を感じている方でも、1人ひとりの状態やペースに合わせた「個別支援」を大切にしており、「どんな働き方が自分に合っているか」を一緒に考えていくことを重視しています。
例えば、以下のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「生活リズムを整えたい」「働けるかどうか自信がない」「自分に合った働き方を見つけたい」など、1人ひとりの悩みに寄り添いながら支援を行っています。
まずは、相談だけでも大丈夫です。「一歩踏み出してみようかな」と感じたときは、お気軽にお問い合わせください。
まずは無理をせず、ストレス要因から離れて過ごすことが大切
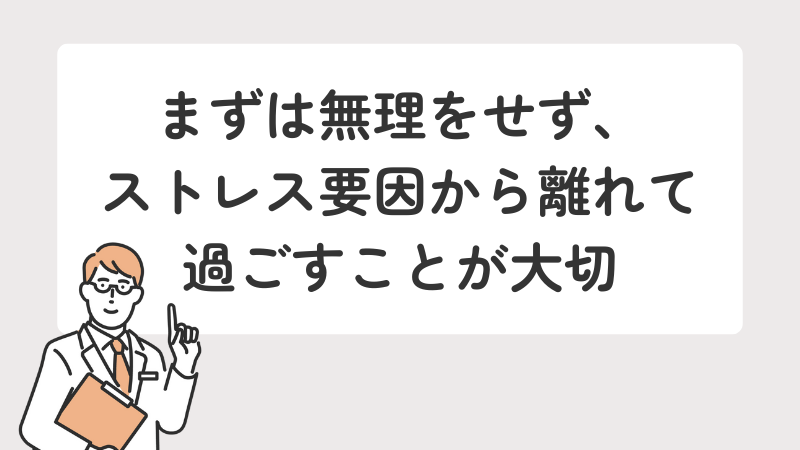
適応障害の回復には、無理をせず、ストレスのもとから一時的にでも離れることがとても大切です。ストレスが原因となって起こる症状が多いため、まずは心と体をゆっくり休ませる時間を持つことが、回復への第一歩になります。
例えば、職場や学校から少し離れてみることや、日常のプレッシャーから解放される環境をつくることが効果的です。この期間は、できるだけリラックスできる空間で、自分の好きなことや落ち着ける時間を大切にして過ごしてみてください。







