ADHDの仕事のミス対策!今日からできる対策やコツとは?
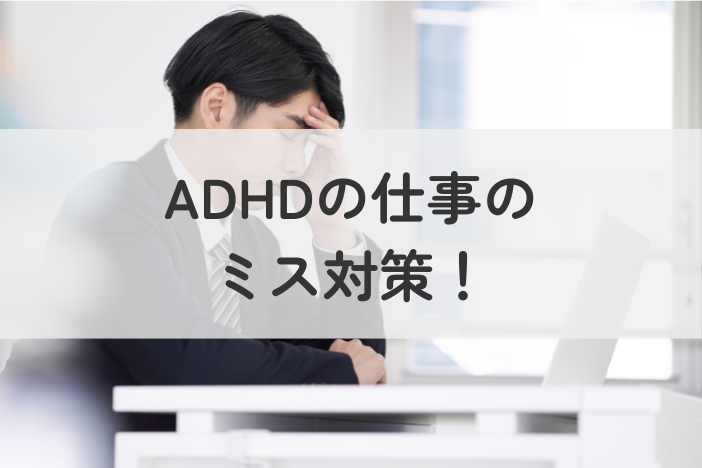
- 今日からできる!ADHD(注意欠如・多動症)の方におすすめの仕事ミス対策
- スケジュールやタスク管理の対策とコツ
- 書類や業務のケアレスミスを防ぐ対策とコツ
- 遅刻を防ぐための対策とコツ
- ADHD(注意欠如・多動症)とは?
- なぜミスが起こりやすいのか?ADHD(注意欠如・多動症)の特性を知ろう
- 「もしかしてADHD(注意欠如・多動症)かも?」と感じたら
- ADHD(注意欠如・多動症)の相談先
- ADHD(注意欠如・多動症)に対応している病院を見分けるポイント
- ADHD(注意欠如・多動症)の診断の流れ
- ADHD(注意欠如・多動症)による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
- 職場の相談先を活用する
- 公的な支援機関を利用する
- 就労移行支援ってどんな所?
- 就労移行支援manabyについて
- ADHD(注意欠如・多動症)の仕事におけるミスは「工夫」でも改善できます
- 今日から取り入れられる対策
- 相談できる主な窓口
仕事でミスが続くと、「また怒られるかも…」「自分には向いていないのかも」と不安になってしまいますよね。特にADHD(注意欠如・多動症)の特性がある方は、「うっかり忘れ」や「つい先延ばしにしてしまう」といったミスが重なりやすく、仕事の中で困りごとを感じやすい傾向があります。
ですが、ADHD(注意欠如・多動症)の特性に合った「ミス対策」や「環境の工夫」を取り入れることで、仕事でのミスはぐっと減らすことができます。
この記事では、ADHD(注意欠如・多動症)の方に向けて、今日からすぐに実践できる仕事のミス対策をわかりやすくご紹介します。
この記事のまとめ
-
●
ADHD(注意欠如・多動症)の特性とミスの関係とは?
「うっかり忘れ」「先延ばし」などの困りごとは脳の特性が関係している -
●
今日からできる!仕事のミス対策の工夫
タスクの見える化・定位置管理・スケジュールの逆算などで改善可能
今日からできる!ADHD(注意欠如・多動症)の方におすすめの仕事ミス対策
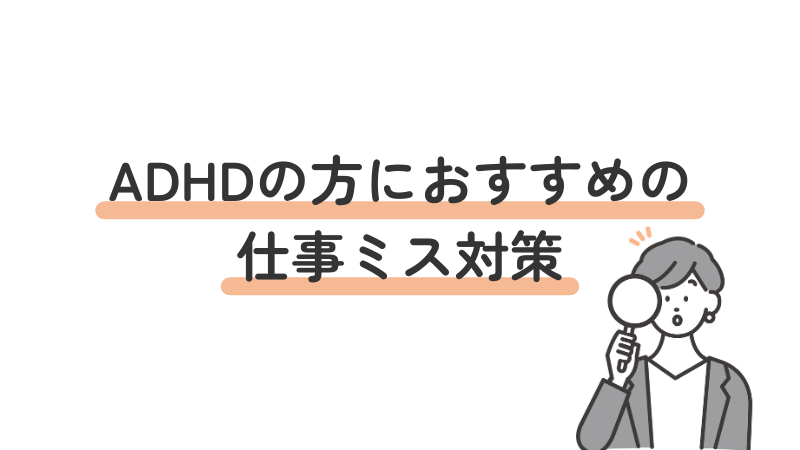
ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある方にとって、忘れ物や失くし物は日常的によく起こることです。例えば「カバンに入れたと思っていたのに、実際には入っていなかった」「どこに置いたか思い出せない」などのケアレスミスが重なってしまうことがあります。
そんな時に役立つのが、「持ち物のチェックリスト」や「置き場所を決める習慣」です。
忘れ物や失くし物を防ぐための具体的な対策を表にまとめました。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 持ち物のチェックリスト化 | 通勤カバンの中身をリストにして玄関に貼っておく | 出発前の確認漏れを防げる |
| 定位置のルールを決める | 鍵や社員証、印鑑などを毎回同じ場所に置くようにする | 探し物の時間が減り、なくすリスクも下がる |
| リマインダーを活用する | スマホやPCで通知を設定する | 忘れそうな用事や持ち物を思い出せる |
| 紛失防止グッズの活用 | AirTagなどの追跡タグを小物につける | 万が一失くしても見つけやすくなる |
| スペア(予備)を準備する | 家や職場に予備の印鑑や文房具を用意しておく | うっかり忘れても業務が止まらない |
大切なのは、「忘れないように頑張る」のではなく、「忘れても困らないように準備しておく」ことがポイントです。
スケジュールやタスク管理の対策とコツ
「あとでやろうと思っていたことをすっかり忘れていた」、「やることが多すぎて、どれから手をつけたらいいか分からない」と感じたことはありませんか?
ADHD(注意欠如・多動症)の特性がある方は、目の前のことに強く集中してしまうあまり、他の予定やタスクを忘れやすい傾向があります。そんな時には、「覚えておこう」とするのではなく、「一度、頭の外に出しておく」ことが効果的です。
以下に、スケジュールやタスクを管理するための具体的な対策をまとめました。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| カレンダー・手帳・アプリで見える化 | ・予定やタスクをカレンダーやアプリに入力し、一覧で確認する・朝に1日の予定を見直す | 抜けや漏れに気づきやすくなり、優先順位が立てやすくなる |
| 具体的にメモする | ・「14時に○○さんへ書類提出」など、時間や内容を明確に記録する・タスクを小さく分けて書く | 取りかかるハードルが下がり、先延ばしや忘れを防ぎやすくなる |
| 通知やアラームを活用する | ・予定の直前にアラームを設定する・1つの予定に複数回通知を入れる | 忘れていてもアラームで思い出せるようになり、うっかりミスが減る |
書類や業務のケアレスミスを防ぐ対策とコツ
「言われていたのに対応できていなかった」「提出期限を忘れていた」といった報告や連絡、書類提出の漏れが続くと、自信をなくしたり、職場での人間関係にも影響が出てしまうことがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある方は、集中力に波があったり、タスクの優先順位をつけるのが苦手なことから、重要な作業をうっかり見落としてしまうことが少なくありません。
ですが、ちょっとした工夫を取り入れることで、こうした「うっかりミス」を防ぐことができます。以下に、書類業務や確認作業における見落としを減らすための対策をまとめました。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
| タスクの分解 | 作業を工程ごとに細かく区切る | 作業の流れが明確になり、複雑な業務でも抜けが起きにくくなる |
| チェックリストの作成 | 書類作成や確認作業ごとに、手順や確認項目をリスト化する | 必要な手順を「見える化」でき、確認ミスを防ぎやすくなる |
| ダブルチェックを習慣化 | 提出前に自分で再確認し、他の人にも確認してもらう | 客観的な視点が加わることで、見落としのリスクを減らせる |
| テンプレートを活用 | 定型的な書類や作業は、毎回同じフォーマットを使う | 作業の一貫性が保たれ、抜けや漏れが起きにくくなる |
| 環境の整理整頓 | デスクやパソコン内のフォルダを必要なものだけに整える | 注意散漫を防ぎ、必要なものをすぐに見つけることができる |
遅刻を防ぐための対策とコツ
「朝が苦手」「準備していたらいつの間にか時間が過ぎていた」など、遅刻や予定遅れに悩む方も多いのではないでしょうか。ADHD(注意欠如・多動症)の方は「時間の流れを把握する力」が弱い傾向があり、時間感覚のズレから遅刻に繋がることがあります。
以下に、「時間を把握する」ための対策をまとめました。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 自分の準備にかかる時間を知る | ・身支度や朝食など、日々の所要時間を測ってみる ・出発時間から逆算して起床 ・準備時間を決める | 時間の見積もりが正確になり、余裕のある行動がとりやすくなる |
| 前もって準備をする | ・服やカバン、持ち物を前日の夜にそろえる ・乗る電車や道順を事前に調べておく | 朝の慌ただしさを減らし、忘れ物やバタつきによる遅刻を防ぎやすくなる |
| 早めに到着するスケジュールを組む | ・出発時間を10〜15分早めて設定する ・準備や出発タイミングに複数アラームを設定する | 予想外のトラブル(忘れ物・電車の遅れなど)にも柔軟に対応できるようになる |
ADHD(注意欠如・多動症)とは?
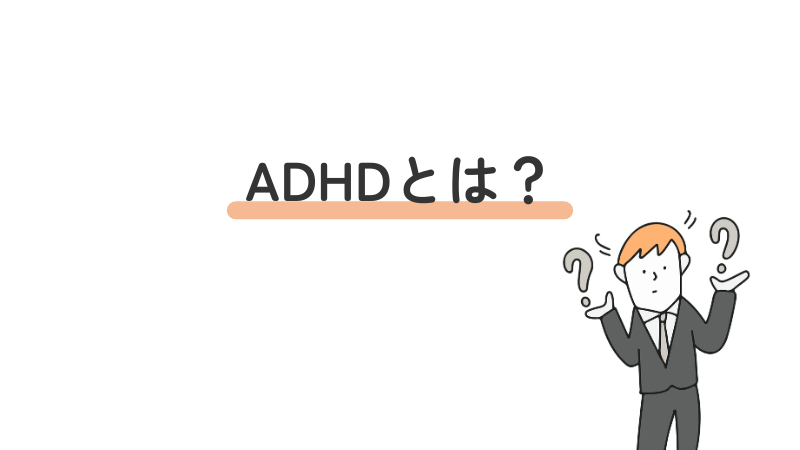
ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障害のひとつで、主に以下の3つの特性が見られます。
- 不注意:注意が散漫になりやすい、集中が続かない、忘れ物が多いなど
- 多動性:落ち着きがない、体がじっとしていられない、せかせかしてしまうなど
- 衝動性:思ったことをすぐ口にしてしまう、順番を待つことが苦手など
子供の頃には気づかず、大人になってから「仕事でミスが多い」「人との約束や予定を忘れてしまう」などの困りごとが積み重なり、気づく場合もあります。
なぜミスが起こりやすいのか?ADHD(注意欠如・多動症)の特性を知ろう
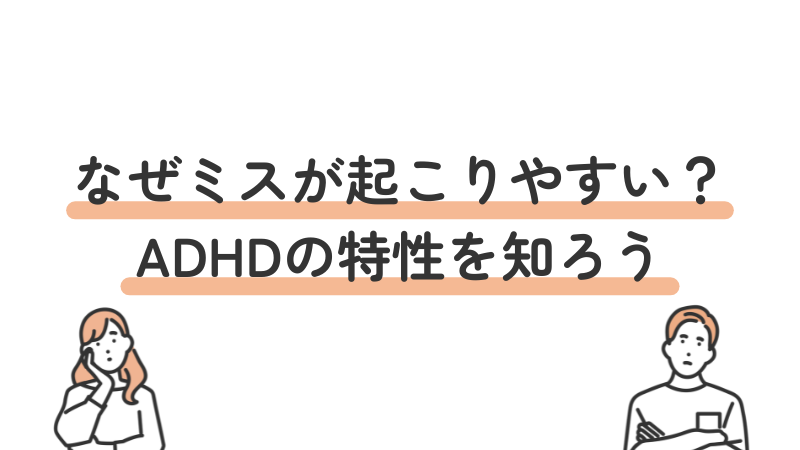
ADHD(注意欠如・多動症)の方が仕事や日常生活でケアレスミスをしやすいのには、理由があります。ここでは、その背景にある代表的な特性を4つ紹介します。
| ADHDの特性 | どう影響するか | 起こりやすいミスの例 |
|---|---|---|
| 注意がそれやすい | 作業中に別のことが気になり、集中が続かない | 書類の誤字・脱字、手順の抜け、話を聞き逃すなど |
| 時間感覚があいまい | 「あとでやろう」と思っていても時間が過ぎてしまう | 約束の時間に遅れる、締切を忘れる |
| 優先順位をつけにくい | どれから手をつけるべきか迷って、行動に移せない | 大事なタスクを後回しにする、準備が間に合わない |
| 衝動性が強い | 思いつきで行動してしまい、後から抜けやミスに気づく | 連絡ミス、手順を飛ばす、必要な確認を飛ばすなど |
ADHD(注意欠如・多動症)のこうした特性は、「努力不足」や「怠け」ではなく、脳の特性によるものです。
意志や根性だけではうまくコントロールすることが難しいため、「どうして自分だけ…」と責めるのではなく、「どうすれば抜けをカバーできるか?」という視点で工夫を取り入れていくことが大切です。
「もしかしてADHD(注意欠如・多動症)かも?」と感じたら
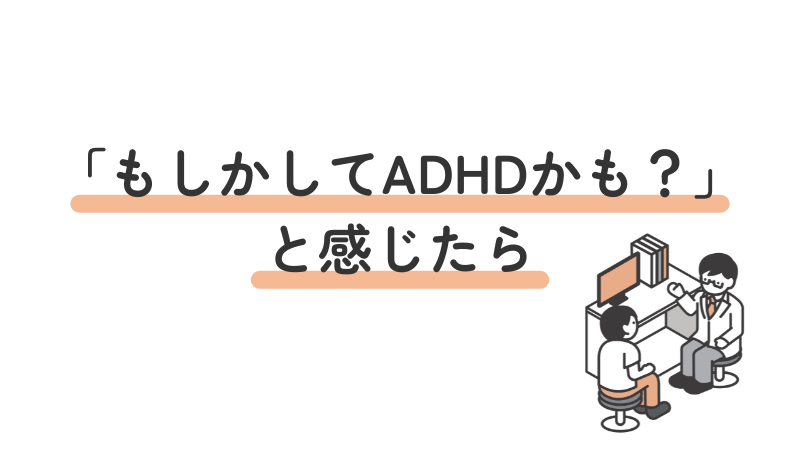
仕事でのミスや忘れ物が続くと、「もしかしてADHDかもしれない」と不安になることがあります。
そんな時は、1人で抱え込まずに、まずは相談してみることが大切です。ここでは、相談できる病院と診断の流れについてご紹介します。
ADHD(注意欠如・多動症)の相談先
ADHD(注意欠如・多動症)かどうかを判断するには、医療機関での診断が必須です。ADHDだと思っていても実は違う病気だったり、同じADHDでも症状の程度が異なり、人によって治療法が異なったりする場合があるため、きちんと専門家に相談することをおすすめします。
医療機関には「心療内科」や「精神科」などの名称がありますが、どこを選べばよいのか迷う方も多いと思います。簡単に違いを整理すると、以下のようになります。
| 診療科 | 対応する主な症状 | 特徴・向いている人 |
|---|---|---|
| 心療内科 | ストレスが原因で起こる体の症状(胃痛・動悸など) | 身体的な不調が強く出ている人向け |
| 精神科 | うつ病・不安などの精神的な症状そのもの | 精神面の症状に対する専門的な診断・治療を受けたい人向け(迷ったら精神科へ) |
ADHD(注意欠如・多動症)の可能性がある場合は、基本的に精神科を選ぶのが安心です。特に「発達障害に対応」と書かれている病院であれば、より専門的な支援を受けられる可能性が高まります。
最近では、「メンタルクリニック」という名前の病院も多くあります。これは、心療内科や精神科とほぼ同じような診療を行っている外来クリニックのことで、名前が違っていても基本的には精神面の相談や発達障害の診療に対応していることが多いです。
ADHD(注意欠如・多動症)に対応している病院を見分けるポイント
病院のホームページをチェックするときは、次のような記載があるかどうかを確認すると、ADHD(注意欠如・多動症)に対応しているかどうかの目安になります。
| チェックポイント | 説明 |
|---|---|
| 「大人のADHD」「発達障害に対応」などの表記がある | 成人の発達障害に対応していることを明記している病院は、専門的な診療が期待できます。 |
| 「注意欠如・多動症(ADHD)」と書かれている | ADHD(注意欠如・多動症)に関する診療を行っていることが明確に示されています。 |
| 「精神保健指定医」「精神科専門医」などが在籍している | 精神科の専門的な知識や経験をもつ医師が在籍しており、安心して相談できます。 |
| カウンセリングや心理検査(WAISなど)に対応している | より正確な診断や支援のために、心理検査やカウンセリングを受けられる体制が整っています。 |
※WAIS(ウェイス)とは:知的能力の特徴や得意・不得意を測定する心理検査です。大人の発達障害が疑われた際にほかの心理検査と一緒によく使われています。
ADHD(注意欠如・多動症)の診断の流れ
診断は以下のようなステップで進むことが多いですが、病院によって流れは異なります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 予約・受診 | 心療内科や精神科、または「メンタルクリニック」などの医療機関に予約し、医師と面談 |
| ② 問診 | 現在の困りごとやこれまでの生活の様子、子どもの頃の様子などを医師に伝える |
| ③ 心理検査 | 必要に応じてWAISなどの知能検査や、発達の傾向を調べる検査を行う |
| ④ 診断結果の説明 | 医師から検査や問診の結果をもとに、ADHD(注意欠如・多動症)かどうかの診断される |
| ⑤ 支援・治療の提案 | 必要に応じて、生活の工夫やカウンセリング、薬の処方など、今後の支援の方向性を決める |
ADHD(注意欠如・多動症)による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
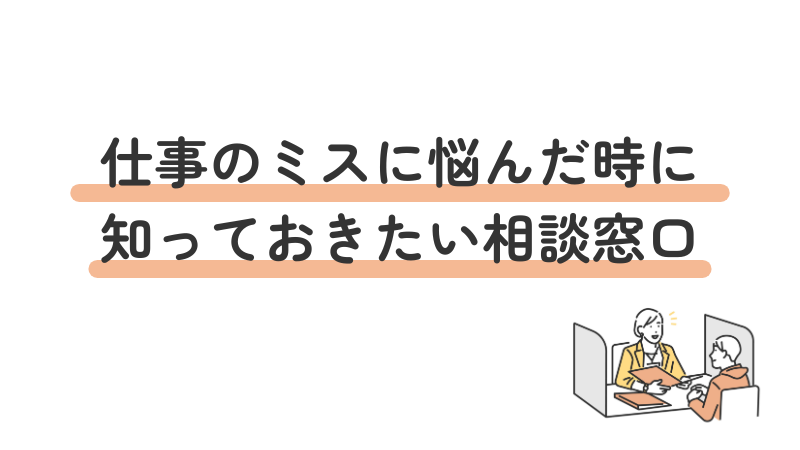
ここでは、仕事や生活の不安を感じた時に相談できる主な窓口をご紹介します。
職場の相談先を活用する
まずは、身近な職場の中に相談できる人や窓口がないか確認してみましょう。会社によっては、働き方や体調に関する悩みをサポートする体制が整っている場合があります。
| 相談先 | 相談できる内容例 |
|---|---|
| 人事・労務・総務部門 | 勤務時間の調整、業務内容の変更、休職制度や配慮の申請など |
| 産業医 | 医療的な視点からのアドバイス、職場での困りごとの相談、中立的な意見の提供など |
| 保健師・社内カウンセラー | ストレスや不調の相談、メンタル面での支援、外部機関の紹介など |
公的な支援機関を利用する
「職場に相談しづらい」「いきなり病院に行くのはハードルが高い」という方は、自治体や国が設けている支援機関に相談することもできます。
| 支援機関名 | 主な相談内容・特徴 |
|---|---|
| 発達障害者支援センター | 発達障害に関する幅広い相談に対応。本人だけでなく家族の相談も可能。医療・就労支援などの情報提供も。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 仕事と生活の両面からサポート。就労の継続や安定した暮らしについての相談ができる。 |
| ハローワーク(障害者窓口) | 障害者専用の窓口があり、就職活動の相談や職場への定着支援、面接練習なども可能。 |
| 就労移行支援事業所 | 就職を目指す障害のある方向けに、ビジネスマナー、職業訓練、職場体験などのサポートを実施。 |
就労移行支援ってどんな所?
就労移行支援とは、発達障害やうつ病などの精神的な困りごとを抱える方が、一般企業への就職を目指して利用できる福祉サービスのひとつです。厚生労働省の制度に基づいて運営されており、就労に向けた訓練やサポートを受けられます。
就労移行支援を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
| 利用対象 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上65歳未満の方 |
| 状況 | 一般企業への就職を目指している方 |
| 障害の有無 | 精神障害・発達障害・知的障害・身体障害などがあり、就労に支援が必要とされる方 |
| 手続き | お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を交付されていること |
※障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できる場合があります。詳しくは自治体の窓口にご確認ください。
就労移行支援manabyについて
就労移行支援manaby(マナビー)ではADHD(注意欠如・多動症)をはじめ、発達障害・精神障害・適応障害・難病などのある方を対象に、「自分に合った働き方」を一緒に考えながら、就職に向けたサポートを行っています。
「仕事でミスが多くて自信をなくした…」「集中力が続かなくて、働き続けるのが不安…」といった悩みを抱えている方でも、自分のペースで訓練できるよう、就労移行支援manaby(マナビー)では1人ひとりの状態に合わせた「個別支援」を大切にしています。
例えば、以下のような支援内容を通じて、安心して就職準備を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した、自宅でもできるスキル学習
- Webデザインやプログラミングなど、IT系のスキル習得
- 通所が難しい方への在宅支援や、柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の可否は、お住まいの自治体によって異なります - 履歴書の書き方や面接練習など、就職活動のサポート
- 働き始めた後も、6か月間の定着支援でフォロー
「自分の強みが分からない」「仕事が続かなくて、将来が不安」という気持ちに寄り添いながら、「どんな働き方なら、無理なく続けられそうか」を一緒に探していきます。
まずは、相談だけでも大丈夫です。少しでも気になった方は、お気軽にお問い合わせください。
ADHD(注意欠如・多動症)の仕事におけるミスは「工夫」でも改善できます
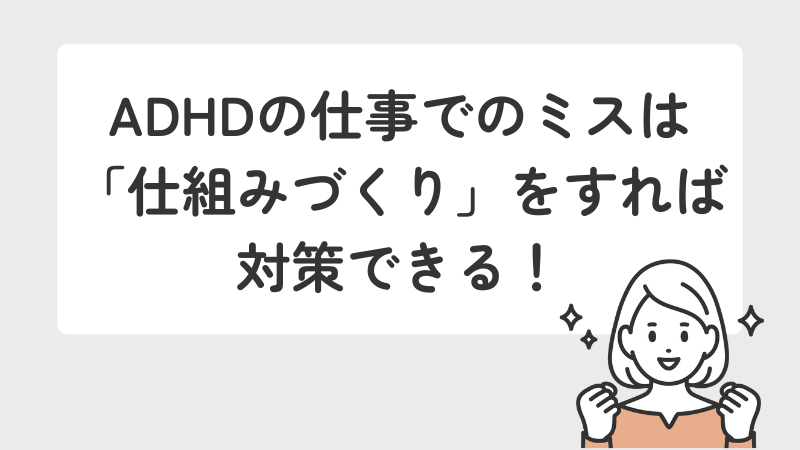
ADHD(注意欠如・多動症)の特性があると、仕事や日常生活の中で「うっかり」や「先延ばし」が続いてしまうことがあります。ですが、それは性格や意志の問題ではなく、脳の特性によるもの。
だからこそ、「覚えておく」「がんばる」だけではなく、忘れても困らないように準備する・行動しやすい環境を整えるといった「仕組みづくり」がとても大切です。
今日から取り入れられる対策
| 悩み | 工夫・対策 | 具体例 |
|---|---|---|
| 忘れ物・失くし物を防ぎたい | 物の定位置を決めて習慣化 | カギは玄関横のフック、財布はバッグに入れっぱなしにする |
| 使ったら戻すルールを作る | 充電器を使ったら必ず定位置に戻す | |
| スケジュール・タスク管理が苦手 | 視覚的にスケジュールを見える化 | 手帳やカレンダーアプリに予定を入れ、前日に確認 |
| タスクを小さく分けてリスト化 | 「請求書作成」を「確認→入力→送信」に分解 | |
| 書類や業務の見落としがある | チェックリストで抜けを防ぐ | 書類提出時の「確認項目チェックシート」を作成 |
| テンプレートを活用 | 毎回のメールや報告書は定型フォーマットに統一 | |
| 遅刻が多い・時間に間に合わない | 逆算スケジュールで行動を組み立てる | 出発時間から逆に起床・準備時間を割り出す |
| アラームを複数セットする | 起床・準備・出発それぞれにアラームを設定 |
相談できる主な窓口
| 窓口名 | 内容・役割 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| 職場内の相談窓口(人事・総務・産業医など) | 働き方の調整や体調・メンタルの相談ができる | 今の職場で働き続けたいが、少し配慮がほしい |
| 発達障害者支援センター | ADHDなどの発達障害についての相談・情報提供 | 診断前後の不安がある、制度のことを知りたい |
| 障害者就業・生活支援センター | 就労と生活の両面をサポートしてくれる | 働きながら生活面でも困りごとがある |
| ハローワーク(障害者窓口) | 障害者雇用に関する仕事探しや相談 | 自分に合った職場を探したい |
| 就労移行支援事業所 | 働くためのスキル習得・実習・就活支援など | 一般企業での就職に不安がある、準備したい |
| 精神科・メンタルクリニック | ADHDかどうかの診断や薬物療法、カウンセリング | 診断を受けたい、集中力の問題を相談したい |
参考:
- 厚生労働省 「発達障害の理解」
- 厚生労働省 「発達障害に気付いたら?大人になって気付いたときの専門相談窓口」
- 国立精神・神経医療研究センター(NCNP病院) 「ADHD(注意欠如・多動症)」
- 厚生労働省 「就労移行支援事業について」








