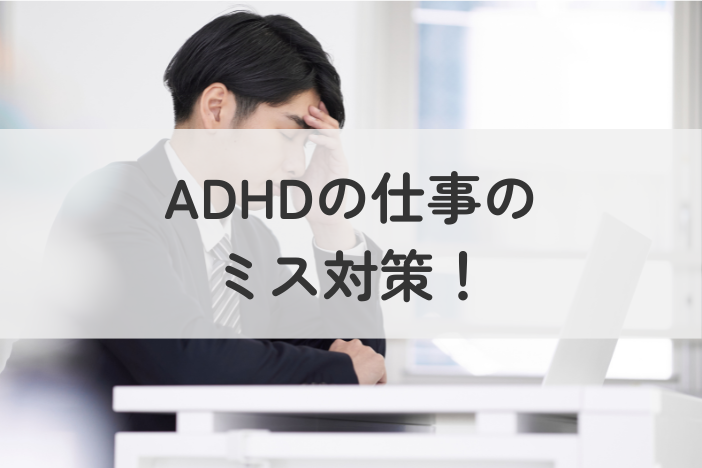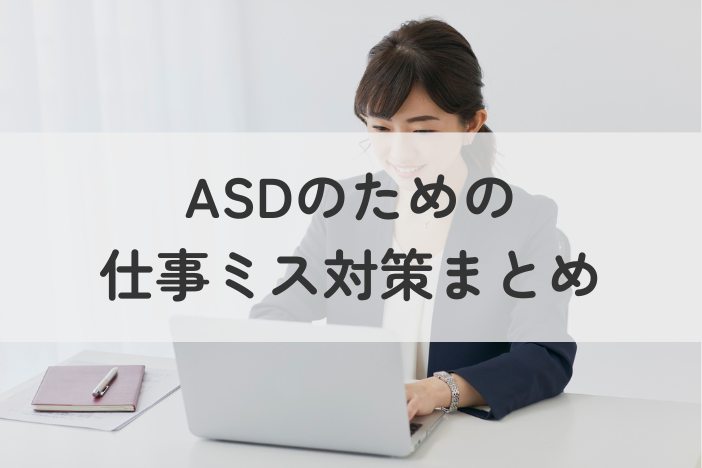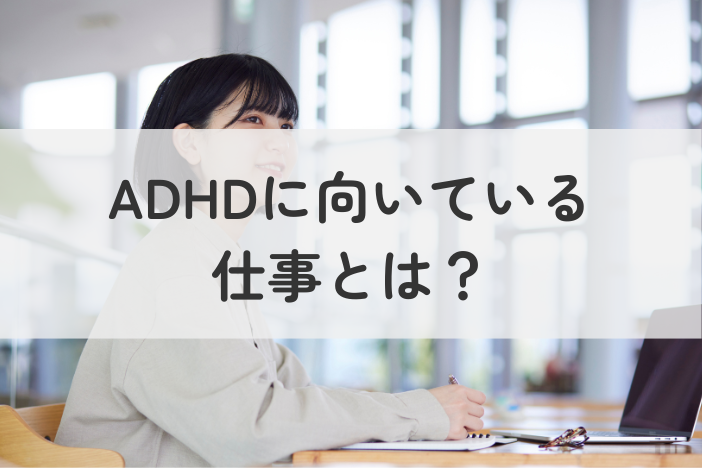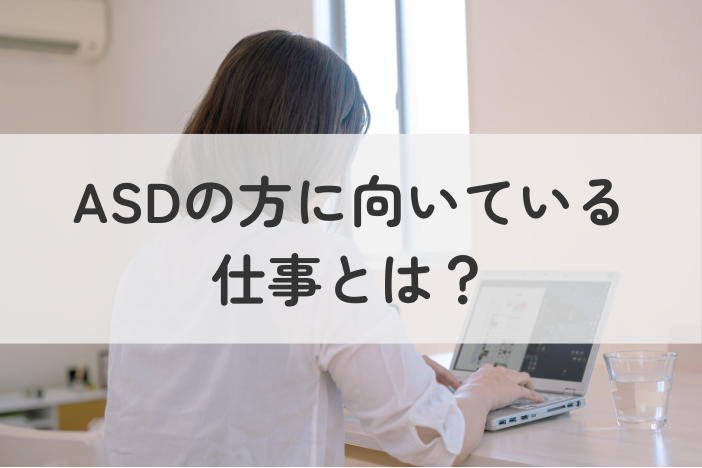仕事でのミスは発達障害のせい?今日からできる具体的な対策を分かりやすく紹介

- 今日からできる!発達障害による仕事のミス対策
- 発達障害の方によくある仕事のミス
- よくある仕事のミス1:納期に間に合わず、提出が遅れてしまう
- よくある仕事のミス2:マルチタスクができず、優先順位をつけられない
- よくある仕事のミス3:メールの返信を忘れたり、書類をなくしてしまう
- 【種類別】発達障害の方が仕事でミスをしやすい理由とは?
- ADHD(注意欠如・多動性障害)に多い「注意がそれやすい」「忘れやすい」
- ASD(自閉スペクトラム症)に多い「柔軟な対応が苦手」「相手の意図を読めない」
- LD(学習障害)に多い「読み書き・計算の困難」
- 発達障害かもしれないと思ったら…
- 発達障害の相談先
- 発達障害に対応している病院の探し方
- 発達障害の診断の流れ
- 発達障害の方に向いている働き方や職場環境
- ADHD(注意欠如・多動性障害)の方に向いている働き方や職場環境
- ASD(自閉スペクトラム症)の方に向いている働き方や職場環境
- LD(学習障害)の方に向いている働き方や職場環境
- 発達障害による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
- 職場の相談先を活用する
- 外部の相談先を利用する
- 就労移行支援ってどんな所?
- 発達障害による仕事のミスは今日から対策できる!
「同じミスを何度も繰り返してしまう」「気をつけているのにうっかり忘れてしまう」という悩みを抱えていませんか?
仕事でのミスが続くと、「努力不足なのかな、それとも発達障害のせいなのかな」と不安になる方も少なくありません。
この記事では、発達障害(ADHD・ASD・LD)の特性と仕事でのミスの関係を整理しながら、今日から実践できる具体的な対策 を分かりやすくご紹介します。
この記事のまとめ
-
●
発達障害によるミスは「努力不足」ではない
ADHD・ASD・LDなどの特性が影響し、注意・記憶・柔軟対応の難しさが原因になることがある。 -
●
今日からできる対策5つ
チェックリスト・リマインダー・作業分割・環境調整・時間区切りで「うっかり」や「過集中」を防ぐ。 -
●
向いている働き方を見つける
手順が明確・静かな職場・配慮のある環境がミスを減らし、力を発揮しやすい。
今日からできる!発達障害による仕事のミス対策
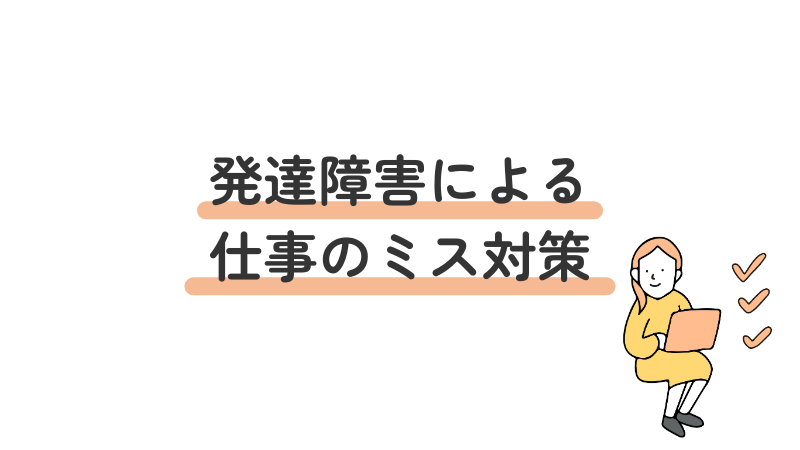
この章のポイント
-
●
発達障害による仕事のミスは「努力不足」ではなく、特性による影響が大きい
-
●
今日からできる5つの対策で「うっかり」を減らせる
チェックリスト・リマインダー・作業分割・環境調整・時間管理の工夫で、抜け漏れや過集中を防ぎます。 -
●
「覚える」より「仕組み化」することがミス防止の近道
頭の中だけで管理せず、見える化とルーティン化を取り入れることで、安定して仕事を進めやすくなります。
発達障害の特性による仕事のミスは、「努力不足」ではなく特性の影響によるものも多いです。自分の特性に合った工夫を取り入れることで、仕事のやりやすさはぐっと変わります。ここでは今日から試せる対策を、特性別に紹介します。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| チェックリストで抜け漏れ防止 | やることを紙やアプリに書き出し、終わったらチェックを入れる | 「やったつもり」で忘れることを減らせる |
| リマインダーで思い出す | 会議や提出物をスマホで通知。メール返信もリマインダーに登録 | 自分の記憶に頼らずに用事を思い出せる |
| 作業を小さく分ける | 「資料を完成させる」を「①データ集め」「②構成」「③清書」に分解 | 混乱や先延ばしを防ぎ、達成感も得やすい |
| 作業環境を整える | デスクを片付け、イヤホンや静かな場所で集中。休憩もこまめに | 集中しやすくなり、ミスや疲れを減らせる |
| 過集中を防ぐ | アラームで時間を区切り、長時間作業を避ける | 他の仕事を忘れたり、疲れて逆にミスするのを防げる |
発達障害の方によくある仕事のミス
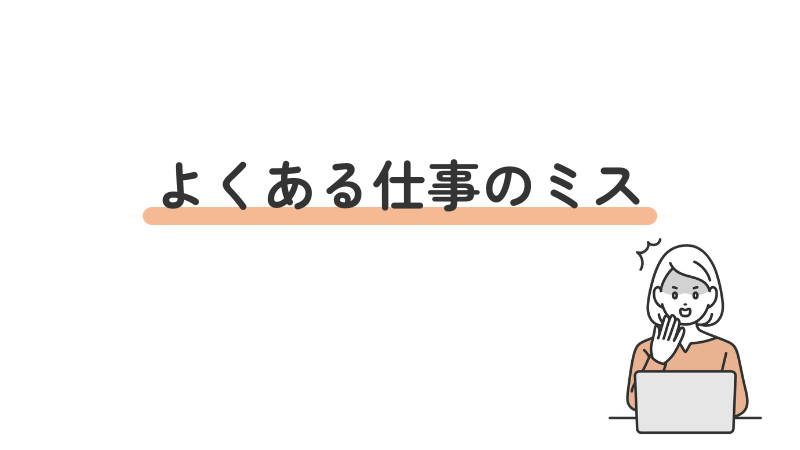
仕事でのミスは誰にでもありますが、発達障害の特性が関係すると「同じような失敗を繰り返してしまう」ことがあります。ここでは、実際に多くの方が経験しやすいシーンを挙げていきます。
よくある仕事のミス1:納期に間に合わず、提出が遅れてしまう
作業にかかる時間を正しく見積もれなかったり、優先順位をつけることが難しく業務を後回しにしてしまうことで、締切に間に合わないことがあります。また、他の業務に気を取られてしまい、気づけば提出直前になっていることも少なくないのではないでしょうか。。このような状況が続くと、本人は「また遅れてしまった」と落ち込んだり、「周囲に迷惑をかけた」と感じやすくなります。一方で、周囲からは「計画性がない」「仕事を任せにくい」と見られることもあり、次は失敗できないという気持ちが重なり、かえって仕事への不安が大きくなってしまいます。
よくある仕事のミス2:マルチタスクができず、優先順位をつけられない
複数の仕事を同時に任されると、どれから手をつければいいのか分からなくなり、頭の中が混乱してしまうことがあります。ひとつの作業に集中しすぎて他の業務が後回しになったり、あれこれ同時に手をつけてしまってどれも中途半端になり、結果的に全体の進行が遅れてしまうこともあります。
本人としては「一生懸命やっているのに成果につながらない」と感じ、焦りや落ち込みにつながることがあります。その一方で、周囲からは「要領が悪い」「段取りを立てられない」と見られてしまい、仕事を任せにくいと判断されることもあります。
よくある仕事のミス3:メールの返信を忘れたり、書類をなくしてしまう
「後で対応しよう」と思ったまま忘れてしまい、メールの返信や小さなタスクを思い出せなくなることがあります。書類や物の置き場所を忘れてしまい、探すのに時間がかかってしまうことも少なくありません。
こうしたことが重なると、本人は「自分は注意力が足りないのでは」と落ち込み、仕事への自信を失ってしまうことがあります。一方で周囲からは「基本的なことができていない」「信頼して仕事を任せにくい」と評価されてしまうこともあり、結果として本人の不安やプレッシャーがさらに強まる悪循環につながることもあります。
【種類別】発達障害の方が仕事でミスをしやすい理由とは?
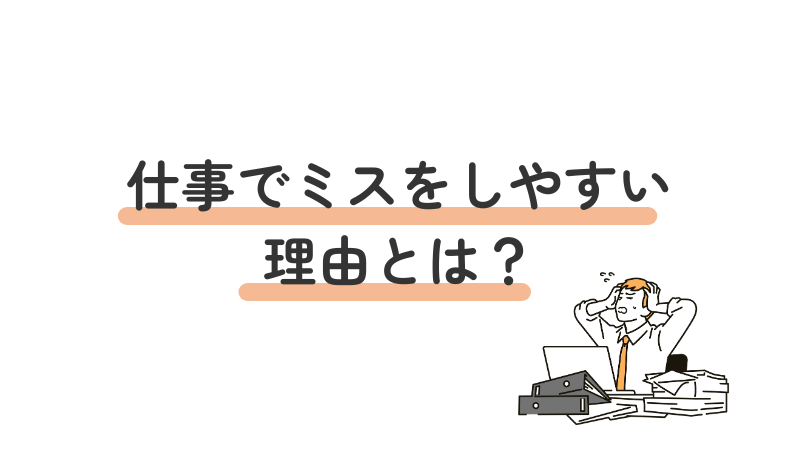
この章のポイント
-
●
同じミスを繰り返す背景には「特性」が関係している
ADHD・ASD・LDの傾向によって、時間管理や注意の切り替えが難しく、結果的にミスが重なりやすくなる。 -
●
よくあるミスは「納期遅れ」「マルチタスクの混乱」「うっかり忘れ」
どれも努力不足ではなく、情報整理や記憶の特性が関係している。 -
●
仕組みで補うことが大切
チェックリスト・タスク管理・環境調整などの工夫を取り入れることで、再発を防ぐ。
ここでは、代表的なADHD(注意欠如・多動性障害)・ASD(自閉スペクトラム症)・LD(学習障害)の特徴と、仕事で起こりやすいミスについて見ていきましょう。
ADHD(注意欠如・多動性障害)に多い「注意がそれやすい」「忘れやすい」
ADHD(注意欠如・多動性障害)には様々な特性がありますが、仕事の場面で特に影響しやすいのが「注意がそれやすい」「忘れやすい」といった傾向です。1つのことに集中していても周りの刺激に気を取られてしまい、必要な情報を聞き漏らしたり、やるべき作業を後回しにして忘れてしまうことがあります。
ADHD(注意欠如・多動性障害)の仕事でのミスと具体的な工夫については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
ASD(自閉スペクトラム症)に多い「柔軟な対応が苦手」「相手の意図を読めない」
ASD(自閉スペクトラム症)の特性は人によって異なりますが、職場で困りごとにつながりやすいのは「柔軟な対応が苦手」「相手の意図を読み取りにくい」といった部分です。曖昧な指示や急な予定変更に戸惑ったり、相手の意図を誤解してコミュニケーションがうまくいかないことがあります。
また、「相手の気持ちを読み取りにくい」ために、忙しそうにしている上司に話しかけてしまったり、無意識に相手の仕事の邪魔をしていることに気付けなかったりすることがあります。このような行動が続くことで社内で孤立化してしまい、仕事に行くのが辛くなることもあります。
LD(学習障害)に多い「読み書き・計算の困難」
LDには読み書きや計算など、複数のタイプがあります。中でも仕事で影響が出やすいのは、文章を正確に読み取ることや数値を扱うことに苦労するケースです。
資料作成や数字の確認に時間がかかったり、うっかり計算ミスをしてしまうことがあります。本人は一生懸命しているつもりでも、「時間かかりすぎ」「ミスしているよ」と指摘されてしまうと焦ってしまい、それがまた多く時間が掛かったり、ミスを引き起こしたりしてまた注意を受けるというスパイラルに陥ることはよくあります。
発達障害かもしれないと思ったら…
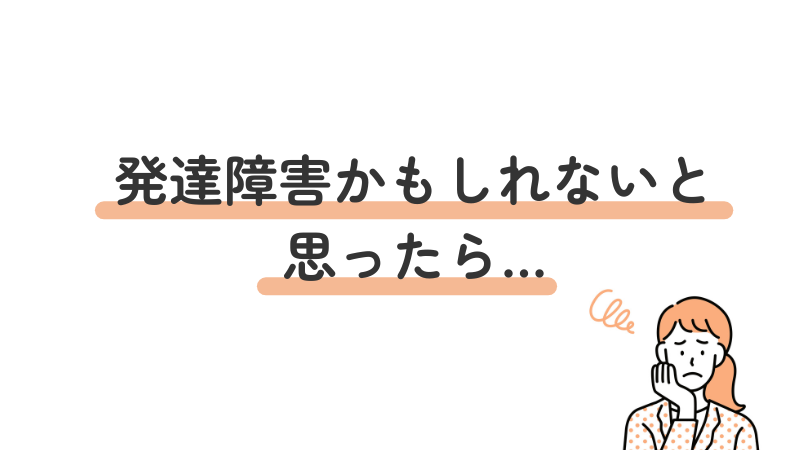
この章のポイント
-
●
「発達障害かも」と感じたら、まずは専門医への相談を
自己判断せず、精神科や心療内科で相談することが大切。 -
●
診断は「問診+心理検査+医師の評価」で行われる
WAISなどの心理検査やカウンセリングを組み合わせ、特性や得意・不得意を客観的に把握する。 -
●
「大人の発達障害」に対応している病院を選ぶと安心
病院サイトで「ADHD対応」「発達障害外来」などの表記を確認し、専門医や指定医がいるかをチェック。
ここでは、発達障害に関する相談先・診断の流れについて紹介します。
発達障害の相談先
「発達障害の傾向があるのでは」と感じた時、自己判断で進めるのではなく、専門の医療機関に相談することが大切です。発達障害の診断には医師による評価が必須で、「自分は発達障害だと思っていたら別の病気だった」「同じ診断名でも人によって症状や対応が違った」ということも珍しくありません。
受診先としてよく選ばれるのが「心療内科」「精神科」「メンタルクリニック」です。違いを簡単に整理すると、次のようになります。
| 診療科 | 対応する主な症状 | 特徴・向いている人 |
|---|---|---|
| 心療内科 | ストレスが原因で起こる体の症状(胃痛・動悸など) | 身体の不調が強い人に向いている |
| 精神科 | うつ病・不安など精神的な症状そのもの | 精神面の診断や治療を受けたい人に向いている(迷ったら精神科へ) |
| メンタルクリニック | 精神科や心療内科と同様の診療を行うクリニック | 発達障害やメンタルの相談に幅広く対応していることが多い |
ADHD(注意欠如・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害が気になる場合は、基本的に精神科を選ぶのが安心です。
発達障害に対応している病院の探し方
受診を考える時は、病院のホームページを確認するのも大切です。特に 「大人の発達障害」や「ADHD」 への対応が書かれているかどうかで、専門的に診てもらえるかの目安になります。
以下はチェックしておきたいポイントです。
| チェックポイント | 説明 |
|---|---|
| 「大人のADHD」「発達障害に対応」などの表記がある | 成人の発達障害に対応していることが明記されている病院は、専門的な診療が期待できます。 |
| 「注意欠如・多動症(ADHD)」と書かれている | ADHDに関する診療を行っていることが明確に示されています。 |
| 「精神保健指定医」「精神科専門医」などが在籍している | 精神科の専門的な知識や経験を持つ医師がいると、安心して相談できます。 |
| カウンセリングや心理検査(WAISなど)に対応している | より正確な診断や支援のために、心理検査やカウンセリングを受けられる体制が整っています。 |
※WAIS(ウェイス)検査とは?:知的能力の特徴や得意・不得意を測定する心理検査です。大人の発達障害が疑われた際には、ほかの心理検査とあわせて使われることが多いです。
発達障害の診断の流れ
発達障害の診断は、次のようなステップで進むことが多いですが、病院によって順序や方法が異なる場合もあります。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 予約・受診 | 精神科や心療内科、または「メンタルクリニック」などの医療機関に予約し、医師との面談を行います。 |
| ② 問診 | 現在の困りごとや生活の様子、子どもの頃の様子などを医師に伝えます。 |
| ③ 心理検査 | 必要に応じて WAIS などの知能検査や、発達の傾向を調べる心理検査を受けることがあります。 |
| ④ 診断結果の説明 | 問診や検査の結果をもとに、発達障害かどうかの診断が行われます。 |
| ⑤ 支援・治療の提案 | 必要に応じて、生活上の工夫、カウンセリング、薬の処方など、今後の支援の方向性が提案されます。 |
発達障害の方に向いている働き方や職場環境
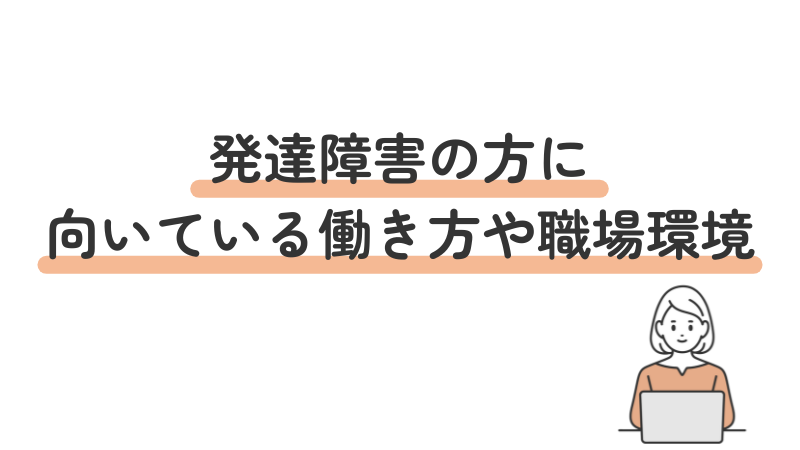
この章のポイント
-
●
発達障害の方に合う働き方は「特性に合った環境」を選ぶことが鍵
得意・不得意を理解し、集中しやすい・見通しが立てやすい職場を選ぶことで働きやすさが大きく変わる。 -
●
ADHDは「シンプルで集中できる仕事」、ASDは「静かで手順が明確な職場」が合いやすい
刺激が少なく、決まった流れで動ける環境が安心。ADHDはリズム感のある業務、ASDはルールやマニュアルが整った仕事が向いている。 -
●
LD(学習障害)は「読み書き・計算の負担を減らす工夫」で力を発揮できる
図解マニュアルや音声入力などICTツールを活用し、理解しやすく確認しやすい職場環境を整えることが重要。
発達障害の方は、特性によって得意・不得意が異なるため、働きやすい職場環境も人によって違います。ここでは、代表的な特性ごとに「どんな働き方が合いやすいのか」を整理します。
ADHD(注意欠如・多動性障害)の方に向いている働き方や職場環境
ADHD(注意欠如・多動性障害)の方は、次のような働き方や職場環境が合いやすいとされています。
【こんな職場がおすすめ】
- 1つの作業に集中できるシンプルな業務内容
- スケジュールや手順が明確で、見通しが立てやすい仕事
- 静かで落ち着いて作業に取り組める環境
- 発達障害への理解があり、配慮のある職場
ADHD(注意欠如・多動性障害)に合う仕事や具体的な働き方について、より詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
ASD(自閉スペクトラム症)の方に向いている働き方や職場環境
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、次のような働き方や職場環境が合いやすいとされています。
【こんな職場がおすすめ】
- 業務内容や手順が明確に決まっている
- 静かで落ち着いた環境
- 1人で集中して取り組める
- 予定外の対応が少なく、見通しを立てやすい
- 特性への理解があり、配慮をしてくれる環境
ASD(自閉スペクトラム症)の方に合う仕事や具体的な働き方について、より詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
LD(学習障害)の方に向いている働き方や職場環境
LD(学習障害)は「読む」「書く」「計算する」といったスキルに部分的な困難がある特性です。そのため、職場では以下のような工夫や環境があると、力を発揮しやすくなります。
| ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 読み書きや計算の負担が少ない業務内容 | 書類作成や数字管理が中心ではなく、体を動かす作業や実務が多い仕事 |
| マニュアルや手順が分かりやすく整理されている職場 | 口頭説明だけでなく、図や写真つきの手順書がある |
| ICTツールを活用できる環境 | 読み上げソフト・音声入力・計算補助ツールの利用 |
| 周囲に理解があり、確認できる体制がある職場 | 分からない時にすぐ質問できる、確認を依頼できる |
発達障害による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
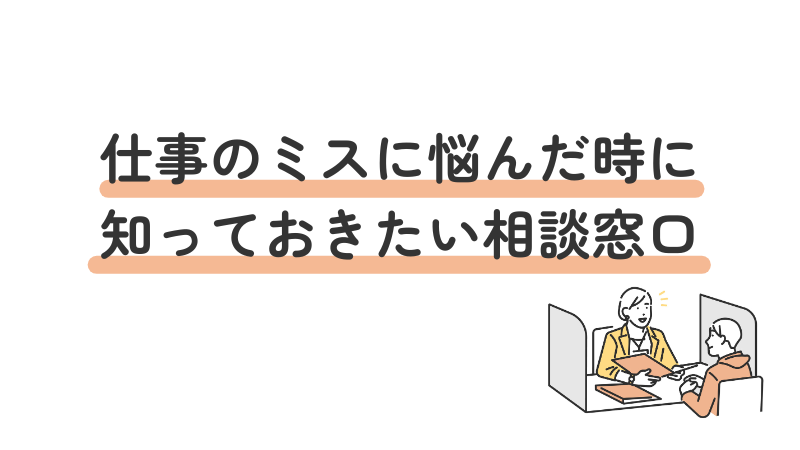
この章のポイント
-
●
職場内の相談先を活用することで、環境調整がしやすくなる
人事や産業医、社内カウンセラーなどに相談すると、勤務時間の調整や配慮の申請など、実際の職場環境を整えるサポートが受けられる。 -
●
「職場では話しにくい」ときは、外部の専門機関を頼るのも一つの方法
心療内科・精神科などの医療機関や、発達障害に理解のある支援機関を利用することで、客観的なアドバイスや支援に繋がる。 -
●
就労移行支援では、働くためのスキルや職場適応をサポートしてもらえる
厚生労働省の制度に基づいた福祉サービスで、ビジネスマナー・PCスキル・職場体験など実践的な支援を受けられる。
ここでは、発達障害による仕事の悩みを相談できる主な窓口をご紹介します。
職場の相談先を活用する
まずは、身近な職場の中に相談できる人や窓口がないか確認してみましょう。会社によっては、働き方や体調に関する悩みをサポートする体制が整っている場合があります。
| 相談先 | 相談できる内容の例 |
|---|---|
| 人事・労務・総務部門 | 勤務時間の調整、業務内容の変更、休職制度や合理的配慮の申請など |
| 産業医 | 医療的な視点からのアドバイス、職場での困りごとの相談、中立的な意見の提供など |
| 保健師・社内カウンセラー | ストレスや体調不良の相談、メンタル面での支援、外部の医療機関や支援機関の紹介など |
外部の相談先を利用する
「職場では相談しづらい」「もっと専門的に相談したい」という場合は、外部の相談先を利用するのも方法です。心療内科や精神科などの医療機関のほか、仕事のスキルや職場での適応に不安がある方には就労移行支援もおすすめです。
就労移行支援ってどんな所?
就労移行支援とは、発達障害やうつ病など精神的な困りごとを抱える方が、一般企業への就職を目指して利用できる福祉サービスのひとつです。厚生労働省の制度に基づいて運営されており、ビジネスマナーやPCスキル、職場体験など、働くために必要なサポートを受けられます。
就労移行支援の仕組みや利用できるサービスについて、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
発達障害による仕事のミスは今日から対策できる!
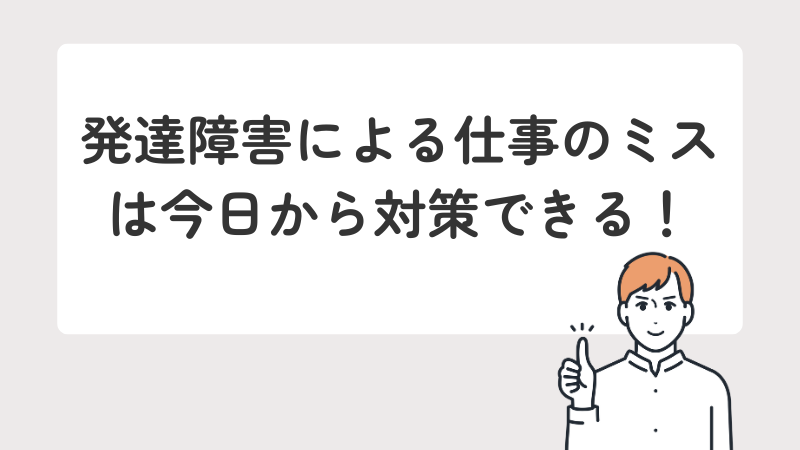
仕事でのミスは誰にでも起こるものですが、発達障害の特性が影響すると同じような失敗を繰り返してしまうことがあります。しかし、工夫や環境の調整を取り入れることで、今日からできる対策はたくさんあります。
【こんな工夫がおすすめ】
- チェックリストやリマインダーの活用 で「うっかりミス」を防ぐ
- タスクの優先順位付けやスケジュール管理で納期遅れを減らす
- 集中しやすい環境づくりで作業効率を上げる
- 専門機関への相談で一人で抱え込まない
大切なのは、ミスを「努力不足」だけで片づけないことです。特性による影響があると理解し、工夫+相談+支援を組み合わせれば改善は十分に可能です。
「自分にできる小さな工夫から始めてみる」ことが第一歩です。それでも不安が続くときは、医療機関や支援サービスに相談してみると、働きやすい方法が見つかるかもしれません。