仕事ができないのはADHD(注意欠如・多動症)のせい?原因とシーン別の対策を分かりやすく解説

- ADHD(注意欠如・多動症)の方が仕事ができないと感じる時の対策
- 出勤前の対策
- 仕事中の対策
- 専門的なサポート・環境調整
- ADHD(注意欠如・多動症)の方が抱える仕事の悩み
- スケジュール管理・タスク管理が苦手
- ケアレスミスや記入漏れが多い
- 気が散りやすく集中力が続かない
- 整理整頓や準備が苦手
- 興味のあることにだけ集中しやすく、他の業務が後回しになる
- 時間の見積もりが苦手で遅刻や忘れ物が多くなる
- 衝動的に発言・行動してしまう
- じっとしているのが苦手
- 順番やルールを守るのが難しい
- ADHD(注意欠如・多動症)の方が「仕事ができない」と感じる理由とは?
- 注意がそれやすく、記憶や段取りのミスで仕事が進みにくい
- 情報が多すぎる、刺激に敏感で集中できない職場環境にいる
- 失敗体験の積み重ねにより、「自分はダメだ」と思い込みやすくなる
- そもそもADHD(注意欠如・多動症)とは?
- ADHD(注意欠如・多動症)かも?と思ったら病院に行くべき?
- 精神科と心療内科の違い
- 診断を受けることで仕事にどんなメリットがある?
- ADHD(注意欠如・多動症)の方に向いている仕事と働き方
- 不注意タイプに向いている仕事
- 多動・衝動性タイプに向いている仕事
- ADHD(注意欠如・多動症)に向いていない仕事の特徴
- 不注意タイプに向かない仕事
- 多動・衝動性タイプに向かない仕事
- 「仕事がしんどい」と感じた時に取れる選択肢
- 心と身体に限界を感じたら「休職」もひとつの手段
- 転職を考える前に、自分の状態や働き方の希望を整理してみる
- 迷ったら「支援機関」や「医療機関」に話を聞いてもらう
- 仕事への悩みがあるADHD(注意欠如・多動症)の方が利用できる就労移行支援
- 就労移行支援manabyについて
- 「仕事ができない」と感じる背景にはADHD(注意欠如・多動症)の特性が関係している
- ADHD(注意欠如・多動症)の特性と、仕事でつまずきやすいシーン
- 「仕事ができない」と感じたときの対策
- 支援を活用して「できる働き方」を見つける
仕事でミスを繰り返してしまう、段取りがうまくできない、集中力が続かないといった悩みを抱えて、「仕事ができないのは自分のせい?」と落ち込んでしまうことはありませんか?実はその「働きづらさ」は、ADHD(注意欠如・多動症)という特性が関係している可能性があります。
この記事では、ADHD(注意欠如・多動症)の傾向の方が仕事でのつまずきの原因や、シーン別の対策、相談できる場所などを分かりやすく解説します。
この記事のまとめ
-
●
ADHDの困りごとは脳の特性によるもの
集中力の続きにくさやミスの多さは努力不足ではない -
●
特性タイプ別に合う仕事とは?
不注意タイプ:データ入力や軽作業
多動タイプ:配達・清掃など体を動かす仕事
衝動タイプ:接客や営業など対人経験が活かせる仕事
ADHD(注意欠如・多動症)の方が仕事ができないと感じる時の対策
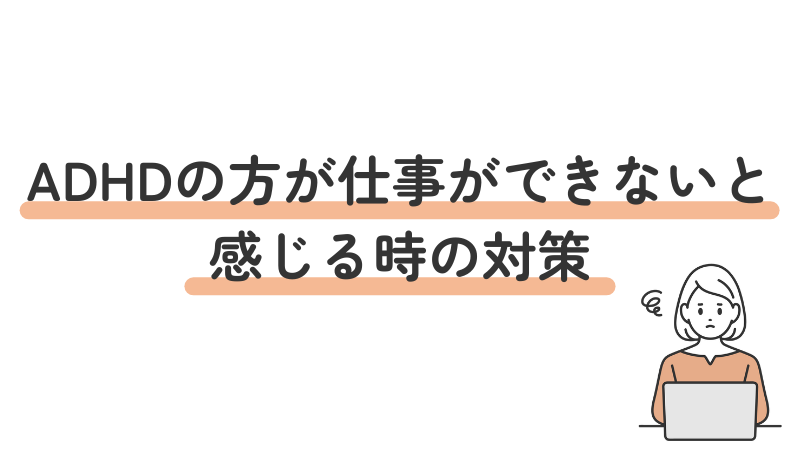
この章では、ADHD(注意欠如・多動症)の傾向がある方が抱える困りごとに対して、「出勤前」「仕事中」「専門的サポート」という3つの場面別に、実際に筆者である私が仕事で使っている対策も交えながら、具体的な方法を紹介します。
出勤前の対策
出勤前は、時間の使い方の見通しが立てにくい、準備に時間がかかるといったADHD(注意欠如・多動症)の特性が表れやすい場面です。
以下のような対策で、朝の慌ただしさによるミスや遅刻を減らすことができます。
| 悩み | 対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 朝にバタバタしてしまう | 前日の夜に着る服や持ち物をセットする | 朝の準備時間を短縮し、忘れ物や遅刻のリスクを減らせる |
| 忘れ物が多くて不安になる | 玄関に「持ち物チェック表」を貼っておく | 出かける直前の確認をルーチン化し、忘れ物を予防できる |
| やることが多くて頭がごちゃごちゃする | 毎朝のタスクをチェックリストで管理する | やることを見える化して、頭の混乱を整理しやすくなる |
| 出発時間ギリギリになってしまう | 外出1時間前に「支度開始アラーム」を設定する | 行動のきっかけをつくり、準備をスムーズに進めやすくなる |
体験談
私は毎晩、翌日の持ち物をすべて揃えておくようにしています。また、朝の行動に迷わないように、乗る電車の時間や乗車する車両まで細かく決めています。予定によってカバンを使い分けるのではなく、用途ごとに固定することで持ち物の入れ忘れを防ぐようにしています。
仕事中の対策
仕事中は、注意が散りやすい、集中力が続かない、段取りの見通しが苦手といったADHD(注意欠如・多動症)の特性が特に目立ちやすい時間です。
以下の対策は、そうした困りごとを軽減し、より仕事がしやすくなる環境づくりに役立ちます。
| 悩み | 対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 大事なことをすぐに忘れてしまう | 重要なことはメモし、すぐ見える場所に置く | 忘れ防止や優先順位の整理に役立ち、業務の抜け漏れを防ぐ |
| 書類の記入ミスや提出忘れが多い | 提出物や記入作業は指差し・ダブルチェックで見直す | ミスを防ぎ、提出後のトラブルや訂正の手間を減らす |
| 集中力が長続きしない | タイマーで25分作業+5分休憩を繰り返す(ポモドーロ・テクニック)を使う | 集中力の維持と疲労軽減につながる |
| 気が散って作業が進まない | やることを1つに絞って机に必要な物だけ出す | 注意の分散を防ぎ、作業効率が上がる |
体験談
私は仕事で複数のタスクを同時に抱えると、どれから手をつけるべきか分からず、混乱してしまうことがあります。そのため、朝の始業前に「今日やるべきこと」を簡単にメモに書き出し、優先順位をつけるようにしています。また、納期や会議の予定を忘れないように、Googleカレンダーに予定を入力し、10分前にアラームが鳴るように設定しています。こうした工夫で、仕事の抜け漏れが減り、少しずつ安心して業務に取り組めるようになってきました。
専門的なサポート・環境調整
「自分の対策だけではうまくいかない…」と感じた時は、外部の力を借りるのも1つの方法です。
ADHD(注意欠如・多動症)による困りごとは、病院で診てもらったり、支援機関に相談したり、働き方を少し変えることで楽になることがあります。
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 上司に相談する | 苦手や困りごとに対して、環境調整を相談してみる(例)感覚過敏や集中力の低下がある場合、耳栓やパーテーションの使用、座席の配置変更などを提案する |
| 医療機関で相談する | 診断を受けることで、自分の困りごとの背景を把握し、必要な配慮や治療に繋がることができます。 |
| 支援機関に相談して困りごとに合ったサポートを受ける | 就労移行支援や障害者就業・生活支援センターなどに相談し、日常生活や仕事の困りごとに具体的に対応できる支援を受けられます。 |
| 雇用形態や働き方を見直す | 例えば、週3勤務にする、午前だけの短時間勤務に変える、在宅ワークを取り入れるなど、自分の体調や集中力に合わせて調整する方法があります。 |
ADHD(注意欠如・多動症)の方が抱える仕事の悩み
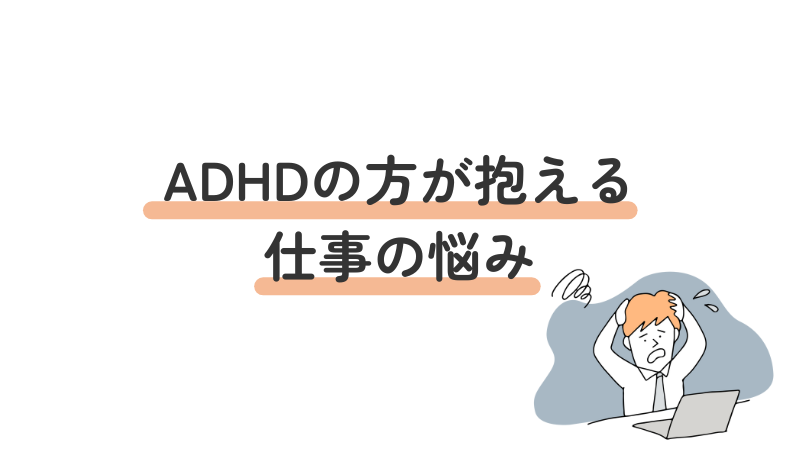
ADHD(注意欠如・多動症)の特性によって、仕事の場面で様々な困りごとが生じることがあります。これらの困りごとは、決して「努力不足」ではなく、脳の働き方に由来する傾向です。
代表的なADHD(注意欠如・多動症)の方が抱える仕事の悩みを9つ紹介します。ADHDの特性は個人差がありますので、人によっては当てはまらない、もしくは強く当てはまる物もあるでしょう。ご自身の生活を振り返りながら確認していきましょう。
スケジュール管理・タスク管理が苦手
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、「今やるべきこと」を整理したり、優先順位をつけて順序立てて行動することに困難を感じやすい傾向があります。特に、情報を一時的に記憶し処理する力であるワーキングメモリ(作業記憶)や目標を達成するために思考や行動を行う力である実行機能がうまく働かず、頭の中で複数の情報を保持しながら判断・計画するのが難しいと感じてしまいます。
例えば、「会議資料の作成」「メールの返信」「経費精算」など、複数の業務が同時に発生した際、どれから着手すればよいか分からず手が止まってしまったり、逆に衝動的に目についたものから始めて非効率になってしまうこともあります。
その結果、タスクの漏れや後回しが頻発し、「抜けが多い」「遅い」といった評価に繋がってしまう場合も。
計画を立てても途中で脱線したり、締切直前になって慌てて対応することが続くと、自信を失い「自分は仕事ができないのでは」と感じるようになってしまうことがあります。
ケアレスミスや記入漏れが多い
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、注意を持続させることや、細部まで意識を向け続けることに難しさを感じる傾向があります。そのため、慎重さや正確さが求められる書類作成や確認作業において、思いがけないミスをしてしまうことがあります。
例えば、請求書の金額を一桁間違えて記載したり、申請書に日付や名前を記入し忘れて提出してしまうなど、基本的な事項でのケアレスミスが起こりがちです。自分では「確認したつもり」でも、頭の中ではすでに別のタスクに意識が向かっていたということも珍しくありません。
こうしたミスが頻発すると、周囲からの信頼に影響を与えるだけでなく、自分自身でも「またやってしまった」と自信を失う原因になります。
気が散りやすく集中力が続かない
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、注意の持続や集中の切り替えが苦手な傾向があり、1つの作業に取り組んでいても周囲の音や視覚的な刺激に反応して意識がそれてしまうことがよくあります。また、気持ちを切り替えて再び集中状態に戻るのにも時間がかかるため、結果として作業の効率が落ちてしまうことも。
例えば、オフィス内で隣の人の電話の声や人の出入りが気になり、書類作成中に何度も手が止まってしまうことがあります。集中できたとしても、数分後には別の作業や思考に移ってしまい、本来の業務に戻るまでにかなりの時間がかかるケースも少なくありません。
このような集中の維持が難しい状態は、周囲から「落ち着きがない」「やる気がない」と誤解されることもあり、本人にとっても「また集中できなかった」と自信を失う要因になります。
特に感覚過敏のある方は、音や光などの刺激に過剰に反応しやすいため、通常よりも環境による影響が大きく、作業に必要な集中状態を保つのが困難になりがちです。
整理整頓や準備が苦手
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、「物の定位置を決める」「使ったものを戻す」「必要な物を事前にそろえておく」といった段取りや整理整頓の習慣づけが苦手な傾向があります。頭の中で複数のタスクを管理しながら物理的な空間を整理することに負担を感じやすく、無意識のうちに机の上が散らかっていくことも少なくありません。
例えば、朝の出勤前に印鑑やUSBメモリが見つからずに探し回る、自宅で準備した資料を持っていくのを忘れて出社してしまう、といったことが繰り返されることがあります。物が多いと視覚的な情報に圧倒され、ますます集中しづらくなるため、「片づけようにもどこから手をつければいいか分からない」と感じてしまうこともあります。
このような傾向により、周囲から「だらしない」「準備不足」と誤解されることがある一方で、本人も「また忘れた」「やっぱり自分はだめだ」と自信を失いやすくなります。
興味のあることにだけ集中しやすく、他の業務が後回しになる
ADHD(注意欠如・多動症)の方には「過集中」という傾向が見られ、特定のことに強く関心を持つと、周囲の状況が目に入らないほど深く没頭してしまう一方で、興味が持てない作業には手がつかなくなる傾向があります。好きなテーマや自分の得意分野には何時間でも取り組めるのに対し、単調で退屈と感じる業務は先延ばしにしやすく、全体のタスク管理に偏りが生まれます。
例えば、新規プロジェクトのアイデア出しや企画の構想には集中力を発揮できても、報告書の作成や経費の処理といった定型業務には手がつかず、締切直前になって慌てて対応するといったケースが見られます。これにより「仕事の優先順位が見えていない」「計画的でない」といった誤解を招くこともあります。
また、本人自身も「なぜ自分は他の業務ができないのか」と自己否定に陥ることがあり、自己肯定感の低下に繋がってしまいます。
時間の見積もりが苦手で遅刻や忘れ物が多くなる
ADHD(注意欠如・多動症)の方は「時間の感覚」に課題を抱えていることが多く、予定を立てても実際にどれくらい時間がかかるかを正確に見積もるのが難しい傾向があります。「あと10分で終わるだろう」と思っていた作業に30分以上かかってしまい、気づけば約束の時間を過ぎていた、というような経験を繰り返しやすいのです。
例えば、家を出る直前に思い出して荷物を詰め始めた結果、出発が遅れ、電車に乗り遅れて遅刻する。仕事でも、メールの返信を「すぐ終わる」と後回しにしていたら、想定より時間がかかって他の業務が遅れてしまうといったようなことが日常的に起こり得ます。
この特性によって、周囲からは「時間にルーズ」「段取りが悪い」と誤解されやすくなり、本人も「また間に合わなかった」と落ち込みやすくなります。
周囲に「時間管理ができていない」などと責められると、よりプレッシャーを感じ、ミスが増える悪循環に陥ってしまいます。
衝動的に発言・行動してしまう
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、思いついたことを即座に言葉に出したり行動に移してしまう「衝動性」の傾向が見られます。これは、頭に浮かんだことを一度立ち止まって整理する前に反応してしまいやすい脳の特性によるものです。
例えば、会議中に話の途中で自分の意見を遮るように発言してしまったり、十分に確認しないまま急いでメールを送信し、後から誤字脱字に気づいたりするケースがあります。これらの行動は、本人に悪気がなくても、周囲からは「せっかち」「配慮がない」と受け取られることがあります。
結果として、チームの中での信頼に影響したり、本人自身も「またやってしまった」と落ち込んでしまうことがあります。
じっとしているのが苦手
ADHD(注意欠如・多動症)の方には、「じっと座っている」「静かにしている」といった状況に苦手意識を持つ方が少なくありません。これは、多動性と呼ばれる特性により、体を動かすことで集中力を保とうとする傾向があるためです。
例えば、会議中やデスクワークの際に足を揺らしたり、席を立ちたくなったりと、じっと座り続けることが難しい場面があります。緊張や不安とは別に、無意識に身体が動いてしまうこともあります。
このような行動は、本人にとっては集中するための手段であっても、周囲には「落ち着きがない」「集中していない」と見られてしまうことがあります。
順番やルールを守るのが難しい
ADHD(注意欠如・多動症)の方には、物事を順序立てて行ったり、手順やルールに従って行動することが難しいという特性があります。これは、頭の中で情報を整理することが苦手で、思いついたことをすぐに行動に移してしまう衝動性とも関連しています。
例えば、職場で順番待ちの列に割り込んでしまったり、会議で話す順番を守れずに発言してしまう、業務フローを飛ばして手続きを進めてしまうといったことが挙げられます。本人にとっては悪気がない行動でも、周囲にはルールを無視しているように受け取られる可能性があります。
こうした行動が続くと、業務上の手順ミスが発生しやすくなり、周囲との信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。
参考:NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター「ADHD(注意欠如・多動症)」
文部科学省「注意欠陥多動性障害」
ADHD(注意欠如・多動症)の方が「仕事ができない」と感じる理由とは?
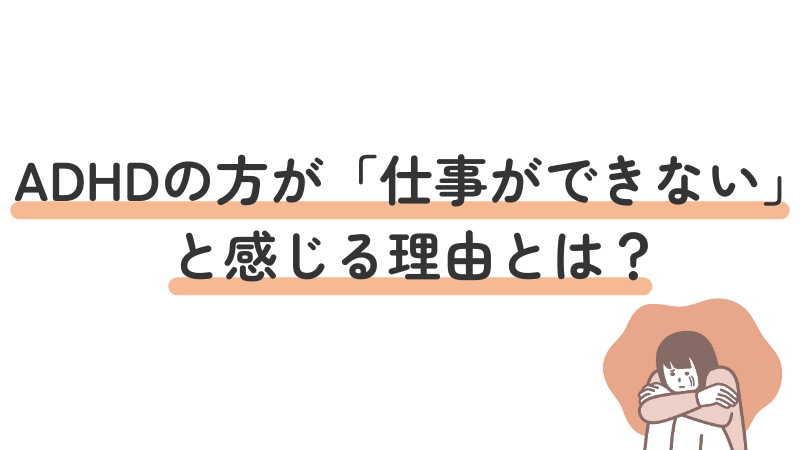
ADHD(注意欠如・多動症)の方が「自分は仕事ができないのでは」と感じてしまう背景には、以下のような要因があります。
注意がそれやすく、記憶や段取りのミスで仕事が進みにくい
周囲の音や動きなど些細な刺激に注意が向いてしまい、作業への集中が続かないことがあります。例えば、資料作成の途中で他の仕事を思い出し、そのまま取りかかって元の作業を放置してしまうといったことが起こりがちです。
また、手順を飛ばしてしまったり、何をすべきか忘れて止まってしまう場面もあります。結果として、ミスが増えたり作業が遅れ、周囲とのペースの違いに悩む方も少なくありません。
情報が多すぎる、刺激に敏感で集中できない職場環境にいる
オフィスで電話の着信音や人の話し声が常に聞こえる、席の近くを頻繁に人が通る、デスク周りに資料や掲示物が多いといった環境は、ADHDの方にとって集中力を保ちにくく、仕事のパフォーマンスに影響が出やすい要因となります。
例えば、資料作成中に隣の席で会話が始まると、思考が中断され作業の流れが止まってしまい、再び集中するのに時間がかかることも。周囲の情報を無意識に拾いやすい特性から、業務に必要以上のエネルギーを使い、疲労感や焦りを感じやすくなることがあります。
失敗体験の積み重ねにより、「自分はダメだ」と思い込みやすくなる
何度もミスを指摘されるうちに、「どうして自分だけ同じことを繰り返してしまうんだろう」と落ち込むことがあります。例えば、書類の記入漏れに気づかず、上司から「またか」と注意されると、「次はもっと気をつけよう」と思っていても自信がなくなっていきます。
自分は周りより劣っているのではないかと感じ、仕事への不安が強まり、緊張からさらにミスが増えてしまうといった悪循環に入ってしまい、「仕事がうまくできない自分」に対する思い込みが強まってしまうこともあります。
そもそもADHD(注意欠如・多動症)とは?
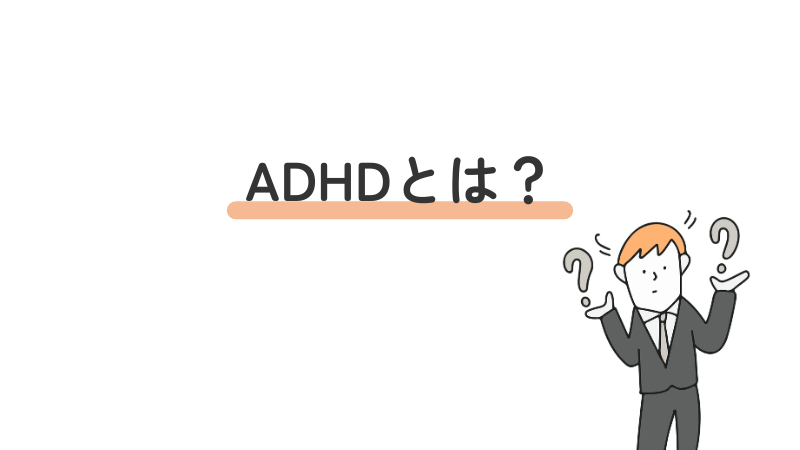
ADHD(注意欠如・多動症)は、発達障害の一つで、注意力の持続が難しかったり、多動性や衝動性が見られたりする脳の特性です。大人になってから困りごとが顕著になることもあり、仕事や人間関係に影響を与えることがあります。
- 注意がそれやすく、忘れ物や抜け漏れが起きやすい(不注意)
- 落ち着いてじっとしているのが苦手(多動性)
- 考える前に行動してしまう(衝動性)
(参考:文部科学省「注意欠陥多動性障害」)
ADHD(注意欠如・多動症)かも?と思ったら病院に行くべき?
この章では、診断を受けるメリットや注意点について分かりやすく解説します。
精神科と心療内科の違い
ADHD(注意欠如・多動症)の傾向を感じた際に相談先としてよく挙げられるのが、精神科や心療内科です。それぞれの診療科の特徴は以下のとおりです。
- 精神科:脳の機能や精神疾患全般を専門とする(例:うつ病、統合失調症、ADHDなど)
- 心療内科:心理的ストレスに起因する体の不調(例:胃痛、頭痛、不眠など)を扱う
ADHD(注意欠如・多動症)の診断は両者で可能ですが、「発達障害専門外来」「青年期発達障害外来」など、発達障害に特化した診療科名や、「児童精神科医」などの資格を持つ医師がいるかどうかを確認すると安心です。
診断を受けることで仕事にどんなメリットがある?
診断を受ける最大のメリットは、自分の特性を客観的に理解できることです。「仕事でのミスが多い」「集中力が続かない」などの悩みが、自分の努力不足ではなく脳の特性であるとわかることで、過剰な自己否定や罪悪感を減らすことができます。
さらに、診断があることで職場に合理的配慮(仕事内容の調整や環境整備)を求めやすくなり、周囲の理解を得るきっかけにもなります。また、就労移行支援などの福祉サービスが利用できるようになるため、「働くうえで困りごとが多い」と感じている方にとって、診断は働きやすさを広げるスタートラインになります。
ADHD(注意欠如・多動症)の方に向いている仕事と働き方
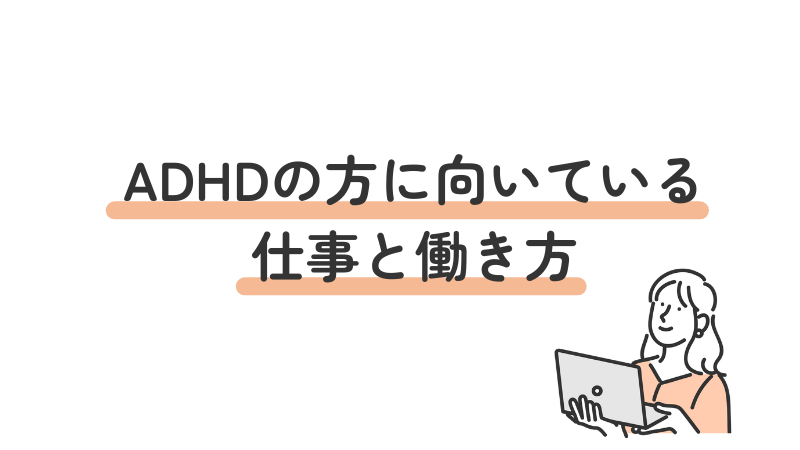
ADHD(注意欠如・多動症)の特性に合った職場や業務内容を選ぶことで、ストレスが少なく、働きやすくなります。
ここでは、ADHD(注意欠如・多動症)のタイプ別に向いている仕事や働き方の例をご紹介します。
不注意タイプに向いている仕事
ADHDのなかでも「不注意が目立つタイプ」の方は、「集中が続きにくい」「うっかりミスが多い」といった傾向がある一方で、一つの作業に没頭できる集中力(過集中)や、丁寧で細やかなこだわりを持っている方も少なくありません。
- 繰り返しの作業や定型業務が中心の仕事:データ入力、書類チェックなど
- 一人で黙々と取り組める仕事:図書館司書、倉庫作業、資料整理、事務など
- 丁寧さや一定の集中が求められる仕事:書類チェック、検品作業など
自分のペースで進めることができ、見通しの立てやすい仕事が向いています。
多動・衝動性タイプに向いている仕事
落ち着いてじっとしているのが苦手なタイプの方には、動きのある仕事やアイデアを活かせる仕事が適しています。「常に動きがある」「自由度が高い」といった要素があると、自分らしく働ける可能性が広がります。
- クリエイティブな仕事:デザイナー、コピーライター、映像編集など
- 身体を動かす仕事:営業職、運送業、イベントスタッフ、介護など
- 自由な働き方:在宅ワーク、フリーランス、リモートワークを活用した柔軟な勤務形態
時間や場所に縛られすぎず、自分のペースで進められる仕事は、衝動的な行動を抑えやすく、ストレスを感じにくくなります。
ADHD(注意欠如・多動症)に向いていない仕事の特徴
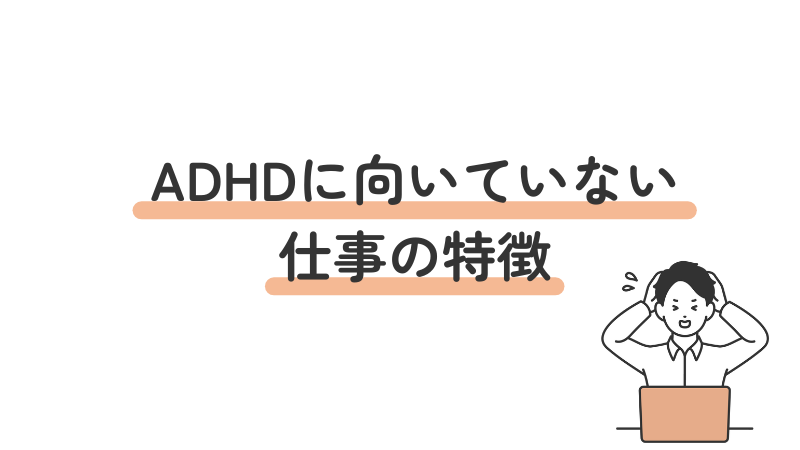
ADHD(注意欠如・多動症)の方は、それぞれの特性によって得意・不得意の傾向が異なります。ここでは、タイプ別に「向いていないかもしれない仕事の特徴」を紹介しながら、無理をしすぎる前に考えたい選択肢についても解説します。
不注意タイプに向かない仕事
注意力が散りやすい、細かいミスが多いといった特性がある方は、以下のような仕事でストレスやミスが増えやすくなります。
| 向いていない仕事の特徴 | 具体例 | 理由・背景 |
|---|---|---|
| ミスが許されないルーティン作業 | 経理、医療記録 | 正確性が求められる業務では、ケアレスミスが大きな問題になる |
| マルチタスクが必要な業務 | 飲食店のホール、受付 | 複数のことを同時に処理しにくく、混乱や遅れが発生しやすい |
| 細かく丁寧な作業 | 校正、検品 | 長時間の集中や注意力の維持が難しく、ミスや疲労が増える |
多動・衝動性タイプに向かない仕事
じっとしているのが苦手だったり、思いつきで動いてしまう傾向がある方は、以下のような仕事がストレスの原因になることもあります。
| 向いていない仕事の特徴 | 具体例 | 理由・背景 |
|---|---|---|
| 長時間じっとする業務 | データ入力、警備 | 体を動かせない環境がストレスとなり集中が続かない |
| 変化が少ない静かな職場 | 図書館、一般事務 | 刺激が少ないことで注意が散漫になりやすい |
| 単調な反復作業 | 製造ライン作業 | 飽きやすく、集中力の維持やルール遵守が難しくなる |
「仕事がしんどい」と感じた時に取れる選択肢
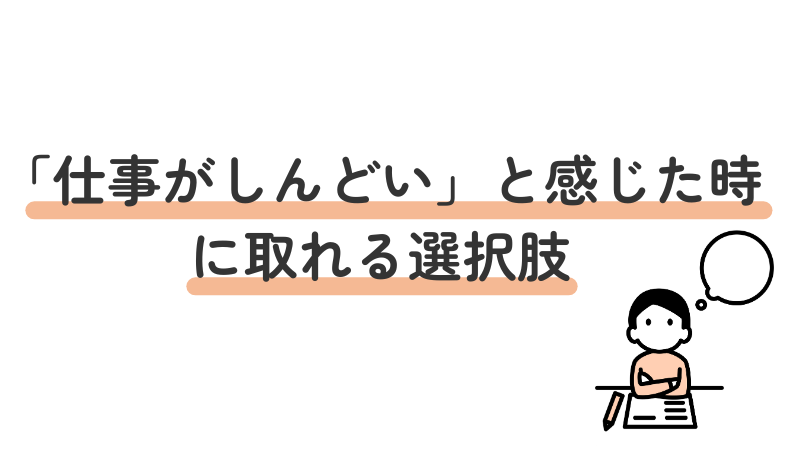
ADHD(注意欠如・多動症)の方が「仕事ができない」と感じる背景には、本人の努力不足ではなく、環境や仕事内容が合っていないというケースが少なくありません。
とはいえ、「合わない」と感じながらも無理に働き続けてしまうと、自信を失ったり、心身の不調に繋がることも。しんどさが続いているなら、以下の3つの対応策を検討してみてください。
心と身体に限界を感じたら「休職」もひとつの手段
疲れやストレスが限界に達していると感じたら、休職を検討することも大切です。
「休職」という選択肢は、決して逃げではありません。診断書があれば、制度としての休職が正式に認められやすくなります。
転職を考える前に、自分の状態や働き方の希望を整理してみる
「今の職場が合わない」と感じても、すぐに辞めるのではなく、まずは自分が苦手な点や希望する働き方を整理してみましょう。
例えば、どんな配慮があれば仕事がしやすくなるのか、どんな働き方なら継続できそうか。紙に書き出して整理するだけでも、次に取るべき行動が見えやすくなります。
迷ったら「支援機関」や「医療機関」に話を聞いてもらう
「どう働けばいいのかわからない」と感じたら、一人で抱え込まず、支援機関に相談してみましょう。
例えば、以下のような代表的な支援機関があります。
- 就労移行支援事業所:障害のある方が自分に合った働き方を見つけるための訓練やサポートを提供
- 障害者職業センター:職業リハビリテーションや職業評価、職場適応援助などを行う専門機関
- 発達障害者支援センター:発達障害のある方やその家族への相談・支援、関係機関との連携を担う
- 精神科・心療内科などの医療機関:診断や治療のほか、診断書の作成や生活上のアドバイスも受けられる
こうした場所では、就職・転職の相談だけでなく、自分の特性理解や生活面のサポートを受けることもできます。
仕事への悩みがあるADHD(注意欠如・多動症)の方が利用できる就労移行支援
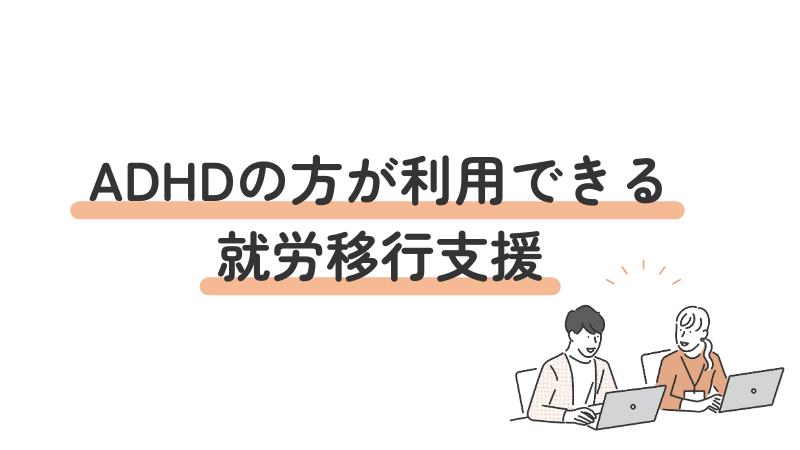
職場での働きづらさやミスマッチを感じている場合、就労移行支援を活用することで、自分に合った働き方を見つけやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 一般企業への就職を目指す、障害のある方(精神・発達・身体など) |
| 主な内容 | 職業訓練、就職活動のサポート(履歴書作成、面接練習、職場体験など) |
| 利用期間 | 原則2年間(必要に応じて延長可能) |
就労移行支援manabyについて
manabyの就労移行支援では、ADHD(注意欠如・多動症)をはじめ、発達障害・精神障害・難病など、さまざまな特性を持つ方が「自分に合った働き方」を見つけられるようサポートしています。
「ケアレスミスが多くて自信をなくした」「集中力が続かず、仕事がうまくいかない」といった悩みに寄り添いながら、それぞれの特性や得意・不得意に合わせた個別支援を大切にしています。
例えば、以下のような支援を通じて、焦らず自分のペースで「働く準備」を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」で、集中しやすい時間帯にあわせて学習できる
- Webデザインや動画編集、プログラミングなど、興味を活かせるITスキルを習得可能
- 通所が不安な方には在宅訓練や柔軟なスケジュール調整にも対応
※在宅訓練の実施可否は自治体によって異なります - 応募書類の作成や面接練習など、就職活動のサポートも充実
- 就職後も6か月間の定着支援があり、職場での困りごとにも対応
「同じミスを繰り返して落ち込んでしまう」「自分に向いている仕事がわからない」と感じている方も、どうぞ1人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
「仕事ができない」と感じる背景にはADHD(注意欠如・多動症)の特性が関係している
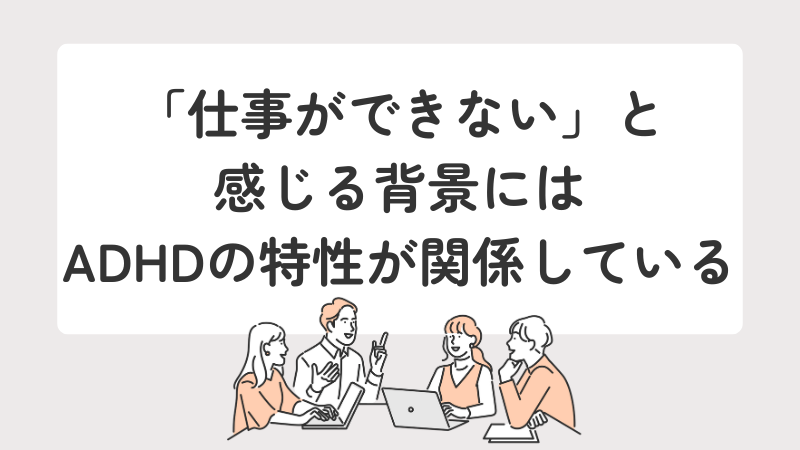
仕事でのつまずきやミスは、努力不足ではなくADHD(注意欠如・多動症)の特性によるものかもしれません。自分の特性を理解し、必要な支援を受けながら「できる働き方」を見つけていくことが大切です。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性と、仕事でつまずきやすいシーン
ADHD(注意欠如・多動症)の人は、以下のような特徴があるとされています。
| ADHDの特性 | 仕事で起こりやすい困りごと |
|---|---|
| 不注意 | ケアレスミス、書類の提出忘れ、指示を聞き漏らす |
| 衝動性 | 話を最後まで聞かずに行動、発言トラブル |
| 多動性 | 落ち着いて作業に集中できない、席を頻繁に立つ |
これらは「やる気がない」「社会人として未熟」と誤解されることもあり、本人が自信を失いやすい原因になります。しかし、これは努力不足ではなく、脳の特性によるものです。
「仕事ができない」と感じたときの対策
つまずきを感じたときは、「どうしたら続けやすいか」「どこが負担になっているのか」を見つめ直して、自分に合った工夫を取り入れてみましょう。
- ミスが多いなら:タスクを細分化したり、ToDoリストやリマインダーで外部サポートを取り入れることでミスを防ぎやすくなります。
- 集中が続かないなら:短時間集中+こまめな休憩で「自分のリズム」を見つけることが効果的です。静かな環境やイヤホンなども集中維持に役立ちます。
- 人間関係に悩んでいるなら:過度なコミュニケーションを求められない職種への転職や、業務の見直しを相談してみるのも選択肢です。
支援を活用して「できる働き方」を見つける
仕事がつらいと感じた時は、1人で抱え込む必要はありません。発達障害者支援センターや就労移行支援などの機関では、専門スタッフと一緒に働き方を見直すことができます。
「どんな仕事が合うのか分からない」「今のままでいいのか不安」といった悩みも、第三者の視点が入ることで、選択肢が広がることがあります。








