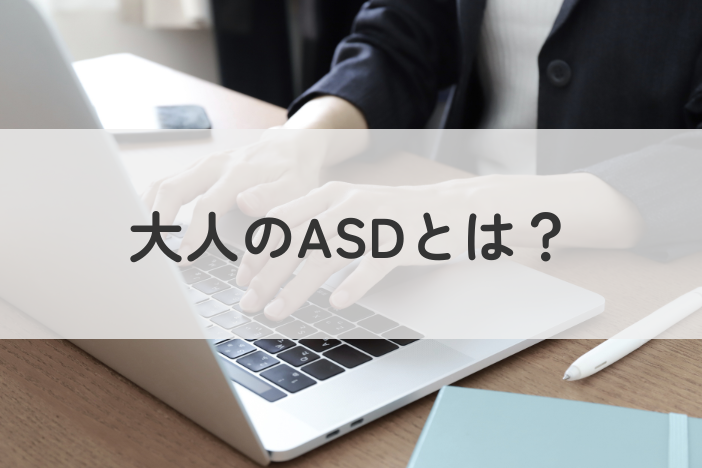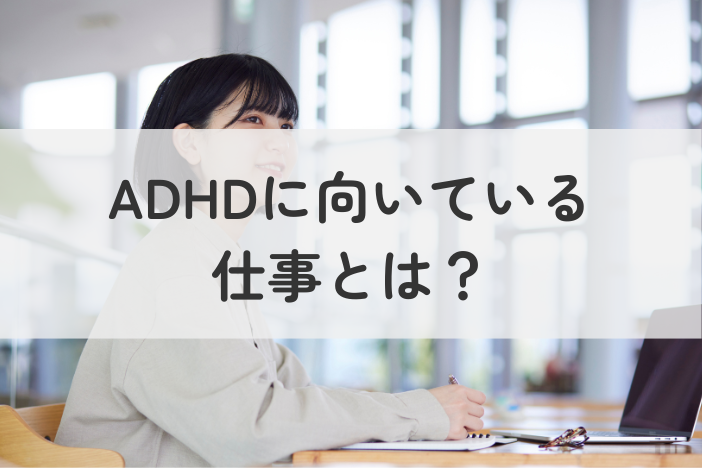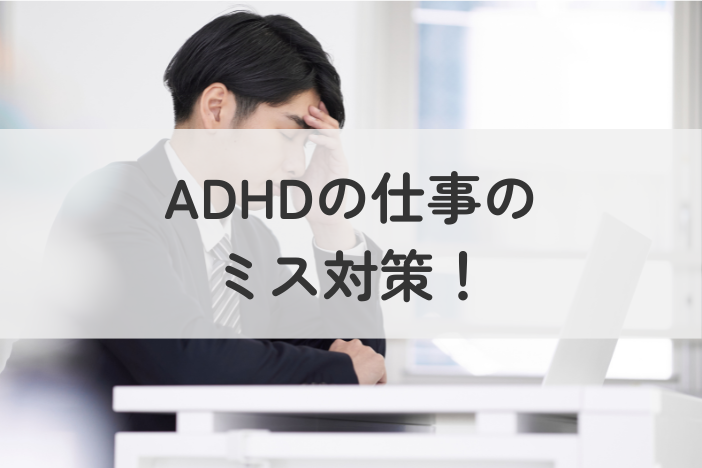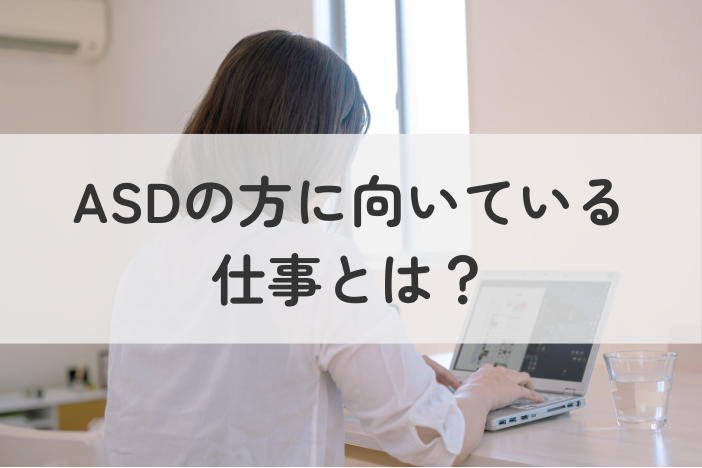【場面別】ASD(自閉スペクトラム症)のための今日からできる仕事ミス対策まとめ
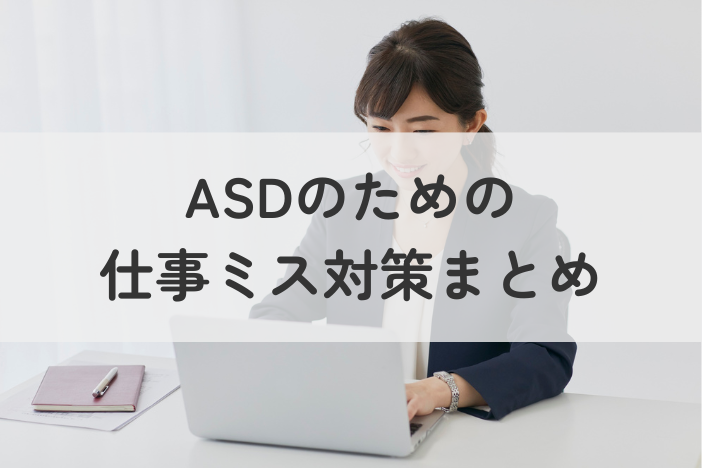
- 今日からできる!ASD(自閉スペクトラム症)の仕事ミス対策
- あいまいな指示を受けた時の対処法とコツ
- 急な予定変更や予想できないことへの対処法とコツ
- スケジュール・タスク管理の対策とコツ
- 書類や業務のケアレスミスを防ぐ対策とコツ
- 報告・連絡・相談(報連相)の抜けを防ぐ対策とコツ
- ASD(自閉スペクトラム症)とは?
- ADHD(注意欠如・多動症)との違いは?
- なぜ仕事でミスが起きやすいのか?ASD(自閉スペクトラム症)の特性と仕事の関係
- ASD(自閉スペクトラム症)に向いている働き方・環境とは?
- ASD(自閉スペクトラム症)による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
- 職場の相談先を活用する
- 職場に開示しなくても特性を伝えるコツ
- 相談するタイミング
- 公的な支援機関を利用する
- 就労移行支援ってどんな所?
- 就労移行支援manabyについて
- ASD(自閉スペクトラム症)によるミスは「仕組み」で減らせる
「自分では確認したつもりなのに、またミスしてしまった…」「仕事を真面目にやっているのに、うまくいかないことが多い…」と悩んでいませんか?ASD(自閉スペクトラム症)の方は、あいまいな指示をそのまま受け取ってしまったり、急な予定変更に混乱しやすかったりするなど、特性によって仕事でミスが起きやすくなることがあります。
しかし、それは決して「不注意」や「努力不足」ではありません。自分に合った工夫や仕組みを取り入れることで、ミスを減らし、安心して働ける環境をつくることは十分可能です。
この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)の特性に合わせて、職場で今日から実践できる具体的なミス対策を場面別にご紹介します。
この記事のまとめ
-
●
ASD(自閉スペクトラム症)の仕事ミス対策のポイント
苦手な場面ごとに具体的な対処法を取り入れることで、ミスを防ぎやすくなる - ● 困ったときは一人で抱え込まず、上司や支援機関に相談することで、無理のない工夫や配慮を得られることがある
今日からできる!ASD(自閉スペクトラム症)の仕事ミス対策
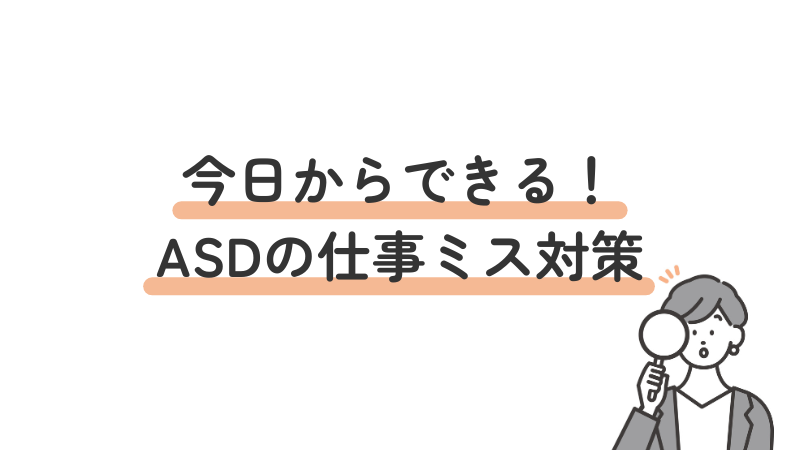
この章のポイント
- ● ASDの仕事ミス対策は、苦手な場面ごとに具体策を持つことがカギ
- ● タスクを見える化して、頭の中を整理しよう
- ● 一人で抱え込まず、報告・相談のルールを決めておくと安心
この章では、ASD(自閉スペクトラム症)の特性に合わせて、今すぐ実践しやすい具体的なミス対策を、場面ごとにご紹介します。自分に合いそうなものから、ぜひ取り入れてみてください。
あいまいな指示を受けた時の対処法とコツ
例えば「いい感じにまとめておいて」「ざっくりでいいよ」と言われると、何をどこまでやればいいのか分からず、手が止まってしまうことはありませんか?
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、相手のあいまいな言葉をそのまま受け取ってしまいやすく、背景や意図を読み取るのが苦手なことがあります。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 指示内容の確認ルールを決める | 「この部分はどういう意味ですか?」と具体的に質問する。 | 誤解によるミスややり直しを防げる。 |
| あいまいな言葉の「言い換えメモ」を作る | 「ざっくりで」「いい感じに」などのあいまい表現を、自分なりの解釈をリスト化する。 | 次回からは迷わず判断できるようになり、不安が減る。 |
| 理解の確認を習慣化する | 作業に入る前に「○○という内容で進めて大丈夫ですか?」と上司に確認する。 | 認識のズレを事前に防ぐことができる。 |
| 作業のゴール・範囲を自分の言葉でメモする | 指示内容を受けたあとに「目的」「納期」「どこまでやるか」などを自分なりに整理してメモに残す。 | 「やりすぎ」「足りない」などのすれ違いを防げる。 |
| 不安な言い回しをメモして上司に確認 | どうしても意味が曖昧な言葉があれば「この表現、こう解釈していいですか?」と確認する。 | 勘違いを防ぐ。 |
| 途中経過を報告する | ある程度進めたところで「こんな感じで進めて大丈夫そうですか?」と中間報告をする。 | 認識違いがあったとしても修正が可能。方向性にOKがもらえることで自信を持って業務に取り組める。 |
急な予定変更や予想できないことへの対処法とコツ
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、突然の予定変更にとてもストレスを感じやすく、苦手を感じることがあります。予想できないことが起こると、他の作業が抜けたり順番が崩れてしまい、ミスに繋がってしまいます。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| メモして一時保留する | 急に仕事を頼まれたら、まずメモに書き出してから取りかかる | 頭の中がパニックにならず、順序立てて対応しやすくなる |
| 作業ごとに「戻り先」を決めておく | 割り込み作業のあとに「タスクリストを見てから戻る」などのルールを決めておく | 中断後に元の作業を忘れず、ミスや漏れを防げる |
| 想定外に備えた「もしもリスト」を作る | 「急に頼まれたらどうするか」「会議が延びたらどうするか」など、よくあるイレギュラーを事前に整理しておく | 想定外の出来事でも、落ち着いて対応しやすくなる |
| 自分なりの「切り替えスイッチ」を決めておく | 作業の前後に深呼吸・お茶を一口飲む・席を立つなど、気持ちを切り替える動作を決めておく | 焦った気持ちをリセットし、次の仕事に入りやすくなる |
| あえて“余白のある予定”を組む | タスクの合間に5〜10分の予備時間を入れておく | 予定変更があっても焦りにくくなり、心の余裕が生まれる |
スケジュール・タスク管理の対策とコツ
ASD(自閉スペクトラム症)の方には、物事を順序立てて進めたり、先の見通しを立てたりすることが難しい傾向があります。そのため、タスクの優先順位がつけられず混乱してしまい、気づいたときには時間が過ぎていて、焦ってしまうこともあります。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| タスクを「見える形」で整理する | 今日やることを紙やToDoアプリなどにリスト化する | 頭の中が整理され、何からやるべきかがはっきりする |
| タスクの順番を決めておく | 「①メール返信 → ②資料作成 → ③報告書提出」など番号を振っておく | 優先順位に迷わず、行動が止まらなくなる |
| 大きな作業は小さく分ける | 「報告書を作る」→「構成を考える」「書く」「見直す」など3〜4ステップに分ける | 負担感が減り、少しずつでも前に進めるようになる |
| タスクの所要時間を見積もる練習をする | 「この作業は30分」と書き、実際の時間と比べて調整していく | 時間感覚が身につき、計画通りに動きやすくなる |
| 曜日や時間でやることを固定する | 「火曜午前は経費入力」「金曜夕方は書類整理」などルーチン化する | 毎回判断しなくてもスムーズに行動できる |
| 朝や前日にスケジュールを立てる習慣をつける | 毎朝5分、「今日やること」「順番」「かかりそうな時間」を書き出す | 1日の見通しが立ち、不安や混乱を防げる |
書類や業務のケアレスミスを防ぐ対策とコツ
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、1つの部分に集中しすぎて、他の情報を見落としたり、全体の流れをつかみにくくなることがあります。注意しているのにミスが出てしまうと、自信をなくしてしまいますよね。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| チェックリストを活用する | 書類提出前に「日付・宛名」など確認項目をリスト化しておく | 毎回同じ流れで見直せるので、ミスが起きにくくなる |
| 1作業1工程で集中する | 書類作成→保存→印刷→送付などを、一つずつ丁寧に区切って行う | 同時進行を避けることで、確認漏れが減る |
| 全体→部分の見直し順にする | 最初に全体のレイアウトや流れを確認し、その後に細かい部分を見るようにする | 一部に集中しすぎて他を見落とすミスを防げる |
| 音読または読み上げ機能を使う | 書いた文章を自分で声に出す、またはPCの読み上げ機能を活用する | 客観的に文章を見直せて、誤字や抜けに気づきやすくなる |
| ミスのパターンを記録する | 過去に指摘されたミスをメモに残し、提出前にそれだけチェックする | 自分がやりがちなミスに集中して対策できる |
報告・連絡・相談(報連相)の抜けを防ぐ対策とコツ
ASD(自閉スペクトラム症)の方にとって報連相は、タイミングの判断・相手の感情の把握・報告の内容の整理といった、目に見えない・明確でない要素が多く含まれるコミュニケーションです。そのため「伝えたいけどどうしたらいいか分からない」「そもそも何を報告すればいいのか分からない」など、あいまいさそのものがストレスに繋がる傾向があります。
| 工夫 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 報連相のタイミングを決めておく | 「お昼前」「退勤前」など決まった時間に報連相の時間を取る | いつ伝えるか迷わなくなり、伝え忘れを防げる |
| 報告すべき内容のパターンを整理する | 「完了したとき」「ミスしたとき」「誰かに聞いたとき」など、自分なりの報告ルールを作る | どの場面で報告が必要か判断しやすくなる |
| 書いてから話す「メモ方式」にする | 相談や報告の内容を事前にメモし、それを見ながら伝える | 頭が整理され、言いたいことがまとまりやすくなる |
| 報連相チェックリストを作る | 「上司に報告」「関係者に連絡」「相談すべきことは?」と1日1回確認する | 抜け漏れを事前に防げる習慣ができる |
ASD(自閉スペクトラム症)とは?
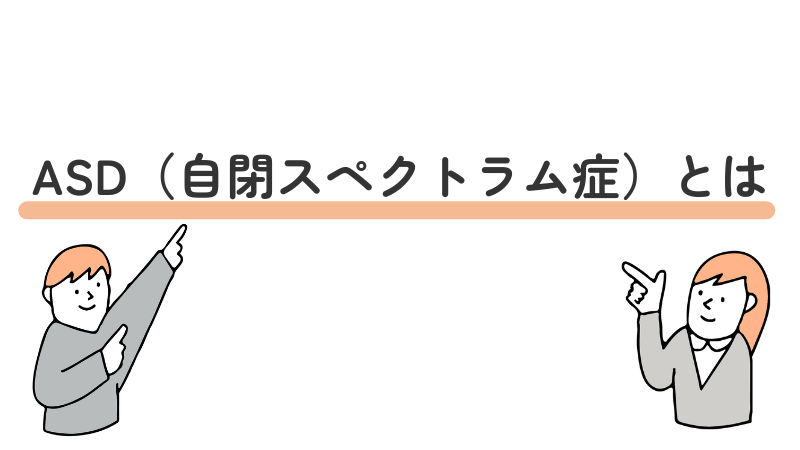
この章のポイント
- ● ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係やコミュニケーションに独自の困難を抱える
- ● 予定外の出来事への不安や、自分なりのこだわりが強いといった特性が、仕事や日常生活に影響を及ぼす
ASD(自閉スペクトラム症)とは、対人関係やコミュニケーションの難しさ、特定の行動へのこだわりがあり、日常生活や社会生活に困難が生じる状態です。
特にASD(自閉スペクトラム症)の方は以下のような特性や困りごとを持っている傾向があります。
- 対人関係の距離感が分からない、空気の読みづらい
- 会話のズレや一方的な話し方などコミュニケーションでつまづく
- 予定通りに進まないことへのストレスや不安を感じる
- 自分なりのルールや手順に強いこだわりを持っている
ADHD(注意欠如・多動症)との違いは?
ADHD(注意欠如・多動症)とは、「不注意」「多動性」「衝動性」といった特徴があり、日常生活や社会生活に困難が生じる状態のことです。
ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害と併発する場合もあります。
- 参考:国立精神・神経医療研究センター「発達障害(神経発達症)」
なぜ仕事でミスが起きやすいのか?ASD(自閉スペクトラム症)の特性と仕事の関係
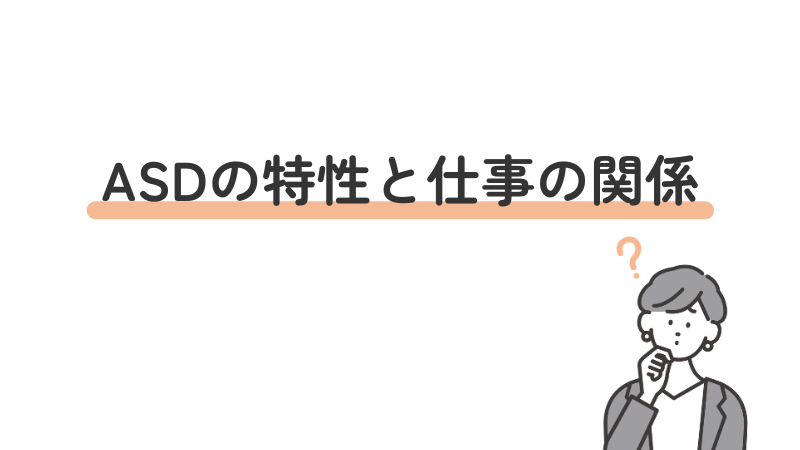
この章のポイント
- ● ASD(自閉スペクトラム症)の方がミスしやすいのは、「注意不足」ではなく特性が関係している
- ● 特性ごとにミスの傾向や場面が異なるため、対策も特性に応じて考えることが大切
ASD(自閉スペクトラム症)の方が、仕事や日常生活でケアレスミスやうっかりミスをしやすいのには、理由があります。
それは、決して「注意力が足りない」「集中していない」といったことではありません。ASD(自閉スペクトラム症)の方には、情報の受け取り方や脳の働き方に独自の特徴(=特性)があり、それが仕事の進め方やコミュニケーションの中で“すれ違い”を生みやすいのです。
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)の方が仕事でミスをしやすくなる背景にある代表的な特性と、実際に起こりやすい場面・ミスの例をご紹介します。
| 特性 | 仕事への影響 | 起こりやすいミスの例 |
|---|---|---|
| 見通しを立てるのが苦手 | タスクの段取りや進行計画を立てるのが苦手で、予定が崩れやすくなる | 優先順位が分からずタスクを飛ばす、締切に間に合わない |
| 過集中しやすい | 他の作業や時間の感覚を見失いやすく、予定外のミスが起こりやすい | 書類作成に集中しすぎて提出時間や添付を忘れる |
| 想定外に弱い | 割り込みや変更指示に混乱し、元の作業に戻れなくなる | 予定が崩れると混乱し、他の作業を忘れてしまう |
| 曖昧な言葉が理解しにくい | 作業内容を誤解したまま進めてしまいやすい | 「ざっくり」「適当に」などの指示で混乱して間違える |
| 同時処理が苦手 | 報連相や進行管理など、複数の視点を同時に持つ場面で混乱しやすい | 一つの作業に集中しすぎて、報告や確認を忘れる |
| 状況や相手の気持ちを察しにくい | コミュニケーションのタイミングや距離感でつまずきやすい | 報告や相談のタイミングを逃す、伝え忘れる |
ASD(自閉スペクトラム症)に向いている働き方・環境とは?
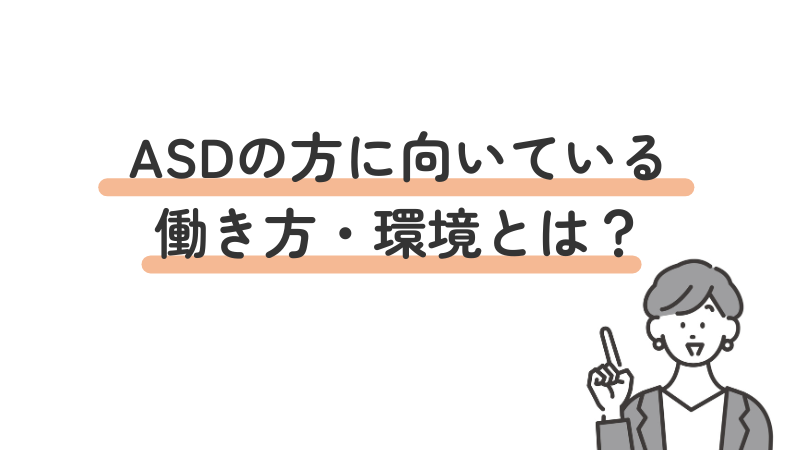
この章のポイント
- ● 手順や業務内容が明確で、予定外の対応が少ない環境は、安心して働きやすい
- ● 静かで1人で集中できる環境かつ、特性への理解や配慮がある職場では、強みが活かされやすい
- 業務内容や手順が明確に決まっている
- 静かで落ち着いた環境
- 1人で集中して取り組める
- 予定外の対応が少なく、見通しを立てやすい
- 特性への理解があり、配慮をしてくれる環境
これらの特徴が多く当てはまる環境では、ASDの特性が強みとして活きる場面も多くなります。
より具体的に知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
ASD(自閉スペクトラム症)による仕事のミスに悩んだ時に知っておきたい相談窓口
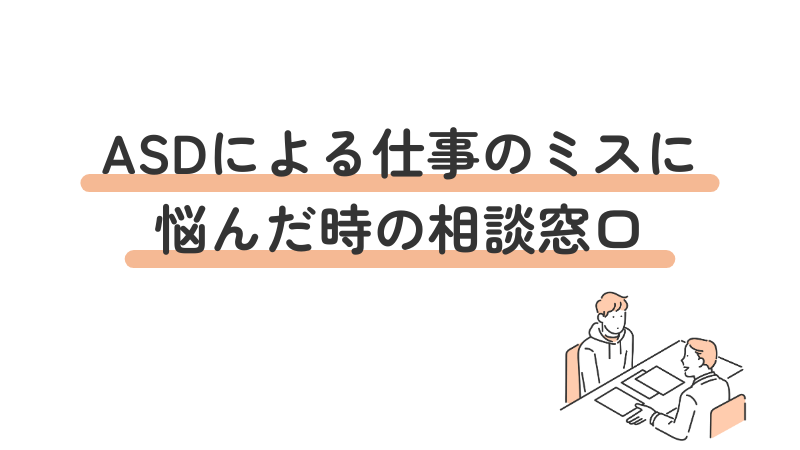
この章のポイント
- ● 仕事や生活の不安は職場の相談先や公的機関で相談できる
- ● 特性を伝えるときは「具体的な困りごとベース」で伝えることで、理解や配慮を得やすくなる
ここでは、仕事や生活の不安を感じた時に相談できる主な窓口をご紹介します。
職場の相談先を活用する
まずは、身近な職場の中に相談できる人や窓口がないか確認してみましょう。会社によっては、働き方や体調に関する悩みをサポートする体制が整っている場合があります。
| 相談先 | 相談できる内容例 |
|---|---|
| 人事・労務・総務部門 | 勤務時間の調整、業務内容の変更、休職制度や配慮の申請など |
| 産業医 | 医療的な視点からのアドバイス、職場での困りごとの相談、中立的な意見の提供など |
| 保健師・社内カウンセラー | ストレスや不調の相談、メンタル面での支援、外部機関の紹介など |
職場に開示しなくても特性を伝えるコツ
ASD(自閉スペクトラム症)という言葉を使わなくても、「こういう作業が少し苦手で…」と具体的な困りごとベースで伝えてみるのもおすすめです。
例えば、
- 急な予定変更があると、頭が真っ白になってしまうことがあって…
- 同時にいろいろ指示されると混乱しやすくて…
- “ざっくりで”と言われると、どこまでやればいいか迷ってしまって…
このように、「自分のせい」ではなく「状況に対してこういう反応が起きやすい」という表現を使うと、相手にも伝わりやすくなります。
また、お願いする形で伝えるのもいいかもしれません。
- なるべく事前にスケジュールを共有していただけると助かります
- 指示があるときは、可能であれば順番をつけてもらえるとありがたいです
相談するタイミング
特性に関する相談は、「困ってから言う」よりも「少し引っかかった時点で軽く伝える」のが理想です。
例えば、
- 上司との1on1面談や月1の面談タイミング
- 新しい業務を任された時
- トラブルやミスが起きた直後(落ち着いてから)
「すみません、最近ちょっと気になっていて…」という伝え方で「気づきの共有」をすると、深刻に受け取られすぎずに話しやすくなります。
また、直接口頭で言いづらい場合は、メモやチャットで伝えるのも良い方法です。
例えば、
ちょっと苦手意識がある部分がありまして…共有させてください。
対応が遅くなった原因を自分なりに振り返ってみました。
公的な支援機関を利用する
「職場に相談しづらい」「いきなり病院に行くのはハードルが高い」という方は、自治体や国が設けている支援機関に相談することもできます。
| 支援機関名 | 主な相談内容・特徴 |
|---|---|
| 発達障害者支援センター | 発達障害に関する幅広い相談に対応。本人だけでなく家族の相談も可能。医療・就労支援などの情報提供も。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 仕事と生活の両面からサポート。就労の継続や安定した暮らしについての相談ができる。 |
| ハローワーク(障害者窓口) | 障害者専用の窓口があり、就職活動の相談や職場への定着支援、面接練習なども可能。 |
| 就労移行支援事業所 | 就職を目指す障害のある方向けに、ビジネスマナー、職業訓練、職場体験などのサポートを実施。 |
就労移行支援ってどんな所?
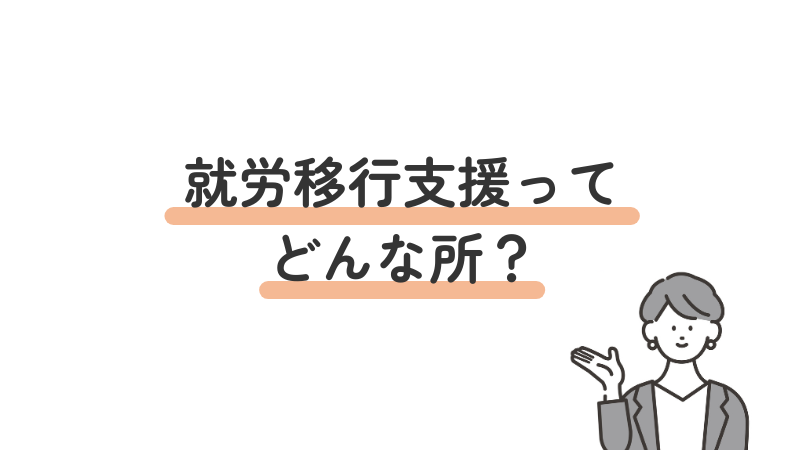
この章のポイント
- ● 就労移行支援は、精神・発達障害などで働きづらさを感じる方が、一般就労を目指して訓練・サポートを受けられる福祉サービス
- ● スキル学習や就職活動のサポート、在宅訓練、定着支援などを通じて、「自分らしく働く」ための準備ができる
就労移行支援とは、発達障害やうつ病などの精神的な困りごとを抱える方が、一般企業への就職を目指して利用できる福祉サービスのひとつです。厚生労働省の制度に基づいて運営されており、就労に向けた訓練やサポートを受けられます。
就労移行支援を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
| 利用対象 | 詳細 |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上65歳未満の方 |
| 状況 | 一般企業への就職を目指している方 |
| 障害の有無 | 精神障害・発達障害・知的障害・身体障害などがあり、就労に支援が必要とされる方 |
| 手続き | お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を交付されていること |
※障害者手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できる場合があります。詳しくは自治体の窓口にご確認ください。
就労移行支援manabyについて
就労移行支援manaby(マナビー)では、ASD(自閉スペクトラム症)をはじめ、発達障害・精神障害・適応障害・難病などのある方を対象に、「自分に合った働き方」を一緒に見つけながら、就職に向けたサポートを行っています。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した、自宅でもできるスキル学習
- Webデザインやプログラミングなど、IT系のスキル習得
- 通所が難しい方への在宅支援や、柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の可否は、お住まいの自治体によって異なります - 履歴書の書き方や面接練習など、就職活動のサポート
- 働き始めた後も、6か月間の定着支援でフォロー
「仕事でミスが多くて落ち込んでしまった…」「急な予定変更が苦手で、職場に馴染めるか不安…」「人とのやりとりに疲れてしまい、長く働き続けられるか心配…」といった悩みを抱えているのは決してめずらしいことではありません。
就労移行支援manabyでは、「どんな働き方なら、自分らしく、無理なく続けられそうか」を一緒に考えていきます。まずは、「今こんなことで困っていて…」と話していただくだけでも大丈夫です。少しでも気になった方は、どうぞお気軽にご相談ください。
ASD(自閉スペクトラム症)によるミスは「仕組み」で減らせる
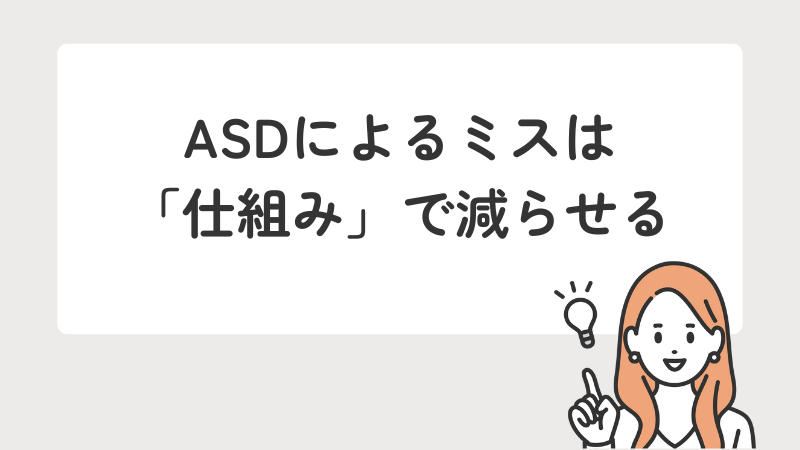
ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある方は、あいまいな指示や急な予定変更、複数の作業が重なる場面などで、混乱やミスが起きやすくなる傾向があります。
こうしたミスは、注意力が足りないからではなく、情報の受け取り方や思考の進め方に特性があるために起こりやすいものです。
そのため、大切なのは「もっと気をつけること」ではなく、ご自身に合った方法や仕組みを取り入れていくことです。
タスクを見える形で整理したり、報告や確認のタイミングを決めておいたりすることで、ミスを減らす工夫は十分可能です。
また、必要に応じて職場での伝え方を工夫したり、就労支援や相談機関などのサポートを利用することで、より働きやすい環境を整えていくこともできます。
無理にすべてを一人で抱え込むことは危険です。皆さんの周りには親身になって相談に乗ってくれる人や場所がたくさんあります。どうすれば働きやすくなるのか、どうしたらもっと自分らしく生きられるのかをたくさんの人と一緒に考え、ご自身のペースで、「自分に合った働き方」を少しずつ見つけていくことが大切です。