社会不安障害(社交不安障害/SAD)に向いている仕事とは?特徴・おすすめ職種を解説

- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)とは?原因・具体的な症状
- 社会不安障害の方が仕事で直面しやすい困りごと6選
- 人前で話すことが怖い、会議やプレゼンが苦痛
- 電話対応や接客など、不特定多数とのやり取りが苦手
- 人の視線が気になって、集中力が続かない
- ミスを過剰に気にしてしまう
- 急な予定変更や臨機応変な対応するのが難しい
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が働きやすい環境・働き方を紹介
- 障害や特性に理解がある職場
- ルーティンワークで、急な予定変更が少ない仕事
- 自分のペースで作業を進められる仕事
- 柔軟な働き方ができる職場
- 静かで落ち着いた環境
- 人前で話す機会や、初対面とのやり取りが少ない仕事
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事とは?おすすめの職種
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事1:コツコツ集中できる仕事
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事2:静かな環境で働ける仕事
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事3:自分のスキルや得意を活かせる仕事
- 自分に向いている仕事を見つけるには
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が仕事を始めるタイミングとは? 判断のポイント
- 「人と会うのが怖い」という気持ちが落ち着いている
- 主治医から「働いてもいい」という診断・許可が出ている
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が仕事について相談できる機関
- 就労移行支援
- manabyの就労移行支援について
- ハローワーク
- 障害者雇用専門の転職エージェント
- その他の相談機関
- 社会不安障害(社交不安障害/SAD)と向き合いながら、自分らしく働くために
「朝になると胸が苦しくなり、仕事に行こうとするたびに涙が出る」「会議の前日は、失敗が怖くて眠れない」「同僚の態度に敏感に反応して、嫌われたかもと仕事中も頭から離れない」と悩みながら、毎日仕事に向き合ってきた方も多いのではないでしょうか。
多くの方は、社会不安障害(社交不安障害/SAD)の症状を「自分の甘え」だと誤解し、限界まで仕事を続けてしまいます。しかし、社会不安障害(社交不安障害/SAD)は本人の努力不足や気の持ちようではなく、誰にでも起こりうる心の病気です。
この記事では、社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方が仕事で直面しやすい困難や、無理のない環境・働き方について解説します。さらに、社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている職種の例や、仕事を始めるタイミングの判断ポイントもあわせてご紹介します。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)とは?原因・具体的な症状
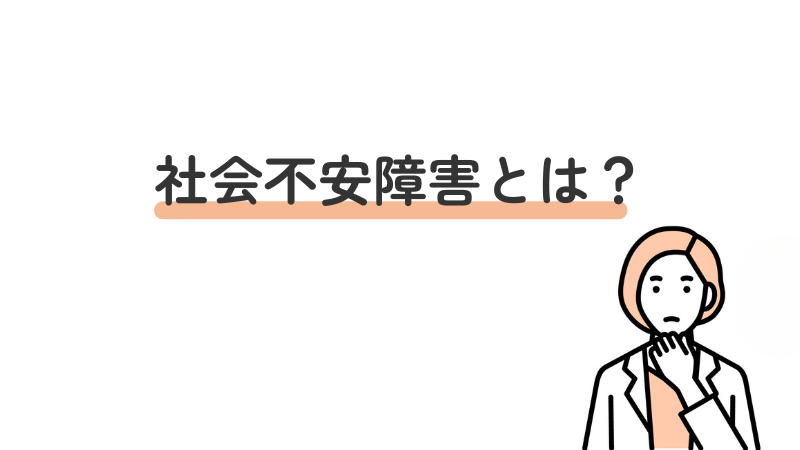
社会不安障害(社交不安障害/SAD)とは、人前で注目されたり、評価されたりする状況に強い不安や恐怖を感じる精神疾患です。
会話や発表、電話応対、食事など日常的な場面でも強い緊張を覚え、「恥をかくのでは」「変に思われるのでは」といった不安にとらわれます。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の原因は一つではなく、過去の失敗体験や性格傾向、環境要因などが複雑に影響し合って発症すると考えられています。
症状の現れ方は人によって異なりますが、一般的には次のような場面で強い不安や身体症状が出ることがあります。
- 会議で発言する場面で、顔が赤くなったり、声が震えてうまく話せない
- 上司や同僚と話す前に「変に思われたらどうしよう」と不安で頭が真っ白になる
- 電話をかけたり受けたりするだけで、強い緊張や動悸を感じる
- 人前で作業をするときに「失敗したら見られている」と感じて手が震える
- 外食時やレジでのやりとりでも「注目されている」と感じて落ち着かなくなる
- 人の視線や態度のちょっとした変化に敏感に反応し、「嫌われたかも」と長時間悩む
- 不安で出勤前にお腹が痛くなったり、涙が止まらなくなることがある
このような状態が続くと、日常生活や仕事をすることが難しくなり、休職・退職するケースも少なくありません。
社会不安障害の方が仕事で直面しやすい困りごと6選
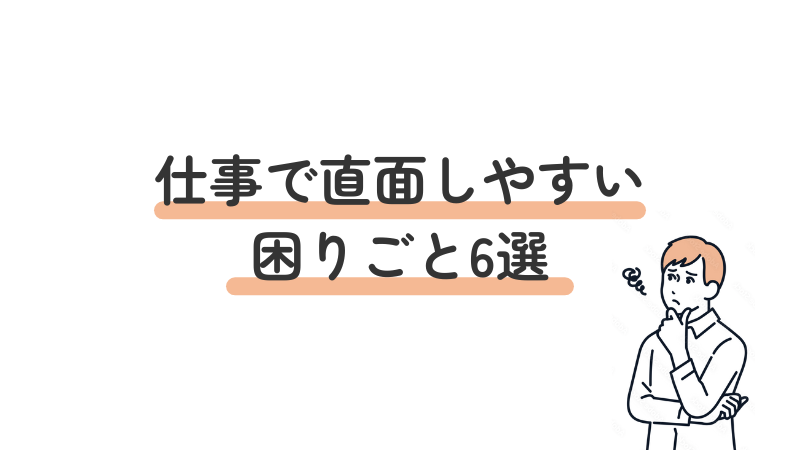
社会不安障害(社交不安障害/SAD)があると、仕事の中で「普通ならなんでもないこと」に強いストレスや不安を感じてしまうことがあります。
例えば、人前で発言することや、上司とのちょっとした会話でさえ緊張し、終わったあとも「変に思われたかもしれない」と何度も思い返してしまう・・・ということも珍しくありません。
これは、「注目されること」や「人にどう思われるか」に対する恐怖心が根底にあるためで、自分の意思だけでコントロールするのが難しいことも多いのが特徴です。
このような不安や緊張が日常的に続くと、仕事に集中できなかったり、作業に時間がかかるだけでなく、体調を崩したりして仕事が続かないという悩みに発展することもあります。
ここでは、社会不安障害のある方が仕事で直面しやすい困りごとを6つ紹介します。
- 人前で話すことが怖い、会議やプレゼンが苦痛
- 電話対応や接客など、不特定多数とのやり取りが苦手
- 人の視線が気になって、集中力が続かない
- ミスを過剰に気にしてしまう
- 急な予定変更や臨機応変な対応をするのが難しい
参考:国立精神・神経医療研究センター「社交不安障害とは」、厚生労働省「不安障害」
人前で話すことが怖い、会議やプレゼンが苦痛
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとって、会議やプレゼンなど人前で話す場面は大きなストレスになります。
「意見を求められたらどうしよう」と前日から不安になり眠れなくなったり、発言の順番が近づくたびに動悸や手の震えが止まらなくなったりすることもあります。
実際に話す場面では、頭が真っ白になって言葉が出てこない、声が震えて自分でも焦ってしまうといった症状が現れやすく、会議後も「変に思われたかも」と一日中気にしてしまうことも少なくありません。
こうした恐怖や不安が積み重なることで、「また失敗したらどうしよう」「この先もずっとこんな状態なのでは」と感じてしまい、会議や人前で話す場面を避けるようになったり、仕事を続けること自体が辛くなってしまう方もいます。
電話対応や接客など、不特定多数とのやり取りが苦手
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、相手が誰か分からない、不特定多数とのやり取りに強い不安を感じることがあります。
例えば、会社の代表電話を取るときに「声が震えたらどうしよう」「失礼な対応をしてしまうかも」と不安が押し寄せ、電話が鳴るたびに心臓がドキッとするような緊張に襲われることがあります。
接客や受付業務でも、相手の反応を過度に気にしてしまい、何を話せばいいかわからなくなる、笑顔が引きつってしまうといったことが起こることもあります。
このような状況が続くと、「また失敗したらどうしよう」という不安から、電話や接客を避けるようになり、業務そのものへの自信を失ってしまうこともあります。
人の視線が気になって、集中力が続かない
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、自分が人からどう見られているかを常に気にしてしまう傾向があり、周囲の視線があるだけで緊張してしまうことがあります。
例えば、オフィスで誰かが近くを通っただけで「今の自分の姿、変じゃなかったかな」「変に思われたかも」と気になり、目の前の作業に集中できなくなることがあります。
特に、人の多い職場やオープンスペースでは、常に誰かに見られているような感覚にとらわれてしまい、タイピングの音や姿勢ひとつにも過剰に意識が向いてしまうことがあります。
こうした状態が続くと、仕事のパフォーマンスが下がるだけでなく、「職場にいるだけで疲れる」「自分はこんな簡単なこともできない」と自己否定が強まり、「このまま働き続けるのは難しいかもしれない」と思い悩んでしまいます。
ミスを過剰に気にしてしまう
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、小さなミスでも「取り返しがつかないことをしたのでは」と過剰に不安を感じやすい傾向があります。
例えば、メールの表現や言い回しが気になって何度も見直してしまったり、上司に提出する資料を慎重にチェックしすぎて、「もし間違っていたら怖い」と手が止まってしまうこともあります。
その結果、仕事に必要以上の時間がかかり、まわりのペースについていけないことが続くと、「自分には向いていない」「仕事が続かないかもしれない」と感じてしまうことがあります。
さらに、不安や疲労が蓄積すると、「もう怖くて出社できない」「今日は休みたい」という状態が増え、最終的には仕事に大きな支障をきたすことになってしまいます。
急な予定変更や臨機応変な対応するのが難しい
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、予定していないことが起こると強い不安を感じやすく、急な変更やイレギュラーな対応が大きな負担になります。
例えば、「今すぐ対応してほしい」と突然頼まれたり、急に会議の時間が変更になっただけで、頭の中が真っ白になってしまい、どう動けばいいか分からなくなることがあります。
もともと綿密に準備して安心を得るタイプの方が多いため、「段取り通りに進まない」こと自体が怖さにつながり、焦りや混乱を引き起こします。
こうした状態が続くと、「臨機応変に対応できない自分はダメだ」と感じ、自信をなくしてしまいます。
さらに、「また急な対応があるかも」と思うだけで緊張が高まり、仕事に行くのが怖くなったり、休みがちになるケースもあります。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が働きやすい環境・働き方を紹介
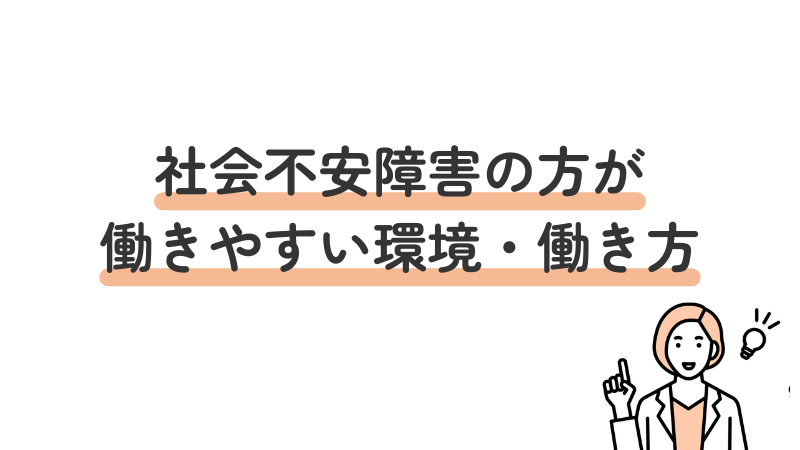
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、仕事の中で人との関わりや予期せぬ対応に強いストレスを感じやすく、日常的な業務でも不安や緊張に悩まされています。
前の章で紹介したように、「人前で話すことが苦痛」「電話対応が怖い」「視線が気になって集中できない」といった困りごとが積み重なると、働き続けること自体が難しくなるケースもあります。
そこでここからは、社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方がより安心して働くために重要な職場環境や働き方の特徴について、具体的にご紹介します。
障害や特性に理解がある職場
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとって、周囲の理解があるかどうかは、働きやすさを大きく左右する要素のひとつです。
ちょっとした声かけや、人とのやりとり、突然の予定変更など、周囲にとっては当たり前のことでも、社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方にとっては大きなストレスになることがあります。
そのため、障害や特性に理解のある職場なら気持ちに余裕を持って、自分に合った働き方がしやすくなります。
具体的には、障害者雇用枠での就労や、障害のある方が働きやすいように配慮された特例子会社が選択肢として挙げられます。
- 障害者雇用:障害のある方が、企業の配慮のもとで働く制度。仕事内容や勤務時間を調整できる。
- 特例子会社:障害のある方が働きやすいように設立された、親会社の特別なグループ会社。支援体制が整っているのが特徴。
このような仕組みを活用すれば、社会不安障害(社交不安障害/SAD)があっても、自分の特性に合った環境で無理なく働くことが可能になります。
「一般の職場はハードルが高い」と感じる場合でも、まずはこうした制度のある職場からスタートしてみるのも1つの選択肢です。
ルーティンワークで、急な予定変更が少ない仕事
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとっては、日々の業務があらかじめ決まっていて、予定外の対応が少ない仕事のほうが安心して取り組みやすい傾向があります。
ルーティンワーク中心の仕事は、業務内容がある程度決まっているため、「今日は何をするんだろう」といった不安を抱えることが少なくなります。
また、急な変更や臨機応変な対応が求められにくいので、事前に心の準備をしながら自分のペースで進めやすいのも特徴です。
自分のペースで作業を進められる仕事
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとって、時間や進め方を自分である程度コントロールできる仕事は、精神的な負担が少なくなりやすい傾向があります。
決まった作業を黙々とこなす仕事や、納期だけが決まっていて「何時までにやって」と細かく指示されない業務であれば、焦らず落ち着いて進めやすく、緊張や不安も感じにくくなります。
また、周囲のスピードに合わせる必要がない仕事や、一人で完結できる作業も、自分のリズムで働きやすい環境といえるでしょう。
柔軟な働き方ができる職場
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方の中には、日によって体調や気分の波が大きく、決まった時間・場所で働くことが負担になる場合もあります。
例えば「朝の通勤だけでぐったりしてしまう」「体調は悪くないのに、人に会うことを考えると出勤できない」といった悩みを抱えることも少なくありません。
そのため、働く時間や出勤日数、勤務場所に柔軟さのある職場のほうが、継続して働きやすいと感じる方が多い傾向があります。
最近では、短時間勤務や週2~3日勤務、在宅ワークを取り入れている企業も増えており、体調に合わせて働くスタイルを選べるケースもあります。
「毎日決まった時間に出勤しなければいけない」と思わず、自分に合ったペースで働ける環境を選ぶことが、安定して仕事を続けるポイントになります。
静かで落ち着いた環境
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとっては、常に人の話し声が聞こえたり、電話の音が鳴り続けたりするような賑やかな環境では、気が散ったり、不安が増してしまうことがあります。
例えば、「周囲の雑音が気になって集中できない」「誰かに話しかけられるのではと落ち着かない」と感じてしまい、仕事に集中するのが難しくなることもあります。
そのため、静かで人の出入りが少ない、落ち着いた雰囲気の職場のほうが、自分のペースで安心して作業を続けやすい傾向があります。
- 私語や電話応対が少ないバックオフィスや作業スペース
- パーテーションや個別ブースのある職場
- 作業中に話しかけられにくい雰囲気の職場(例:スキャン・清掃・軽作業など)
このような環境だと周囲を気にしすぎず、落ち着いて仕事に集中しやすくなります。
人前で話す機会や、初対面とのやり取りが少ない仕事
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方にとっては、「初対面の人と話す」「とっさに対応する」といった場面に強い不安や緊張を感じることが少なくありません。
例えば、電話応対や接客、受付などでは、相手の反応を過剰に気にしてしまったり、「うまく話せなかったらどうしよう」と不安になり、仕事が始まる前から疲れてしまうという声も多くあります。
そのため、やり取りをする相手が限定されていたり、基本的に会話が少ない仕事のほうが、気持ちが落ち着いて働きやすくなる傾向があります。
人と関わること自体がストレスになる場合は、「人との接触が少ない」「一人で完結する作業が多い」という職場だと働きやすいです。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事とは?おすすめの職種
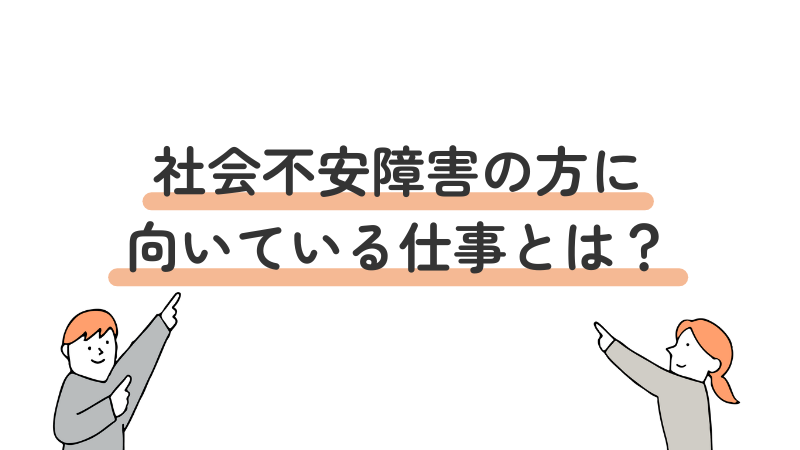
働く上での不安や苦手な場面をできるだけ減らし、自分の特性に合った環境を選ぶことは、長く安心して働くためにとても重要です。
これまで紹介してきたように、社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方が働きやすい職場には、以下のような特徴があります。
- ルーティンワークで、急な予定変更が少ない
- 自分のペースで作業を進められる
- 短時間勤務や在宅勤務など、柔軟な働き方ができる
- 静かで落ち着いた環境
- 人前で話す機会や、初対面とのやり取りが少ない
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事1:コツコツ集中できる仕事
| 職種 | 特徴・仕事内容 |
|---|---|
| データ入力 | 決まったフォーマットに入力。会話が少なく一人で黙々とできる。 |
| 書類のスキャン・仕分け | 紙の書類を電子化・分類。ルーティン作業中心 |
| 文書管理 | ファイリングや保管作業など |
| 清掃スタッフ | 一人作業が中心。人との接触が少なく、マイペースに取り組める |
| 軽作業(シール貼り・検品など) | 単純作業の繰り返し。集中しやすく変化が少ない |
| 倉庫内作業 | ピッキングや梱包など、人との会話が少なく作業に集中しやすい |
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方は、データ入力、書類のスキャン・仕分け、文書管理、清掃スタッフ、軽作業、倉庫内作業など、会話が少なく、一人で黙々と進められ、集中して取り組める仕事がおすすめです。
これらの職種は、障害者雇用枠や特例子会社でも比較的求人が多く見つかる傾向にあり、就職先として選ばれやすい仕事でもあります。
また、障害者雇用枠や特例子会社では、個々の特性に応じた配慮を受けながら働くことができる職場も多く、初めての就職や職場復帰にも適しています。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事2:静かな環境で働ける仕事
| 職種 | 特徴・仕事内容 |
|---|---|
| 図書館スタッフ(裏方) | 本の整理や棚入れなど |
| 工場の検品・検査 | 手順が決まった作業。静かで緊張の少ない職場が多い |
| 文書管理・ファイリング | 整理・保管中心の業務 |
| 備品管理・チェック | 決まったルート・スケジュールで物品を確認する。会話も最小限。 |
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方は、図書館スタッフ、工場の検品・検査、文章管理・ファイリング、備品管理・チェックなど、音や人の気配に敏感な方でも比較的安心して働きやすい仕事です。
作業の手順が決まっていて、突然の対応や人とのやり取りが少ないため、緊張や不安を感じにくく、落ち着いて業務に取り組みやすく、おすすめです。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方に向いている仕事3:自分のスキルや得意を活かせる仕事
| 職種 | 特徴・仕事内容 |
|---|---|
| 画像チェック・文字校正 | 集中力を活かせるパソコン作業。在宅可の求人もあり |
| Webライター | 章作成を自宅で行える在宅ワーク。会話なしで作業できる |
| イラスト制作・デザイン補助 | 自分のペースで創作に取り組める仕事 |
| プログラミング | 静かな環境でスキルを活かせる専門職。非対面中心の働き方も可能 |
| 経理補助 | 正確な処理を求められるが、会話は少なくルールに沿って進めやすい |
画像チェックや文字校正、Webライター、イラスト制作・デザイン補助、プログラミング、経理補助などの仕事は、非対面でのやり取りが中心だったり、在宅ワークとして取り組めるものが多くあります。
人と直接話す機会が少ないため、社会不安障害のある方にとっても、比較的負担が少なく取り組みやすい仕事といえるでしょう。
自分に向いている仕事を見つけるには
3つのタイプに分けて適職の例を紹介しましたが、大切なのは、「この仕事が向いている」と決めつけることではなく、自分が安心して働ける条件を見つけ、その条件に近い仕事を選ぶことです。
「これしか選べない」と思い込まず、少しずつ仕事を経験しながら、自分にとっての適職を探していくことが、無理なく働き続けるためのポイントとなります。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が仕事を始めるタイミングとは? 判断のポイント
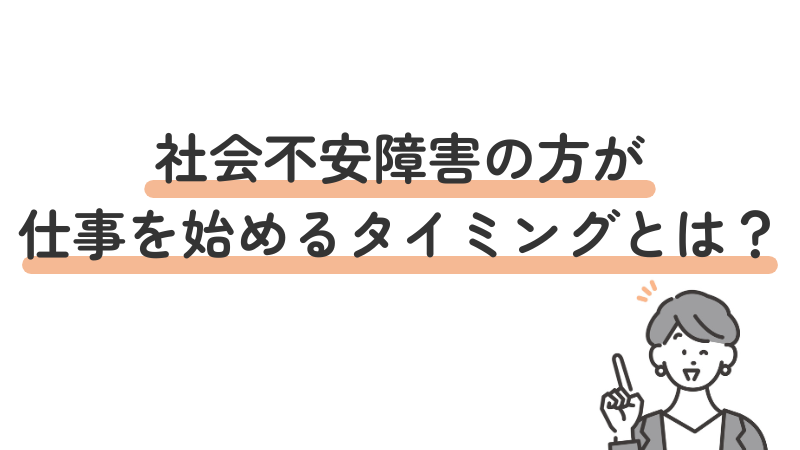
社会不安障害(社交不安障害/SAD)があると、「また人間関係で失敗したらどうしよう」「仕事を始めるのが怖い」と感じて、なかなか一歩を踏み出せないことがあります。
不安が完全になくなるのを待つのではなく、「少しならやってみたい」と思える状態かどうかが、仕事を始めるひとつの判断材料になります。
ここでは、仕事を始めるタイミングを見極めるための具体的なポイントを2つご紹介します。
「人と会うのが怖い」という気持ちが落ち着いている
社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方の中には、知らない人と話したり、職場で誰かとすれ違うだけでも、「怖い」「緊張する」と感じてしまう方が少なくありません。
しかし、「人と会うのが怖い」という気持ちが少しずつ落ち着いてきたと感じるようになれば、それは仕事を始めるタイミングを考えるサインのひとつです。
例えば、「短時間なら外出できるようになった」「一言だけなら挨拶できそう」といった小さな変化でも、自分の中で前に進んでいる証拠です。
不安が完全になくなることはなくても、「なんとかやってみよう」と思える瞬間があるかどうかが、次のステップを考える目安になります。
主治医から「働いてもいい」という診断・許可が出ている
自分では「もう働けるかも」と思っていても、主治医の見解を仰ぐことはとても大切です。
体調や気分の波、生活リズムなどを診断や経過観察を通じて総合的に見てもらったうえで、主治医から「働いても大丈夫」と言われたタイミングであれば、安心して次のステップを考えやすくなります。
不安が残っていても、「短時間からならOK」「週に数日から始めよう」といった提案をもらえることもあります。
1人で抱え込まず、専門家と相談しながら決めていくことが、無理なく仕事を始めるための大事なポイントです。
社会不安障害(社交不安障害/SAD)の方が仕事について相談できる機関
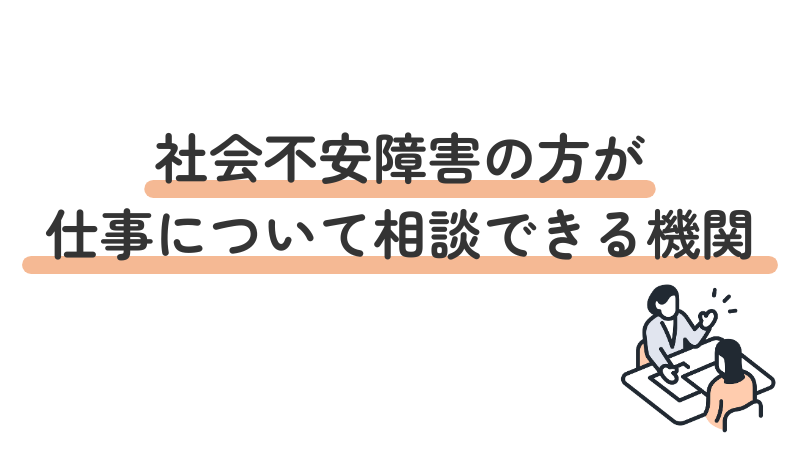
「働くのが怖い」「制度がよくわからない」「このままで大丈夫なのかな」と社会不安障害(社交不安障害/SAD)のある方は、日常の不安に加えて、仕事や生活、将来について一人で悩みを抱えてしまいやすい傾向があります。
そんなときは、一人で抱え込まず、専門の機関や支援サービスを活用することがとても大切です。
就労移行支援
就労移行支援は、障害や体調に不安のある方が、自分のペースで働く準備ができる福祉サービスです。
「働くことが怖い」「ブランクがある」「どんな仕事が向いているかわからない」といった悩みにも寄り添いながら、就職に向けたサポートが受けられます。
利用には自治体の手続きが必要ですが、障害者手帳がなくても利用できる場合もあり、社会不安障害の診断を受けている方であれば対象になることが多いです。
「すぐに働けなくても大丈夫」「まずは通うところからでいい」という考え方に基づいているため、働くことへの不安が強い方にも安心して利用しやすい支援です。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manaby(マナビー)では、社会不安障害(社交不安障害/SAD)をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方が自分らしく働くための支援を行っています。
1人ひとりの特性や不安に合わせた個別支援を大切にしており、「自分に合った働き方」を一緒に見つけていくことを重視しています。
例えば、以下のような支援を通じて、安心して働く準備ができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
-
通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否についてはお住まいの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「働くのが不安」「自分に合う職場がわからない」と働くことへお悩みがある方はぜひ、お気軽にご相談ください。
ハローワーク
ハローワークとは、国が運営する就職支援機関で、誰でも無料で利用することができます。
求人紹介や職業相談、応募書類の添削、面接対策など、就職に関する幅広いサポートを受けることができます。
ハローワーク内には障害のある方向けた専門の窓口もありますので、よりきめ細かな支援を受けることも可能です。
障害者雇用専門の転職エージェント
障害者雇用に特化した転職サポートのサービスもあります。
社会不安障害のある方も対象となっており、精神障害・発達障害に理解のあるキャリアアドバイザーが担当してくれるため、自分の症状や特性に合った働き方や職場環境を一緒に考えてくれるのが大きなポイントです。
その他の相談機関
就労移行支援、ハローワークや転職エージェント以外にも社会不安障害のある方が相談できる支援機関があります。
- 精神保健福祉センター:病気に関する相談や支援制度の案内を受けられる
- 障害者就業・生活支援センター:仕事と生活の両面から就労をサポートしてくれる支援機関
- お住まいの市区町村の障害福祉課:手帳・医療費・支援制度など公的手続きへの相談ができる
社会不安障害(社交不安障害/SAD)と向き合いながら、自分らしく働くために
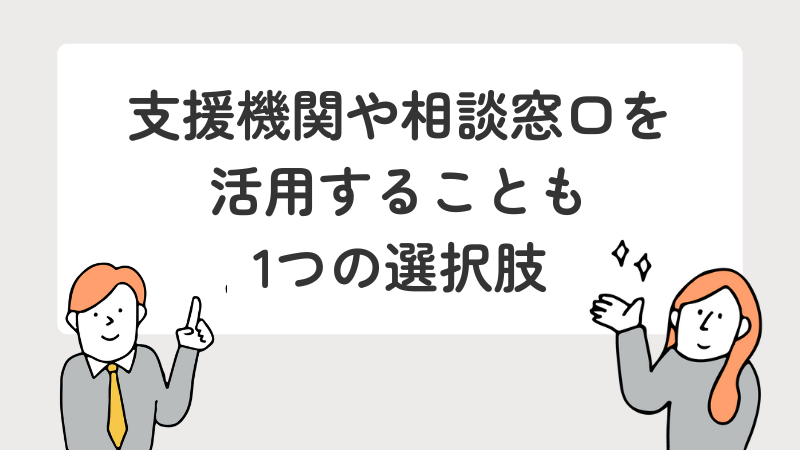
社会不安障害(社交不安障害/SAD)があると、働くことへの強い不安やストレスを感じやすく、周囲から理解されにくい場面も少なくありません。
「自分に合った仕事がわからない」「また辛い思いをするのでは」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そんな時は、ひとりで抱え込まずに、支援機関や専門の相談窓口を活用することも1つの選択肢です。
今すぐ就職を目指す必要はありません。
まずは情報を集めたり、誰かに気持ちを話してみたりするだけでも、少し気持ちが軽くなることがあります。
焦らず、自分にとって無理のない選択肢を見つけていきましょう。






