ASD(自閉スペクトラム症)の方が仕事で「できない」と感じる理由と対策を徹底解説

- ASD(自閉スペクトラム症)の方が仕事ができないと感じる時の対策
- 出勤前の対策
- 仕事中の対策
- 専門的なサポート・環境調整
- ASD(自閉スペクトラム症)の方が抱える仕事の悩み
- 人間関係や職場の空気を読むのが苦手
- 急な予定変更や曖昧な指示に対応しづらい
- 感覚過敏によるストレス(音・光・においなど)
- こだわりが強く柔軟な対応が苦手
- 同時に複数の作業を進めるのが難しい
- 疲れやすく、気力が続かないことがある
- ASD(自閉スペクトラム症)の方が「仕事ができない」と感じる理由とは?
- 職場の暗黙のルールや曖昧なコミュニケーションが苦手だから
- 感覚過敏や特定の環境で集中できず、パフォーマンスが落ちるから
- 周囲との違いに悩み、自己肯定感が下がりやすいから
- そもそもASD(自閉スペクトラム症)とは?
- ASD(自閉スペクトラム症)の主な特徴
- ASD(自閉スペクトラム症)かも?と思ったら病院に行くべき?
- 診断を受けるメリット
- 診断を受けるデメリット
- 病院に行く前に知っておきたいこと
- ASD(自閉スペクトラム症)の方に向いている仕事と働き方
- 「仕事が辛い…」と感じた時の選択肢
- 心と身体に限界を感じたら「休職」もひとつの手段
- 転職を考える前に、自分の特性や働き方の希望を整理してみる
- 迷ったら「支援機関」や「医療機関」に話を聞いてもらう
- 仕事への悩みがあるASD(自閉スペクトラム症)の方が利用できる就労移行支援
- 就労移行支援manabyについて
- 環境や支援で、ASD(自閉スペクトラム症)の「働きにくさ」は変えられる
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、「仕事がうまくできない」「指示通りに動けない」「周囲と同じようにできない」と感じて悩む場面が少なくありません。
こうした「できない」という感覚の背景には、ASD(自閉スペクトラム症)特有の感じ方や考え方の違いによって生じる困りごとが関係していることも多くあります。
この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)の特性が仕事にどう影響するのかを丁寧にひもときながら、「自分だけできない」と感じてしまう原因や、仕事での不安をやわらげるための対策、さらには支援制度の活用方法まで、わかりやすく解説していきます。
この記事のまとめ
-
●
ASD(自閉スペクトラム症)の方が仕事に悩んだときの対策
出勤前・仕事中・専門機関の活用など、場面ごとにできる工夫をする -
●
ASD(自閉スペクトラム症)の特性に合った働きやすい職場環境とは
明確な業務内容・静かな環境・配慮ある職場など
ASD(自閉スペクトラム症)の方が仕事ができないと感じる時の対策
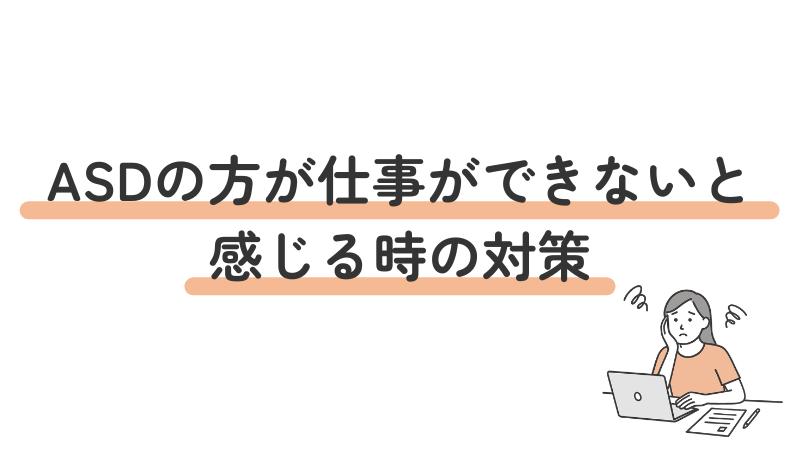
この章では、ASD(自閉スペクトラム症)の方が職場で直面しやすい具体的な課題と、それに対して取り組める対策について紹介します。
出勤前の対策
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、朝の準備や出勤までの流れで混乱しやすい、予定外のことがあると気持ちが乱れてしまうといった悩みを抱えている方がいます。
これは、ASD(自閉スペクトラム症)の特性として「予定やルールが決まっていると安心できる」という傾向があるため、朝のルーティンが乱れることで心の準備が追いつかず、不安や焦りにつながってしまうことがあるからです。
こうした問題をやわらげるためには、朝の行動パターンをあらかじめ決めておくことが効果的です。以下に、取り入れやすい工夫と期待できる効果をまとめました。
| 悩み事 | 対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 朝の準備中に何から手をつければいいか分からず混乱する | 起床〜出勤までの流れをメモやタイマーで可視化する | やるべきことが明確になり、混乱や焦りを減らせる |
| 朝、着る服や持ち物を考えるのに時間がかかってしまう | 前日のうちに服や持ち物を準備しておく | 朝の選択によるストレスを軽減し、余裕をもって準備できる |
| 出勤前になると緊張や不安で気持ちがざわつく | 通勤前に深呼吸や音楽などでリラックスする時間をつくる | 不安を落ち着け、出勤への緊張を和らげる |
仕事中の対策
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、業務中に「集中力が続かない」「些細なことが気になって作業が止まってしまう」といった困りごとを感じている方も少なくありません。
これは本人の努力不足ではなく、ASD(自閉スペクトラム症)特有の感覚過敏や、一度に複数の情報を処理することの苦手さなどが背景にあることが多いです。そのため、一般的な職場環境や業務の進め方が、大きなストレスの原因になってしまうことがあります。
こうした困難をやわらげるためには、自分の特性に合わせて、仕事の進め方や職場環境に工夫を取り入れることが効果的です。
| 悩み事 | 対策 | 効果 |
|---|---|---|
| 作業が多く、何から手をつければいいか分からなくなり混乱する | ToDoリストや付箋を使い、作業を「1つずつ」整理する | 作業の全体像を把握しやすくなり、優先順位や手順に迷わず進められる |
| 指示があいまいで、何をすればいいのか分からなくなってしまう | 曖昧な指示はそのままにせず、できるだけ確認・メモを取る | 誤解や混乱を防ぎ、指示通りの行動が取りやすくなる |
| 職場の雑音や話し声などで集中が途切れてしまう | イヤーマフや耳栓で音の刺激を軽減する | 周囲の雑音を遮断し、集中力の維持に繋がる |
| 周囲の人の会話や動きが気になり、作業に集中できない | 集中しやすい席や静かなスペースに移動できるよう相談する | 外的刺激を減らし、自分に合った環境で働ける |
専門的なサポート・環境調整
「どう頑張っても職場でうまくいかない」「周囲と比べて自分だけ浮いている気がする」と感じるとき、個人の工夫だけでは限界があるかもしれません。
そんな時は、外部の専門機関や医療機関を活用するのも有効です。
| 支援・相談先 | 具体的なサポート |
|---|---|
| 産業医や職場の相談窓口 | 座席・業務内容の見直し、業務量の調整などをお願いできる |
| 発達障害者支援センター | 就労・生活の相談全般、職場での困りごとへのアドバイスを受けることができる |
| 就労移行支援事業所 | 自分に合った仕事の訓練、職場体験、就職サポートを受けることができる |
| 医師(診断・意見書) | 診断書をもとに職場と連携し、制度や支援に繋がることができる |
※補足:就労移行支援や支援センターの利用には、地域や年齢、医師の意見書など条件がある場合があります。詳細はお住まいの自治体や福祉窓口に確認しましょう。
ASD(自閉スペクトラム症)の方が抱える仕事の悩み
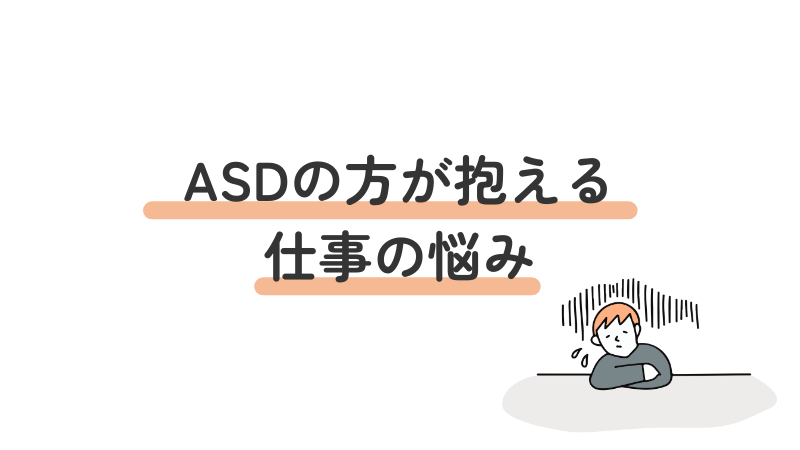
この章では、ASD(自閉スペクトラム症)の方が職場でどのような場面にストレスを感じやすいのか、よくある困りごとを具体的に紹介します。
人間関係や職場の空気を読むのが苦手
ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ方の中には、「表情や言葉の裏にある意図を読み取るのが難しい」と感じる方が少なくありません。
こうした認知の違いから、相手の気持ちに気づけなかったり、自覚のないまま冷たい態度を取ってしまったりすることがあります。
その結果として、「雑談の輪に入れない」「ノリが悪いと思われる」といった場面に直面することもあります。本人は丁寧に対応しているつもりでも、職場での距離感がつかめず、誤解を受けたり、孤立感を抱いたりしやすいのです。
このような人間関係のギャップは、ASD(自閉スペクトラム症)の方にとって大きなストレス要因となり、自信の喪失や「自分は職場に合っていないのでは」といった不安にも繋がってしまいます。
急な予定変更や曖昧な指示に対応しづらい
ASD(自閉スペクトラム症)の方は「今日の会議、30分早まったからよろしく」「この件、ざっくり対応しておいて」といった突然の変更や曖昧な指示に、戸惑ってしまうことがあります。
あらかじめ決められたスケジュールや手順に沿って動くことで安心感を得やすい傾向がある一方で、急な変更や抽象的な表現には不安や混乱を感じやすく、気持ちが追いつかずにパニックになってしまいます。
その結果、作業に手がつかなくなったり、上司や同僚から「話を理解していない」「臨機応変に動けない」と誤解されてしまうことも。
このような状況が続くと、「自分は仕事ができないのでは」「職場に合っていないのかもしれない」といった自己否定につながり、最終的には「仕事を辞めたい」と思い詰めてしまうこともあります。
感覚過敏によるストレス(音・光・においなど)
ASD(自閉スペクトラム症)の特性をもつ方の中には、感覚過敏(聴覚・視覚・嗅覚などの刺激に対して敏感に反応する状態)に悩まされている方も少なくありません。
例えば、周囲の雑音が気になって集中できなくなったり、蛍光灯のまぶしさで頭痛を感じたり、強いにおいで気分が悪くなってしまうといったケースがあります。
さらに、「同僚のキーボードの打鍵音が気になって仕事に集中できない」「制服のタグが肌に触れるだけで不快に感じる」といったように、日常のささいな感覚刺激が強いストレスとなることもあります。
こうした感覚的なストレスは、周囲からは一見してわかりづらく、「大げさ」「神経質」と誤解されてしまうこともあるため、本人が苦痛を言い出しにくく、孤立感を深めてしまう原因にもなることも多いです。
こだわりが強く柔軟な対応が苦手
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、「物事を決まったやり方で進めたい」「手順を変えたくない」といった強いこだわりを持つ傾向が見られることがあります。
このようなこだわりは、本人にとっては「安心して行動できる手順」や「混乱を避けるための工夫」であり、日常生活や仕事の中で安定を保つための大切な要素です。しかし、周囲からは「柔軟性がない」「頑固だ」と誤解されてしまい、対人関係のストレスに繋がることも少なくありません。
例えば、「この順番でないと落ち着かない」「なぜ急にやり方を変えるのか理解できない」と感じたり、「納得できないことは譲れない」「小さなミスが気になって次に進めない」といった思考が、仕事のスピードやチームとの調和に影響を与えることもあります。
同時に複数の作業を進めるのが難しい
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、「一つの作業に集中していると、他のことがまったく入ってこない」「突然話しかけられると、思考が一瞬で止まってしまう」といった特性を持つ方も少なくありません。
職場では、「電話を取りながらデータ入力を行う」「複数の業務を同時に進める」といったマルチタスクが求められる場面が多くあります。しかし、ASD(自閉スペクトラム症)の方にとっては、このような状況が大きな負担や混乱のもとになることがあります。
一度に複数の情報を処理しようとすると、思考が追いつかず、頭が真っ白になってしまったり、「何から手をつければよいのか分からない」といった状態になって動けなくなることもあります。
こうした反応に対して、周囲からは「仕事が遅い」「段取りが悪い」といった誤解を受けてしまうこともあり、強いストレスや疲労、さらには「自分は仕事ができないのでは」といった自己否定感に繋がってしまうこともあります。
疲れやすく、気力が続かないことがある
「他の人は普通にこなしているのに、自分だけぐったりしてしまう」「仕事が終わったら何もできないくらい消耗する」と疲労感を抱えるASD(自閉スペクトラム症)の方もいます。
こうした疲れは、単なる体力の問題ではなく、ASD(自閉スペクトラム症)特有の感覚の敏感さや情報処理の特性からくる「見えないストレス」が影響していることが多いです。
職場では、常に周囲の空気を読もうとしたり、感覚的な刺激(音・光・においなど)に耐えたり、慣れないコミュニケーションに気を配ったりと、目には見えない努力が重なっています。そのため、ただ業務をこなすだけでも、心身に大きな負荷がかかってしまうのです。
特に以下のような職場環境では、疲労が蓄積しやすくなります。
- 人の話し声や雑音が絶えず聞こえる空間での作業
- 頻繁に話しかけられる、集中しにくい環境
- 予定変更や突発対応が多く、先の見通しが立てにくい業務内容
こうした状況が続くと、週の途中で体調を崩したり、出勤前から気分が落ち込んでしまったりすることもあります。
「自分が弱いから疲れるのでは」「社会人として失格なのでは」と自分を責めてしまう方もいますが、それは誤解です。感じている疲労の背景には、ASD(自閉スペクトラム症)の特性に起因するストレスが隠れていることが多くあります。
- 厚生労働省「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン」
- 厚生労働省「発達障害に気付いたら?大人になって気付いたときの専門相談窓口」
- 厚生労働省「発達障害の理解」
ASD(自閉スペクトラム症)の方が「仕事ができない」と感じる理由とは?
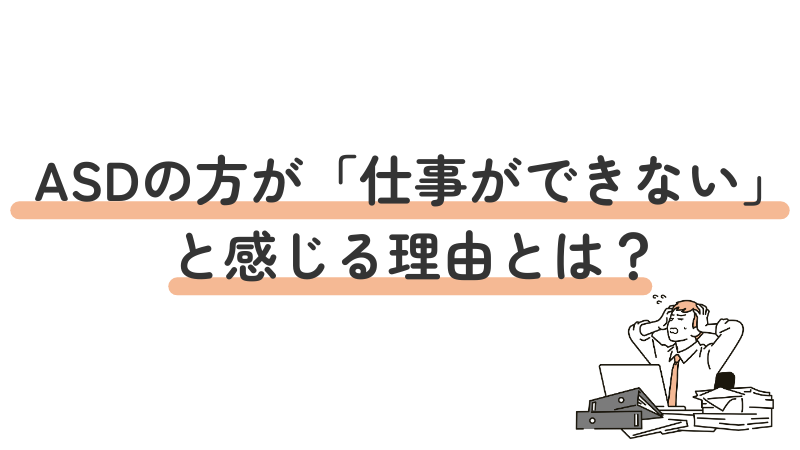
ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、どんなに頑張っても「うまくいかない」「ミスばかりしている気がする」と感じ、自信を失ってしまう方が多くいます。
しかし実際には、「仕事ができない」のではなく、職場環境や業務の進め方がASDの特性に合っていないことが、つまずきの原因になっているケースも多くあります。
この章では、「なぜ自分はこんなに仕事がつらいのか」「なぜミスや誤解が多いのか」と悩む方に向けて、ASD(自閉スペクトラム症)特性に基づく「つまずきの背景」を解説します。
職場の暗黙のルールや曖昧なコミュニケーションが苦手だから
ASD(自閉スペクトラム症)の方にとって、職場に存在する「言わなくても察してほしい」空気や、「なんとなくの共通認識」は大きな壁になることがあります。
例えば、「これ、いつもの感じでやっておいて」「言わなくても分かるよね」といった曖昧な指示は、どこまで・どのように対応すればいいかが明確でなく、混乱や不安を招きがちです。
また、「報連相は空気を読んでタイミングよく」「忙しそうなときは声をかけない方がいい」など、明文化されていない“ルール”が多い職場では、何が正解なのか分からず戸惑ってしまうことも。
こうした曖昧さや暗黙のルールが重なると、「自分だけいつも怒られる」「うまくできないのは自分が悪い」と感じやすくなり、自己否定感が強まってしまいます。
感覚過敏や特定の環境で集中できず、パフォーマンスが落ちるから
ASD(自閉スペクトラム症)の特性のひとつに「感覚過敏」があります。これは、音や光、におい、触覚などに対して、一般的な人よりも強く反応してしまう状態です。
職場では、電話の着信音、複数人の話し声、蛍光灯のちらつき、空調の風音、強い香水など、さまざまな感覚刺激が同時に存在しています。ASDの方にとって、これらは「気にしないようにする」ことが難しく、作業に集中できなくなってしまう原因になります。
「静かだと思っていた職場でも人のタイピング音が気になってしまう」「窓際の光がまぶしすぎて頭がぼーっとする」「人とすれ違うときのにおいで気分が悪くなる」ということも珍しくありません。
このような環境で長時間過ごすと、集中力や思考力が落ちるだけでなく、精神的・身体的な疲労も溜まりやすくなります。その結果、「もっとできるはずなのにうまくいかない」「がんばっても評価されない」といった感情が積み重なり、自信の低下にも繋がります。
周囲との違いに悩み、自己肯定感が下がりやすいから
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、他の人が当たり前にできていることに苦手さを感じたり、自分だけがうまく適応できていないように思えてしまうことがあります。
例えば、「みんなは自然に雑談できているのに、自分は何を話せばいいか分からない」「突然の変更にもすぐ対応している人を見ると、自分は仕事に向いていないのではと落ち込む」といった感覚を抱く場面です。
このような経験が積み重なると、「また迷惑をかけた」「努力しても意味がない」と感じるようになり、自己肯定感が下がってしまいます。
実際には、「本人に能力がない」わけではなく、「特性と環境の相性」や「コミュニケーションのすれ違い」が原因であることも多いです。しかし、当事者はそのことに気づきにくく、一人で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。
そもそもASD(自閉スペクトラム症)とは?
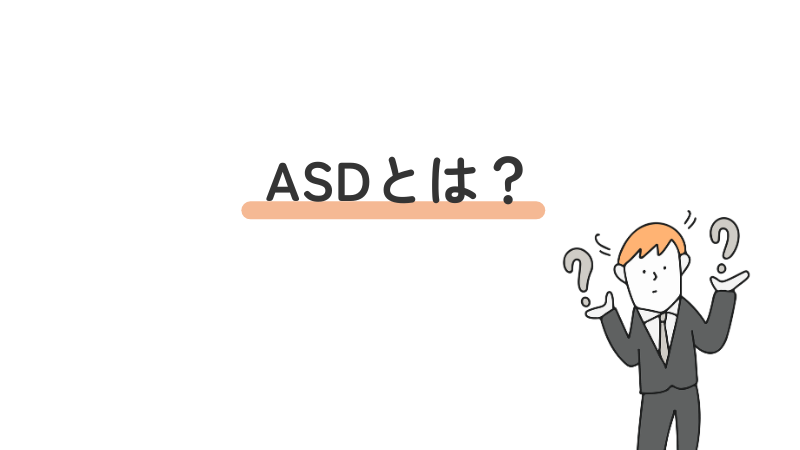
ASD(自閉スペクトラム症)は、脳の働き方の違いにより、「人との関わり方」「コミュニケーション」「興味や行動のパターンへの偏り」が見られる状態を指します。
最近では「発達障害の一種」として広く知られるようになりましたが、その特徴や困りごとは人によって大きく異なります。
どれも本人の性格の問題ではなく、「情報の受け取り方・感じ方の違い」によって起こることが多いのです。
ASD(自閉スペクトラム症)の主な特徴
ASD(自閉スペクトラム症)には大きく分けて、以下のような特徴があります。
| 特徴 | 具体的な傾向や例 |
|---|---|
| 対人関係やコミュニケーションの難しさ | 言葉の裏の意図を読み取るのが苦手表情や距離感、声のトーンが独特雑談など目的のない会話が難しい |
| 興味や行動の偏り | 特定の物事を繰り返すことで安心する物の並べ方やルールに強くこだわる |
| 感覚の偏り(感覚過敏・鈍麻) | 音、光、におい、触感に過敏に反応する逆に、痛みや刺激に鈍感なこともある |
| 運動の不器用さ(発達性協調運動障害の併存) | 字を書く、はさみを使う、ボールを投げるなどが苦手手先の作業や複雑な動作に困難がある |
| その他の特性 | 睡眠リズムが不安定になりやすい特定のことに強く集中しすぎてしまう(過集中)記憶力は高いが柔軟な対応が苦手なこともある |
- 厚生労働省「発達障害の理解」
- 国立精神・神経医療研究センター(NCNP病院)「自閉スペクトラム症(ASD)」
ASD(自閉スペクトラム症)かも?と思ったら病院に行くべき?
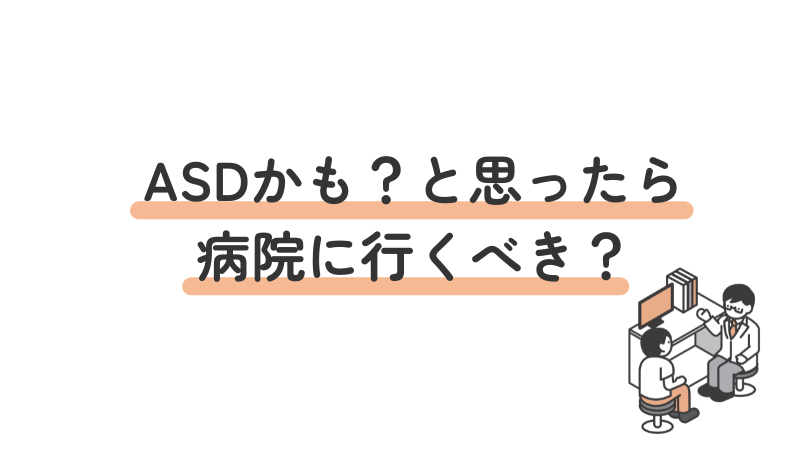
生きづらさや働きづらさに悩んでいて、「ASD(自閉スペクトラム症)かもしれない」と感じたら、一度専門の医師に相談してみることをおすすめします。ただし、診断を受けるかどうかは、あくまで個人の選択です。
この章では、診断を受けるメリット・デメリット、そして病院を受診する前に知っておきたいポイントについて詳しく解説します。
診断を受けるメリット
ASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けるメリットは5つあります。
- 自分の困りごとに理由があると分かり、安心できる
- 特性に合った働き方や人間関係の工夫がしやすくなる
- 就労移行支援やカウンセリングなど、必要な支援に繋がりやすくなる
- 障害者手帳の取得が可能になり、職場での配慮や制度の活用がしやすくなる
- 「なぜうまくいかないのか」という自己否定感が和らぎ、周囲に相談しやすくなる
診断を受けるデメリット
ASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けるデメリットは2つあります。
- 診断が確定までに複数回の通院や心理検査が必要になることがある
- 診断名にとらわれてしまい、自分の強みに目が向きにくくなることがある
病院に行く前に知っておきたいこと
ここでは病院に行く前に知っておきたいことをQ&A方式で解説します。
Q:どんな病院に行けばいいの?
A:発達障害に対応している精神科や心療内科を受診しましょう。病院の公式サイトや口コミで「発達障害外来」「大人の発達障害に対応」といった記載があるかを事前に確認すると安心です。また「メンタルクリニック」「こころのクリニック」などの名称でも、精神科や心療内科が含まれていれば対象になります。
Q:精神科と心療内科の違いは?
A:
- 精神科:うつ病、不安障害、発達障害などの「心の病気」全般を対象に診療
- 心療内科:ストレスによる体調不良(頭痛・胃痛・不眠など)を中心に診療
ASD(自閉スペクトラム症)の診断には、精神科または精神科を併設する心療内科が適しています。
Q:どんな資格を持っている先生が望ましい?
A:精神保健指定医や精神科専門医(日本精神神経学会)の資格を持つ医師が在籍していると、より安心して診断を受けられます。
ASD(自閉スペクトラム症)の方に向いている仕事と働き方
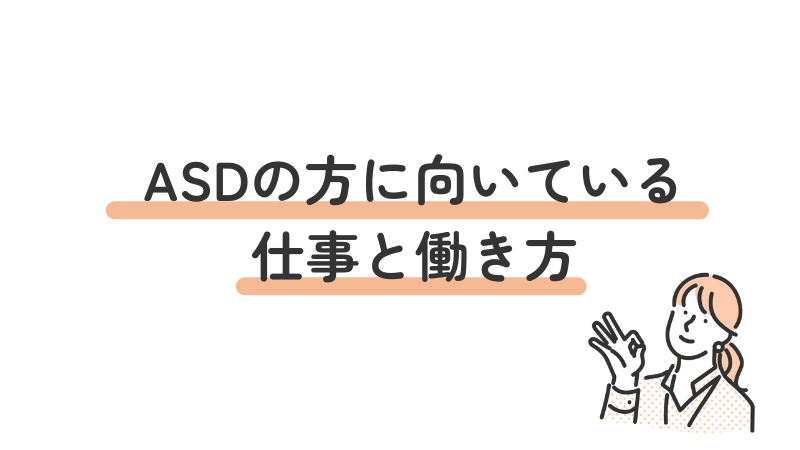
この章では、ASD(自閉スペクトラム症)の方が働きやすい仕事の特徴を5つ紹介します。
- 業務内容や手順が明確に決まっている
- 静かで落ち着いた職場環境が整っている
- 1人で集中して取り組める業務が中心
- 予定外の対応が少なく、見通しを立てやすい
- 特性への理解があり、配慮をしてくれる環境がある
こうした特徴がそろっている職場では、無理なく自分らしく働ける環境が整いやすくなります。
「とはいえ、実際にどんな仕事が向いているの?」と気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
「仕事が辛い…」と感じた時の選択肢
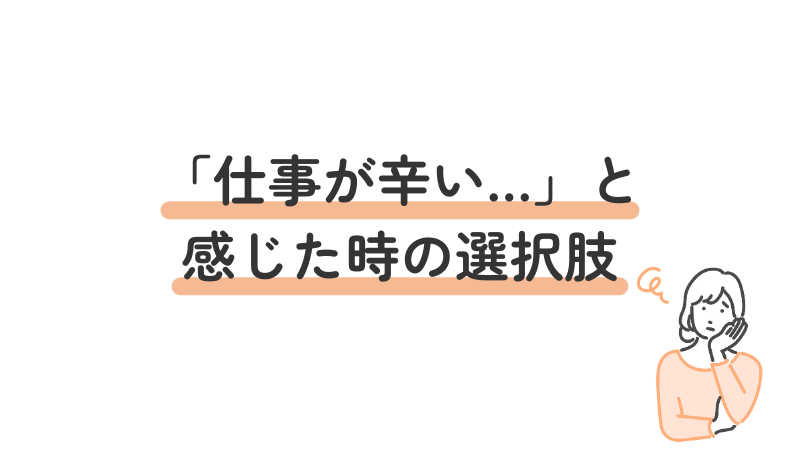
ASD(自閉スペクトラム症)の特性からくる困りごとは、努力や根性だけで乗り越えられるものではありません。頑張りすぎることで心や身体に不調が出てしまう前に、「どうすれば今の状態を少しでも軽くできるか」という視点で、選択肢を広げていくことが大切です。
ここでは、「今の働き方が辛い」と感じている方が、今後のために考えておきたいことをご紹介します。
介します。
心と身体に限界を感じたら「休職」もひとつの手段
「朝起きるのが辛い」「出勤前から強い緊張や不安を感じる」「小さなミスでも過剰に落ち込んでしまう」などといった状態が続いている場合、心身が限界に近づいているサインかもしれません。
無理に働き続けることがかえって悪化させてしまうこともあります。
そのような時は、いったん立ち止まって休むことも大切な選択肢です。
医師の診断をもとに「休職」を申し出ることで、一定期間仕事から離れ、心と身体の回復に専念する時間を確保できます。これは決して「逃げ」や「甘え」ではなく、必要なリカバリー期間です。
特にASD(自閉スペクトラム症)の方は、環境から受ける刺激やストレスに敏感な傾向があり、継続的な負荷がかかることで、うつ病や不安障害などを併発しやすいとされています。
また、職場によっては休職制度が整っていることもあります。主治医や産業医、人事担当者などと相談しながら手続きを進めると、より安心して対応できるでしょう。
転職を考える前に、自分の特性や働き方の希望を整理してみる
「今の職場がつらい」「もう辞めたい」と感じた時、「転職」という選択肢が思い浮かぶかもしれません。
ただし、ASD(自閉スペクトラム症)の方の場合は、「何が自分に合っていなかったのか」を整理せずに環境を変えてしまうと、同じつまずきを繰り返してしまうリスクがあります。
まずは、次のような視点でご自身の状況を振り返ってみることをおすすめします。
こうした項目を整理することで、「自分にとって無理のない働き方」「安心して力を発揮できる職場環境」へのヒントが見えてきます。
転職を急ぐよりも、まずは自分の特性や希望を言語化することが、納得のいく次の一歩を考えるための土台になります。
迷ったら「支援機関」や「医療機関」に話を聞いてもらう
「自分はASD(自閉スペクトラム症)かもしれないけど、診断を受けるべきか分からない」「今の職場を続けるべきか迷っている」といった悩みは、ひとりで抱えていると、ますます不安や混乱が大きくなることがあります。
そのような時は、支援機関や医療機関に相談することも視野に入れてみてください。
例えば、以下のような場所で相談を受けられることがあります。
| 相談先 | 説明 |
|---|---|
| 発達障害者支援センター | 地域にある専門窓口。発達障害に関する相談や情報提供を行っている |
| 就労移行支援などの福祉サービス事業所 | 働くことに不安がある方に対し、職業訓練や就職支援を提供する場所 |
| 精神科・心療内科などの医療機関 | 診断や治療を受けられる。必要に応じて紹介状の作成も可能 |
仕事への悩みがあるASD(自閉スペクトラム症)の方が利用できる就労移行支援
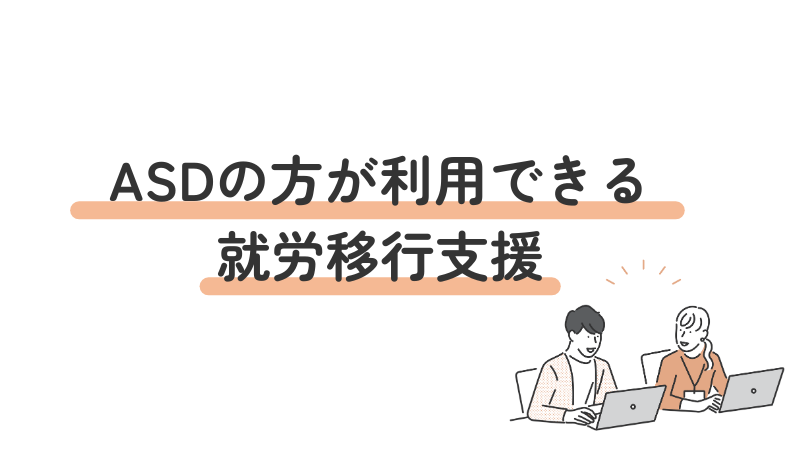
「今の働き方が辛い」「自分に合った仕事が分からない」という悩みを抱えるASD(自閉スペクトラム症)の方にとって、就労移行支援という福祉サービスは、大きな助けになります。
就労移行支援とは、障害や病気のある18歳以上65歳未満の方が「一般企業への就職」を目指すために利用できる支援サービスです。全国に事業所があり、通所やオンラインでの利用が可能です。
就労移行支援manabyについて
就労移行支援manaby(マナビー)は、ASD(自閉スペクトラム症)をはじめ、発達障害や精神疾患のある方がのある方へ自分らしく働くための支援を行う場所です。
気分の波や体調の変化に不安を感じている方でも、一人ひとりの状態やペースに合わせた「個別支援」を大切にし、「どんな働き方が自分に合っているか」を一緒に考えていくことを重視しています。
例えば、以下のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができるでしょう。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「調子の波があるから働くのが不安」「今の自分にできる仕事があるか分からない」と働くことへお悩みがある方はぜひ、お気軽にご相談ください。
環境や支援で、ASD(自閉スペクトラム症)の「働きにくさ」は変えられる
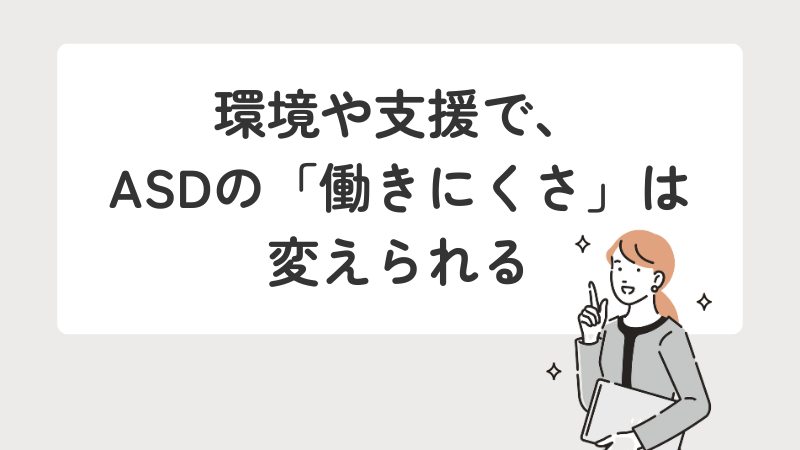
ASD(自閉スペクトラム症)の特性による働きづらさを感じやすい背景は、本人の努力不足や甘えではなく、脳の情報処理の仕方や感じ方の違いによって生じるものです。
例えば、人間関係の築き方に悩んだり、急な予定変更に混乱したり、音や光などの刺激に敏感だったりと、周囲と同じように対応しようとしても難しさを感じてしまうことがあります。その結果、「自分は仕事ができない」と思い込んでしまう方も少なくありません。
しかし実際には、自分の力が足りないのではなく、今の環境や働き方が自分に合っていないだけという場合も多いのです。
まずは、自分の特性を正しく理解し、それに合った対策やサポートを取り入れていくことで、少しずつ働きやすさを感じられるようにしていきましょう。
また、「今の職場で頑張り続けること」だけが正解ではありません。無理をして心身のバランスを崩してしまう前に、環境を見直したり、支援を受けたり、いったん立ち止まって休むことも大切な選択肢のひとつです。
例えば、就労移行支援のような福祉サービスを活用すれば、特性に合った働き方や職場環境を一緒に探すことができます。専門の支援員によるサポートのもとで、自分らしく働ける仕事と出会えるきっかけになるかもしれません。
自分を責めるのではなく、「どうすれば心地よく働けるか」を考えることが、ASDの方にとっての第一歩になります。無理をしすぎず、必要なサポートを取り入れながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。








