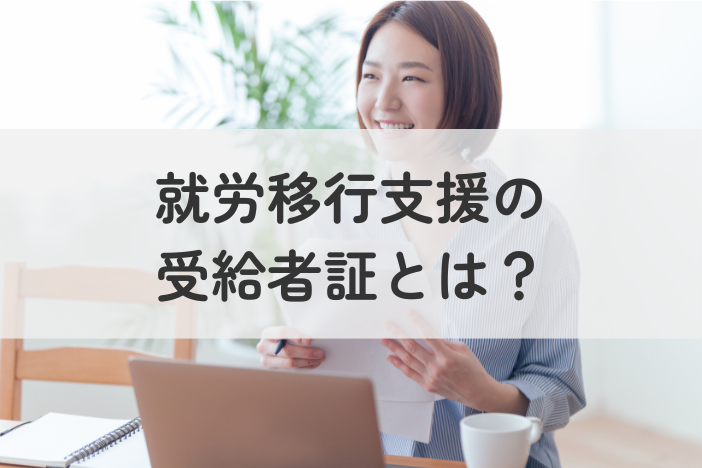【発達障害向け】就労移行支援の探し方|失敗しない選び方と支援内容を解説

- 発達障害の方が就労移行支援事業所を選ぶ時のポイント
- 【前提】発達障害の方は、就労移行支援の利用対象
- 自分が就職したい業種で、就職実績があるか?
- 自分がやりたい仕事が分からない時は?
- 自分の困りごとに合った支援があるか?
- 自分が身につけたいスキルや資格が訓練プログラムに含まれているか?
- 無理なく続けて通える立地・アクセスであるか?
- 発達障害の方におすすめの就労移行支援プログラム4選
- 段取りや時間管理をサポートする訓練
- コミュニケーションや報連相の練習
- 自分の特性に合う働き方を見つけるための自己理解支援
- 就職後の困りごとに備える定着支援
- 発達障害の方におすすめの就労移行支援の環境
- 静かで落ち着いた作業環境が整っている
- 少人数制で自分のペースを尊重してくれる
- 特性を理解したスタッフがサポートしてくれる
- 在宅やオンライン支援に対応している
- 発達障害の方が就労移行支援を利用する5つのメリット
- 自分の特性や苦手を整理し、強みを活かせるようになる
- コミュニケーションの練習で人間関係への不安を減らせる
- 生活リズムや体調の安定を支援してもらえる
- 働き方の工夫や配慮の伝え方を学べる
- 就職後も定着支援でフォローしてもらえる
- 発達障害の方の就労移行支援体験談
- 就労移行支援とは?
- 就労移行支援の利用までの流れ
- 1. 主治医への相談
- 2. 情報収集・相談
- 3. 事業所の見学・体験
- 4. 利用申請・受給者証の交付
- 5. 利用契約・通所開始
- 発達障害に合った就労移行支援を選ぶことが就職成功のカギ
「就労移行支援に興味はあるけれど、発達障害の自分に合う事業所をどう選べばいいのか分からない」という悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。支援内容や環境は事業所によって様々で、発達障害の特性に合わない場所を選んでしまうと「通いづらい」「力を発揮できない」と感じてしまうこともあります。
この記事では、発達障害の方が就労移行支援を探す際に確認すべき選び方のポイントや、発達障害の方におすすめの支援内容をわかりやすく解説します。さらに、就労移行支援を利用するメリットや、実際に利用を始めるまでの流れも紹介します。
この記事のまとめ
-
●
就労移行支援とは?
発達障害のある方が自分に合った働き方を見つけるための福祉サービス -
●
事業所を選ぶポイント
特性に合った支援や通いやすさ、就職実績をチェックすることが重要 -
●
発達障害の方のおすすめプログラム
時間管理やコミュニケーション練習、自己理解、定着支援など
発達障害の方が就労移行支援事業所を選ぶ時のポイント
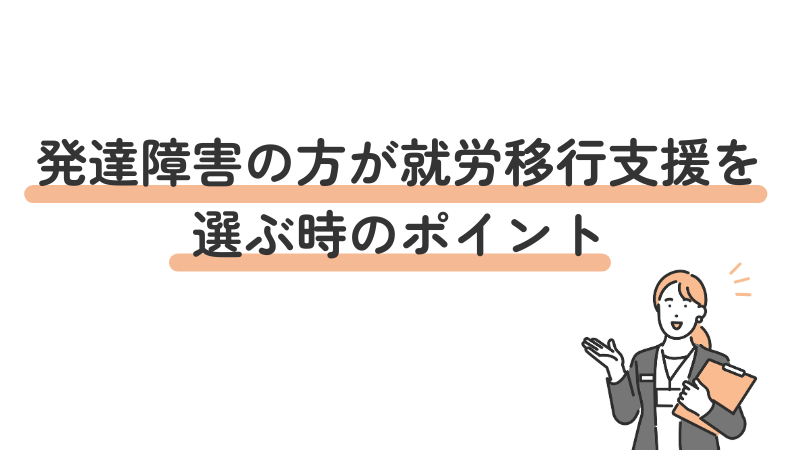
この章のポイント
- ● 就職実績や特性に合った支援内容を確認する
- ● 身につけたいスキルや資格が学べるかチェックする
- ● 無理なく通える立地や在宅対応の有無を確認する
ここでは、発達障害の方が就労移行支援事業所を選ぶときに確認しておきたいポイントを解説します。よくある困りごとに合わせて「どんな支援や環境があると安心できるか」を具体例と一緒に紹介していきます。
【前提】発達障害の方は、就労移行支援の利用対象
就労移行支援は、発達障害の方が利用できる福祉サービスです。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できる場合があります。
また、「グレーゾーンかもしれない」「診断は受けているけれど、まだ手帳は持っていない」「自分は対象になるのか分からない」と不安に感じている方も、まずは市区町村の障害福祉課や気になる就労移行支援事業所に相談してみましょう。
自分が就職したい業種で、就職実績があるか?
就職実績を見る時のポイントは、「自分の希望する業種が含まれているか」、そして「自分の特性に近い人がどんな職種で就職しているか」です。この2つの視点で確認することで、「この事業所なら自分に合った就職が目指せそうか」を判断しやすくなります。
就労移行支援の公式サイトには、「就職実績」や「定着率」が掲載されていることがあります。すでに「事務職で働きたい」「接客に挑戦したい」といった希望がある方は、その業種で就職実績があるかをチェックしましょう。
さらに同じ特性を持つ人が就職している事例があれば、自分のキャリアをイメージしやすくなります。
自分がやりたい仕事が分からない時は?
「どんな仕事をやりたいのか分からない」という方も少なくありません。その場合は、実績の数字だけでなく「どんな職種に就職している人が多いか」に注目すると、自分に合いそうな働き方のヒントを得られます。
例えば、事務職への就職実績が多い事業所は、ルールやマニュアルに沿った作業やPCスキルの訓練が充実していることが多いです。もし「自分もマニュアル通りの作業なら得意」なら、その事業所は安心して力を伸ばせる環境かもしれません。
逆に、接客や販売の就職実績が多い事業所は、人とのやり取りを想定したコミュニケーション練習が充実している可能性があります。「人との会話は苦手だけど練習して慣れたい」と思っている方には合っている一方、「人と関わる仕事は避けたい」と感じている方には向かないかもしれません。
自分の困りごとに合った支援があるか?
発達障害の方は、人によって苦手や不安が違うため、合わない支援ばかりだと続けにくくなってしまいます。ADHD(注意欠如・多動性障害)の方なら「時間の使い方がうまくいかず、遅刻や締め切りに間に合わない」、ASD(自閉スペクトラム症)の方なら「人との会話で何をどう話せばいいか分からず、不安になる」という悩みを持っている方が多いです。
就労移行支援では、以下のように特性に合わせたサポートを受けられます。
| 困りごとの例 | 支援内容の例 |
|---|---|
| 時間管理が苦手 | タスク管理やスケジュール調整の練習 |
| コミュニケーションに不安がある | 報連相の練習、グループワークでの会話練習 |
| 体力に不安がある | 無理のない通所ペースの設定、休憩の取り方を学ぶ |
自分の困りごとをまだうまく言葉にできなくても、公式サイトなどに書かれている「訓練プログラムの内容」や「過去の利用者の事例」を見てみると参考になります。
自分が身につけたいスキルや資格が訓練プログラムに含まれているか?
就労移行支援では、WordやExcelといった基本的なパソコンスキルの習得や、MOS・簿記などの資格取得をサポートしてくれる事業所もあります。
| カテゴリー | スキル・資格の例 |
|---|---|
| パソコン系 | Word、Excel、PowerPointなどの基本操作 |
| 事務系資格 | MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)、日商簿記 |
| IT・デジタル系 | ITパスポート、プログラミング基礎、タイピングスキル |
| ビジネス系 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修、電話応対 |
こうしたスキルや資格は就職活動での強みになりやすく、履歴書に記載してアピールできる場合もあります。
また、発達障害の方の中には「勉強を一人で進めるのが難しい」「繰り返し練習しないと覚えにくい」と悩む方もいるかもしれません。そのような方は、基礎から繰り返し学べるカリキュラムや、資格試験に向けた模擬問題・勉強会などのサポートがあるかも確認すると安心です。
無理なく続けて通える立地・アクセスであるか?
事業所までの通いやすさは、就労移行支援を継続できるかどうかに直結します。発達障害のある方の中には、電車のラッシュや人混みが強いストレスになる方や、朝が苦手で決まった時間に通うのが難しい方も少なくありません。
そのため、自宅から近い場所にあるかどうかに加えて、通勤時の電車の混み具合や人の多さが負担にならないかを確認しておくと安心です。駅からの距離や周囲の環境(静かで落ち着いているか、騒がしすぎないか)も選ぶ際の参考になります。
さらに、通所時間を柔軟に調整できるかどうか、在宅やオンラインでの支援に対応しているかも大切なポイントです。こうした仕組みが整っていれば、体調や気分の波がある方でも無理なく続けやすくなります。
発達障害の方におすすめの就労移行支援プログラム4選
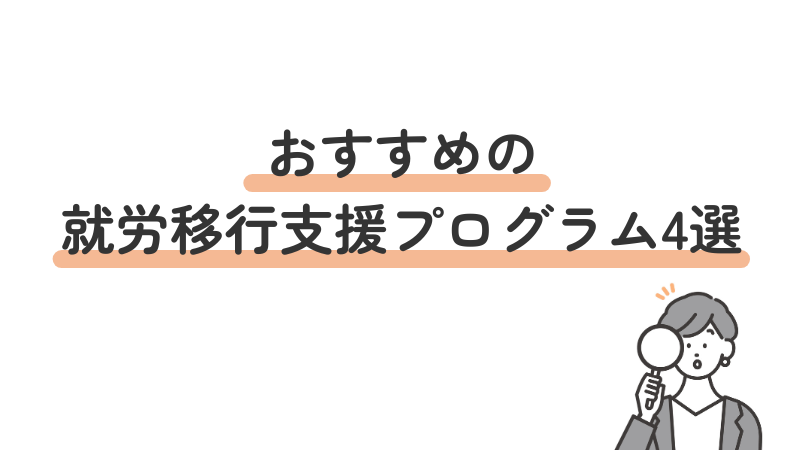
この章のポイント(おすすめプログラム)
-
●
おすすめ① 段取りや時間管理のプログラム
優先順位の付け方やスケジュール管理を練習 -
●
おすすめ② コミュニケーション・報連相のプログラム
グループワークやロールプレイでやり取りを練習 -
●
おすすめ③ 自己理解を深めるプログラム
得意・苦手を整理し、自分に合う働き方を見つける -
●
おすすめ④ 就職後を支える定着支援プログラム
定期面談や職場調整で長く働きやすくなる
ここでは、発達障害の方が安心して取り組みやすく、就職に繋がりやすい支援プログラムを4つに絞って紹介します。
段取りや時間管理をサポートする訓練
発達障害の中でもADHD(注意欠如・多動性障害)の方に多い「やることが多いと混乱してしまう」「締め切りを守るのが難しい」といった困りごとに対応する訓練です。タスクの優先順位をつける練習や、スケジュールを見える化する方法、チェックリストの使い方などを学ぶことで、仕事の進め方が安定しやすくなります。
事業所によっては、例えば「タイムマネジメント講座」「タスク管理トレーニング」 といったプログラム名で実施されていることがあります。
【こんな人におすすめ】
- 朝の準備に時間がかかって遅刻してしまう
- 締め切り直前まで取りかかれない
- 複数の作業を同時に進めるのが苦手
コミュニケーションや報連相の練習
ASD(自閉スペクトラム症)の方に多い「相手の意図をくみ取るのが難しい」「自分の伝え方に自信がない」といった不安に対応するプログラムです。グループワークやロールプレイを通じて、報告・連絡・相談の仕方を繰り返し練習することで、人間関係のストレスを軽減し、職場での安心感につながります。
事業所によっては 「コミュニケーションスキル講座」「報連相トレーニング」 といった名前で実施されていることもあります。
【こんな人におすすめ】
- 上司や先輩に相談するのが怖い
- 報告を忘れてしまい、注意されやすい
- 人とのやり取りで緊張しすぎてしまう
自分の特性に合う働き方を見つけるための自己理解支援
「自分の得意や苦手が分からない」という方に向けて、スタッフと一緒に特性を整理するプログラムです。面談やワークシートを使いながら、集中しやすい環境や避けた方がよい業務を整理することで、自分に合った働き方や職種の方向性が見えてきます。
事業所によっては 「自己分析ワーク」「職業適性チェック」「キャリアデザイン講座」 といったプログラム名で実施されていることがあります。こうした支援を受けることで、自分の強みや苦手を客観的に把握しやすくなります。
【こんな人におすすめ】
- どんな仕事が向いているのか分からない
- 苦手を説明できずに面接で困ったことがある
- 職場で長く働ける自信がない
就職後の困りごとに備える定着支援
「働き始めたあとに続けられるか不安」という発達障害の方のために、定期的な面談や職場との調整を通じてフォローしてもらえる仕組みです。就労移行支援のプログラムでは、「職場定着面談」「ジョブコーチ支援」「職場との三者面談」 などの形で実施されることが多く、働き始めてからの不安や困りごとを早めに解消するサポートが受けられます。
【こんな人におすすめ】
- 過去に就職したけれど長続きしなかった
- 職場で困っても誰に相談していいか分からない
- 無理をして体調を崩してしまうことが多い
発達障害の方におすすめの就労移行支援の環境
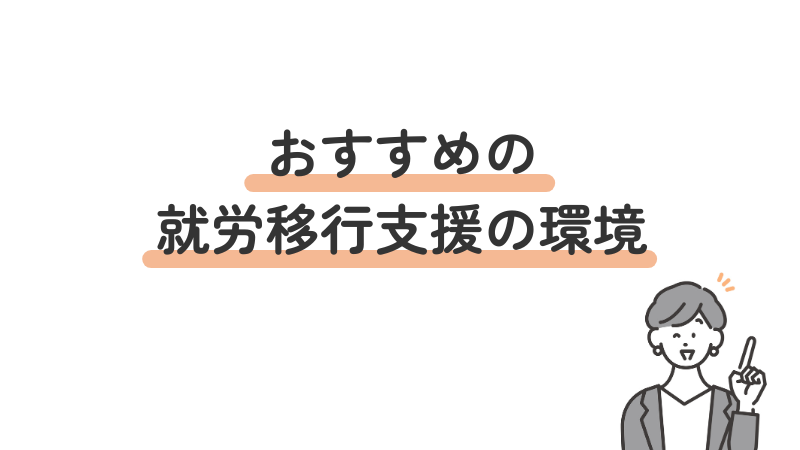
この章のポイント(環境選び)
-
●
集中できる環境があるか
静かな作業スペースや個別ブースなどの工夫が整っているかを確認 -
●
自分のペースで学べるか
少人数制や負担の少ない雰囲気があると続けやすい -
●
柔軟な通所スタイルに対応しているか
在宅やオンライン支援の有無が、継続や就職に大きく影響
就労移行支援を続けるうえで、プログラムの内容と同じくらい大切なのが「通う環境」です。発達障害の方の中には、人混みや騒音に強いストレスを感じる方や、集団が多い場面で疲れてしまう方も少なくありません。環境が合わないと、せっかくの支援があっても通い続けるのが難しくなることがあります。
ここでは、発達障害の方が安心して取り組みやすい環境のポイントを紹介します。
静かで落ち着いた作業環境が整っている
周囲の音や刺激が強いと集中しにくい方にとって、作業環境はとても大切です。例えば、パーテーションで区切られた個別ブースがある、イヤーマフや静音スペースを用意している、BGMや雑音が少ないといった工夫がされている事業所なら、安心して作業に取り組めます。自分のペースで集中できる空間があるかどうかを見ておくと、通いやすさが大きく変わります。
【こんな人におすすめ】
- 周囲の話し声や雑音が気になって集中できない
- オープンスペースだと緊張して作業が進まない
- パーテーションや静かな部屋で、自分のペースを大切にしたい
少人数制で自分のペースを尊重してくれる
大人数の場が苦手な方には、少人数制の事業所が安心です。参加人数が限られていると、人間関係の負担が少なく、講義形式でも質問がしやすいなど、自分のペースで学びやすくなります。大人数のグループワークが中心だと緊張してしまう方も、少人数制なら無理なく通い続けられる可能性が高まります。
【こんな人におすすめ】
- 人が多い場所にいるとすぐに疲れてしまう
- グループ活動が多いと緊張する
- 自分のペースでゆっくり学びたい
特性を理解したスタッフがサポートしてくれる
発達障害に理解のあるスタッフがいるかどうかは、安心して通えるかに直結します。ミスや困りごとを責めるのではなく、「どうすればうまくいくか」を一緒に考えてくれる事業所なら、無理なく続けやすいでしょう。
特に、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアコンサルタント などの専門資格を持つスタッフが在籍している事業所は、より安心感があります。こうしたスタッフなら、特性に応じた工夫や就職活動での配慮の伝え方まで、専門的にサポートしてもらいやすいです。
【こんな人におすすめ】
- 失敗すると強く責められるのではと不安になる
- 自分の特性をどう伝えればいいか分からない
- 困ったときに安心して相談できる人が欲しい
在宅やオンライン支援に対応している
体調や気分の波がある方にとって、毎日通所するのは大きな負担になることがあります。そのため、自宅からでもプログラムに参加できる仕組みがあるかどうかは重要なポイントです。
例えば、チャットでの相談対応や、自宅でも取り組める学習プログラム が用意されている事業所なら、気分が安定しない日でも安心です。さらに、在宅訓練から就職につながった実績がある事業所なら、「通所が難しくても就職を目指せるかどうか」だけでなく、「将来的に在宅勤務などの働き方を実現できるか」を判断する目安にもなります。
【こんな人におすすめ】
- 毎日通うのが体力的に負担になる
- 気分の波で外出できない日がある
- 自宅でもスキル学習や面談を続けられる環境が欲しい
※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります
発達障害の方が就労移行支援を利用する5つのメリット
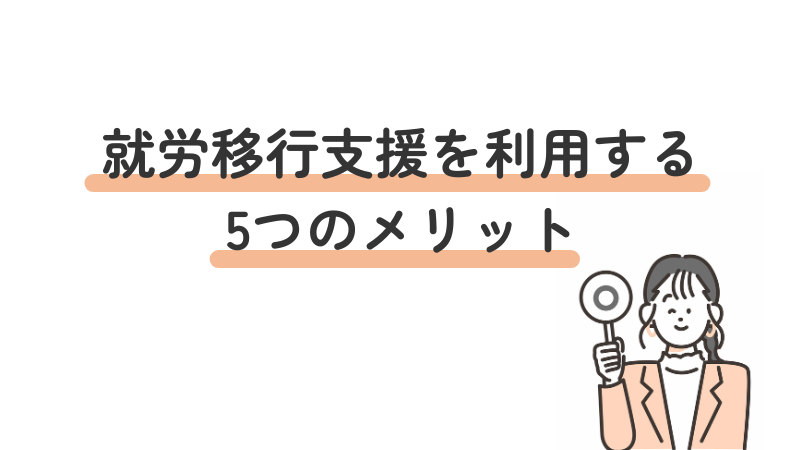
この章のポイント(メリット)
-
●
自分の特性や強みを整理できる
自己理解が深まり、就職活動や職場での配慮につなげやすい -
●
働くための基盤を整えられる
生活リズムやコミュニケーションスキルを支援してもらえる -
●
就職後もフォローを受けられる
定着支援で困りごとを早めに解決し、安定して働き続けやすい
ここでは、発達障害の方が就労移行支援を利用することで得られる代表的な5つのメリットを紹介します。
自分の特性や苦手を整理し、強みを活かせるようになる
発達障害の方は、「なぜ仕事が続かないのか分からない」「自分に合った仕事が分からない」と悩むことが少なくありません。就労移行支援では、スタッフとの面談や日々の訓練を通して、自分の得意・不得意を客観的に整理する機会があります。
例えば「人との会話は苦手だけど細かい作業は得意」「ルールが厳しいと混乱するけれど、自由度が高いと力を発揮できる」といった、自分でも気づいていなかった強みや傾向に気づけることがあります。
こうした特性を言葉にできると、就職活動では自己PRや面接で自分を説明しやすくなるだけでなく、入社後に職場へ配慮を伝える根拠にもなるため、長く働きやすい環境づくりに繋がりやすくなります。
コミュニケーションの練習で人間関係への不安を減らせる
「上司にどう相談していいか分からない」「相手の意図がつかめずに誤解されてしまう」という悩みは、発達障害の方が職場でつまずきやすい大きな要因です。
就労移行支援では、グループワークやロールプレイを通じて、実際の職場を想定したコミュニケーション練習を行います。繰り返し練習することで、報告や相談の仕方が自然に身につき、人間関係によるストレスが減り、安心して働き続けやすくなるのが大きなメリットです。
生活リズムや体調の安定を支援してもらえる
就職を目指すうえで意外と大きな壁になるのが「生活リズムの乱れ」や「体調の不安定さ」です。発達障害の方の中には、夜更かしや寝坊が習慣化してしまい、毎日決まった時間に行動することが難しい人も少なくありません。
就労移行支援では、通所を通じて少しずつ生活リズムを整えたり、体調に合わせて無理のないスケジュールを組んでもらえます。定期的にスタッフと振り返ることで、疲れやすさへの対策や休憩の取り方も学べ、働くための基盤を整える大きな助けになります。
働き方の工夫や配慮の伝え方を学べる
「マルチタスクが苦手」「音や光に敏感で集中できない」など、自分の特性をどう説明したらよいか分からず、結果的に我慢してしまう方も少なくありません。
就労移行支援では、そうした特性を整理し、企業に伝える練習ができます。例えば「電話対応は苦手だけどメールなら正確に対応できる」「静かな作業環境だと力を発揮しやすい」といった具体的な伝え方を学ぶことができます。
こうして自分に合った工夫や配慮を伝えられるようになると、面接で自分を説明しやすくなるだけでなく、企業側も「どんな配慮があれば働きやすいか」を理解できるようになります。その結果、採用につながりやすくなるだけでなく、入社後も無理のない環境で長く働き続けやすくなるのが大きなメリットです。
就職後も定着支援でフォローしてもらえる
就労移行支援では、就職後も定期的な面談や、必要に応じた企業との調整を通じてサポートが受けられる「定着支援」があります。例えば「業務量が多すぎてついていけない」と感じたときにスタッフが間に入り、業務内容を調整してもらえることもあります。
このように、困ったときにすぐ相談できる仕組みがあることで、離職のリスクを減らし、安定して働き続けられる可能性を高められることが就労移行支援を利用する大きなメリットです。
発達障害の方の就労移行支援体験談
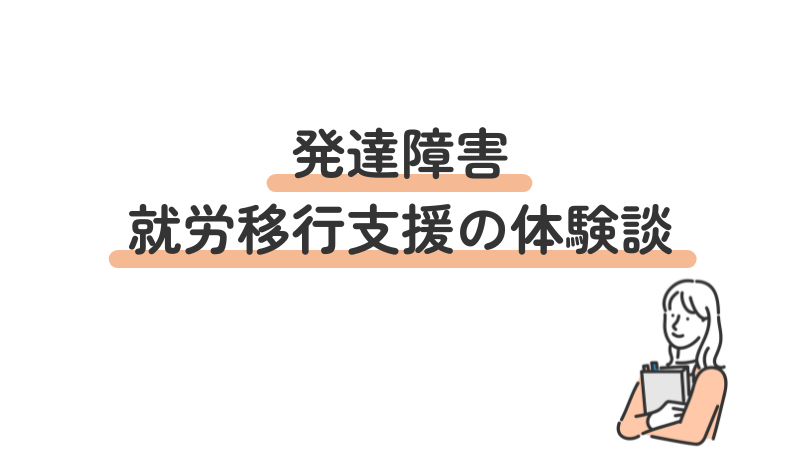
新卒で就職しましたが、マルチタスクや人間関係が原因で体調を崩し退職。うつ病と診断され、治療を続ける中で発達障害があることも分かりました。「この先働けるのか」と不安を抱えていたとき、主治医から就労移行支援を勧められました。スタッフが体調に合わせて通所ペースを調整してくれたことで無理なく続けられ、PCスキルや報連相を学ぶ中で「大人数は苦手だが落ち着いた環境なら集中できる」といった特性を整理できました。事業所を選ぶ際に「特性を理解してくれるスタッフがいるか」「無理なく通える環境か」を重視したことが、今の在宅勤務や定着支援に繋がり、「工夫次第で働き続けられる」という希望を持てるようになりました。
就労移行支援manabyでは、ほかにも実際の利用者のストーリーを紹介しています。リアルな体験談を知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
就労移行支援とは?
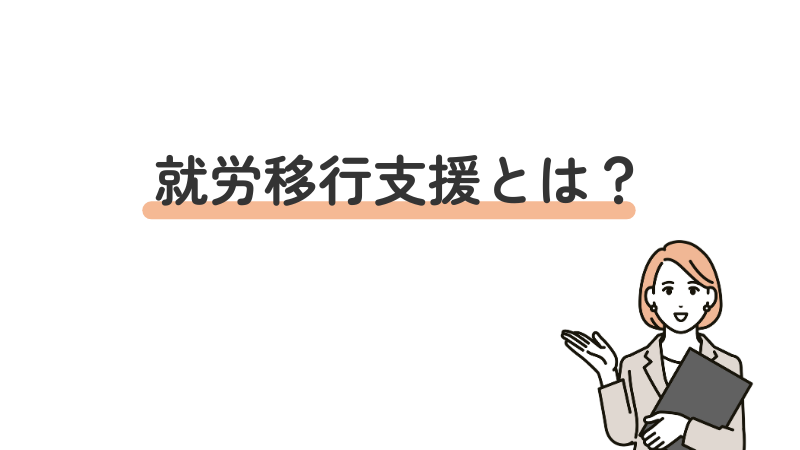
この章のポイント
-
●
利用条件
18歳〜65歳未満で、発達障害・精神障害などのある方が対象 -
●
費用
原則1割負担。多くの方は0円〜数千円程度で利用可能 -
●
利用期間
原則2年間。必要に応じて延長も可能
就労移行支援とは、障害や難病などがある方が一般企業への就職を目指すために、働く準備やスキルを身につけることができる福祉サービスです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用条件 | 18歳〜65歳未満が対象。発達障害・精神障害・知的障害・身体障害などがある方。障害者手帳がなくても医師の診断書などで利用できる場合あり。 |
| 費用の目安 | 原則1割負担。世帯所得に応じて月額上限が設定され、多くの方は0円〜数千円程度。生活保護・低所得世帯は無料の場合も。 |
| 利用期間 | 原則2年間。必要に応じて延長が認められる場合もあるが、基本は「2年以内に就職を目指すサービス」。 |
就労移行支援の利用までの流れ
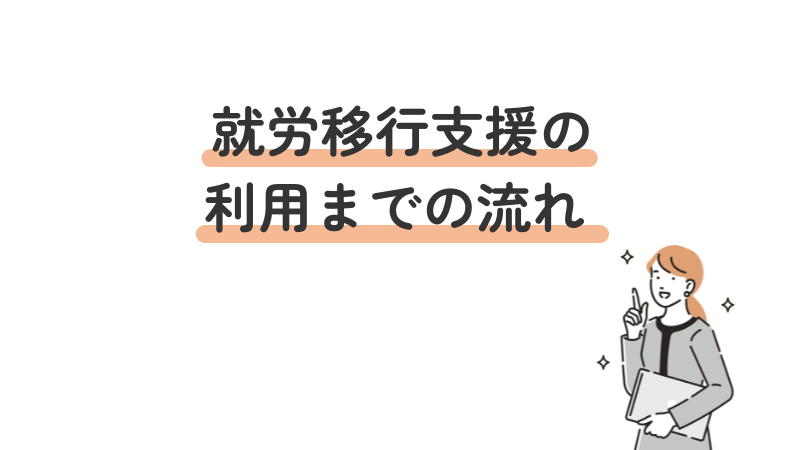
この章のポイント
-
●
医師・自治体へ相談
主治医や自治体窓口に相談し、利用の可否や必要書類を確認する -
●
事業所を見学・体験
雰囲気や支援内容を直接確認し、自分に合うかを判断する -
●
受給者証を取得して利用開始
受給者証が交付されてから契約・通所を開始できる
就労移行支援を利用するには、医師や自治体への相談、事業所の見学・体験、申請手続きといったステップを経て利用開始となります。ここでは、その基本的な流れを整理して紹介します。
1. 主治医への相談
就労移行支援を利用できるかどうか、不安がある方はまず主治医に相談しましょう。診断書や意見書が必要になる場合もあるため、医師と一緒に方向性を考えておくと安心です。
2. 情報収集・相談
次に、自治体の障害福祉課やハローワーク、インターネットで情報を集めます。「自分も対象になるのか」「どんな事業所があるのか」といった疑問は、自治体の窓口や福祉サービスの相談窓口で確認する方が多いです。
3. 事業所の見学・体験
気になる事業所があれば、見学や体験に参加します。雰囲気やスタッフの対応、訓練内容を自分の目で確かめることが大切です。「静かな環境で集中できるか」「自分の困りごとに合ったサポートがあるか」を意識してチェックすると、利用のイメージがしやすくなります。
4. 利用申請・受給者証の交付
利用したい事業所が決まったら、市区町村の障害福祉課で申請を行います。この際、障害者手帳や医師の診断書などが必要になる場合があります。申請が認められると「受給者証」が交付され、正式に利用できるようになります。
5. 利用契約・通所開始
受給者証が交付されたら、事業所と契約を結び、いよいよ訓練がスタートします。最初は週数日の通所から始め、体調や生活リズムに合わせて少しずつ日数を増やしていくケースもあります。
発達障害に合った就労移行支援を選ぶことが就職成功のカギ
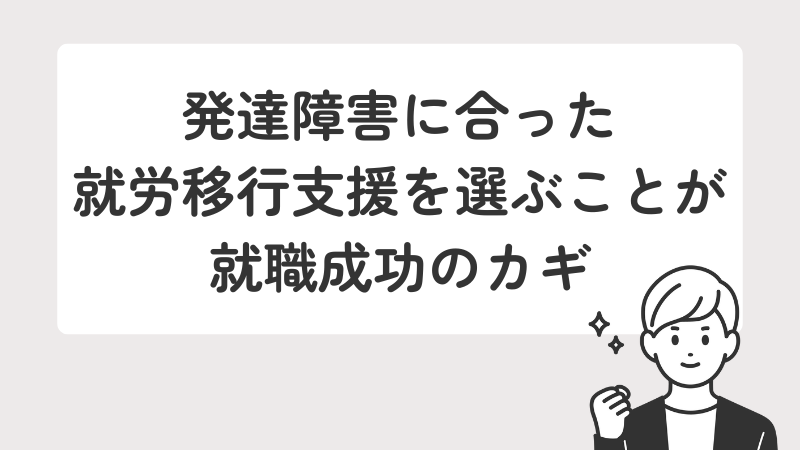
就労移行支援は、発達障害のある方が「自分に合った働き方」を見つけるための大きな支えになります。ただし、支援内容や環境は事業所によって異なるため、就職を成功させるには「自分の特性に合った事業所」を選ぶことが欠かせません。
自己理解を深めるプログラムやコミュニケーション練習、体調に合わせたサポート、就職後の定着支援など、困りごとに合った支援があるかを確認することが大切です。さらに、スタッフの理解度や通いやすさ、就職実績といった客観的な情報も判断材料になります。
自分に合った就労移行支援を選べば、就職活動の成功だけでなく、その後の「長く働き続ける力」につながります。

臨床心理士・公認心理師
米澤 駿
数多くある就労移行支援について1つ1つ調べることを面倒に感じ、つい「どこでもいいから早く決めてしまいたい」と思うこともあるでしょう。しかし、仕事選びで「給料さえ良ければ、どんな会社でも良い」と簡単に割り切れないように、就労移行支援も「就職をサポートしてくれるなら、どこでも良い」というわけではありません。
また、発達障害のある方にとっては、就労移行支援の本当の価値は就職後も受けられる「定着支援」にあります。発達障害の特性を考えると、環境の変化に適応するまでに時間がかかることも多いため、就職後のフォローが充実している事業所を選ぶことが、長く安定して働き続けるための大事なポイントになります。
就労移行支援は、単なる就職活動のサポートにとどまらず、入社後も継続して関わりを持つ重要なパートナーです。時間をかけてでも、自分に合った事業所を選ばれることをぜひお勧めします。