福祉的就労とは?メリット・注意点・相談窓口までわかりやすく解説

- 福祉的就労とは
- 福祉的就労の対象者
- 福祉的就労での平均賃金
- 一般就労・福祉的就労との違い
- 福祉的就労の種類と特徴
- 就労継続支援A型の特徴
- 就労継続支援B型の特徴
- 地域活動支援センターの特徴
- 福祉的就労のメリット
- 福祉的就労のデメリット
- 福祉的就労の注意点
- 利用料金の負担
- 副業・アルバイトの制限
- 福祉的就労について相談できる窓口
- 「働けるかどうか」の相談は主治医へ
- 支援や制度のことは自治体窓口へ
- 求人や仕事探しはハローワークへ
- 福祉的就労についてよくある質問
- 利用するための条件は?
- 利用できる期間は決まっていますか?
- 障害者手帳がなくても利用できますか?
- 利用料金はかかりますか?
- どんな仕事ができますか?
- 給料や工賃はどのくらいですか?
- どこに相談すればいいですか?
- 福祉的就労は障害のある方が安心して働くための選択肢のひとつ
「福祉的就労って何?」「名前は聞いたことがあるけどよくわからない」
そんな方も多いのではないでしょうか。
福祉的就労とは、障害のある方が安心して働ける環境を提供する就労形態のことです。一般企業での勤務が難しい場合でも、自分のペースで働くことができます。
この記事では、福祉的就労とはどのような仕組みなのか、メリットや注意点、相談できる窓口までわかりやすく解説します。
この記事のまとめ
-
●
福祉的就労とは
障害や病気のために一般企業での就労が難しい方が、福祉サービス事業所で支援を受けながら働く形態 -
●
メリット
専門スタッフのサポートを受けられ、人間関係の配慮など安心して働ける環境が整っている点
福祉的就労とは
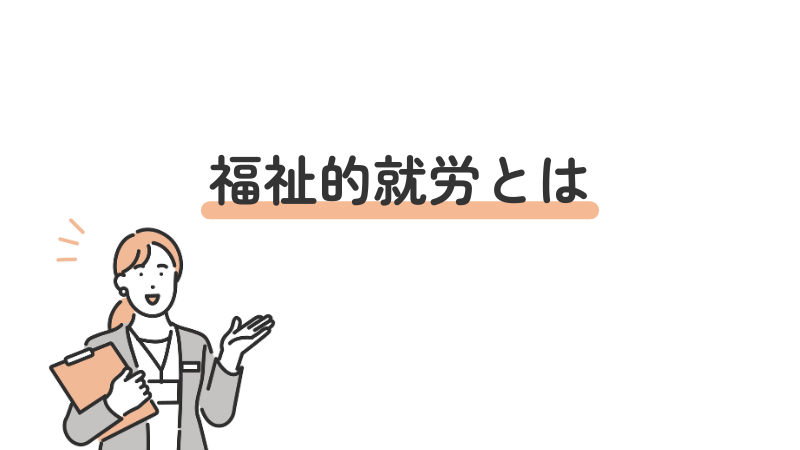
この章のポイント
-
●
就労継続支援A型
対象者:雇用契約のもとで働ける障害のある方(18歳以上65歳未満)
平均賃金:月額約86,752円(最低賃金保証あり) -
●
就労継続支援B型
対象者:自分のペースで働きたい障害のある方
平均賃金:月額約23,053円(雇用契約なし) -
●
地域活動支援センター
対象者:施設のある市区町村に住む障害のある方
平均賃金:基本なし(活動に応じて工賃あり)
福祉的就労とは、障害や病気のために一般の会社での仕事が難しい人が、福祉サービス事業所で支援を受けながら働く形のことです。働きながら生活のリズムをつくり、体力や能力に合わせて仕事を続けることができます。
福祉的就労には、主に次のような形があります。
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
- 地域活動支援センター
参考:和歌山県庁「障害のある人の「働く」(就労)について」
福祉的就労の対象者
| 施設種類 | 対象者 |
|---|---|
| 就労継続支援A型事業所 | 一般企業での就労が難しいが、雇用契約に基づいて働くことができる障害のある方(原則18歳以上65歳未満) |
| 就労継続支援B型事業所 | 雇用契約に基づいて働くことが難しく、自分のペースで働きたい障害のある方 |
| 地域活動支援センター | 障害のある方で、施設のある市区町村に住んでいる方 |
福祉的就労の対象者は、利用する施設によって少しずつ異なります。
参考:厚生労働省「障害者の就労支援について」
大阪市役所「大阪市地域活動支援センター(生活支援型)について」
福祉的就労での平均賃金
| 施設種別 | 平均工賃(賃金)月額 |
|---|---|
| 就労継続支援A型事業所 | 86,752円 |
| 就労継続支援B型事業所 | 23,053円 |
| 地域活動支援センター | 基本なし |
就労継続支援A型事業所
雇用契約が結ばれているため、最低賃金が保証されます。そのため、安定した収入を得ることができます。
就労継続支援B型事業所
雇用契約はなく、事業所ごとに決められた工賃で収入が決まります。そのため、平均賃金はA型事業所より低めに設定されています。
地域活動支援センター
基本的に収入は発生しません。ただし、生産活動を行った場合のみ、工賃が支払われることがあります。
参考:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について 」
一般就労・福祉的就労との違い
一般就労と福祉的就労の主な違いは、雇用形態、収入の安定性、サポート体制、働き方の柔軟さにあります。以下の表で詳しく比較します。
| 項目 | 一般就労 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 地域活動支援センター |
|---|---|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | あり | なし | なし(福祉サービス利用契約) |
| 給与・工賃 | 最低賃金以上 | 最低賃金以上 | 工賃(数千円〜数万円) | 原則なし(活動費補助ありの場合も) |
| 対象者 | 原則制限なし/障害者雇用枠もあり | 一般就労が困難だが、雇用契約で働ける障害のある方 | 雇用契約に基づいて働くことが難しく、自分のペースで働きたい障害のある方 | 就労が難しい障害のある方で、施設のある市区町村に住んでいる方 |
| 年齢制限 | 制限なし | 原則18歳以上65歳未満 | 制限なし | 制限なし |
| サポート体制 | 基本は企業による。障害者雇用は合理的配慮あり | 職業指導員や生活支援員など専門的な職員がサポート | 職業指導員や生活支援員など専門的な職員がサポート | 生活支援・社会参加サポート |
| 主な活動内容 | 業務に従事、企業活動 | 工場作業・事務作業・清掃等 | 軽作業・工場作業・事務作業等 | 創作活動・交流・レクリエーション等 |
| 社会保険・雇用保険 | 加入必須 | 条件次第で加入 | なし | なし |
一般就労
一般就労は、企業などで正社員やアルバイトとして働く一般的な働き方です。給料や社会保険が整っていて安定していますが、サポートを受けながら働く仕組みは少なく、自分で職場に適応していく力が求められます。
福祉的就労
一般就労が難しい方が、福祉サービスを活用しながら働くことができる場です。体調や障害に合わせて働き方やサポート内容を調整しやすく、無理なく仕事を続けやすい環境が整っています。
参考:発達障害ナビポータル「一般就労と福祉的就労」
福祉的就労の種類と特徴
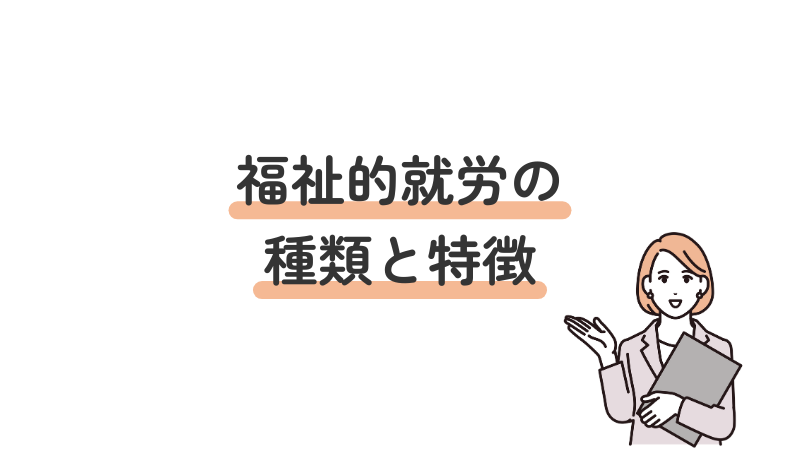
この章のポイント
-
●
就労継続支援A型の特徴
雇用契約あり、最低賃金保証。事務・軽作業・接客など。契約に基づき安定して働きたい方向け。 -
●
就労継続支援B型の特徴
雇用契約なし、工賃で報酬。軽作業・手工芸など。自分のペースで働きたい方向け。 -
●
地域活動支援センターの特徴
雇用契約なし、収入基本なし。創作・交流・生活支援など。社会参加を優先したい方向け。
福祉的就労とは、障害や病気によって一般企業で働くことが難しい方に向けた福祉サービスです。代表的な種類は以下の3つです。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 地域活動支援センター
参考:厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
では具体的な特徴を見ていきましょう。
就労継続支援A型の特徴
就労継続支援A型は会社員と同じように雇用契約を結んで働く場所です。契約を結ぶので、国で決められた最低賃金より少ないお給料になることはありません。アルバイトのように安定した収入を得ることができます。
仕事内容の例
- 事務作業(パソコン入力、データ入力、電話応対)
- 軽作業(部品組み立て、検品、梱包、清掃)
- 接客・販売(カフェ・レストランの接客、商品陳列、レジ業務)
- 農作業・食品製造(パン作りなど)
- クリエイティブ業務(Webデザイン、イラスト作成)
向いている人
- 一般就労は難しいが、雇用契約に基づいて働ける方
- 将来的に一般就労を目指している方
- アルバイト並みの収入を得たい方
就労継続支援B型の特徴
就労継続支援B型は雇用契約を結ばず、自分のペースで無理なく働ける場所です。給与ではなく「工賃」という形で報酬が支払われます。年齢の制限がないことも特徴です。
仕事内容の例
- 軽作業(製品の仕分け、梱包、シール貼り)
- 清掃や洗濯などの家事補助
- 手工芸や創作活動
- 簡単な調理や農作業
向いている人
- 支援を受けながら働きたい方
- 無理のないペースで作業をしたい方
- 一般就労を目指して段階的に準備したい方
地域活動支援センターの特徴
雇用契約はなく、収入も基本的には発生しません。社会参加や生活支援を中心とした活動が行われる場です。
活動内容の例
- 創作活動や手工芸
- 交流・仲間づくりのためのグループ活動
- レクリエーションや外出イベント
- 日常生活の支援や訓練
向いている人
- 就労よりも社会参加や生活支援を優先したい方
- 働くことがまだ難しいが、社会とのつながりを持ちたい方
福祉的就労のメリット
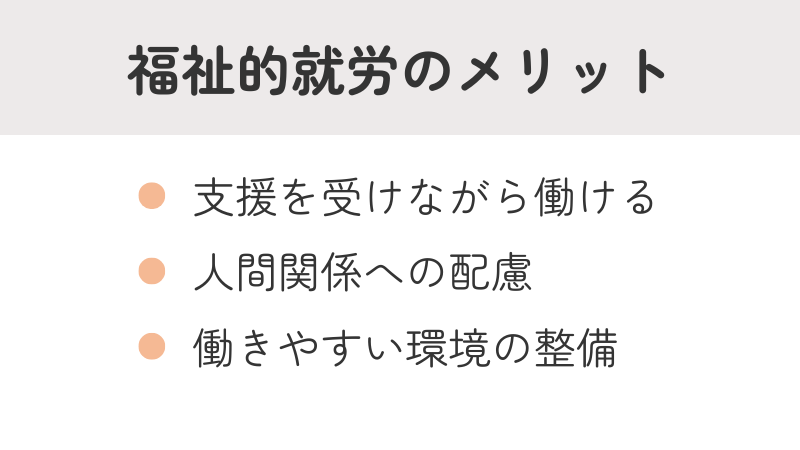
この章のポイント
-
●
支援を受けながら働ける
専門スタッフが相談や指導をしてくれる -
●
人間関係への配慮
個性や体調を尊重した安心できる環境 -
●
働きやすい環境
バリアフリーや休憩スペースなど、体調に配慮した職場
福祉的就労では、障害や体調の特性に合わせて無理なく働くことができます。柔軟な働き方が可能で、安心して過ごせる職場環境が整っているのも大きな特徴です。
支援を受けながら働ける
専門スタッフや職業指導員がサポートしてくれるため、困ったことがあってもすぐに相談ができます。自分一人で悩みを抱え込む心配はありません。
人間関係やコミュニケーションへの配慮
職場での人間関係のトラブルや孤立が起こりにくい環境が作られています。お互いの個性や体調を尊重する雰囲気が根付いています。
働きやすい環境の整備
車いすでも移動しやすいバリアフリー、疲れたときに休めるスペースなど、障害や体調に配慮した職場作りが行われています。
福祉的就労のデメリット
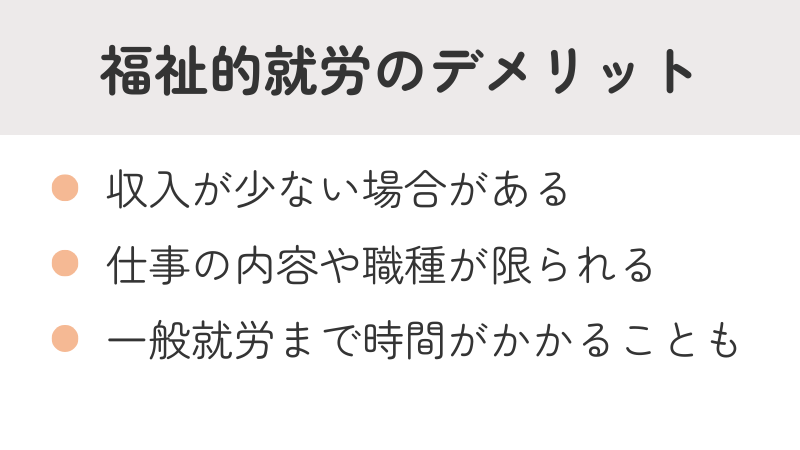
この章のポイント
-
●
収入が少ない場合がある
B型では最低賃金の保証がなく、工賃が低め -
●
職種や仕事の内容が限られる
希望する仕事内容が必ずしもあるわけではない -
●
一般就労まで時間がかかることがある
準備やスキル習得に時間が必要だが、A型・B型から一般就労への移行は可能
一方で、福祉的就労には以下のような注意点もあります。
収入が少ない場合がある
特に、就労継続支援B型では「工賃」と呼ばれる報酬が支払われますが、最低賃金の保証はなく、金額が低くなることが多いです。たくさん稼ぐことを目標にする場合には物足りなく感じるかもしれません。
仕事の内容や職種が限られる
施設ごとに業務内容が決まっているため、希望する職種や仕事内容が必ずしもあるわけではありません。
一般就労への移行に時間がかかる場合がある
福祉的就労は、すぐに一般企業で働くことが難しい方が、働く準備やスキルを身につける場として利用する制度です。そのため、一般就労に移るまでには時間がかかる場合があります。しかし、一般就労への移行は十分可能です。
厚生労働省の令和5年度データによると、就労継続支援A型からは約26.9%、B型からは約11.2%の方が一般就労に移行しています。このことから、福祉的就労は一般就労へのステップとして有効に活用できることがわかります。
参考:厚生労働省「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」
福祉的就労の注意点
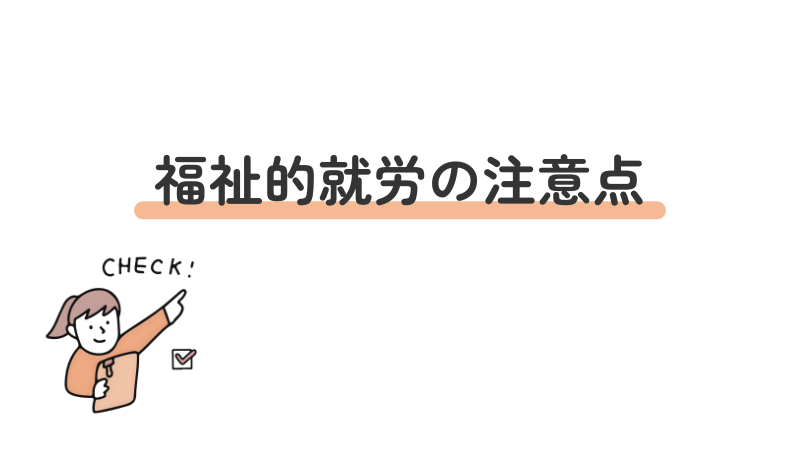
この章のポイント
-
●
利用料金の負担
利用者は原則1割負担。世帯の収入により自己負担上限が異なる。 -
●
副業・アルバイトの制限
福祉的就労中は原則禁止。収入確保が目的でないため、事前確認なしで行うと資格を失う可能性あり。
福祉的就労を利用する際には、いくつか注意しておきたい点があります。ここでは代表的な2点を紹介します。
利用料金の負担
| 区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得世帯 | 市町村民税が非課税の世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税され、所得割が16万円未満の世帯(注2)(注3) | 9,300円 |
| 一般2 | 所得割が16万円以上の世帯 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、収入が概ね300万円以下の世帯が「低所得世帯」に該当します。
(注2)「一般1」は、収入が概ね670万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設の利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税が課税されている場合、「一般2」に区分されます。
福祉的就労サービスは、原則として利用者が費用の1割負担する必要があります。
自己負担の上限は世帯の収入によって決まっており、生活保護を受けている世帯や市区町村民税が非課税の世帯では自己負担は0円です。一方、市区町村民税が課税されている世帯では、収入に応じて月9,300円か37,200円が上限となります。
また、利用料金のほかに昼食代や交通費などの実費がかかる場合もあります。事前に確認して必要な予算を考えておくことが大切です。
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
副業・アルバイトの制限
福祉的就労を利用している間は、原則として副業やアルバイトを行うことはできません。
これは、福祉的就労が働く準備や社会に参加する練習を目的としているためで、収入確保が目的ではないからです。
もし副業やアルバイトをしていることが分かると、一般就労が可能と見なされ、サービスを利用する資格を失う可能性があります。
ごくまれに例外として副業やアルバイトが認められるケースもありますが、必ず事前に自治体や事業所で確認するようにしましょう。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
福祉的就労について相談できる窓口
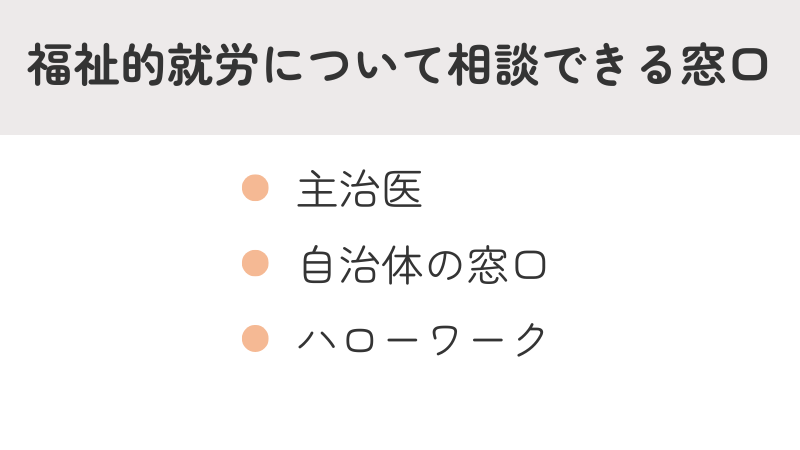
この章のポイント
-
●
働けるかどうかの相談:主治医
症状や体調に合わせた無理のない働き方や就労タイミングを相談 -
●
支援や制度の相談:自治体の障害福祉窓口
利用できるサービスや近くの事業所情報の案内 -
●
求人や仕事探し:障害者専門ハローワーク
職業適性の相談や事業所紹介、自分に合った働き方の参考に
福祉的就労や関連する制度について相談したいときは、内容によって窓口が分かれています。迷ったときは、相談内容に合わせて使い分けると安心です。
「働けるかどうか」の相談は主治医へ
働くことができるか、どの程度働くことが適切かなどは、主治医に相談してみましょう。症状や体調に応じて、無理のない働き方や就労のタイミングを一緒に考えてもらえます。
支援や制度のことは自治体窓口へ
支援内容や利用手続き、制度のことを知りたい場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に相談すると安心です。利用できるサービスや近くの事業所の情報も案内してもらえます。
求人や仕事探しはハローワークへ
仕事探しや求人情報を知りたい場合は、障害者専門のハローワークを利用するとよいでしょう。職業適性の相談や事業所紹介も行っており、自分に合った働き方を考える際の参考になります。
福祉的就労についてよくある質問
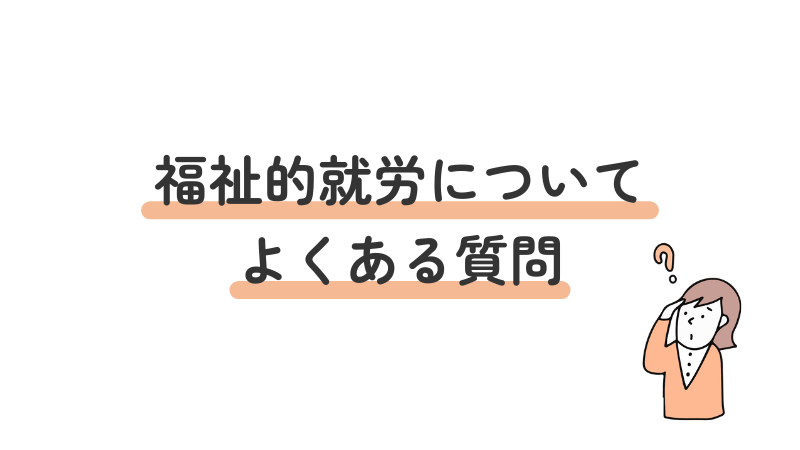
福祉的就労に関するよくある質問とその回答をまとめます。
利用するための条件は?
身体障害・知的障害・精神障害・難病などがある方が対象になります。利用には、市町村で発行される「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
就労継続支援A型には年齢制限があり、18歳以上65歳未満が対象です。
利用できる期間は決まっていますか?
原則として、明確な利用期限はありません。ご自身の体調や状況に合わせて、必要な期間だけ利用することができます。
障害者手帳がなくても利用できますか?
医師の診断書や意見書で障害が認められれば、手帳がなくても利用できる場合があります。
詳しくは自治体の担当窓口で確認してみるのがおすすめです。
利用料金はかかりますか?
原則として利用者は費用の1割を負担します。
ただし、月の自己負担額には上限があり、前年度の世帯の収入によって0円~約4万円程度までと決まっています。
どんな仕事ができますか?
清掃、軽作業、製造業務、事務作業、パソコン作業など、多様な仕事があります。
給料や工賃はどのくらいですか?
- 就労継続支援A型:86,752円(平均)
- 就労継続支援B型:23,053円(平均)
- 地域活動支援センター:基本的に支給なし
これはあくまで平均の金額です。詳しくは、事業所に確認してみましょう。
どこに相談すればいいですか?
- 「働けるかどうか」の相談は主治医へ
- 制度や申請、支援全般については、市区町村の福祉窓口や障害者就業・生活支援センターへ
- 求人や仕事探しは、ハローワーク障害者窓口や地域障害者職業センターで相談可能
まずは、体調や状況をよく知っている主治医に、福祉的就労が自分に合うかどうかを相談してみるのがおすすめです。
福祉的就労は障害のある方が安心して働くための選択肢のひとつ
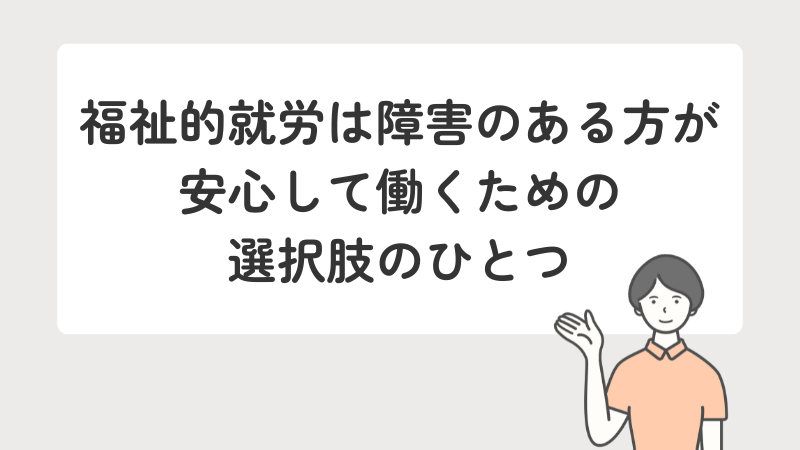
福祉的就労は、障害のある方が自分のペースで働きながらスキルを身につけられる場です。一般就労が難しい場合でも、支援を受けながら働くことで社会参加の一歩を踏み出すことができます。
ただし、賃金や副業の制限、利用料金などの注意点もあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
福祉的就労に興味がある場合は、まず主治医や自治体窓口、ハローワークなどに相談してみましょう。主治医は体調や就労可否の相談に、自治体窓口は制度や手続きに、ハローワークや障害者職業センターは求人情報や職業相談に対応してくれます。
それぞれの窓口に相談することで、状況に合ったアドバイスや支援を受けながら、自分に合った働き方を検討することができます。







