障害年金とは?初心者向けにやさしく解説

- 障害年金とは?
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 障害者手帳との違いとは?
- よくある誤解「重度じゃないと申請できない?」
- 障害年金の対象となる人とは?
- 精神障害でも受け取れる?
- 身体障害・難病・知的障害の対象範囲は?
- 働いていても受給できるの?
- 障害年金の等級と判断基準
- 等級はどう決まる?1級・2級・3級の違い
- 障害年金でもらえる金額の目安
- 基礎年金・厚生年金での支給額の違い
- 配偶者・子どもがいる場合の加算制度
- 扶養されている場合はどうなる?
- 障害年金を受け取るための3つの条件
- 条件1:初診日に関する要件
- いつ・どこの病院がカギになる
- 初診日が不明・病院が閉院していた場合の対応
- 初診日の証明に使える書類の例
- 条件2:保険料納付に関する要件
- 条件3:障害の状態に関する要件
- 65歳以上は原則対象外?例外はある?
- 障害年金の申請方法と手続きの流れ
- どこに相談すればいい?
- 申請に必要なもの
- 審査に落ちた場合の対応(不服申し立て)
- 支給決定後の流れと受給のタイミング
- 年金証書が届くまでの期間
- 初回支給日はいつ?振込日の目安
- 支給が始まった後も更新が必要?
- 症状が軽くなったらどうなる?
- 障害年金を受け取りながら働くときの注意点
- 働いても受給は可能?収入の目安とは
- 働きすぎると支給停止になる?
- 働く場合の申告義務と注意点
- 障害年金のメリットとデメリット
- メリット
- デメリット
- 障害年金の申請に迷った時の判断ポイント
- 主治医にどう伝える?相談する時のポイント
- 障害年金について相談できる窓口
- 障害年金に関するよくある質問
- 障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?
- 生活保護と併用できる?
- 働きながら障害年金はもらえる?
- 申請にはどれくらい時間がかかる?
- 支給が決まったら、いつからお金がもらえる?
- 申請が通らなかった場合、再チャレンジできる?
- 障害年金は「悩んでいる今のあなた」にも使える制度です
病気やケガで、これまで通りの生活や仕事ができなくなってしまった時、お金の心配は尽きないものです。
そんな不安を少しでも軽くしてくれるのが、「障害年金」という制度です。年金というと高齢になってから受け取るものと思われがちですが、障害年金は年齢に関係なく、病気やケガによって生活や仕事に大きな制限がある方が受け取れる仕組みです。
この記事では、障害年金がどんな制度なのか、どんな人がもらえるのか、わかりやすく説明します。
この記事のまとめ
-
●
障害年金とは
障害年金は、病気やケガが原因で日常生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代でも受け取れる公的年金 -
●
働きながらでも受給可能
就労していても障害年金を受け取れるが、働き方によっては更新時に支給が停止される可能性がある
障害年金とは?
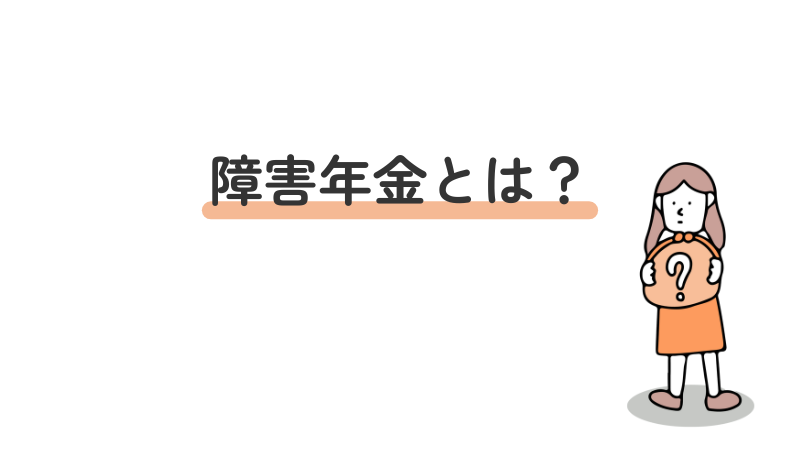
この章のポイント
- ● 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がある
- ● 障害者手帳とは全く違う制度
- ● 日常生活や仕事に「ある程度の支障」があれば、申請できる
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障や制限が生じた場合に受け取ることができる「公的年金」です。年齢は関係なく、高齢者だけでなく現役世代でも要件を満たせば受給の対象になります。
参考:日本年金機構「障害年金」
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分かれており、サラリーマンか自営業者によって対象が異なります。「障害基礎年金」は主に自営業者や無職、学生などが対象で、「障害厚生年金」は会社員等が対象になります。
| 種類 | 対象者 | 障害等級 | 支給額 | 併給 |
|---|---|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 国民年金の加入者 | 1級・2級 | 一律の定額(子ども加算あり) | – |
| 障害厚生年金 | 厚生年金の加入者 | 1級・2級・3級 | 働いていた時の収入に応じて計算(配偶者加給あり) | 1・2級は基礎年金もあわせて受給、3級は厚生年金のみ |
障害厚生年金は、障害基礎年金に比べて支給の範囲や金額が手厚いという特徴があります。この点については後ほど具体的に説明します。
障害者手帳との違いとは?
障害年金と障害者手帳は、名前が似ていますが全く別の制度です。目的や申請先、サポートの内容が異なります。
| 制度 | 運営主体 | 申請窓口 | サポート内容 | 等級基準 |
|---|---|---|---|---|
| 障害年金 | 国(日本年金機構) | 年金事務所など | 現金給付(年金) | 年金制度独自の基準 |
| 障害者手帳 | 地方自治体 | 市区町村役所 | 税控除、医療費や交通機関の割引など | 手帳制度ごとの基準 |
障害年金と障害者手帳は、それぞれ独立した別の制度です。そのため、手帳がなくても受給することができます。
よくある誤解「重度じゃないと申請できない?」
「障害年金は、とても重い障害がないともらえない」と思っている方がいますが、それは間違いです。実は、障害年金は日常生活や仕事に「ある程度の支障」があれば、申請や受給が可能です。
障害年金の対象となる人とは?
この章のポイント
- ● 病名だけではなく「症状が長く続き、日常生活や仕事にどのくらい支障があるか」が重要
- ● 働いていても受給できるが、働き方によっては審査に影響が出る場合がある
年金種類ごとの主な対象者は以下の通りです。
| 年金種類 | 主な対象者の例 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入していた人(自営業、学生、専業主婦など) 20歳未満で初診日のある人60~65歳未満で国内に住み、未加入期間に初診日のある人 |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金加入中(主に会社員、公務員等)の人 |
参考:日本年金機構「障害等級表」
精神障害でも受け取れる?
「障害年金」と聞くと、身体の病気やケガが原因でもらうもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、実は精神障害も障害年金の対象になるのです。対象となる精神障害の例は、次のとおりです。
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- 認知症などの認知障害
- てんかん
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
これらの障害により、日常生活を送ることが難しくなったり、今まで通りに働けなくなったりした場合に障害年金をもらえる可能性があります。
ただし、すべての精神障害が受給の対象になるわけではありません。人格障害、神経症、アルコール依存症、薬物依存症などは、原則として障害年金の対象外です。
参考:日本年金機構「年金Q&A 障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。」
「障害認定基準 精神の障害」
身体障害・難病・知的障害の対象範囲は?
障害年金は、身体の障害、難病、知的障害など、様々な病気や障害が対象になります。ここでは、それぞれの対象範囲をわかりやすくまとめます。
1. 身体障害の対象範囲
ケガや病気が原因でこれまでのように生活や仕事をすることが難しくなった場合、障害年金を受け取れることがあります。
対象となる例は次のとおりです。
具体的には、次のような障害が挙げられます。
- 視覚障害(視力が弱い、視野が欠けるなど)
- 聴覚障害(聞こえにくい、失聴など)
- 声や言葉の障害
- 手足などの機能障害、欠損、変形
症状が長く変わらず回復が見込めない場合は、認定されやすくなります。
2. 難病(内部障害)の対象範囲
原因がはっきりしない病気や、治療法がまだ見つかっていない難病も対象になります。指定難病だけでなく、指定外の難病が対象となる場合もあります。体の内部に関わる病気も含まれます。
具体例は次のとおりです。
- 呼吸器疾患
- 心疾患
- 腎疾患
- 肝疾患
- 血液・造血器疾患
- 糖尿病
- がん
大切なのは病名そのものではなく、その病気によってどれだけ長く日常生活や仕事に制限があるかです。
例えば「すぐ疲れて家事ができない」「少し歩くだけで息切れがする」などの状態が判断のポイントになります。
3. 知的障害の対象範囲
知的障害も障害年金の対象です。精神障害の一つとして扱われます。
病気や診断名があるだけではなく、次のような状態が重要になります。
- 働くことが難しい
- 仕事の内容や量に大きな制限がある
こうした状況であれば、障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金は、身体障害・難病・知的障害・精神障害まで対象がとても幅広い制度です。認定のポイントは「症状が長く続いていること」と「日常生活や仕事に制限があること」です。自分が障害年金の対象になるのか不安な場合は、社会保険労務士や公的機関に相談することをおすすめします。
参考:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
働いていても受給できるの?
| 障害の種類 | 就労しながら受給している割合(2019年) |
|---|---|
| 身体障害 | 48.0% |
| 知的障害 | 58.6% |
| 精神障害 | 34.8% |
「働いているから障害年金はもらえない」と誤解している方は少なくありません。ですが、実際には働きながらでも障害年金を受け取れる場合があります。ただし、フルタイムで働いているなど、病気や障害が軽いと判断される働き方をしていると、審査に影響が出る可能性があります。
2019年のデータによると、障害年金をもらっている方のうち、身体障害がある方の約48%、知的障害がある方の約58%、精神障害がある方の約35%が、働きながら障害年金を受け取っています。この数字から、障害年金は働いていない人だけがもらえるものではないことが分かります。
ただし、どのくらい働いているかや、どんな仕事をしているかによって審査に影響が出る場合があります。
参考:厚生労働省「障害年金制度」
障害年金の等級と判断基準
この章のポイント
-
●
障害年金の等級の判断基準
障害の重さや日常生活・仕事への影響度によって、国が定めた「障害認定基準」で決まる -
●
等級は1級、2級、3級があり、それぞれ判断基準が異なる
3級は障害厚生年金のみ
障害年金の等級は、障害の重さや日常生活・仕事への影響の程度をもとに、国が定める「障害認定基準」に基づいて審査されて決まります。それぞれの違いと判断基準は以下のとおりです。
等級はどう決まる?1級・2級・3級の違い
| 等級 | 特徴 | 日常生活 | 労働 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 最も重度。ほぼ寝たきりや常時介助が必要 | 自分ひとりで日常生活のすべてができず、身の回りのこともほぼ介助が必要 | 原則として働けない |
| 2級 | 重度。必ずしも常時介助は必要ないが、日常生活に著しい制限がある | 単独での活動範囲が限定され、日常生活が極めて困難で他人の助けが必要な場面が多い | 通常の仕事ができず、安定した収入を得るのは困難 |
| 3級 | 2級より軽度。労働に著しい制限がある(厚生年金のみ) | 家事や日常生活は大きな制限なしの場合もあるが、仕事面で配慮が必要 | 障害のため通常通り働くことが困難で、仕事内容や勤務時間が配慮される場合がある |
等級は、身体障害・精神障害・知的障害などそれぞれの障害ごとに国が定めた基準に沿って判定されます。
3級は障害厚生年金のみの等級で、会社員や公務員など厚生年金加入者が対象です。
参考:日本年金機構「障害等級表」
障害年金でもらえる金額の目安
この章のポイント
- ● もらえる金額は、障害の等級と加入している年金の種類で異なる
- ● 配偶者や子供がいる場合、受け取る金額に加算される部分がある
- ● 扶養家族になっていることは、障害年金をもらうための制限にならない
障害年金は、障害の等級や加入している年金の種類によって受け取れる金額が異なります。2025年度の目安は以下の通りです。
| 等級 | 障害基礎年金(月額) | 障害厚生年金(月額) | 厚生3級の最低保証 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 86,635円 | 基礎年金1級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給等 | — |
| 2級 | 69,308円 | 基礎年金2級 + 報酬比例部分 + 配偶者加給等 | — |
| 3級 | 支給なし | 報酬比例部分のみ | 約51,983円(月額)/623,800円(年額) |
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の年額は、1級:1,036,625円、2級:829,300円です。
基礎年金・厚生年金での支給額の違い
- 2025年度の障害基礎年金:1級は月額86,635円、2級で69,308円
- 厚生年金は報酬比例部分+基礎年金(1・2級のみ)となり、金額は個人ごとに異なる
報酬比例部分とは?
障害厚生年金は、「報酬比例部分」というお金がもらえるのが大きな特徴です。報酬比例部分とは、これまでの給料や働いた期間によって決まる金額のことです。
具体的には、障害厚生年金は「2階建て構造」となっています。
- 1階部分:障害基礎年金で、全員に支給される定額の金額
- 2階部分:報酬比例部分で、厚生年金に加入していた期間中の平均標準報酬月額と加入期間に基づいて算出
報酬比例部分が多いほど、受け取れる障害厚生年金の額も大きくなります。
等級による違いもあります。
- 1級:報酬比例部分 × 1.25倍
- 2級:報酬比例部分そのまま
- 3級:最低保証あり
簡単に言うと、報酬比例部分は「これまでの働きぶり(給与水準)」に基づいて決まる給付部分であり、給与が高かったり、長期間厚生年金に加入しているほど多く支給されます。この仕組みによって、厚生年金加入者はより実際の収入に近い金額の障害年金を受け取ることができるようになっています。
参考:日本年金機構「報酬比例部分」
配偶者・子どもがいる場合の加算制度
配偶者や子供がいる場合、受け取る金額に加算される部分があります。
子供がいる場合の加算
子供がいると、障害基礎年金と障害厚生年金の両方で、もらえる金額が上乗せされます。
1人目・2人目:1人につき月19,941円
3人目以降:1人につき月6,650円
この加算は、18歳になる年度の終わりまでの子供か、20歳になるまでの障害等級1級か2級の子供がいる場合にもらえます。
参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額 子の加算額」
2. 配偶者がいる場合の加算
障害厚生年金の1級か2級を受け取っている場合、月19,941円が加算されます。
ただし、配偶者が65歳未満で、一定の収入を超えていないことが条件です。障害基礎年金には配偶者加算はありません。
参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額 配偶者の加給年金額」
扶養されている場合はどうなる?
扶養家族になっていること自体は、障害年金をもらうための制限にはなりません。ただし、加算がもらえるかどうかは、家族の関係や収入などの細かい条件で決まります。
障害年金を受け取るための3つの条件
この章のポイント
-
●
障害年金を受け取るには、3つの条件をすべて満たす必要がある
①初診日 ②保険料の納付状況 ③障害の重さが国の基準に当てはまる -
●
原則として65歳以上の場合は、障害年金をもらうことはできない
しかし、初診日が65歳になる前であればもらえる可能性がある
障害年金を受け取るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初診日 | 原因となった傷病で最初に医師の診察を受けた日(病院名・日付が重要) |
| 受給権 | 年金資産を受け取る権利のこと |
| 納付要件 | 原則:保険料を3分の2以上納付または免除 例外:直近1年間に未納がない |
| 障害状態 | 障害認定日に該当等級の障害状態があること |
| 障害認定日 | 初診日から1年6か月経過した日、または症状が固定した日 |
| 65歳以上 | 初診日が65歳以上は原則不可 |
条件1:初診日に関する要件
障害の原因となった傷病(病気やケガ)で「初めて医師の診療を受けた日」が初診日です。障害年金では、この初診日が非常に重要で、どの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたかで受給権の種類と有無が決まります。
いつ・どこの病院がカギになる
最初に診察を受けた病院と日にちが、原則として初診日となります。
もし途中で別の病院に変わっていたとしても、一番最初に診察を受けた日が初診日です。
初診日が不明・病院が閉院していた場合の対応
初診日が不明・病院が閉院していた場合は、様々な書類を使って初診日を証明することができます。
初診日の証明に使える書類の例
- 障害者手帳:手帳に書かれている発行日や診断書の日付から、初診日を証明できる場合があります。
- 健康診断の記録:昔の健康診断で「異常あり」と書かれていた場合、その後の治療のために初めて病院に行った日が初診日となります。
- 母子健康手帳(母子手帳):母子手帳に、生まれた時から病気や障害があったことが書かれていれば、20歳になる前の障害だと証明できます。
- 健康保険の記録:健康保険組合などに頼んで、過去の病院の記録(レセプト)を取り寄せることができれば、初診日を証明する大切な資料になります。
- お薬手帳や診察券:お薬手帳には、いつ、どんな薬をもらったかの記録が残っています。また、昔の診察券や領収書にも初診日が分かる情報が載っている場合があります。
- 学校の記録:小学校や中学校の健康診断の記録や成績表に病気や障害のことが書かれていれば、初診日を証明する資料になります。特に、知的障害などで使えることがあります。
- 第三者証明:もし、どんな書類も残っていない場合は、近所の人や友人など3親等ではない2人以上の人に当時の様子を証明してもらうことで、初診日を認めてもらえることがあります。医療関係者の証明であれば、1人でも認められる場合があります。
できるだけ「初診日」に近い医療機関の記録や第三者証明を提出し、総合的に判断されます。初診日が特定できない場合でも、本人申立てや客観資料をもとに認定されることがあります。
参考:日本年金機構「障害年金の初診日証明書類のご案内」
条件2:保険料納付に関する要件
障害年金を受けるには、年金保険料を一定程度納めていることが必要です。基本的には、初診日の前々月までの期間で「納付済期間+免除期間」が全期間の3分の2以上であることが求められます。
ただし、例外として、直近1年間に未納がなければ受給可能な場合もあります。また、20歳前に発症した場合は保険料の納付要件はありません。
条件3:障害の状態に関する要件
病気やケガがどれくらい重いか、国の決めた「障害認定基準」に当てはまっていることも大切です。
障害認定日に、障害等級の1級、2級、または3級(厚生年金の場合)の障害の状態になっていることが必要です。
参考:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
65歳以上は原則対象外?例外はある?
原則として65歳以上の場合は、障害年金をもらうことはできません。しかし、初診日が65歳になる前であればもらえる可能性があります。
障害年金の申請方法と手続きの流れ
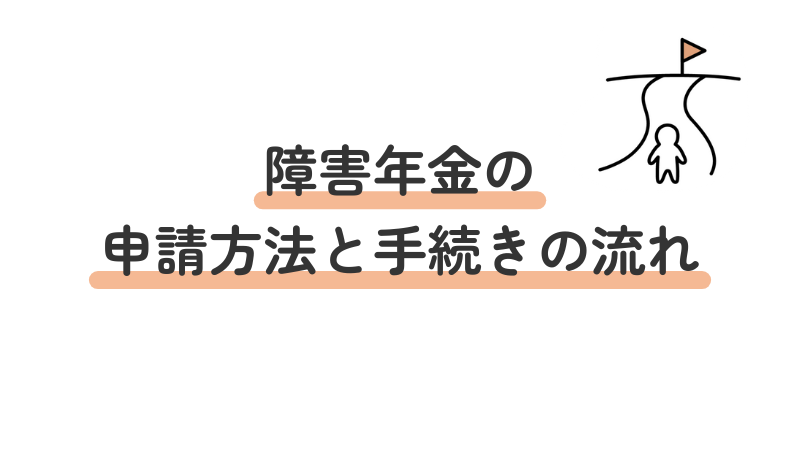
この章のポイント
-
●
まずは医療機関で相談
専門的なサポートが必要な場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談も有効 -
●
審査に落ちた場合
通知を受け取ってから3ヶ月以内に「不服申し立て」ができる
障害年金は、自動的に受け取れるものではなく、本人が申請してはじめて受給できる制度です。老齢年金のように、一定の年齢になると書類が届く仕組みはありません。そのため、障害年金を受け取るには、自分で必要な書類をそろえて申請手続きを行う必要があります。ここでは、障害年金の申請方法や必要な書類について説明します。
どこに相談すればいい?
まずは医療機関で相談してみましょう。障害基礎年金の場合は、自治体の窓口でも相談できます。手続きの流れや必要書類について案内してもらえます。さらに専門的なサポートが必要な場合は、年金事務所や社会保険労務士への相談も有効です。社会保険労務士は、申請の代行まで依頼できる点が大きな特徴です。
申請に必要なもの
障害年金を申請する際に必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容・確認事項 |
|---|---|
| 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | ご本人の生年月日を確認するための書類です。 |
| 医師の診断書(所定様式) | 障害の状態を証明するための最も重要な書類です。所定の様式があり、障害認定日から3ヶ月以内に書かれたものが必要になります。 |
| 受診状況等証明書 | 初診医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合に、初診日を確認するために使用します。 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 障害状態や日常生活・就労状況を補足するための書類です。 |
| 受取先金融機関の通帳など(本人名義) | 年金の振込先を確認するために必要です。 |
以下のような特別な場合は、さらに追加で書類が必要になります。
- 配偶者や子供がいる場合:加算として年金額に反映される場合があります。そのため、家族の関係を証明する書類が必要になります。
- 障害の原因が、交通事故など第三者の行動にある場合:交通事故証明書などの書類が必要になります。
参考:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」
「障害厚生年金を受けられるとき」
審査に落ちた場合の対応(不服申し立て)
申請したけれど、残念ながら審査に通らなかった場合でも、諦める必要はありません。審査の結果に納得できない場合は、「不服申し立て」という手続きを行うことができます。不服申し立ては、通知を受けてから3か月以内に行う必要があります。
申立て後は、再審査や専門の審査会での審理が行われ、支給が認められれば年金が決定・再開されます。
不服申し立ての手続きは、専門的な知識が必要な場合もあります。もし不安な場合は、社会保険労務士に相談してみることをおすすめします。
参考:日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」
支給決定後の流れと受給のタイミング
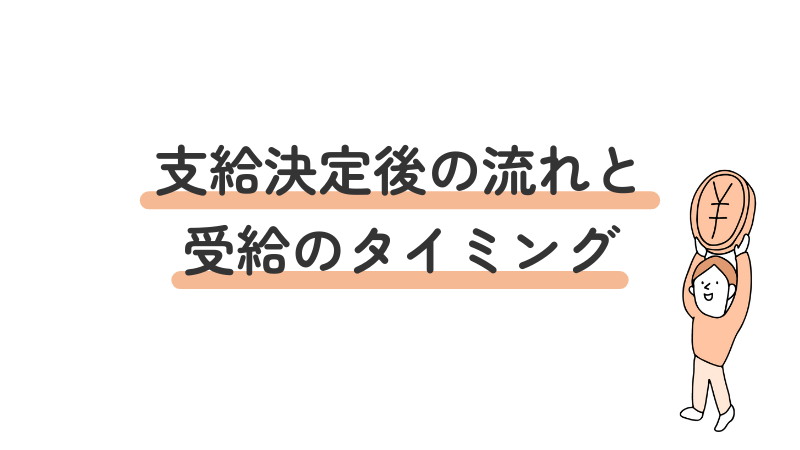
この章のポイント
-
●
最初の支給日
「年金決定通知書」が届いてから、およそ50日後に初回の年金が振り込まれることが多い -
●
更新手続きは必要?
障害年金は、一度もらえたら終わりではなく定期的に更新手続きが必要 - ● 症状が改善して基準に該当しなくなると、支給が停止される場合がある
障害年金は支給が決定した後も、いくつかの手続きや確認があります。ここでは、支給決定後の流れや受給のタイミングについて解説します。
年金証書が届くまでの期間
障害年金の審査に通ると、日本年金機構から「年金決定通知書(年金証書)」が自宅に届きます。この書類には、もらえる金額や年金の開始日、次回の更新時期など、今後の受給に関する重要な情報が記載されています。支給決定から通知書が届くまでには、数週間から1か月程度かかることがあります。
初回支給日はいつ?振込日の目安
初回の年金支払いは、年金証書の作成日からおおよそ50日後に行われることが一般的です。
参考:厚生労働省「障害基礎年金のお手続きの完了について」
支給が始まった後も更新が必要?
障害年金は、一度もらえたら終わりではありません。ほとんどの場合、障害の状態が続いているかを確認するための「更新」という手続きが必要です。
更新期間は障害の種類や等級によって異なり、1年~5年ごとに日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されます。
受給者は、指定の期限までに住所や氏名を記入し、医師に障害の現状を診断してもらった書類を提出する必要があります。更新の審査で症状に変化がなければ、同等の等級で支給が続きます。
症状が軽くなったらどうなる?
症状が改善し、障害等級に該当しなくなると、障害年金の支給は終了することがあります。将来、もしまた病気やケガが悪化して生活が大変になった場合は、もう一度申請して年金をもらうことが可能です。
障害年金を受け取りながら働くときの注意点
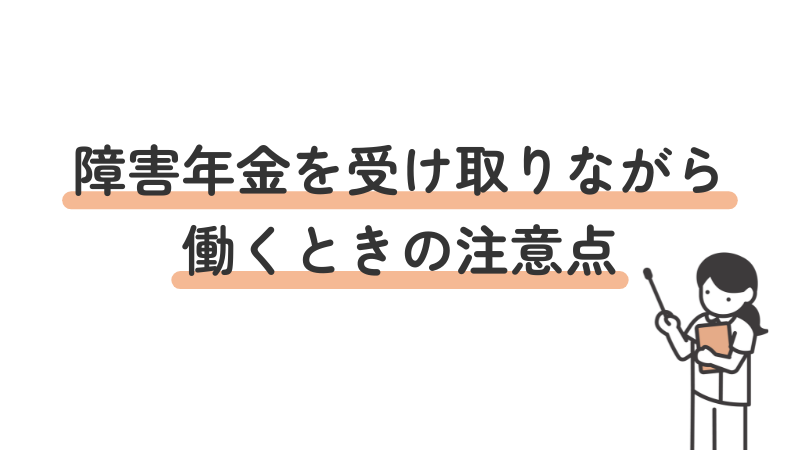
この章のポイント
-
●
収入の目安
障害年金は「障害の重さ」で決まるため、働くこと自体が支給停止の理由にはならない -
●
就労状況の申告義務
申請や更新の際、働き方を正確に申告する必要がある -
●
支給に影響する働き方
障害の程度が軽いと判断されかねない働き方をしていると、支給が停止される場合がある
障害年金を受給しながら働く場合には、いくつかの注意点があります。ここでは、申告義務や収入の目安について解説します。
働いても受給は可能?収入の目安とは
障害年金は「障害の重さ」によってもらえるかどうかが決まります。ですから、働いているからといって、すぐに年金がもらえなくなることはありません。実際に、年収400万円を超えても受給を継続している方もいます。
本人労働収入階級別構成割合(単位:%)
| 本人の仕事による年間収入(単位:万円) | ||||||||||
| 制度 | 等級 | ~50 | 50~100 | 100~150 | 150~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~ | 不明 |
| 厚生年金(障害厚生年金) | 計 | 25.3 | 14.9 | 11.8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 6.7 | 8.9 | 1.5 |
| 1級 | 31.0 | 17.0 | 10.1 | 7.4 | 13.7 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | |
| 2級 | 27.9 | 15.2 | 11.7 | 7.7 | 12.8 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 1.8 | |
| 3級 | 22.6 | 14.5 | 12.0 | 9.2 | 13.1 | 11.2 | 6.5 | 9.9 | 1.0 | |
| 国民年金(障害基礎年金) | 計 | 53.3 | 15.9 | 12.7 | 4.6 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 3.2 |
| 1級 | 56.2 | 9.9 | 8.4 | 6.4 | 6.8 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | |
| 2級 | 52.1 | 18.4 | 14.6 | 3.9 | 3.5 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 3.1 | |
この表は、厚生年金・国民年金の加入者が1年間に得た収入を等級別にまとめたものです。
参考:政府統計の総合窓口(e-Stat)「年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)令和元年 集計結果の概要」
働きすぎると支給停止になる?
障害年金は、原則として働いていることや所得による制限はありません。
ただし、20歳前に発症した障害基礎年金の場合のみ、前年の所得が一定額を超えると支給額が減額されたり停止されることがあります。
- 所得が一定額以下:全額支給
- 所得が一定額を超えると:半額支給または全額停止
※給与所得控除や扶養親族数によって計算が変わります。
障害等級が1級の受給者の所得による支給制限
| 年齢帯 | 前年の本人の所得額 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 4,721,000円を超える(全額停止) | 0円 |
| 3,704,001円から4,721,000円(2分の1の年金額停止) | 519,813円 | |
| 3,704,000円以下(全額支給) | 1,039,625円 | |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 4,721,000円を超える(全額停止) | 0円 |
| 3,704,001円から4,721,000円(2分の1の年金額停止) | 518,313円 | |
| 3,704,000円以下(全額支給) | 1,036,625円 |
障害等級が2級の受給者の所得による支給制限
| 年齢帯 | 前年の本人の所得額 | 支給金額 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 4,721,000円を超える(全額停止) | 0円 |
| 3,704,001円から4,721,000円(2分の1の年金額停止) | 415,850円 | |
| 3,704,000円以下(全額支給) | 831,700円 | |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 4,721,000円を超える(全額停止) | 0円 |
| 3,704,001円から4,721,000円(2分の1の年金額停止) | 414,650円 | |
| 3,704,000円以下(全額支給) | 829,300円 |
※所得には給与所得控除後の金額や扶養親族数による加算があります。
参考:日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
働く場合の申告義務と注意点
障害年金を受給しながら働く場合、いくつか注意すべき点があります。
1. 就労状況の申告義務
障害年金の申請や更新、再認定などの手続きの際に提出する診断書や報告書には、就労状況や働き方を正確に記載する必要があります。虚偽の申告をすると、不正受給とみなされる場合があります。
2. 会社への報告義務
原則として、会社に障害年金を受給していることを報告する必要はありません。就業規則で特別に定められていない限り、申告は不要です。
3. 支給に影響する働き方
障害年金を受給しながら働くこと自体が支給停止の原因になるわけではありません。しかし、働き方によっては「障害の程度が軽い」と判断され、更新の審査で年金が打ち切られることがあります。
障害の程度が軽いと判断されやすい働き方の例
- フルタイム勤務:週5日、朝から晩までの勤務
- 特別な配慮がない:仕事の内容や勤務時間に対して、会社から支援や配慮をしてもらっていない
障害年金のメリットとデメリット
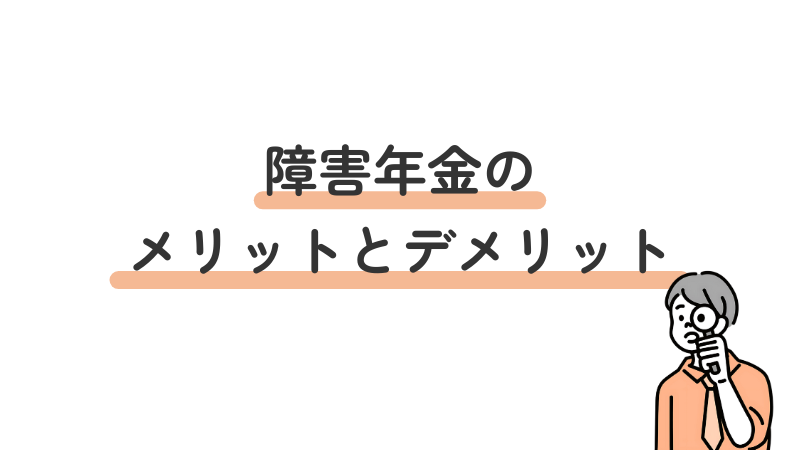
この章のポイント
-
●
メリット
生活の安定/国民年金保険料の免除/働きながら受給可能 -
●
デメリット
申請手続きの複雑さ/周囲に知られることへの不安/併用制度に影響が出る可能性
病気やケガでつらい生活を送っている方にとって、障害年金は大きな支えとなります。ただし、良い面ばかりではありません。ここでは、障害年金をもらうことのメリットとデメリットを整理して紹介します。
メリット
安心して療養や生活の立て直しに集中できる
障害年金をもらうことで、定期的な収入を得られます。お金の心配が減ることで、焦らずに治療に専念したり、ゆっくりと生活を立て直したりする時間が作れます。
国民年金保険料の法定免除
障害年金の1級または2級を受給すると、国民年金の支払いは免除となります。これを法定免除といいます。免除期間は半額を支払ったとみなして計算されるため、将来の老齢基礎年金にも半額が反映されます。年金額を満額にしたい場合は、追加で保険料を納付することも可能です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
働きながらも受給可能
一定の条件を満たせば、仕事をしていても障害年金をもらい続けることができます。「年金をもらうために仕事を辞めなければいけない」と心配する必要はありません。
デメリット
申請が複雑
受給申請には、多くの書類や詳細な診断書など準備が必要で手間や不安を感じやすいです。
周囲に知られることへの不安
制度上はプライバシーが守られますが、書類の手続きなどで、どうしても身近な人に知られてしまう可能性はゼロではありません。
併用制度に影響が出る可能性もある
障害年金は、他の公的制度や生活状況によって支給額や受給条件に影響が出ることがあります。主なポイントは以下の通りです。
- 老齢年金:原則どちらか一方のみ。65歳時に受給方法を選択。条件次第で組み合わせも可能。
- 傷病手当金・労災保険:同一の傷病では満額併給できず調整。異なる傷病なら併用可能な場合も。
- 生活保護:形式上は併給可能だが、障害年金分が差し引かれ、合計が最低生活費を上回らないよう調整。
- 児童扶養手当・遺族年金など:障害年金と同時に受給できない場合や減額調整される場合がある。
- 20歳前障害基礎年金:所得制限あり。一定以上の所得があると支給停止・減額される。
障害年金の申請に迷った時の判断ポイント
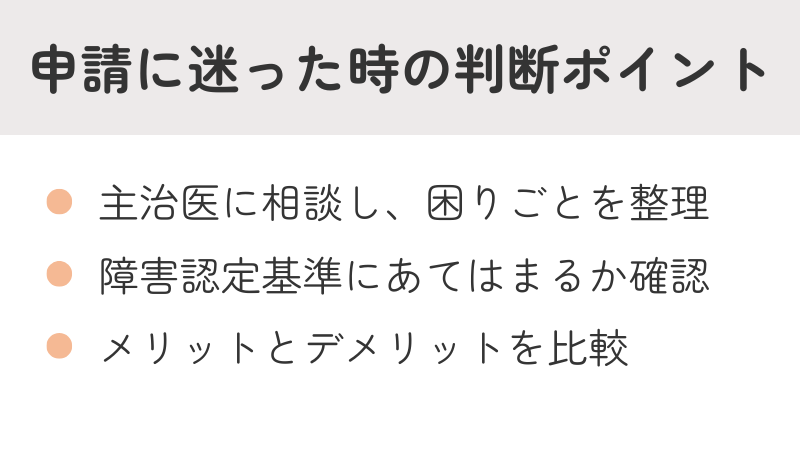
この章のポイント
- ● 主治医に相談する際には、日常生活でどのような困難があるかを具体的に伝えることが重要
-
●
障害年金について相談できる窓口
年金事務所/街角の年金相談センター/社会保険労務士 など
障害年金は手続きが複雑で、「自分はもらえるのだろうか」と悩む人が少なくありません。ここでは、申請に迷ったときにどうすれば良いか、判断するためのポイントを説明します。
まずは主治医に相談し、困りごとを整理する
医師は診察室での様子しか把握できないことが多いため、障害年金の診断書を作成する際には、生活上の困難を具体的に整理して伝えることが重要です。「食事の準備ができない」「通院に付き添いが必要」「人混みに出るのが不安」といった具体例を挙げると、診断書が障害認定基準に沿った内容になりやすくなります。
書類作成や手続きに不安がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談すると安心です。
障害認定基準にあてはまるか確認する
障害年金には「障害認定基準」があり、等級ごとにどんな状態が対象かが定められています。自分の状態がどの等級に近いかをチェックしてみましょう。少しでも該当する可能性があれば、申請を検討する価値があります。
メリットとデメリットを比較する
申請には手間や時間がかかるというデメリットがあります。それでも申請した方がいいか、メリットと比較して考えてみましょう。
- メリット:年金の受給で生活が安定し、治療や生活の立て直しに専念できる。1級・2級の場合は国民年金保険料の免除もある
- デメリット:書類作成や通院など手間がかかる、不支給になる可能性もある
しかし、申請して不利益になることはほとんどありません。もし不支給になっても、再申請や不服申し立てを行うことも可能です。
主治医にどう伝える?相談する時のポイント
主治医に障害年金について相談する際には、日常生活でどのような困難があるかを具体的に伝えることが重要です。医師は診察室での様子しか把握できないため、普段の生活状況を正確に伝える必要があります。
伝えるときのコツ
- 具体的な例を話す:単に「体調が悪い」と伝えるのではなく、具体的な場面を話すことが大切です。「食事がうまく作れない」「人が多い場所に出かけるのが怖い」「一人で通院するのが難しい」といった、日常生活で実際に困っていることを詳しく話しましょう。
- 診断書に書いてほしいことを率直に伝える:精神的な病気の場合、特に日常生活のつらさを診断書に反映してもらうことが大切です。具体的にどのような内容を診断書に記載してほしいのかを、遠慮せずに医師に伝えましょう。
- 家族に手伝ってもらう:本人がうまく話せない場合は、家族に同席してもらい、普段の様子を説明してもらうのも良い方法です。第三者の視点から、より客観的な情報を伝えることができます。
これらのポイントを踏まえて、主治医に相談することで、適切な診断書を作成してもらい、スムーズな申請手続きにつなげることができます。
障害年金について相談できる窓口
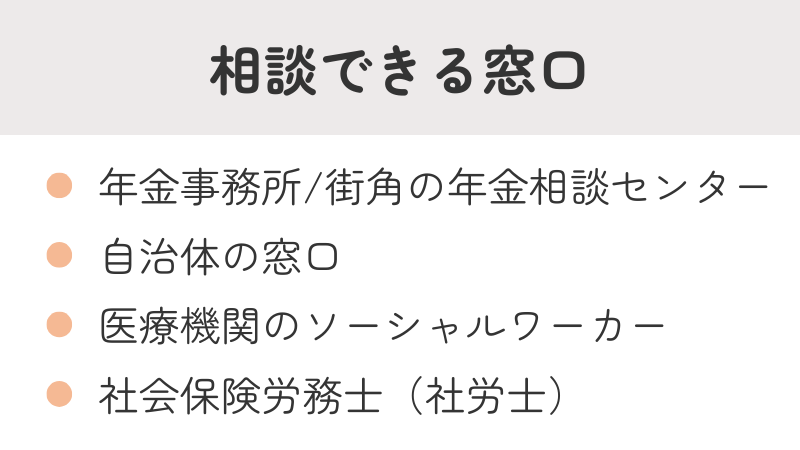
障害年金の申請や手続きは複雑で、一人で進めるのは難しいかもしれません。そんなときは、専門家や詳しい方に相談することが大切です。ここでは代表的な相談窓口を4つ紹介します。
年金事務所/街角の年金相談センター
年金に関する相談は、まず年金事務所や街角の年金相談センターに行くのが一番確実な方法です。ここでは、障害年金がもらえる条件や等級の決め方、必要な書類の書き方など制度に関する情報を正確に教えてもらえます。混み合うことが多いので、事前に予約しておくとスムーズです。
参考:全国社会保険労務士会連合会「街角の年金相談センター一覧」
自治体の窓口(保険年金業務担当窓口)
障害基礎年金に関しては自治体の窓口でも相談できます。ここでは障害基礎年金の申請手続きのほか、地域ごとの福祉サービスや、生活を助けてくれる別の制度についても教えてもらえることがあります。地域に密着しているので、年金以外の困りごとにも対応してくれるのが良い点です。
医療機関のソーシャルワーカー
大きな病院などには、ソーシャルワーカーという専門家がいます。日常生活や通院で困っていること、医師に診断書を書いてもらう際の相談に乗ってくれます。医師との間に入って、手続きをスムーズに進めてくれる役割も担います。
社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士は、年金や労働の専門家です。書類の作成や申請の手続きを代わりに行ってくれます。もし審査に落ちてしまった場合でも不服申し立ての手続きをサポートしてくれます。専門家に任せることで申請のミスを防ぎ、受給の可能性を高められます。初回相談無料の事務所も多いため、費用やサービス内容を事前に確認しておくと安心です。
障害年金に関するよくある質問
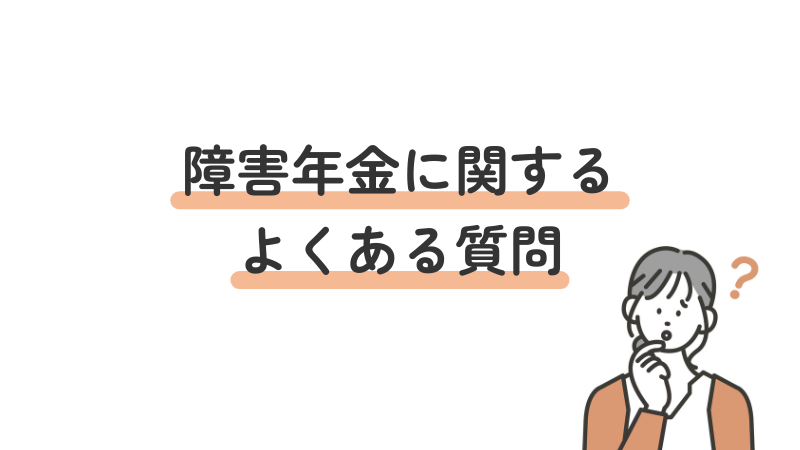
障害年金に関するよくある質問に答えていきます。
障害者手帳がなくても障害年金はもらえる?
障害年金は障害者手帳がなくても受給可能です。障害年金と障害者手帳は、それぞれ目的や基準が違う別の制度です。そのため、手帳の有無に関係なく障害年金の受給条件を満たせば申請・受給できます。
生活保護と併用できる?
障害年金と生活保護は併用可能です。ただし、障害年金は収入として扱われるため、生活保護費は障害年金分だけ減額されます。そのため、両方を受給しても合算支給額が変わらないことが一般的です。障害年金が生活保護費より多い場合は、生活保護費は支給されません。
働きながら障害年金はもらえる?
働きながら障害年金を受給することは可能です。実際、身体障害や知的障害、精神障害など多くの受給者が就労しながら障害年金を受給しています。
申請にはどれくらい時間がかかる?
障害年金の申請から審査、支給決定まで平均して3〜6ヶ月程度かかります。
支給が決まったら、いつからお金がもらえる?
審査が通って支給が決まると、「支給決定通知書(年金証書)」という書類が届きます。この書類が届いてから約50日後に初回の年金が振り込まれます。
申請が通らなかった場合、再チャレンジできる?
申請が通らなかった場合、再申請は可能です。もう一度申請することもできますし、「審査請求」や「再審査請求」といった、国に再検討を求める手続きも可能です。専門家に相談することで申請が通る可能性が高まります。
障害年金は「悩んでいる今のあなた」にも使える制度です
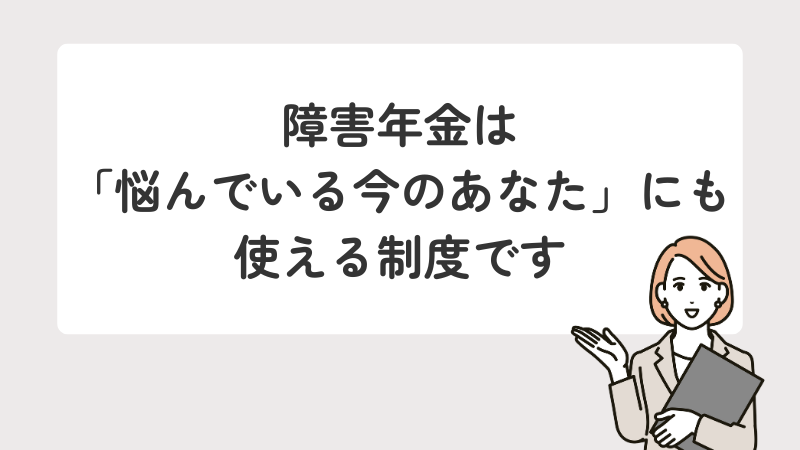
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に困難を感じている方を経済的に支える制度です。働いていても、障害者手帳がなくても利用できます。
-
対象になるか不安な場合
障害年金は病名だけで決まるのではなく、「生活や仕事にどれくらい制限があるか」が基準です。少しでも困りごとがある場合は、整理してみましょう。 -
手続きは自己申請
自動で受給できるわけではありません。書類の準備や申請が必要です。 -
働きながら受給できる場合もある
就労と受給は原則両立可能ですが、働き方によって更新時に支給が停止されることがあります。
少しでも心当たりがある場合は、まず自分の困りごとを整理し、障害年金をもらえる可能性があるか、専門家に相談してみましょう。
年金事務所や市区町村の窓口、社会保険労務士など、力になってくれる窓口はたくさんあります。障害年金という制度を上手に活用して、安心して生活を立て直す一歩を踏み出してくださいね。








