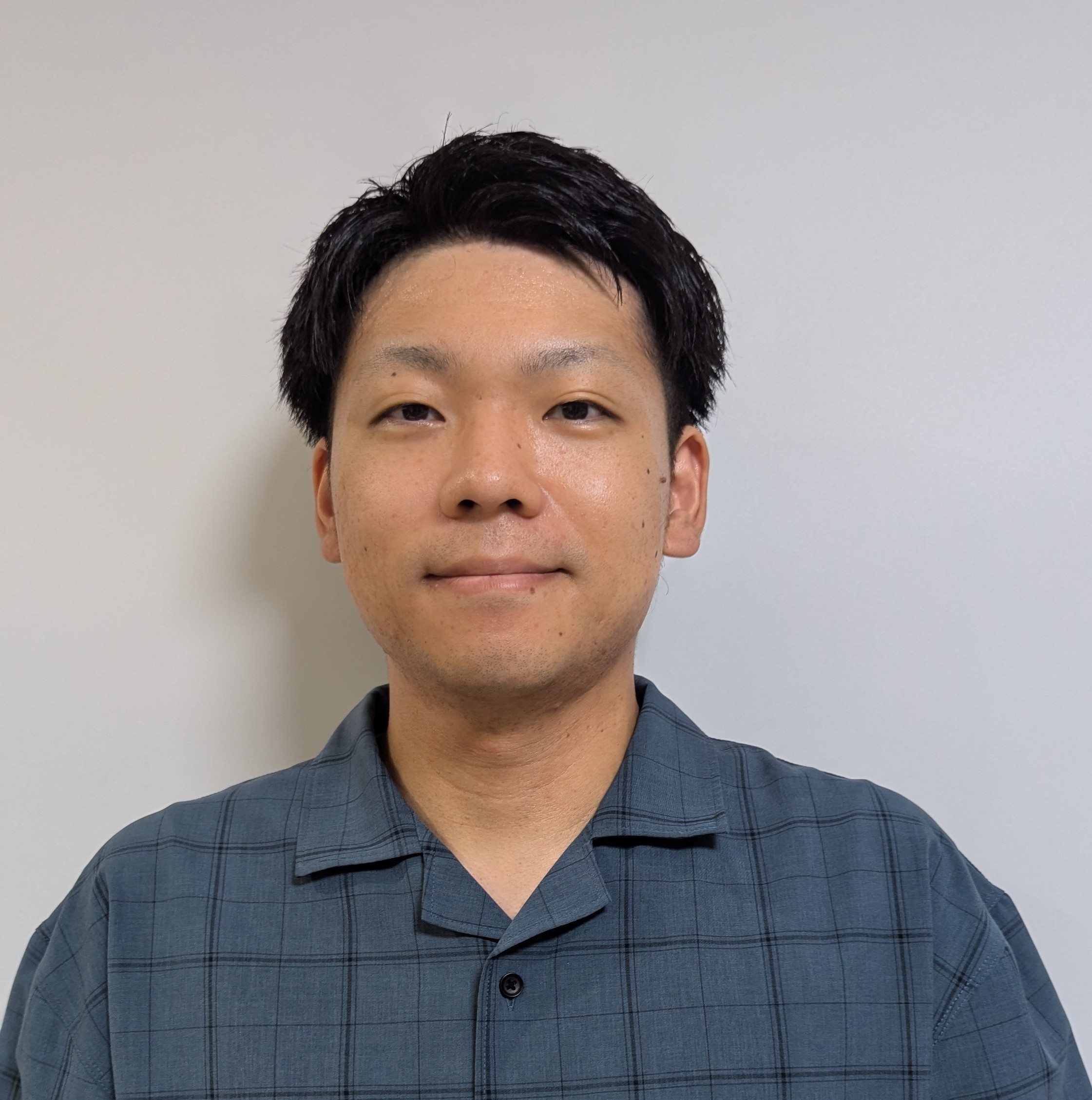SST(ソーシャルスキル・トレーニング)とは?仕事で役立つコミュニケーションを学びたい方におすすめ
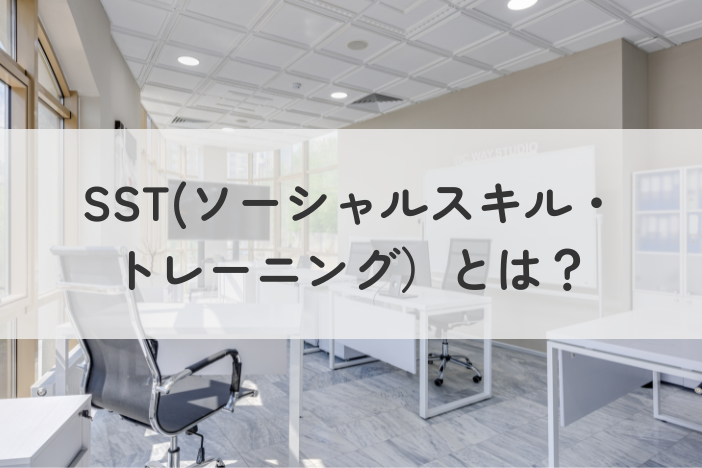
- ソーシャルスキルとは?
- ソーシャルスキル・トレーニング(SST)とは?
- 職場のコミュニケーションでこんな悩みはありませんか?
- ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の内容
- ロールプレイング
- ゲーム、レクリエーション
- ディスカッション、ディベート
- ソーシャルスキル・トレーニング(SST)で期待できる効果
- 基本的な仕事の対応が分かるようになる
- 職場の人間関係の改善
- ストレスの軽減
- どれくらいの期間で効果がでるのか
- ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けられる場所
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型・B型事業所
- ハローワーク
- メンタルクリニックや病院の精神科
- よくある質問
- Q1 平均的な利用期間は?
- Q2 利用料金は?
- Q3 平均的な利用の頻度は?
- Q4 どんな人が向いているの?
- Q5 何人でやるの?
- Q6 はじめて参加する人でも大丈夫?
- まとめ
皆さんは、周囲とのコミュニケーションがうまくいかず、普段の生活や仕事で困ってしまったり、受け持った仕事を失敗してしまったりした経験はありませんか?
ミスが続くと、職場の人間関係が悪化してしまったり、なにより自分の気持ちも落ち込んでしまいますよね。
今回はこうした場面の解決に役立つSST(ソーシャルスキル・トレーニング)という訓練について、解説していきます。
この記事のまとめ
-
●
ソーシャルスキル・トレーニングとは?
ソーシャルスキル・トレーニングとは、「対人コミュニケーションや社会生活に関するスキルを高めるトレーニング」のことを指す -
●
ソーシャルスキル・トレーニングはどんな時に受けるの?
仕事でのコミュニケーションに困り感がある場合の受講がおすすめ
ソーシャルスキルとは?
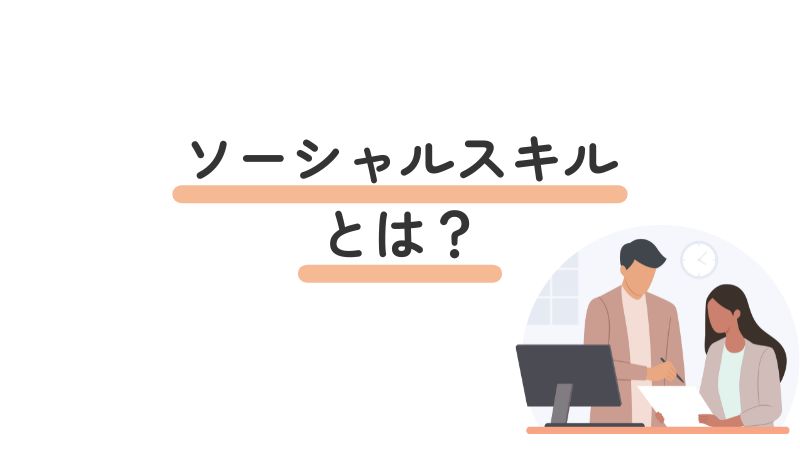
この章のポイント
- ● ソーシャルスキルとは、「対人コミュニケーションや社会生活に関するスキル」のこと
- ● ソーシャルスキルといわれる能力には、「周りと協力する力」「相手の表情から相手の感情を読み取る力」などがある
ソーシャルスキルとは、“自分の感情を表現する力や人付き合いの能力など、対人コミュニケーションや社会生活に関わるスキル”をまとめた言葉です。
例えば、ソーシャルスキルとして認識されている能力には、次のようなものがあります。
- 上下関係を認識する力
- 周りと協力する力
- 自分の感情を適切に表現する力
- モラルやルールを守った対応をする力
- 相手の表情から相手の感情を読み取る力
- 自分のストレスをコントロールする力 など
このように、ソーシャルスキルとして分類される能力はたくさんあります。
なかには、「こんなスキルもソーシャルスキルなんだ…!」と驚く能力もあったかもしれません。
ソーシャルスキルは、上にあげたとおり、普段の生活や仕事でよく使われるようなスキルをあらわした言葉です。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)とは?
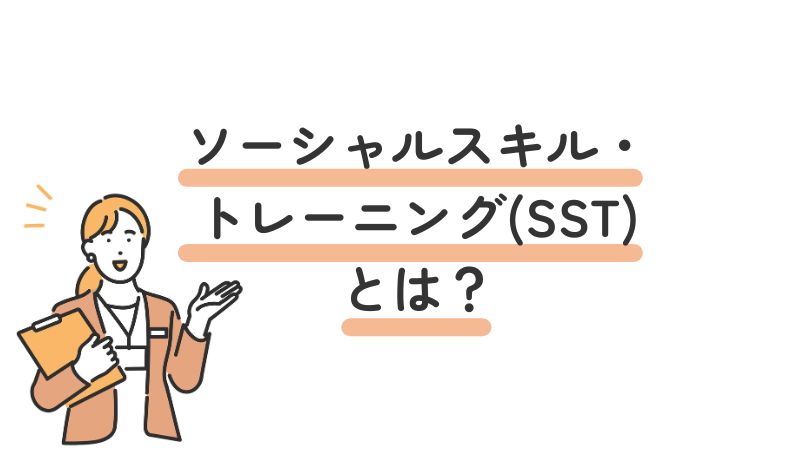
この章のポイント
- ● ソーシャルスキル・トレーニングとは、日常生活や仕事の場面を想定したソーシャルスキルを高めるトレーニングのこと
- ● 障害の有無に関わらず参加することができる
ソーシャルスキル・トレーニング(social skills training、以下SSTとする)とは、日常生活や仕事の場面を想定したソーシャルスキルを高めるトレーニングのことです。
精神障害や発達障害または発達障害の傾向があるグレーゾーンの方を対象に行われることが多いですが、障害のあるなしに関わらず参加することができます。
この記事では、特に職場や仕事でのソーシャルスキルに焦点をあてて、解説していきます。
職場のコミュニケーションでこんな悩みはありませんか?
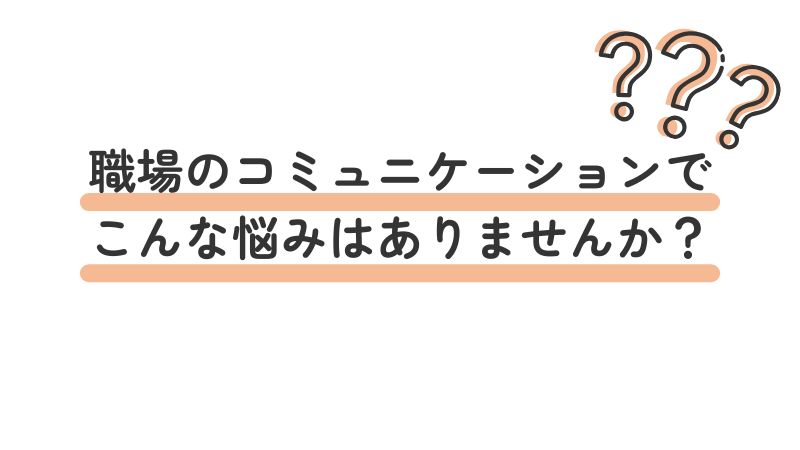
この章のポイント
- ● 「相手に対して余計なことを言ってしまった」などのお悩みはソーシャルスキルの不足が原因のことも
- ● ソーシャルスキルの不足が続くと、職場での人間関係が悪くなってしまう
- ● ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の目的は、これらの問題を解決するために、コミュニケーション能力を身につけること
例えば、職場のコミュニケーションに関わる場面で、こうした経験のある方はいらっしゃいませんか?
- 上司から「適当にやっておいて」と指示された時に、「適当」という加減が分からない
- 相手に対して、よく失礼なことを言ってしまう
- 上下関係が理解できず、上司やお客様に不適切な対応をしてしまった
実は、こういった出来事はソーシャルスキルの不足がきっかけとなって起こっている困り事なのです。
このケースでは、「上司の指示を適切に理解できず、実行できなかった」という問題が原因となっています。
このようなソーシャルスキルの不足によるミスが続くと、信用を失い、職場での人間関係が悪くなってしまうことも起きかねません。
他にも、ソーシャルスキルの不足が原因となる仕事での困りごととしては、
- 上司にうまく報告、連絡、相談ができない
- 発言してはいけないタイミングで発言してしまい、相手から不快に思われてしまう
- 相手の表情や意図を読み取れず、人間関係で誤解が生じる
- 自分の意見を周囲に伝えられず、ストレスが溜まる
といったものが挙げられます。
このように、コミュニケーションがうまくいかないと、業務にたくさんの支障が出てしまいます。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の目的は、これらの問題を解決するために、仕事で必要なコミュニケーション能力を身につけることにあります。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の内容
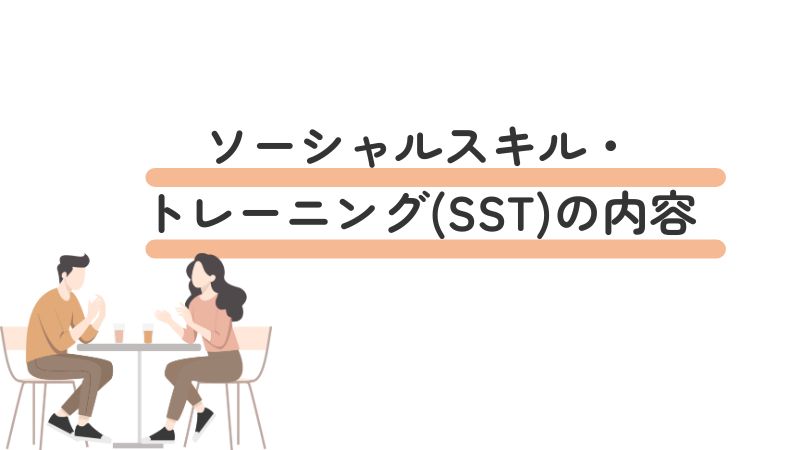
この章のポイント
- ● ソーシャルスキル・トレーニング(SST)では、少人数のグループに分かれてレクリエーションをおこなう
- ● ロールプレイングやゲーム、ディスカッションといった活動がある
では、実際にソーシャルスキル・トレーニング(SST)では、どのような活動をおこなうのか見ていきましょう。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)では、コミュニケーション能力を高めるために、少人数のグループに分かれてレクリエーションやロールプレイングなどをおこないます。
以下では、主にSSTでおこなわれている活動プログラムについて紹介します。
ロールプレイング
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の基本的なプログラムとして、ロールプレイングという活動があります。
このロールプレイングでは、職場でのコミュニケーションの方法について、実践的な形で学びます。
具体的なテーマとしては、
- 上司に仕事の進捗を報告する
- クレーム対応をする
- 電話対応
- 来客対応
- 謝罪やお礼の練習
といったものがあり、実際に職場で起こる身近なシーンに対処する力を学びます。
このプログラムで身につくスキルは非常に多く、
- クレーム対応をする力
- 電話対応、来客対応をする力
- ミスした時に謝る力
- 仕事を手伝ってもらった時にお礼をいう力
- 問題や課題を言語化して理解する力
- 周囲と協力して仕事をする力
などを養うことができます。
一般的にロールプレイングでは、最も実際の仕事に近いスキルを磨くことができます。
ロールプレイングは、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の基本のプログラムとなっています。職場で直接活かせるソーシャルスキルを身につけたい方は、ぜひ参加してみてください。
ゲーム、レクリエーション
主に、周りの人とコミュニケーションを取る必要があるゲームや工作、調理などの活動を通じて、社会性を高めるプログラムです。
このプログラムは、対人コミュニケーション能力の底上げを目的としておこなわれます。
この活動へ参加することによって、
- 自分の考えや感情を伝える力
- 相手に合わせた説明をする力
- 協調性
- 計画性
- イレギュラーへの対応力
といった能力を身につけることができます。
こうしたゲームやレクリエーションは、ロールプレイングの前のアイスブレイクの時間におこなわれることもあります。
ロールプレイングよりも、対人コミュニケーション能力を高めることが期待できるため、コミュニケーション能力をより重点的に高めたい方におすすめの活動となっています。
ディスカッション、ディベート
この活動では、実際の仕事でよく見られる場面や疑問について、自分の意見を発表し、周りの意見を聞いて、より良い答えを導き出すというプログラムです。
具体的なディスカッション・ディベートのテーマとしては、
- 職場の飲み会には参加すべきか
- 仕事とプライベートのバランスをどう取るべきか
といったものが挙げられます。
普段は話題になりづらいような、業務外のコミュニケーションについてのテーマを話すことで、新しい発見があるかもしれません。
また、この活動を通して、
- 多様な意見に耳を傾ける力
- 自分の意見を論理的に組み立て、相手にわかりやすく伝える力
- 相手の意見を正確に理解し、自分の考えと比較する力
- 必要に応じて、相手の意見を自分の考えに取り入れる力
といったソーシャルスキルを身につけられます。
この活動では、“自分の考えや意見を持って、周りの人とのコミュニケーションをとる必要がある”ため、実際の会話や人とのやり取りに近い経験を積むことができます。
SSTのプログラムに慣れてきた方や応用的なトレーニングを始めたい方に、おすすめできるトレーニングです。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)で期待できる効果
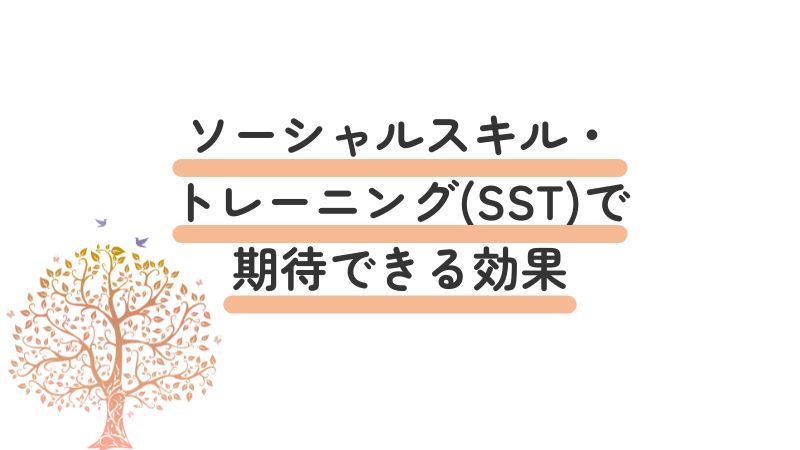
この章のポイント
- ● ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の効果は大きく分けて3つある
- ● 短期での利用は、「ピンポイントで改善したい分野がある場合」などにおすすめ
- ● 長期での利用は、「どの場面でも通用するソーシャルスキルを身につけたい場合」におすすめ
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)で得られる効果は大きく分けて3つです。
- 基本的な仕事の対応が分かるようになる
- 職場の人間関係が改善する
- ストレスが軽減する
下記では、上の効果についての詳細とどれくらいの期間で得られるかという点について、詳しく解説します。
基本的な仕事の対応が分かるようになる
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)では、基礎的な1対1のコミュニケーションから段階的に始めて、ゴールに向かってグループで協力する方法を学ぶことができます。
これらの学びは、仕事に直接活かすことができ、ロールプレイングではクレーム対応や電話対応・来客対応などの実践的なスキルも身につけることができます。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)では、取り組みやすい課題から始めて、応用的な仕事の対応まで段階的にトレーニングすることが可能です。
自分のペースでゆっくり学習していくことで、基本的な仕事のスキルが分かるようになります。
職場の人間関係の改善
自分の意見や感情を伝えられるようになると、コミュニケーションに起因する仕事のミスを減らすことができます。
そのため、ミスが減るのと同時に自分と周囲の人との関係も良くなり、職場の人間関係を改善する効果が期待できます。
また、仕事ができるようになると、気持ちに余裕ができ、周りの人にも配慮することもできるようになるでしょう。
そして、今度は自分が周りを助けられるようになることで、より一層職場の人間関係の充実を目指すことができます。
ストレスの軽減
職場での対人関係が上手くいくことによって、人間関係のストレスも軽減されます。
また、仕事でのミスが減ることによって、自分を責める気持ちもなくなり、精神的にもよい影響を得ることができます。
上手に仕事を進められるようになると、自信にもつながり、よく眠れるようになったり、新しい仕事への適応力を高められます。
ソーシャルスキルを身につけることで、将来的に多くのストレスを軽減できるようになります。
どれくらいの期間で効果がでるのか
SSTの効果が出るまでの期間は、個人の状況やトレーニングの目標によって変わってきます。
しかし、一般的には次のような期間で一定の効果が得られます。
①短期間での効果(数回~1か月)
SSTのプログラムに数回参加した状態から、利用して1か月未満の比較的短期の利用では以下のような効果があります。
- 自分のコミュニケーションの課題が理解できるようになる
- 練習を重ねた場面で、スムーズなふるまいができるようになる
このように、短期的な利用では、自分の課題を客観的に理解できるようになったり、特定の場面でのコミュニケーション能力を向上させるといった効果があります。
短期的な利用がおすすめの場合は、以下の通りです。
- 自分の苦手な分野がはっきりと分かっており、ピンポイントで改善したい分野がある
- SSTに興味があるが、まだ利用するか悩んでおり、体験から始めたい場合
このような場合は、短期間での利用が向いています。
②中長期での効果(3か月~半年)
中長期的な利用では、短期間での利用の場合よりも、応用的なスキルを身につけることができます。
具体的には、次のような効果が期待できます。
- スキルを定着させる
- 応用力が身につく
- 人間関係の改善
このように、中長期的な利用では、学んだソーシャルスキルを確実に自分のものにしたり、基礎的な学びを応用的な形に変化させたり、人間関係を改善する効果が期待できます。
中長期的な利用は次のようなケースにおすすめです。
- どの場面でも通用するソーシャルスキルを身につけたい場合
- ソーシャルスキルに自信がなく、じっくり学習を進めたい場合
- 日常生活だけでなく、仕事でもソーシャルスキルを活かしたい場合
学んだソーシャルスキルをしっかり定着させて、より応用的な場面で対応できるようになりたい場合は、中長期的な利用がおすすめです。
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けられる場所
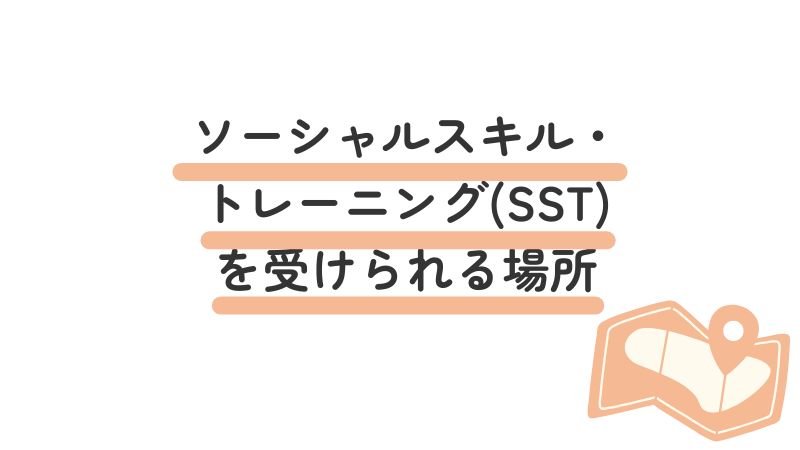
この章のポイント
- ● ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受ける場所は、自分のニーズに合わせて決めるのがおすすめ
- ● SSTは「就労移行支援」「就労継続支援A型B型」「ハローワーク」「病院」などで受けることができる
ここまでソーシャルスキル・トレーニング(SST)の活動内容や期待できる効果について解説してきました。
ここからは、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けられる場所について紹介していきたいと思います。
就労移行支援
就労移行支援事業所は、障害や病気がある方が、一般企業への就職を目指す際に、就職に必要な知識や能力を習得するためのサポートを受けられる場所です。
就労移行支援事業所では、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムを実施しているところが多くあります。
就労移行支援でソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けるメリットとしては、
- ビジネスマナーや報連相の仕方
- 職場での人間関係の築き方
- チームでの作業における役割分担や協力の仕方
- 仕事でストレスを感じた時の対処方法
といったスキルを重点的に身につけられるということが挙げられます。
障害やご病気をお持ちの方の支援に特化した就職サービスを提供しているのが特徴のため、障害やご病気の診断を正式に受けている方で、就職を検討していらっしゃる方におすすめです。
就労継続支援A型・B型事業所
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムを受ける候補となる場所で、就労継続支援A型・B型事業所という選択肢もあります。
就労継続支援A型・B型事業所は、企業での就職が困難な方が、雇用契約を結び、体調を考慮しつつ働きながら、一般就労を目指すことができる場所となっています。
就労継続支援を利用中は、給料や工賃を受け取りながらソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムを受けることができます。
お金を受け取りながら、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムを受講したい方に特におすすめです。
ハローワーク
ハローワークは国が運営している就職やキャリアの総合的な支援をおこなう機関です。
ハローワークでソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けるメリットとしては、障害やご病気の有無に関わらず、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けられるという点があります。
就労移行支援や就労継続支援ほどではありませんが、設置数が多く比較的手軽に、通うことができるのも、強みの一つです。
正式な障害やご病気の診断がおりていない方でも利用することができるため、健常者の方やご自分が発達障害のグレーゾーンではないかと感じていらっしゃる方におすすめです。
メンタルクリニックや病院の精神科
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けられる場所として、メンタルクリニックや病院の精神科も挙げられます。
クリニックや病院でソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けるメリットとしては、医療的なサポートを軸としたトレーニングが受けられるという点があります。
メンタルクリニックや精神科では、医師や看護師、臨床心理士、精神保健福祉士といった医療・福祉の専門家がソーシャルスキル・トレーニング(SST)を提供しています。このため、利用者の症状や特性を正確に考慮したプログラムを受けることができるという特徴があります。
例として、コミュニケーションにおける困り事が、単なるスキル不足ではなく、統合失調症やうつ病の症状と関連している場合、その医学的な背景が考慮されたソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムを受けることができます。
このため、ご自身のご病気や障害に対して、より医学的な観点からサポートを受けたい場合は、メンタルクリニックや病院の精神科でソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けることがおすすめです。
よくある質問
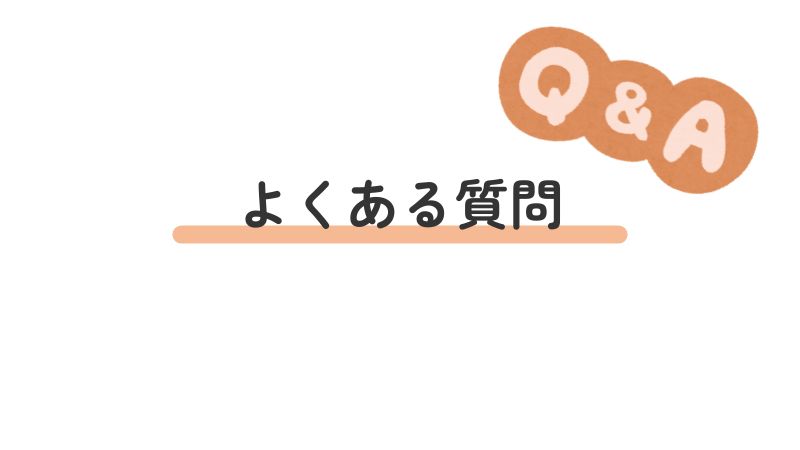
Q1 平均的な利用期間は?
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受ける場所によって平均的な利用期間は異なるようです。就労移行支援は2年程度、就労継続支援はそれ以上の期間で、じっくり利用する方が多いため、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)への参加も長期化する傾向があります。ハローワークでは早期の再就職を望まれる方が多いため3か月程度、クリニックや病院では病気療養のため数か月から1年程度継続して利用するケースが多いようです。
Q2 利用料金は?
就労移行支援・就労継続支援では、利用される方の所得によって料金が異なりますが、自己負担0円で利用されている方が多い事業所もあります。ハローワークは国が設置している機関のため、誰でも無料でソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けることができます。クリニックや病院ではその医院ごとに異なる料金体系をしているため、確認が必要です。
Q3 平均的な利用の頻度は?
どの機関でも、SSTのプログラムは週1~2回の頻度で設定されている場合が多いようです。利用頻度は平均で週1~2回ほどになります。
Q4 どんな人が向いているの?
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)のプログラムは、対人関係に課題を感じている方、就職や社会復帰を目指している方、ストレス対処法を学びたい方におすすめです。
Q5 何人でやるの?
一般的に3~7人ほどの少人数のグループを作り、実施されることが多いです。
Q6 はじめて参加する人でも大丈夫?
大丈夫です。ご安心ください。はじめは、利用希望者の方が参加しやすいと感じるプログラムから参加できる場合が多いようです。また、いきなり参加することが不安な場合は、見学から始められるケースもあるため、ご自身の状況に合わせて、柔軟にトレーニングを進めることができます。
まとめ
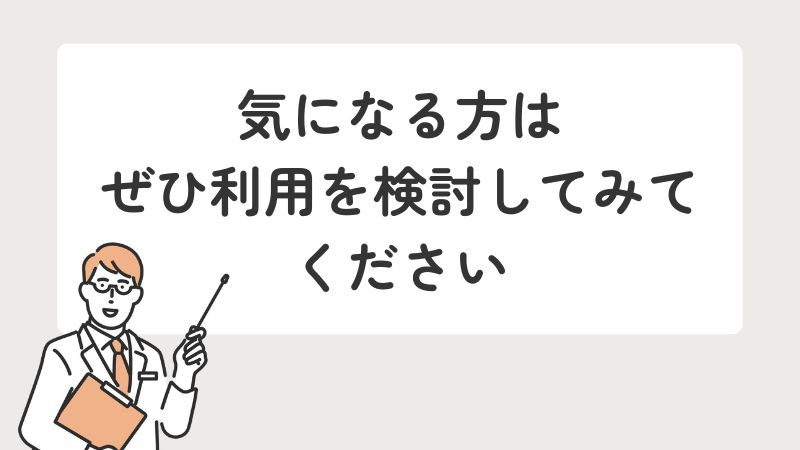
ソーシャルスキル・トレーニング(SST)は、対人関係の能力を高めるために効果的なトレーニングです。
仕事や普段の生活でコミュニケーションに困ってしまう場合は、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)を受けることで、困り事を解決できるかもしれません。
人が怖いなど、対人関係に苦手意識がある方でも、無理のない範囲から、トレーニングを始めることができます。
仕事や日常生活で、対人関係に苦手意識があるという方は、ソーシャルスキル・トレーニング(SST)の利用をぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。