障害者雇用とは何か?対象・仕組み・安心して働けるサポート制度まで徹底解説

- 障害者雇用とは?基本の仕組みと目的をやさしく解説
- 障害者雇用とは何か
- 一般雇用との違い
- 制度を支える「障害者雇用促進法」とは
- どんな人が対象になるの?
- 対象となる障害の種類
- 障害者雇用を利用するには障害者手帳が必要?
- 障害者手帳を取得していない場合は?
- 最新データから見る障害者雇用の今
- 雇用者数・実雇用率は年々上昇、過去最高を記録中
- 精神障害者の雇用が急増している背景とは
- 法定雇用率の引き上げでどんな影響がある?
- 障害者雇用のメリット・デメリット
- 実際に働いている人の事例
- 利用できる支援制度を知ろう
- 就労移行支援
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 障害者雇用専門エージェント
- 障害者雇用に関するよくある質問
- 障害者雇用で採用されるのは難しいですか?
- 障害者雇用の仕事はどんな職種が多いですか?
- 職場で配慮してもらえることって具体的にどんなことですか?
- 在宅勤務や時短勤務は可能ですか?
- ボーナスや昇給は期待できますか?
- 障害者雇用から一般雇用へ転換できますか?
- 自分に合った働き方を選ぶために、制度を知ることから始めよう
障害者雇用とは、障害のある方が安心して働けるように整えられた制度です。企業には、一定の割合で障害のある方を雇う義務があり、働きやすさを支えるための仕組みや配慮も用意されています。
この記事では、障害者雇用とはどのような制度なのか、制度の目的や対象となる人など知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
この記事のまとめ
-
●
障害者雇用とは
障害のある方が安心して働けるように社会が整えた制度で、企業には一定割合の障害者雇用が義務づけられています。職場環境の配慮やサポートが法律で定められており、自分らしく働ける環境を広げることが目的です。 -
●
どんな人が対象?
身体・精神・知的障害のある方が対象で、障害者手帳の所持が基本条件。
障害者雇用とは?基本の仕組みと目的をやさしく解説
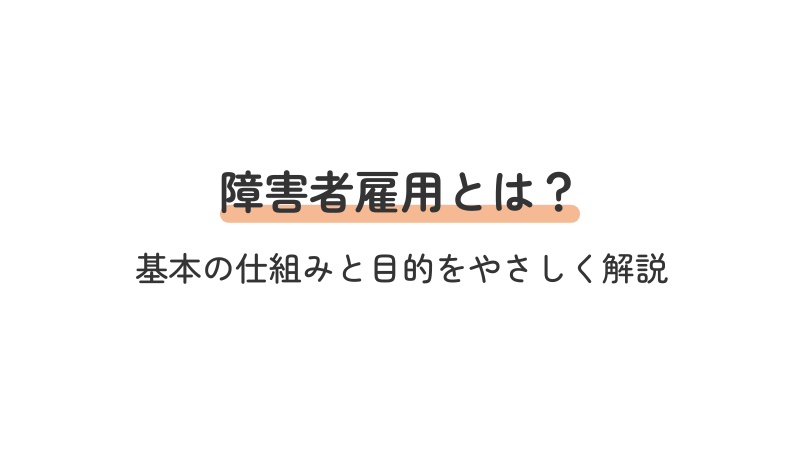
ここでは、障害者雇用とは何か、その目的や一般雇用との違い、関係する法律について解説します。
障害者雇用とは何か
障害者雇用とは、障害のある方が安心して働けるように、社会全体で支えていくための仕組みです。
一人ひとりの特性や体調に合った働き方を実現し、自分らしく働ける環境を広げていくことが目的とされています。仕事を通じて、経済的な自立や社会とのつながりを築けるようにサポートする制度です。
一般雇用との違い
働き方には大きく分けて「一般雇用」と「障害者雇用」の2つがあります。
| 項目 | 一般雇用 | 障害者雇用 |
|---|---|---|
| 対象 | 障害の有無に関わらずすべての求職者 | 原則、障害者手帳を所持している方 |
| 採用基準 | 通常の採用基準に基づく | 障害の特性に配慮しながら採用 |
| 法定雇用率 | なし | 企業は法定雇用率(一定割合の障害者雇用)が義務 |
| 合理的配慮 | 任意(個別交渉が必要) | 法律で配慮が義務付けられている |
| 支援内容 | 基本的に一般的な就業支援のみ | 勤務時間調整、職場環境改善、業務内容の調整など個別支援あり |
| 評価方法 | 能力・実績・成果で評価 | 障害に応じた配慮を考慮した評価 |
一般雇用は、障害の有無に関係なく誰でも応募できる求人です。企業は、特別な配慮を前提とせず、業務内容やスキルをもとに採用を判断します。
一方の障害者雇用は、障害のある方が無理なく働けるように、職場環境や業務の内容などに配慮がなされる働き方です。企業には法律に基づく採用義務があり、必要に応じたサポート体制も整備されています。
制度を支える「障害者雇用促進法」とは
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 障害者雇用促進法 | 障害のある方が働きやすくなるよう、障害者の差別の禁止、合理的配慮の提供義務や、ハローワーク等における障害者雇用支援、企業に一定割合以上の障害のある方を雇うこと等を義務づけている法律。雇用の安定や社会参加を目的としている。 |
| 法定雇用率 | 企業が雇うべき障害のある方の割合。会社の規模(民間企業では、従業員数40人以上の企業から障害者雇用義務が発生)によって決まっていて、これを守るのが企業の義務。 |
| 納付金制度 | 法定雇用率を満たしていない企業(従業員数101人以上の企業が対象)が払うお金。障害のある方の雇用を促すために使われる。 |
| 調整金・報奨金 | 法定雇用率を超えて障害のある方を雇用している企業に支給されるお金。企業の努力を後押しするための仕組み。 |
| 合理的配慮 | 障害のある方が働きやすくなるように、会社が必要なサポートをすること。業務の工夫、休憩の時間調整、机や椅子の調整など。 |
| 障害者差別の禁止 | 障害があることを理由に不利に扱うことを法律で禁じている。採用・昇進・待遇などで公平な取り扱いを受ける権利がある。 |
障害者雇用は「障害者雇用促進法」という法律に基づいて進められています。企業はこの法律に基づき、一定の割合(法定雇用率)以上の障害のある方を雇う義務があります。
法定雇用率を満たしていない企業(従業員数101人以上の企業)には「納付金」が課され、逆に、基準を上回って雇用している企業には「報奨金(従業員数100人以下の企業)」や「調整金(従業員数101人以上の企業)」が支給される仕組みです。さらに、企業には「障害者差別の禁止」や「合理的配慮の提供」も求められています。
この法律は、障害のある方の働く機会を守り、社会全体でその自立や活躍を支える大切な制度です。2024年や2025年にも法改正が行われており、支援の内容や対象の範囲が広がるなどより使いやすくなるよう見直しが進んでいます。
参考:厚生労働省「障害者雇用促進法の概要(昭和35年法律第123号)」
どんな人が対象になるの?
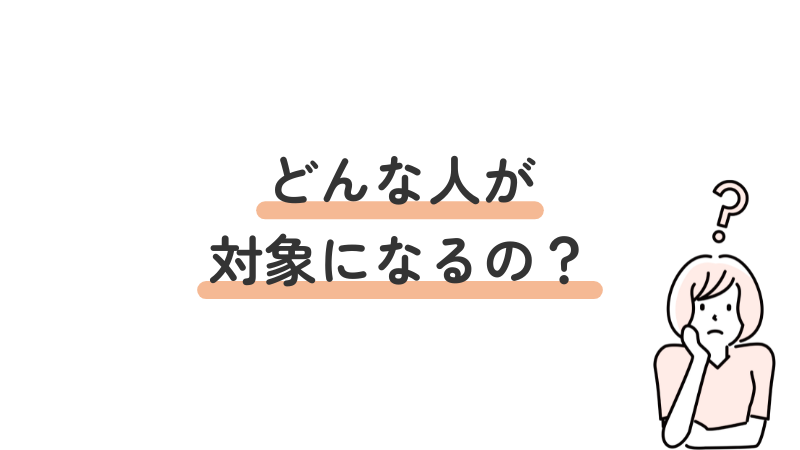
「障害者雇用」という働き方は、どのような方が利用できるのでしょうか。ここでは、対象となる障害の種類や手帳の必要性について説明します。
対象となる障害の種類
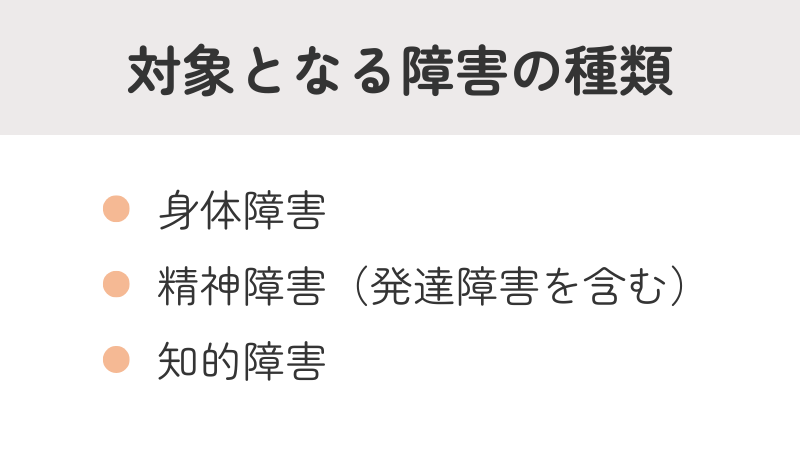
「障害者雇用」の対象になるのは、大きく分けて次の3種類の障害がある方です。
- 身体障害
- 精神障害(発達障害を含む)
- 知的障害
これらのいずれかの障害があり、障害者手帳を持っていることが基本の条件となります。
障害者雇用を利用するには障害者手帳が必要?
障害者雇用を利用するためには、障害者手帳の取得が必須となっています。
障害のある方でも手帳を持っていない場合、障害者雇用枠で働くことはできません。
障害者手帳を取得していない場合は?
障害者手帳をまだ取得していない場合、考えられる働き方は主に2つあります。
1. 障害者手帳を取得して、障害者雇用枠で働く
障害者手帳を取得することで「障害者雇用枠」の求人に応募できるようになります。
手帳の申請には一定の手続きと時間が必要ですが、安心して働ける環境を整えやすくなるというメリットがあります。
2. 一般雇用枠で、障害を伝えて働く(オープン就労)
オープン就労とは一般雇用枠の求人に応募し、障害や必要な配慮について職場に伝えながら働く方法です。自分の困りごとを説明することで、障害者雇用と同じように配慮を受けられる場合があります。
最新データから見る障害者雇用の今
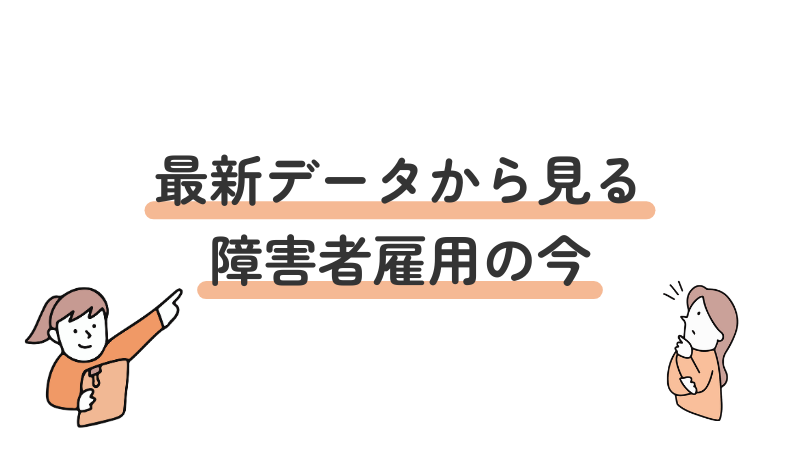
近年の障害者雇用は大きく変化しています。最新のデータをもとに今の様子をわかりやすく紹介します。
雇用者数・実雇用率は年々上昇、過去最高を記録中
令和6年時点で、民間企業で働く障害のある方の数は、約67万7,462人にのぼります。この人数は、21年連続で過去最多を更新しました。
また、企業全体の従業員のうちどれくらいの割合で障害のある方が働いているかを示す「実雇用率」も、2.41%と過去最高を記録しています。
これらの数字からも、障害のある方を受け入れる会社が年々増えていることが分かります。
参考:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果 」
精神障害者の雇用が急増している背景とは
障害の種類ごとの雇用者数は、以下のようになっています。
| 障害の種類 | 雇用者数(人) | 前年比増加率(%) |
|---|---|---|
| 身体障害 | 約369,000 | +2.4 |
| 知的障害 | 約158,000 | +4.0 |
| 精神障害 | 約150,000 | +15.7 |
なかでも、精神障害のある方の増加がとくに目立ちます。前年と比べて、15.7%も増えました。
この背景には、いくつかの理由があります。
-
精神障害が「雇うべき対象」になったこと
2018年4月から、精神障害のある方も法律で雇用の対象になりました。これにより、多くの会社が採用を進めるようになりました。
-
法定雇用率の引き上げ
2024年4月から、会社が雇うべき障害のある方の割合(法定雇用率)が2.5%に上がりました。この変化も、採用が増えた大きな理由の一つです。
-
社会的な理解の広がり
発達障害やうつ病など精神障害についての理解が少しずつ進んでいます。
-
就労移行支援などの制度整備
働く前に準備ができる「就労移行支援」などの制度が増え、安心して仕事を始めることができる環境が整ってきています。
-
合理的配慮の浸透
仕事内容や勤務時間の調整など、職場での配慮が広がってきたことで、精神的な特性を持つ方でも働きやすくなっています。
法定雇用率の引き上げでどんな影響がある?
「法定雇用率」とは、企業が雇うことが義務づけられている障害のある方の割合のことです。。近年、この割合は段階的に引き上げられています。
| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象事業主の範囲(従業員数) |
|---|---|---|
| 令和3年~ | 2.3% | 43.5人以上 |
| 令和6年~ | 2.5% | 40.0人以上 |
| 令和8年~ | 2.7% | 37.5人以上 |
つまり、今後はより少人数の企業でも障害者雇用が義務化され、採用数の増加が見込まれます。
メリット:雇用機会の拡大と多様な働き方の促進
雇用率の上昇により、障害者向けの求人が増加し、これまで対象外だった中小企業でも採用活動が活発になると考えられます。精神障害や発達障害のある方の雇用が増えるほか、短時間勤務など多様な働き方も広がる可能性があります。
課題:雇用のミスマッチと定着率の低下
一方で、採用数の確保を優先するあまり、能力や特性に合わない職務に就くケースが増え、早期離職につながる懸念もあります。受け入れ体制やサポートが不十分なまま採用された場合、職場での孤立や業務遂行の困難が生じやすくなります。また、単に「数を満たすこと」が目的になると、長期的なキャリア形成やスキルアップの機会が不足し、雇用の質が低下する恐れがあります。
法定雇用率の引き上げは、障害のある方の社会参加を促進する大きな機会です。しかし、その効果を十分に発揮するためには、企業が雇用の「量」だけでなく「質」にも配慮し、安心して働き続けられる環境を整えることが不可欠です。
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
障害者雇用のメリット・デメリット
障害者雇用には、安心して働ける環境が整っている反面、気をつけたいポイントもあります。ここでは、メリットとデメリットをわかりやすく一覧で比較していきます。
| ポイント | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 環境 | 合理的配慮を受けられ、安心して働ける | 職場によって配慮の度合いが異なる |
| 働き方 | 勤務時間や仕事内容に柔軟性がある | キャリアアップの機会が限られる場合がある |
| 安定性 | 自分の特性に合った職場で長く働ける可能性 | 給与や待遇が一般雇用より低いケースも |
障害者雇用は、特性に応じた配慮が法律で義務づけられており、無理なく働きやすい制度です。一方で、会社によって受けられる支援に差があることや、収入・昇進の面で不安を感じる方もいます。
大切なのは、メリット・デメリットを知ったうえで、自分に合った働き方を選ぶこと。気になる点は、応募前や面接時にしっかり確認しておきましょう。
実際に働いている人の事例
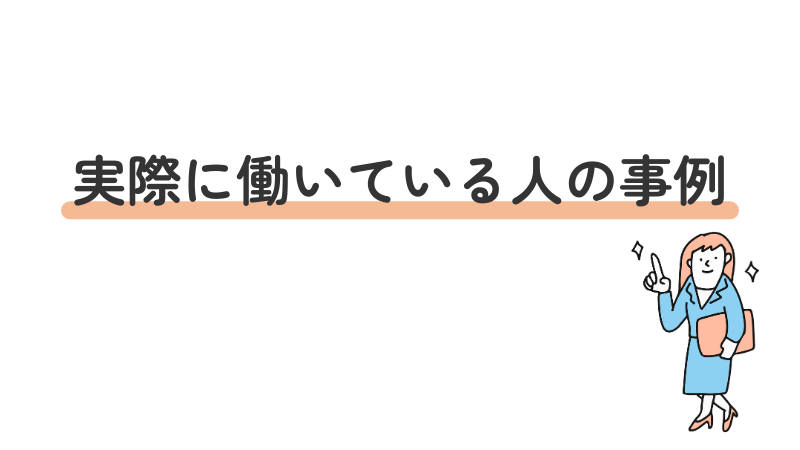
自閉スペクトラム症・社交不安障害の20代女性の体験談
これまで一般雇用枠でいくつか仕事をしてきましたが、マルチタスクや臨機応変な対応、人との距離感などどうしても苦手なことが多くて、長く働き続けるのがなかなか難しい状態でした。
無理が続き、ある時からは働くことそのものが怖くなってしまい、しばらく外に出られない時期もありました。
それでも「もう一度働いてみたい」「今度こそ自分らしく安定して長く働き続けたい」という気持ちはずっと心の中にあって、そんな時に知ったのが障害者雇用という働き方でした。
今は、障害者雇用枠の完全在宅でお仕事をしています。通勤がないぶん体への負担が少なく、自分のペースで取り組める環境が本当にありがたいです。
職場では、口頭の説明だけだと混乱してしまうことがあるので参考画像を使って説明してもらったり、作業の順番や締め切りを分かりやすく伝えてもらったりといった配慮を受けています。
こうしたサポートのおかげで、落ち着いて仕事に取り組めていますし「自分にもできることがあるんだ」と思えるようになりました。
利用できる支援制度を知ろう
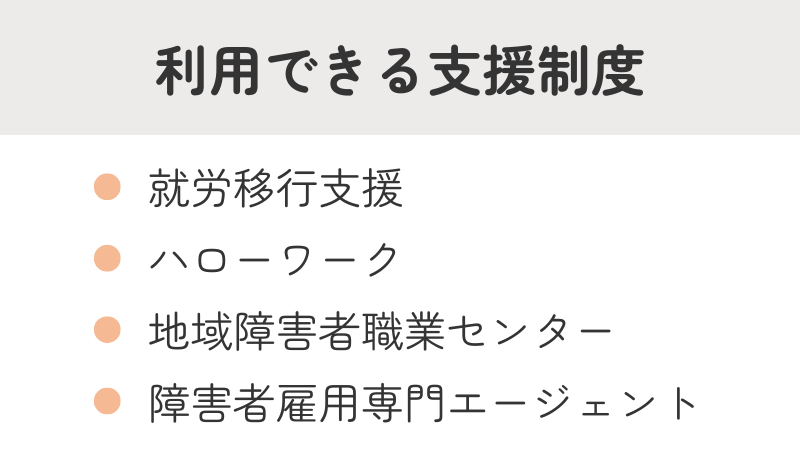
障害者雇用で働くことを考えるとき、さまざまな支援制度を活用することができます。ここでは、代表的な4つの支援制度を紹介します。
就労移行支援
就労移行支援は、障害のある方が一般企業で働くために必要なスキルや知識を身につけるための福祉サービスです。障害者雇用のメリット・デメリットの説明や自分の特性を理解してどんな配慮が必要か整理するサポート、配慮を伝えるタイミングの相談なども行っています。
就労移行支援manaby(マナビー)ではITスキルの習得や体調管理の方法など、長く働き続けるために必要な力を身につけることができます。一人ひとりの特性や目標に合わせた個別支援を大切にしており、自分のペースで通うことが可能です。
ハローワークや転職エージェントのように「求人紹介」がメインの支援ではなく「働く前の準備」や「働き続ける力」を育てる場として利用できます。
ハローワーク
ハローワークには、障害者雇用に対応した専門窓口が設けられており、障害のある方に対する求人紹介や職業相談を行っています。
障害に関する知識をもつ専門の職員・相談員が在籍し、個々の状況に応じた就職支援や、情報提供を行う体制が整備されています。
また、障害のある方を対象とした就職面接会なども随時開催されています。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、各都道府県に設置されている障害者雇用を専門とする公的な支援機関(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営)です。
仕事における得意なことや課題を整理し、それに合わせた支援のプランを立てていきます。職業訓練などを通じてスキルを身につけたり、レベルアップしたりするサポートも行っており、就職後も安心して働き続けられるように継続的なフォローが受けられます。さらに、本人だけでなく雇用する企業に対しても専門的な助言を提供し、双方にとってより良い職場環境の実現を目指しています。
参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」
障害者雇用専門エージェント
障害者雇用に特化した転職エージェントを利用すると、自分に合った企業を紹介してもらえます。非公開求人も扱っていることが多く、就職活動を一人で進めるのが不安な方にとっては頼りになるサポートです。
障害者雇用に関するよくある質問
障害者雇用について、よくあるご質問をまとめました。
障害者雇用で採用されるのは難しいですか?
採用の難しさは企業や職種によって異なりますが、自分の特性や希望に合った支援機関を活用することで、採用の可能性を高めることができます。
障害者雇用の仕事はどんな職種が多いですか?
- 事務職
- 清掃・軽作業
- 販売サポート
- 製造業
などが多い傾向にあります。
参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
職場で配慮してもらえることって具体的にどんなことですか?
企業によって違いはありますが、このようなサポートを受けられることがあります。
- 勤務時間や勤務形態の調整
- 作業や業務内容の工夫
- 職場環境の整備
- コミュニケーションへの配慮
などです。具体的な内容は企業によって異なるため、事前に確認することが大切です。
在宅勤務や時短勤務は可能ですか?
企業によって異なりますが、障害者雇用においては在宅勤務や時短勤務が合理的配慮として認められることがあります。
ボーナスや昇給は期待できますか?
障害者雇用でもボーナスや昇給が期待できる場合があります。ただし、内容や頻度は企業や雇用形態、評価制度によって大きく異なります。
障害者雇用から一般雇用へ転換できますか?
障害者雇用から一般雇用への転換は可能です。主に以下の2つの方法があります。
- 現在の会社内での切り替え
※業務内容や評価、企業の制度によっては難しい場合もあります。 - 転職による一般雇用への切り替え
一度、障害者雇用で働いたからといって一般雇用で働けなくなるわけではありません。
自分に合った働き方を選ぶために、制度を知ることから始めよう
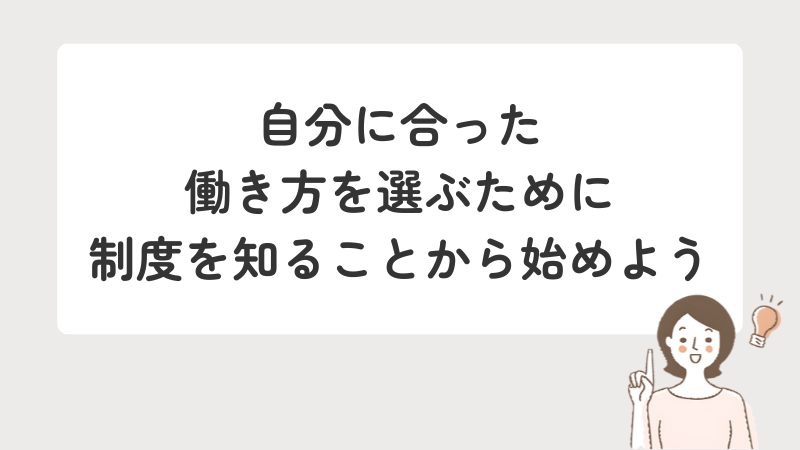
障害者雇用とは、障害のある方が安心して、自分らしく働けるように整えられた制度です。企業には一定の割合で障害のある方を雇う義務があり、合理的配慮や支援制度も用意されています。
法律の整備や社会の理解も進み、障害のある方が働きやすい環境はどんどん広がってきています。特に近年では、精神障害や発達障害に対する認知が進み、在宅勤務や柔軟な働き方を選べるケースも増えてきました。
「働きたいけど不安がある」「自分に合った仕事が見つからない」と感じている方も、一度制度について知ることで、新しい可能性が見えてくるかもしれません。
大切なのは、自分の特性や希望を理解したうえで無理のない働き方を選ぶこと。自分に合ったペースで、できることから動き出してみるのもひとつの方法です。








