就労移行支援の就職率は約2人に1人!|就職するためにできることは?

- 就労移行支援の就職率はどのくらい?【厚労省データで解説】
- 全国平均は58.8%
- 就職後の職場定着率は?
- 給与や雇用形態の実態は?
- 就労移行支援とは?制度の基礎知識とサポート内容
- 一般企業での就職を目指せる福祉サービス
- 対象者と利用条件
- 就労継続支援A型・B型との違いとは?
- 就労移行支援を利用しても就職できないことがある?主な原因と注意点
- 体調が不安定で通所・就活が続かない
- 希望条件が厳しすぎる(職種・勤務地など)
- 支援内容が本人に合っていない(プログラムとのミスマッチ)
- ミスマッチをしない就労移行支援事業所の選び方とは?
- 実践的な職業訓練がある
- 専門スタッフが在籍している
- 就職後のサポートも手厚い
- 就職率を高めるためにできること【利用者目線の工夫】
- 希望条件を広げる
- 体調を安定させる
- 通所の継続が成功への第一歩:スタッフとの相談を通じて計画的に進める
- どんな企業に就職できる?就職先の一例
- 職場での配慮内容
- 成功事例紹介【障害別・職種別のリアルな事例】
- 【身体障害】得意なデザインを活かし、完全在宅で働くRさんの挑戦
- 【精神障害】ひきこもりから一歩ずつ、新しい世界へ踏み出したAさんの挑戦
- 【発達障害】事務職でプログラミングスキルを活かすNさんの活躍
- 就労移行支援の利用で得られるメリット
- 就職後も定着支援が受けられる
- 相談支援・生活面のサポートがある
- 就労以外の社会参加・自信回復にもつながる
- 就労移行支援に関するよくある質問
- 就労移行支援に通いながら自分で就活してもいい?
- 就職までにどれくらいの期間がかかる?
- 障害者手帳がないと利用できない?
- まずは見学・相談からスタート
- 就労移行支援manabyの特徴
- 就労移行支援の就職率は高く、正しく活用すれば就職の可能性を広げることができます
就労移行支援は、働くための準備や就職活動を手助けする福祉サービスです。就労移行支援を利用する上で、気になるのが「実際の就職率」ではないでしょうか。この記事では、厚生労働省のデータをもとに、就労移行支援の就職率がどのくらいなのか、そしてどのような支援を受けられるのかを分かりやすく紹介していきます。
この記事のまとめ
-
●
就労移行支援の就職率
就労移行支援の全国平均就職率は58.8%で、約2人に1人が仕事に就いています。他の支援サービスと比較しても高い水準です。 -
●
事業所選びと自己管理が成功のカギ
自分に合った事業所を選ぶことが重要です。また、体調を整え、希望条件を柔軟にすることで就職の可能性を高めることができます
就労移行支援の就職率はどのくらい?【厚労省データで解説】
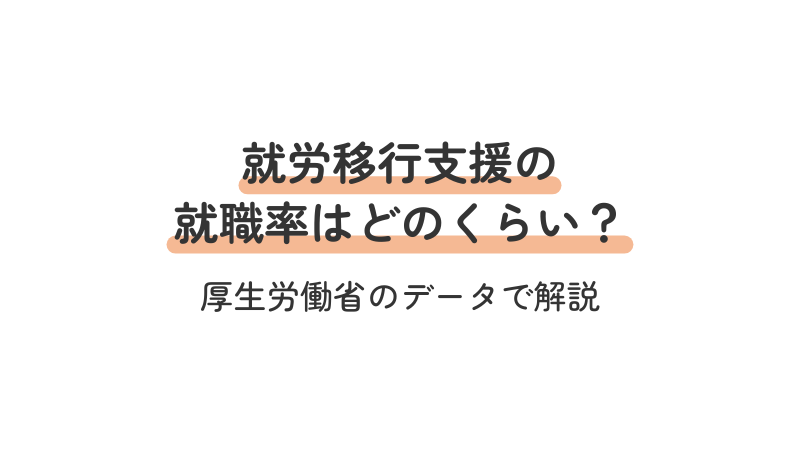
就労移行支援を利用した場合、実際にどれくらいの方が仕事を見つけているのでしょうか。ここでは、厚生労働省が公表しているデータをもとに解説します。
全国平均は58.8%
厚生労働省の調査によると、就労移行支援を使った方の全国平均の就職率は58.8%となっています。就労移行支援を通じて一般企業での就職を目指した方のうち、約2人に1人が実際に仕事に就いているということになります。
他の就労系サービスと比べても、この数字は高い水準です。
就労継続支援A型の就職率は26.9%、B型では11.2%とされており、就労移行支援が就職に強い支援であることがわかります。
参考:厚生労働省「障害者就労の現状(令和5年))」
就職後の職場定着率は?
職場定着率とは、「就職したあとも、その職場で継続して働けているかどうか」を示す指標です。単に就職できたかどうかだけでなく、その職場で安心して働き続けられているかを測る大切な数字です。
就労移行支援では、就職がゴールではなく「就職後に安定して働けること」も重視されています。そのため、多くの事業所では、職場に慣れるための支援や、困りごとが起きたときの相談サポートなど、「定着支援」に力を入れています。
では実際に、就労移行支援を利用して就職した方は、どのくらい長く働き続けているのでしょうか?
実際に就労移行支援を利用して就職した方が、どれくらい長く働いているのかを「障害の種類別」と「求人の種類別」の2つの視点で見てみましょう。
障害の種類ごとの定着率(就職後1年)
- 身体障害: 60.8%
- 知的障害: 68.0%
- 精神障害: 49.3%
- 発達障害: 71.5%
この結果から、発達障害のある方の定着率が71.5%と高いことが分かります。これは、個々の特性に応じた業務の調整や、コミュニケーション支援などの工夫が、定着につながっている可能性があると考えられます。もちろん、身体・知的・精神など他の障害がある方に対しても、それぞれのニーズに合わせた支援が行われており、一定の定着率が示されています。就労移行支援では、一人ひとりの状況に合わせたサポートを受けられる点が大きな強みです。
求人の種類ごとの定着率
- 障害者求人:70.4%
- 一般求人(障害を伝えて応募):49.9%
- 一般求人(障害を伝えずに応募):30.8%
この結果で特に注目すべきなのは、「障害者求人での定着率が高い」という点です。障害の特性に配慮した職場に就くことで、長く職場に働き続けられる傾向があることが分かります。これは、障害者求人では、企業が障害への理解や配慮を前提に採用しているため、入社後のミスマッチが少ないことなどが理由と考えられます。
参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者の就業状況等に関する調査研究」
給与や雇用形態の実態は?
就労移行支援を利用して仕事に就いたあと、どれくらいの給料がもらえるのか、どんな雇用形態で働いているのかも気になるところです。ここでは、障害の種類ごとに見た給与や雇用形態の傾向を紹介します。
月収の平均額(超過勤務手当を除いた基本給)
- 身体障害:22万3千円
- 精神障害:14万6千円
- 知的障害:13万3千円
- 発達障害:12万8千円
この金額は、残業代などを含まない「基本給」の平均です。
中でも身体障害のある方は、専門職やフルタイム勤務などに就くケースが比較的多く、月収が高い傾向にあります。
一方で、精神・知的・発達障害のある方は、体調や特性に合わせた働き方を優先し、短時間勤務や柔軟なシフト制で働いている方も多いことから、月収はやや控えめになる傾向があります。
ただしこれは「収入が少ない」というよりも、無理のない働き方を選びながら、長く働き続ける工夫をしている結果ともいえます。
雇用形態の傾向
次に、どのような働き方をしている方が多いのかを見ていきましょう。「正社員」といっても、期間の定めがある「有期契約」と、期間の定めのない「無期契約」があります。以下は、障害の種類別に見た雇用形態の分布です。
| 障害別 | 無期契約の正社員 | 有期契約の正社員 | 無期契約の正社員以外 | 有期契約の正社員以外 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害 | 53.2% | 6.1% | 15.6% | 24.6% | 0.5% |
| 知的障害 | 17.3% | 3.0% | 38.9% | 40.7% | 0.1% |
| 精神障害 | 29.5% | 3.2% | 22.8% | 40.6% | 3.9% |
| 発達障害 | 29.5% | 3.2% | 22.8% | 40.6% | 3.9% |
このデータからは、身体障害のある方は正社員として安定的に働いている割合が高いことがわかります。
一方で、知的障害や精神障害、発達障害のある方は、契約社員やパート・アルバイトといった柔軟な働き方を選ぶケースが多く見られます。
これはネガティブなことではなく、体調や生活リズムを大切にしながら、無理なく働き続けるための選択として捉えることができます。
また、非正社員であっても、実績を重ねて正社員登用につながるケースもあるため、「まずは自分に合った働き方からスタートする」ことが大切です。
参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書 」
就労移行支援とは?制度の基礎知識とサポート内容
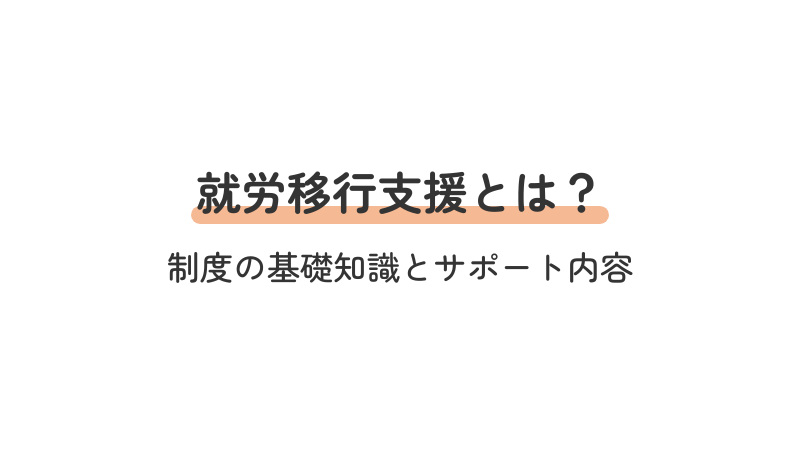
「就労移行支援」という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的にどんなサービスなのかはよく分からないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、就労移行支援の基本的な仕組みとサポート内容、対象者、他の福祉サービスとの違いについて解説します。
一般企業での就職を目指せる福祉サービス
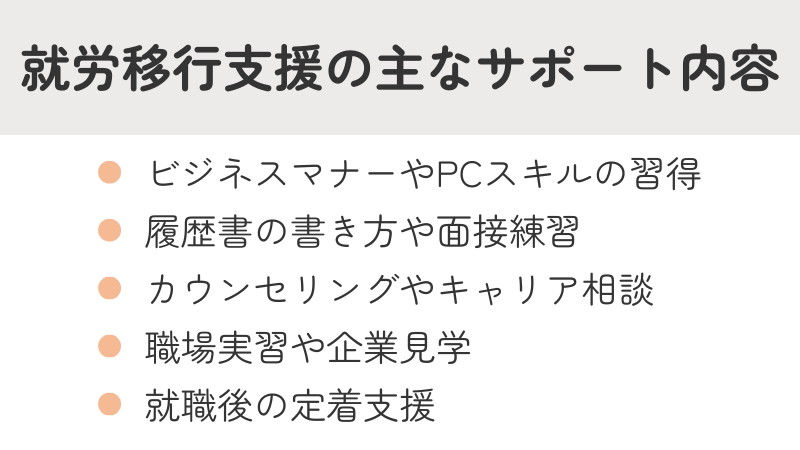
就労移行支援は、障害や難病などを抱えている方の一般企業への就職を支援する福祉サービスです。
次のようなサポートを受けながら、段階的に就職を目指すことができます。
主なサポート内容
- ビジネスマナーや基本的なPCスキルの習得
- 履歴書の書き方や面接練習
- カウンセリングやキャリア相談
- 職場実習や企業見学
- 就職後の定着支援
就労移行支援の大きな特徴は、個々の特性に応じた支援を受けながら「一般企業で働く力」を身につけられることです。就職後も、支援事業所が職場と連携して定着をサポートしてくれるため、安心して長く働き続けることが可能になります。
対象者と利用条件
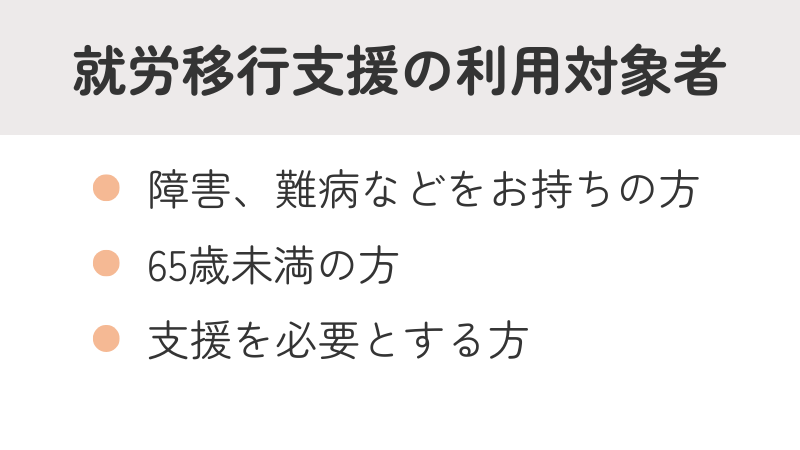
就労移行支援を利用できるのは、以下の3つの条件を満たす方です。
- 精神障害、発達障害、身体障害、難病などのある方
- 65歳未満の方
- 一人で就労することが難しく、支援が必要な方
なお、障害者手帳を持っていない方でも、医師の診断や意見書があれば利用できる場合があります。
詳しいことは、自治体の窓口に相談すると安心です。
参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
就労継続支援A型・B型との違いとは?
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 就職するために必要なスキルを身につける | 就労の機会の提供、生産活動の機会の提供 | 就労の機会の提供、生産活動の機会の提供 |
| 対象者 | 一般企業への就職を希望する方 | 雇用契約に基づいて働くことができ、一般企業への就職が不安・困難な方 | 雇用契約に基づく就労が難しく、一般企業への就職が不安・困難な方 |
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 工賃(賃金) | なし | あり | あり |
| 平均月収 | なし | 86,752円 | 23,053円 |
| 年齢制限 | 18歳以上65歳未満 | 18歳以上65歳未満 | なし |
| 利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | 定めなし |
就労移行支援と、名前が似ている「就労継続支援A型」や「就労継続支援B型」も、障害のある方の働くことを助ける福祉サービスです。しかし、それぞれのサービスには、目的や内容に大きな違いがあります。
就労移行支援は、「一般企業で働きたい」「就職に向けてスキルを磨きたい」という方に適しています。
一方で、就労継続支援A型・B型は、すぐに一般企業で働くのが難しい方が、安定した環境のなかで働くことを目的としたサービスです。
参考:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」
就労移行支援を利用しても就職できないことがある?主な原因と注意点
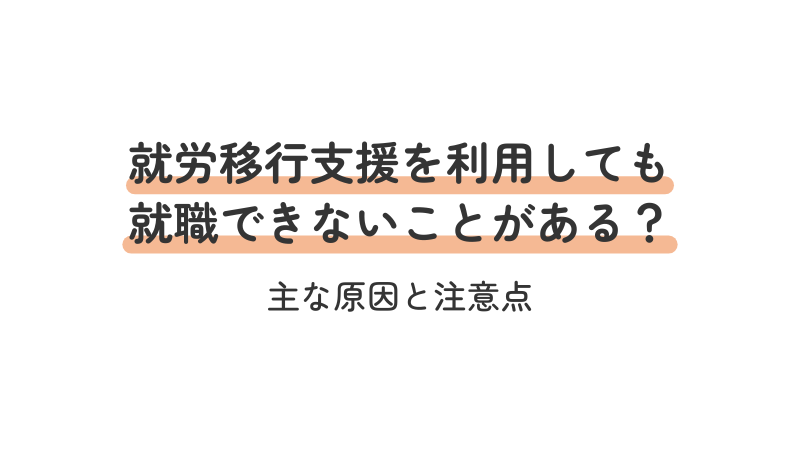
就労移行支援は、障害や難病のある方が一般企業への就職を目指すための心強いサポートですが、利用すれば必ず就職できるというわけではありません。ここでは、なぜ就職がうまくいかないことがあるのか、考えられる主な原因を3つ解説します。
体調が不安定で通所・就活が続かない
就職を目指すうえで、「安定して通所できること」はとても大切です。
しかし、心身の調子が不安定な状態だと、訓練への参加や面接準備を継続するのが難しくなることも。
実際、企業の面接では「どれくらい休まずに通所できているか」が確認されることもあります。
そのため、体調が整わずに欠席が多くなると、「仕事を続けられるのか?」と不安を持たれ、就活で不利になる可能性もあるのです。
一度通所が難しくなると、訓練にも遅れが出て自己肯定感も下がってしまう、という負のループに陥ることもあります。
希望条件が厳しすぎる(職種・勤務地など)
「この職種でしか働きたくない」「自宅から30分以内が絶対条件」などといった希望が強すぎると、マッチする求人が極端に少なくなることがあります。もちろん、希望や理想を持つことは悪いことではありません。ただ、こだわりが強すぎると、就職のチャンスを逃す原因になることも。
支援内容が本人に合っていない(プログラムとのミスマッチ)
就労移行支援事業所ごとに、支援の方針やカリキュラムの内容は異なります。「事務職向けのPC訓練が充実している」「職場実習に力を入れている」など、それぞれに特徴があります。
そのため、自分の目指す職種や身につけたいスキルと、事業所の支援内容が一致していない場合、十分な準備ができず、就職活動がうまく進まない原因になることがあるのです。
ミスマッチをしない就労移行支援事業所の選び方とは?
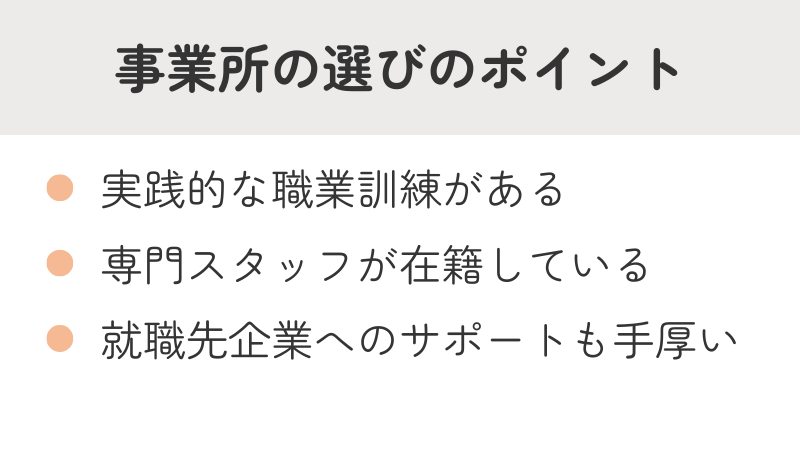
就労移行支援を受けてもうまく就職につながらないことがあります。その理由の一つが、「通っている事業所が自分に合っていない」というミスマッチです。こうしたズレを防ぐために、事業所を選ぶときに大切にしたい3つのポイントを紹介します。
実践的な職業訓練がある
事務作業やパソコンの基本操作、作業系の仕事に関連した訓練が充実しているかを確認することが大切です。実際の職場で役立つスキルを身につけられる内容であれば、就職後に即戦力として活躍しやすくなります。できるだけ現場に近い訓練が受けられるかどうかを見極めましょう。
専門スタッフが在籍している
福祉の知識や支援の経験があるスタッフがいるかどうかも重要です。体調の波や人間関係の悩みなど、個別の事情に合わせて柔軟にサポートできる人がいれば、安心して通所できます。
「社会福祉士」「精神保健福祉士」「公認心理師」などの資格を持つスタッフがいるか、実際にどのような支援を行っているかを見ておくと安心です。
就職後のサポートも手厚い
就職がゴールではありません。働きはじめてからも、気になることや困ったことは出てきます。就労移行支援では、就職後の「職場定着支援」として、職場訪問や定期的な面談などのフォローを受けられます。
また、事業所によっては、就職後6か月以降〜最長3年間利用できる福祉サービス「就労定着支援」につなげてもらえることもあります。
長く働き続けたいとお考えの方は、こうした就職後の支援体制についても確認しておくと安心です。
就職率を高めるためにできること【利用者目線の工夫】
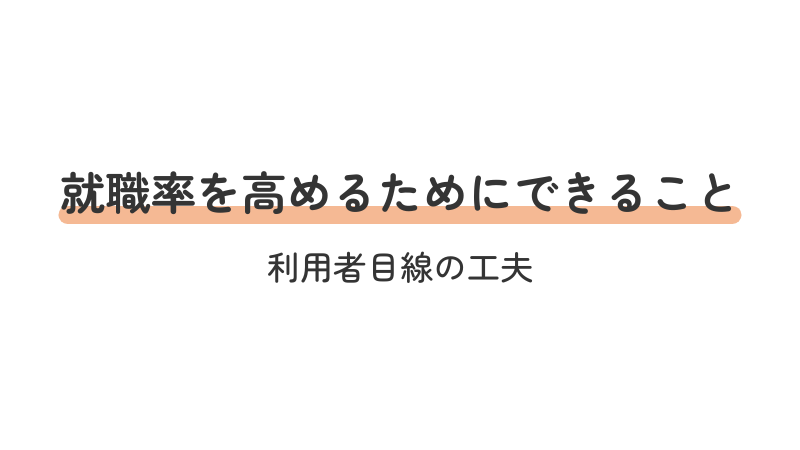
就職率を高めるためには、利用者自身も積極的に取り組むことが重要です。ここでは、就職に繋がりやすくするための工夫を3つご紹介いたします。
希望条件を広げる
就職の選択肢を増やすためには、自分の適性を深く理解することが大切です。「得意なこと」「苦手なこと」「やりがいを感じる瞬間」などを振り返ってみることで、自分に合った働き方が見えてくるかもしれません。
就労移行支援では、支援員と一緒に自己分析を進めることが可能です。その過程で、当初は視野に入れていなかった職種や業界にも興味が広がるケースがあります。結果として、希望条件が幅広くなり、自分にぴったりの職場に出会える可能性が高くなります。
体調を安定させる
心と体の健康は、働き続けるうえで欠かせない土台です。毎日決まった時間に起きる、食事や睡眠のリズムを整える、ストレスとの付き合い方を見つけるといった日々の積み重ねが、安定した生活を支えてくれます。
就労移行支援のなかで、セルフケアの方法を学ぶこともできます。自分に合った健康管理の方法を知ることで、体調を整える習慣が身につき、就職後の職場定着に繋がります。
通所の継続が成功への第一歩:スタッフとの相談を通じて計画的に進める
就労移行支援の事業所へ継続して通うことは、就職への大切なステップです。定期的に通うことで、職業訓練の成果が積み重なり、継続した通所が実績として認められ、、就職活動で企業からの評価に繋がります。
もし通所を続けることが難しいと感じたときは、無理をせず、支援員に相談してみるのがおすすめです。状況に応じた支援や調整を行ってもらいながら、自分のペースを大切にして通所を続けることが可能になります。
どんな企業に就職できる?就職先の一例
就労移行支援を利用して就職された方は、さまざまな企業で活躍されています。ここでは、実際に決まった職種や職場での配慮内容についてご紹介します。
産業別の就職先割合
| 障害種別 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 製造業(21.3%) | 卸売業・小売業(21.2%) | サービス業(14.9%) |
| 知的障害者 | 卸売業・小売業(32.9%) | 製造業(15.4%) | サービス業(13.2%) |
| 精神障害者 | 卸売業・小売業(25.8%) | 製造業(15.4%) | サービス業(14.2%) |
| 発達障害者 | 卸売業・小売業(40.5%) | サービス業(14.6%) | 製造業(10.2%) |
このデータから、卸売業・小売業や製造業、サービス業が多くの障害のある方にとって主要な就職先であることがわかります。特に発達障害のある方は卸売業・小売業での就職が多い傾向にあります。
職業別の就職先割合
| 障害種別 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 事務的職業(26.3%) | 生産工程の職業(15.0%) | サービスの職業(13.5%) |
| 知的障害者 | 事務的職業(23.2%) | 運搬・清掃・包装等の職業(22.9%) | 販売の職業(16.8%) |
| 精神障害者 | 事務的職業(29.2%) | 専門的・技術的職業(15.6%) | サービスの職業(14.2%) |
| 発達障害者 | サービスの職業(27.1%) | 事務的職業(22.7%) | 運搬・清掃・包装等の職業(12.5%) |
この結果から、障害の種類によって職業の傾向が異なることが分かります。中でも「事務的職業」はどの障害種別でも上位に入り、多くの方が選んでいる仕事のひとつです。
職場での配慮内容
厚生労働省の報告書によると、障害者雇用において多くの企業が障害のある社員に対し、以下のような配慮を実施しています。
- 休暇を取りやすくしたり、休憩を認めたりするなど休養に関する配慮
- 通院や服薬管理など、健康管理のための支援
- 短時間勤務やフレックスタイムなど勤務時間の調整
- 能力を発揮しやすい仕事への配置
- 仕事の進め方について、分かりやすい指示や説明を行う
これらの配慮により、多くの企業が障害のある方が安心して長く働き続けられる職場づくりに努めていることが分かります。
参考:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
成功事例紹介【障害別・職種別のリアルな事例】
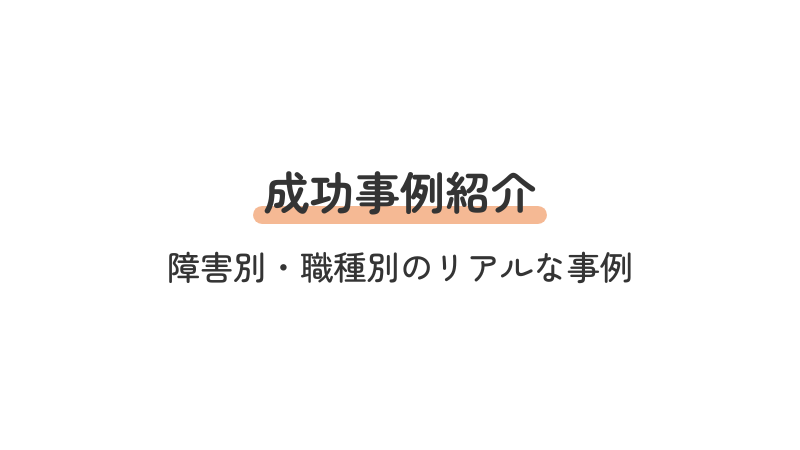
就労移行支援を利用して、実際にどのように就職を実現したのか、具体的な事例を紹介します。
【身体障害】得意なデザインを活かし、完全在宅で働くRさんの挑戦
20代女性(先天性筋ジストロフィー)→広報誌の編集・デザインで活躍
Rさんは、先天性筋ジストロフィーがあり、在宅でデザインの仕事を希望していました。就労移行支援でパソコンスキルを磨き、自分に合った働き方を探します。現在は広報誌の編集・デザインを完全在宅で行い、仕事に大きなやりがいを感じています。
自宅で集中できる環境を活かし、アラームで休憩を取るなど体調管理を徹底。幼い頃から好きだったデザインを仕事にし、「働くってこういうこと」と母親に教わったように、自立した生活を送っています。不安だった就職活動も、支援員との二人三脚で乗り越え、自分らしく働く道を見つけられました。
【精神障害】ひきこもりから一歩ずつ、新しい世界へ踏み出したAさんの挑戦
30代男性(統合失調症)→データ入力・事務作業で新たなスタート
統合失調症と診断され、長い間ひきこもり生活を送っていたAさん。あるきっかけで「変わりたい」と思い立ち、就労移行支援の利用を決めました。
manabyでExcelやプログラミングを学び、得意なデータ入力の仕事を見つけました。訓練を通して体調も安定し、人とのコミュニケーションにも慣れていきました。支援員からの具体的なフィードバックを受けながら、初めての就職活動を乗り切り、特例子会社での事務・軽作業の仕事に就職。自分に合ったペースで社会とつながり、新たな一歩を踏み出しました。
【発達障害】事務職でプログラミングスキルを活かすNさんの活躍
20代男性(ADHD)→事務職で社内業務の効率化に貢献
ADHDの診断を受け、生活面での困難を抱えていたNさん。就労移行支援で、苦手だったコミュニケーションを克服し、自己分析を深めました。
もともと興味のあったプログラミングスキルをmanabyで習得。就職活動では事務職に就きましたが、入社後にこのプログラミングスキルが役立ち、社内の備品管理や発注業務の効率改善に貢献しています。支援員との連携で生活リズムも整え、自身の特性を理解した上で、自分らしく楽しく働ける場所を見つけました。
今回紹介した以外にも、就労移行支援manabyの公式サイトでは、利用者の様々な体験談を掲載しています。
就労移行支援の利用で得られるメリット
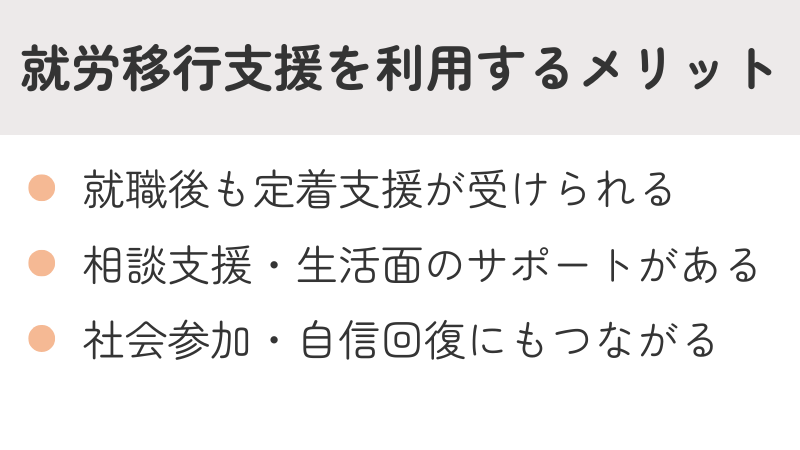
就労移行支援を利用することで、就職に向けたサポートはもちろん、生活面や心の安定にもつながる多くのメリットがあります。ここでは代表的な3つをご紹介します。
就職後も定着支援が受けられる
就職がゴールではなく、その先の「職場で長く働き続ける」ことも大切にしているのが、就労移行支援の特徴です。就職後も、職場での人間関係や業務に関する不安を相談できる「定着支援」があり、悩みをひとりで抱え込まずに済みます。働き始めてからも支援が続くことで、安心して仕事に取り組める環境が整います。
相談支援・生活面のサポートがある
就職を目指すには、生活リズムや心の安定も欠かせません。就労移行支援では、通所を通じて規則正しい生活習慣を身につけたり、通院や服薬の管理、金銭管理や家事の習慣づくりまで、生活全般の課題に寄り添い支援を行います。支援員と相談しながら日々の生活を整えていくことで、自然と働く力が育まれていきます。
就労以外の社会参加・自信回復にもつながる
就労移行支援は、仕事に就くための場所だけでなく、社会とのつながりを広げる場でもあります。グループワークやレクリエーションなどに参加することで、人と関わることに慣れたり、自分の得意なことや強みを見つけたりする機会が増えます。
就労移行支援に関するよくある質問
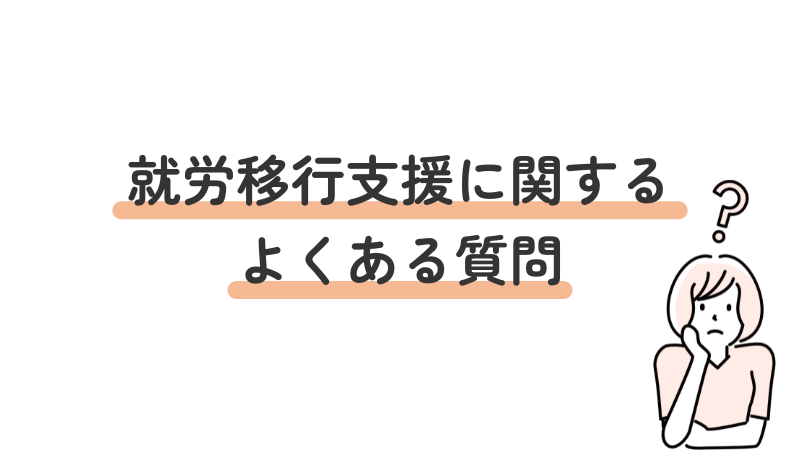
就労移行支援の利用を考える際に、よく聞かれる疑問についてまとめました。
就労移行支援に通いながら自分で就活してもいい?
ご自身で就職活動を行うことも可能です。ただし、応募先企業の選定や情報収集、書類の作成、面接対策など、就職活動には専門的な知識や実践的な準備が必要となる場面が多くあります。
そのため、事業所の支援員と連携しながら進めていただくことをおすすめいたします。支援員のサポートを受けることで、より効率的に就職活動を進めることができ、就職後のミスマッチも防ぎやすくなります。
就職までにどれくらいの期間がかかる?
就職までの期間は、体調や目標、準備の進み方によって個人差があります。東京都の令和3年度の実績によると、6か月以上1年6か月未満で就職された方が全体の約60%を占めています。半年以内に決まる方もいれば、2年以上かけてじっくり取り組む方もいらっしゃいます。
参考:東京都福祉局「令和4年度 就労移行等実態調査 結果概要」
障害者手帳がないと利用できない?
必ずしも障害者手帳が必要なわけではありません。医師の診断書や意見書があれば、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。
詳しい手続きや条件については、お住まいの自治体の福祉窓口までお問い合わせください。
まずは見学・相談からスタート
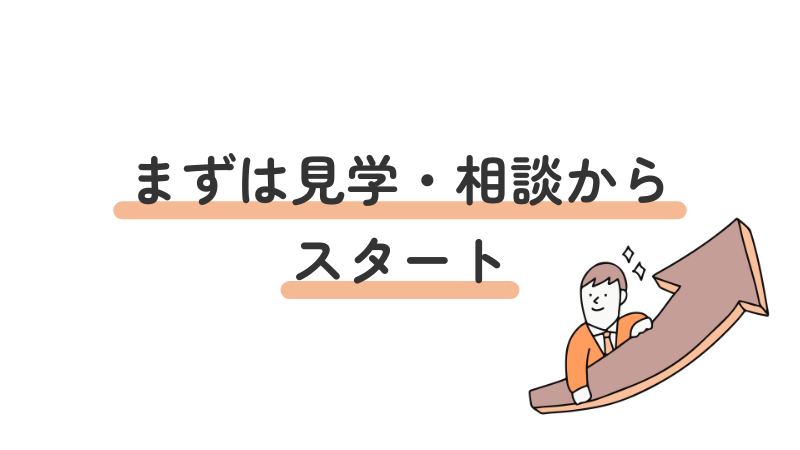
就労移行支援の利用に興味があっても、「自分に合っているのか分からない」「どんな場所か想像がつかない」など、不安や疑問を抱える方は少なくありません。そんなときは、まず事業所の見学や相談から始めてみるのがおすすめです。
就労移行支援manabyでは、就職を目指すだけでなく、安心して一歩を踏み出せるよう、ひとり一人に寄り添ったサポートを大切にしています。
就労移行支援manabyの特徴
通所も在宅も選べる柔軟なスタイル
就労移行支援manaby(マナビー)は通所はもちろん、ご自宅からオンラインで訓練を受けることも可能です。体調や生活スタイルに合わせて学び方を選べます。
パソコンスキルや自己理解を深める学習教材が豊富
自分のペースで学べる独自のeラーニング「マナe」で、プログラミングやデザイン、ビジネスマナーなど、実践的なスキルを身につけることができます。
専門スタッフによる面談と個別サポート
専門の支援員が、就職に向けた悩みや生活のことなど、さまざまな相談に対応しています。定期的な面談を通して、「どんな仕事が合っているのか」「どう進めていけばよいか」などを一緒に考えながら、一人ひとりに合った就職プランを作成していきます。
見学や体験は、もちろん無料です。「まずは雰囲気を見てみたい」「相談だけでもしてみたい」という方も歓迎しています。お気軽にお問い合わせください。
就労移行支援の就職率は高く、正しく活用すれば就職の可能性を広げることができます
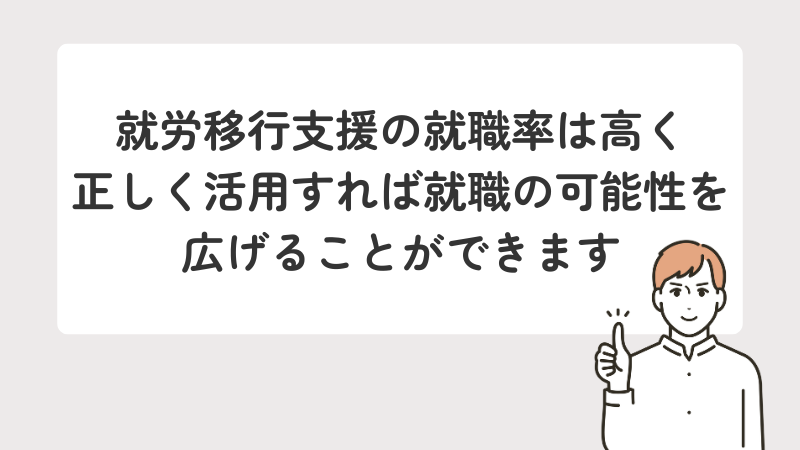
就労移行支援の就職率は約58.8%と、およそ2人に1人が仕事に結びついていることを意味します。これは、多くの方が就労移行支援を活用して就職を実現していることを示しています。
ただし、大切なのはこの数字だけにとらわれることではなく、サービスを「どう活用するか」という点です。
特に重要なのは、自分に合った事業所を選ぶということです。見学や相談を通じて以下のポイントを確認しておくことが大切です。
- 希望する職種や働き方に対応できる支援があるか
- 体調や障害特性に配慮した柔軟な対応が可能か
- 支援員と信頼関係を築けそうな雰囲気か
- 通所・在宅など、自分に合ったスタイルを選べるか
また、事業所のサポートとあわせて、希望条件を柔軟に広げたり、生活リズムを整えたりするなど、自分自身の取り組みや工夫も就職のチャンスを広げる大切なポイントです。
例えば
- 希望条件を少し広げてみる
- 生活リズムを安定させる
- 不安や悩みを支援員に相談する
といった行動も、無理のない範囲で続けていくことが大切です。
まずは比較・体験しながら、自分に合った就労移行支援を選びましょう。







