障害者雇用のメリット・デメリットとは?初心者向けに分かりやすく解説

- 障害者雇用とは?制度の基本をわかりやすく解説
- 障害者雇用とはどんな制度?一般雇用との違い
- 対象となる障害の種類や等級とは?
- 障害者手帳は必要?診断書だけでも応募できる?
- 障害者雇用で企業側に求められる配慮と義務とは?
- 障害者雇用のメリットとは?
- 障害者雇用の最大のメリットは「働きやすさ」
- 体調に合わせた勤務時間や業務調整ができる
- 通院や休職への理解、柔軟な対応が受けられる
- 支援制度や職場定着サポートが受けられる
- 障害者雇用のデメリットとは?
- 給与水準が低くなりやすいのは本当?
- 業務が限定的でやりがいを感じにくいこともある
- キャリアアップが難しい職場もある
- 障害者雇用で実際に働いている人へアンケート!障害者雇用のメリット・デメリット
- 障害者雇用のメリット
- 障害者雇用のデメリット
- よくある誤解:障害者雇用=単純作業?
- 障害者雇用でも多様な職種がある
- 事務・IT・販売など、実際の職種事例
- 一般雇用と障害者雇用、どちらが向いている?
- 働き方や職場環境の違いを比較する
- 配慮が必要な場面があるかを見極めよう
- 体調・通院頻度に応じた働き方を選ぶ
- 将来的なキャリアで選ぶ
- 障害者雇用に向いている方の特徴とは?
- 体調の波があり、フルタイム勤務が難しい方
- 職場で配慮してほしいことが具体的にある方
- 自分の障害特性をある程度理解している方
- 再発を防ぎながら長く働きたいと考えている方
- 障害者雇用で働く方の体験談
- 障害者雇用の求人はどこで探せる?
- ハローワークの障害者専門窓口を活用しよう
- 障害者雇用に特化した転職エージェントとは?
- 就労移行支援事業所からの紹介も
- 障害者雇用の働くサポートする支援機関
- 就労移行支援事業所とは?
- manabyの就労移行支援について
- 障害者就業・生活支援センターとは?
- 支援機関ごとの役割の違いとは?
- 障害者雇用に関するよくある質問
- 障害者手帳がなくても障害者雇用は利用できますか?
- 障害者雇用でも正社員になれますか?
- 障害者雇用でもキャリアアップは難しいですか?
- 障害者雇用から一般雇用に戻ることはできますか?
- 障害者雇用に応募するにはどうすればいいですか?
- 障害者雇用のメリット・デメリットを理解して、自分に合った働き方を見つけよう
障害者雇用という言葉を聞いたことはあっても、「具体的にどんな働き方なの?」「メリットとデメリットを知りたい」と感じている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、障害者雇用の基本から、メリット・デメリットまでを初心者向けにやさしく解説します。
この記事のまとめ
-
●
障害者雇用のメリット・デメリット
「合理的配慮」や「通院配慮」など、働きやすい環境が整いやすい。一方で、給与や仕事内容の幅が限られるケースも… -
●
自分に合う働き方を選ぶには?
障害者雇用と一般雇用の違いを理解し、自分の特性や希望に合った職場環境を選ぶことが大切
障害者雇用とは?制度の基本をわかりやすく解説
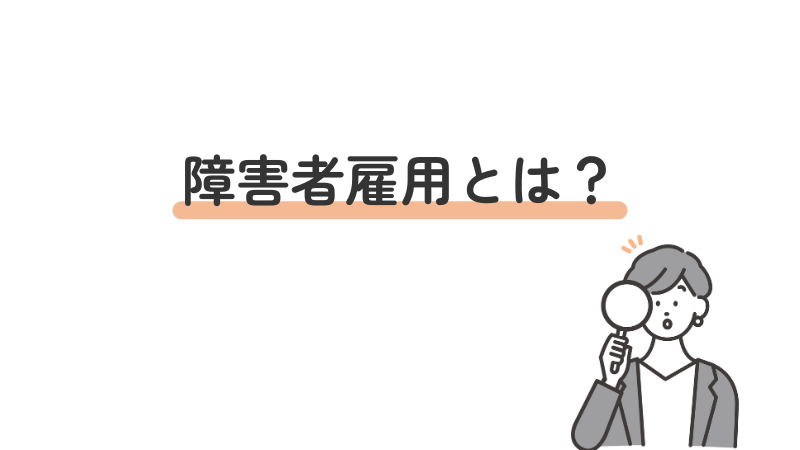
この章のポイント
- ● 障害者雇用は法律に基づいた「制度」として整備されている
- ● 企業には「合理的配慮」を行う義務がある
- ● 安定して働き続けるためには、障害者手帳の取得が基本
この章では、障害者雇用の基本的な仕組みや、対象となる障害、必要な手続きなどをやさしく解説していきます。
障害者雇用とはどんな制度?一般雇用との違い
障害者雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づいて運用されている制度です。これは、障害のある方が安定して働けるように、企業に対して雇用の機会を提供するよう義務づけた仕組みです。
「障害者雇用と一般雇用では、どんな違いがあるの?」と疑問を持つ方も多いと思います。以下に、主な違いをまとめました。
| 項目 | 障害者雇用 | 一般雇用 |
|---|---|---|
| 雇用枠 | 障害者枠 | 一般枠 |
| 障害の開示 | 必要(オープン) | 不要(クローズでも可) |
| 働き方 | 体調に合わせて調整しやすい | フルタイムが基本 |
| 配慮 | 通院・業務量などの配慮を受けやすい | 原則なし(企業による) |
障害者雇用では、障害があることを開示したうえで採用されるため、業務内容や働き方について、企業からの配慮を受けながら働けるのが特徴です。対して、一般雇用では障害を開示する義務はなく、制度としての配慮もないため、自ら調整しながら働く必要があります。
対象となる障害の種類や等級とは?
障害者雇用の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 等級区分 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など | 1級〜6級(1級が最重度) |
| 療育手帳(自治体により名称は異なる) | 知的障害 | A(重度)、B(中軽度)などの区分が多い |
| 精神障害者保健福祉手帳 | うつ病、統合失調症、発達障害、パニック障害など | 1級〜3級(1級が最重度) |
※障害者雇用では、どの等級でも対象になる可能性があります。
参考: 厚生労働省 「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」
障害者手帳は必要?診断書だけでも応募できる?
障害者雇用枠での応募には、原則として「障害者手帳(身体・知的・精神いずれか)」の所持が必要です。診断書のみで障害者雇用枠に応募することは基本的にできません。
ただし、手帳を取得していなくても、一般枠で就職し、社内で配慮を受けながら働いている方もいます。その場合、会社ごとに対応は異なり、制度上の配慮や保障が受けられるとは限りません。障害者雇用枠で安定して働きたいと考えている方には、障害者手帳の取得を前向きに検討することをおすすめします。
障害者雇用で企業側に求められる配慮と義務とは?
障害者雇用では、企業側に対して「合理的配慮」を行う義務があります。これは、2016年に施行された「障害者差別解消法」にもとづき、企業に提供が義務づけられている支援です。合理的配慮とは、障害のある方が、他の従業員と同じように仕事ができるよう、必要な調整やサポートを行うことを指します。配慮の内容は、障害の特性や働く人の希望に応じて柔軟に調整されます。
具体的には、以下のような配慮が含まれます。
- 体調や通院に合わせた勤務時間の調整
- 業務量や業務内容の調整(負担を軽減する)
- 静かな環境で集中できるよう、座席配置を配慮する
- 作業手順を視覚的にわかりやすく提示する(マニュアル、チェックリストの活用)
- 相談しやすい支援担当者や上司を明確にする
これらの配慮は、障害者雇用として働く方にとって「お願いごと」ではなく、「法的に認められた権利」です。「こんなことをお願いしたら迷惑かも…」と感じてしまうことがあるかもしれませんが、働くために必要な支援を受けるのは権利ですので安心してくださいね。
参考: 厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」
障害者雇用のメリットとは?
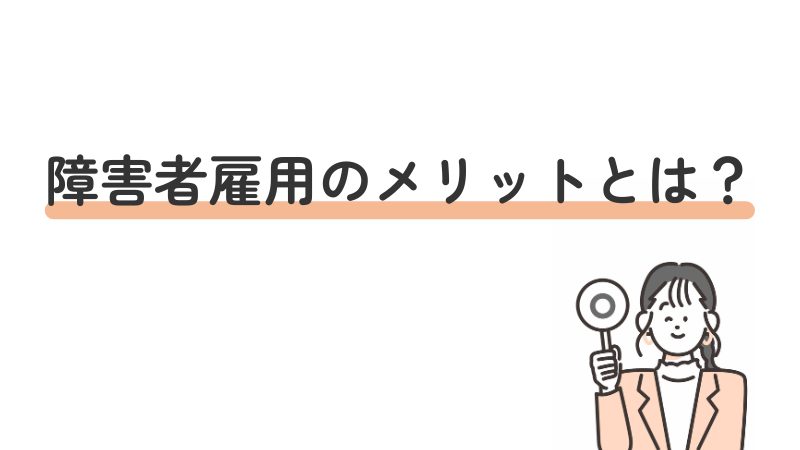
この章のポイント:障害者雇用のメリット
- ● 体調や特性に合わせて、勤務時間や仕事内容の調整が可能
- ● 通院や体調不良にも柔軟に対応してもらえる環境がある
- ● 就職後も支援担当者や面談によるフォローが受けられる
- ● 「配慮される前提」で働けるから、安心して再スタートできる
この章では、うつ病や発達障害など見えにくい障害を持つ方にとって、障害者雇用がどう「働きやすさ」に繋がるのか、代表的なメリットを4つ紹介します。
障害者雇用の最大のメリットは「働きやすさ」
障害者雇用の最大の魅力は、「自分の体調や特性に合わせた働き方がしやすい」ことです。
例えば、「人との会話が多い業務は不安」「体調の波があるから勤務日数を減らしたい」といった希望も、障害者雇用では相談しやすい環境が整っています。
これは、「配慮されることが前提」の制度だからです。一般雇用では言い出しづらいことも、障害者雇用であれば最初から相談できる前提で働けます。
「働きたい気持ちはあるけれど、無理してまた体調を崩したくない」という方にとって、障害者雇用はゼロから安心して再スタートできる選択肢となります。
体調に合わせた勤務時間や業務調整ができる
特にうつ病などの精神的な障害は、日によって体調の波が大きくなることがあります。そのため、無理のない勤務時間や業務内容の調整が重要です。
障害者雇用では、例えば以下のような柔軟な対応が可能です。
- 週3〜4日の短時間勤務からスタート
- 出勤時間を遅らせたり、休憩時間を長めに取る
- 負担の少ない作業から始めて、徐々に慣れる
- 突発的な体調不良時にも休みが取りやすい
こうした働き方ができるのは、「障害があることを前提に雇用されている」からこそです。一般雇用ではこうした相談が難しい場合もありますが、障害者雇用では自然な流れとして受け入れてもらえるケースが多くあります。
「いきなりフルタイムで働くのは不安」「まずは少しずつ社会に慣れたい」と感じている方にとって、無理のない復職・就職を目指せる制度といえるでしょう。
通院や休職への理解、柔軟な対応が受けられる
定期的な通院や急な体調の変化に対して、理解や配慮を受けやすいことも、障害者雇用の大きなメリットのひとつです。
例えば、通院のために週に1回午後出社にしたり、体調がすぐれない日は在宅勤務や有給休暇で調整するなど、状況に応じて対応してもらうことができます。こうした理解のある職場環境は、精神的な負担を軽くし、「働くことそのもの」への不安を減らすことに繋がります。
「迷惑をかけてしまうかも…」と不安になりやすい方でも、制度のもとで働けることで、気持ちに余裕を持ちながら日々の業務に取り組みやすくなります。
支援制度や職場定着サポートが受けられる
障害者雇用のメリットは、「働き始めた後も支援が受けられる」ことです。就職するまでのサポートだけでなく、「職場に定着するまで」「働き続けるためのサポート」も制度として整えられています。
例えば、以下のような支援があります。
- 企業による社内メンターや支援担当者の配置
- 1対1での定期的な面談
こうした支援を受けながら働くことで、「もし困ったことがあっても、すぐに相談できる」という安心感が生まれます。
初めて障害者雇用を検討する方にとって、「入社後に放置されたらどうしよう」という不安はつきものですが、支援体制があることでその不安を軽減することができます。
障害者雇用のデメリットとは?
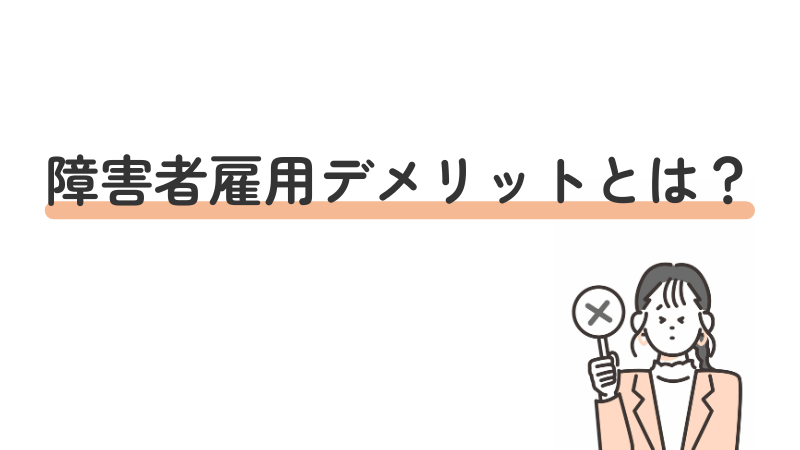
この章のポイント:障害者雇用のデメリット
- ● 障害者雇用は、短時間勤務や契約雇用が多く、平均給与が低めになりやすい
- ● 業務が限定されるケースもあり、人によっては物足りなさを感じることも
- ● 昇進・職種変更などのキャリアアップ制度が整っていない企業もある
この章では、障害者雇用を検討する際に知っておきたい代表的なデメリットについて、解説していきます。
給与水準が低くなりやすいのは本当?
障害者雇用では、一般雇用と比べて給与水準が低くなる傾向があります。実際、厚生労働省が公表した令和5年のデータでは、障害種別ごとの平均月収(所定内給与額・残業代を除く)は以下のとおりです。
| 障害の種類 | 平均月収(所定内給与額) |
|---|---|
| 身体障害者 | 約23万5千円 |
| 知的障害者 | 約13万7千円 |
| 精神障害者 | 約14万9千円 |
| 発達障害者 | 約13万円 |
※超過勤務手当(残業代など)を除いた所定内給与額です。
※あくまで平均値であり、実際の給与は労働時間・雇用形態・職種・企業規模・地域・勤続年数などによって大きく異なります。
参考:厚生労働省 「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
業務が限定的でやりがいを感じにくいこともある
障害者雇用では、働く方の体調や特性に配慮することが前提となるため、最初のうちは業務が限られてしまうことがあります。例えば、書類のスキャンやファイリング、備品の補充、データ入力など、比較的シンプルな作業を任されることが多く、慣れるまでは繰り返しの作業が中心となる場合も少なくありません。
これは無理なく業務に慣れていくための配慮ですが、人によっては「もっと責任のある仕事がしたい」「自分のスキルを活かせていない」と、物足りなさややりがいの薄さを感じてしまうこともあるかもしれません。
ただし、全ての職場が単調な業務ばかりというわけではなく、本人の希望やスキルを見ながら、徐々に業務の幅を広げてくれる企業もあります。
例えば、
- Excelを使った社内資料の作成
- Web制作や広報などのクリエイティブ業務
- 経験を活かした顧客対応や事務リーダー業務
などに挑戦できるケースもあります。
やりがいや成長を重視したい方は、面接や職場見学の際に「どのような業務を担当しているか」「業務の変更や幅は広がるか」といった点を確認しておくと安心です。
キャリアアップが難しい職場もある
障害者雇用では、「キャリアアップを前提とした制度」がまだ十分に整っていない企業もあるのが現実です。例えば、障害者雇用枠では正社員登用や昇進のルートが明確に用意されておらず、長く働いていても同じ業務のまま、給与や役職に変化がない…というケースも少なくありません。
また、体調や特性への配慮があるぶん、企業側も「あまり負担をかけてはいけない」と配慮するあまり、責任のあるポジションやチャレンジングな業務を任せづらいと感じてしまうことがあります。結果として、本人が希望していても成長の機会が限られてしまうことがあるのです。
とはいえ、全ての企業がそうというわけではありません。近年は、「障害があっても成長したい」という意欲を尊重し、スキルアップ研修や資格取得支援を用意している企業、定期的に業務の見直しを行い、ステップアップの機会を提供してくれる企業も増えてきています。
例えば、
- 定期的なスキルアップ研修やOJTの実施
- 資格取得支援制度の導入
- 正社員登用や職種変更制度の整備
など、成長を支援する環境づくりに力を入れている企業も多くあります。
キャリアアップを目指したい方は、就職前に「正社員登用の実績」「昇給や昇格の制度」「長く働いている方のキャリアの例」などを確認しておくと、将来のイメージが持ちやすくなります。
障害者雇用で実際に働いている人へアンケート!障害者雇用のメリット・デメリット
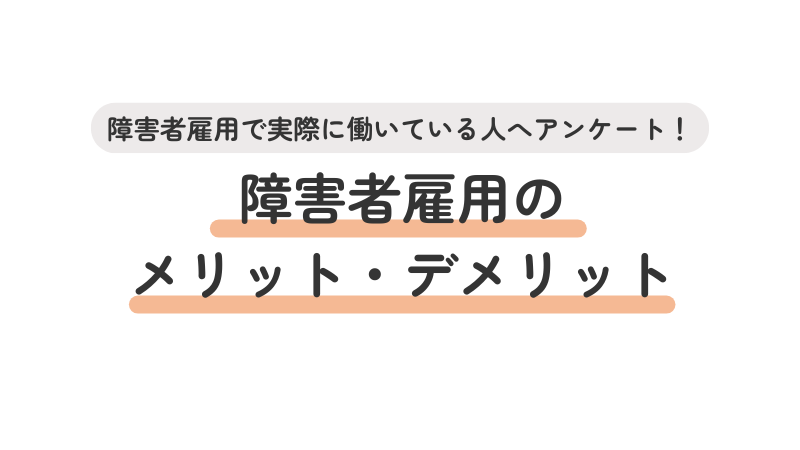
ここでは、障害者雇用で働いた経験がある43名の方に行ったアンケート結果から、リアルな体験談をご紹介します。
■ アンケート概要
- 調査内容:障害者雇用の良い点と悪い点に関するアンケート調査
- 調査方法:インターネット調査
- 調査期間:2024年4月15日 ~ 2024年4月29日
- 対象者 :障害者雇用で働いた経験がある方
障害者雇用のメリット
体調が悪いときは日数や時間を減らしていただきました。作業量も体調によって調節してもらえて、良かったです。電話対応などは台本を作っていただけたので、緊張せず行うことができました。
学校事務補助、障害者福祉施設で事務補助をしていました。足が悪く手も不自由なのですが、それを考慮してくださって業務してました。なるべく事務室から出ずに作業できる様にしてくれたり、他の職員さんからも頻繁に体調を気にかけてくださったりしていました。
コミュニケーションが苦手ということを理解してくれて、良い人ばかりの部署に配属されました。明らかに優しい人ばかりですし、仕事の進捗などもこまめに聞いてくださってとてもうれしかったです。
障害者雇用のデメリット
軽減勤務をしているので仕方のないことであり、納得していた面ではありますが、一般就労の方と比較すると、給与が5万円程度低かったことです。
人間関係で嫌になることがある。特に直接働く人や上司がかわることで、ガラッと雰囲気や仕事内容もかわる
障害者である以上業務がある程度限定的になってしまうのでステップアップに関しても限定的になってしまうことです。
よくある誤解:障害者雇用=単純作業?
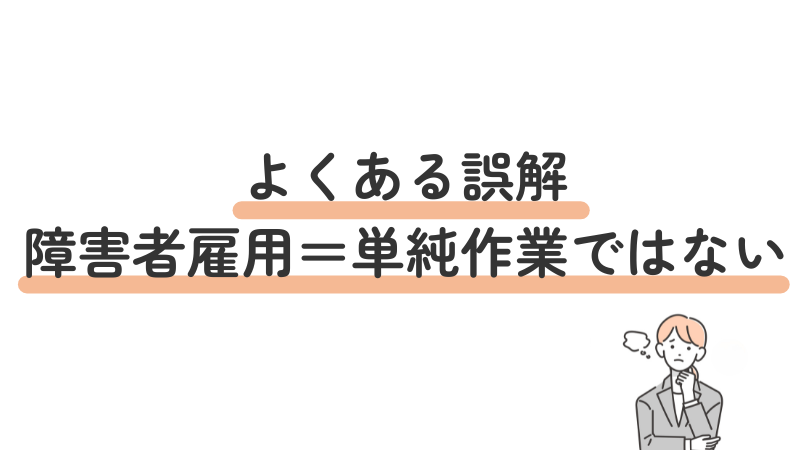
この章のポイント
- ● 障害者雇用=単純作業というイメージは誤解
- ● 実際には事務・IT・販売・農業など多様な職種がある
- ● スキルや経験を活かせる職場も増えてきている
「障害者雇用って、単純作業しかできないのでは?」「スキルや経験を活かせる仕事なんて、ほとんどないのでは…?」という不安やイメージを持っている方も少なくありません。確かに、業務を限定的に調整する企業もありますが、近年では障害者雇用の枠でも、多様な職種や働き方が増えています。
この章では、実際にはどのような仕事があるのか、どんなスキルを活かせるのかについて、解説します。
障害者雇用でも多様な職種がある
「障害者雇用=軽作業や清掃」といったイメージを持たれる方も多いかもしれません。ですが、実際には幅広い職種で活躍している方がたくさんいます。
厚生労働省の調査でも、障害の種類ごとに就いている主な職種に違いがあることが明らかになっています。
以下は、障害種別ごとの主な職種(上位3位)です。
| 障害種別 | 主な職業(上位3位) |
|---|---|
| 身体障害者 | 事務的職業、生産工程の職業、サービスの職業 |
| 精神障害者 | 事務的職業、専門的・技術的職業、サービス業 |
| 知的障害者 | サービス業、運搬・清掃・包装などの職業、販売の職業など |
参考: 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
また、例えば就労移行支援事業所manaby(マナビー)では、約7割の方が事務職に、約2割の方がIT・クリエイティブ系の職種に就職しています。PCスキルを活かして、デザインやWeb関連の仕事にチャレンジする方も少なくありません。
このように、障害者雇用だからといって単純作業に限られるわけではなく、自身の得意なことや経験を活かせる場面がたくさんあります。
事務・IT・販売など、実際の職種事例
| 職種カテゴリ | 主な仕事内容 |
|---|---|
| 事務職 | データ入力、書類整理、電話対応、経理補助、郵送物の仕分けなど |
| IT・クリエイティブ系 | Webデザイン、プログラミング、動画編集、ライティング、SNS運用など |
| 販売・接客業 | レジ業務、商品陳列、接客、品出し、簡単な調理補助など |
| 軽作業 | 検品・梱包・仕分け、シール貼り、清掃、資材の運搬など |
| 農業・園芸 | 植物の手入れ、収穫、種まき、施設の花壇管理など |
| 動物関連 | 犬猫の世話、散歩補助、ケージの清掃など |
| 専門職・在宅ワーク | 通訳・翻訳、データ入力、テスト業務、カスタマーサポート(チャット・メール)等 |
実際に障害者雇用で働く人たちが、どんな経緯で就職し、どんな仕事をしているのか気になる方は、就労移行支援manabyを利用して就職した方のインタビューも参考にしてみてください。
関連記事:就労移行支援manaby「ストーリー」
一般雇用と障害者雇用、どちらが向いている?
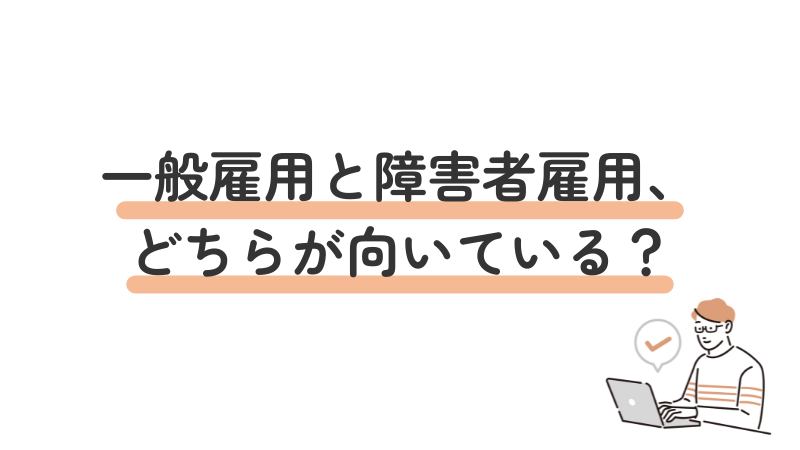
この章のポイント
- ● 一般雇用はフルタイム勤務や即戦力が求められる
- ● 障害者雇用は体調や特性に合わせた働き方が可能
- ● 「合理的配慮」で職場環境や業務内容の調整がしやすい
- ● 自分の体調・通院・将来像に合った働き方を考えることが大切
この章では、働き方や職場環境など、一般雇用と障害者雇用を比較しながら、紹介します。
働き方や職場環境の違いを比較する
| 項目 | 一般雇用 | 障害者雇用 |
|---|---|---|
| 勤務時間 | フルタイムが基本 | 体調や希望に応じて柔軟な勤務が可能(例:週3日、時短勤務など) |
| 業務内容 | 幅広い業務を担当し、即戦力を期待される | 特性や体調に配慮し、内容が調整されることが多い |
| 働くペース | 自己管理が前提 | 無理のないペースで働けるよう配慮される |
| 職場環境 | 配慮の有無は職場ごとに異なる | 光・音・人間関係などの刺激に対する相談や調整がしやすい |
一般雇用では、フルタイム勤務や幅広い業務を前提とした働き方が求められますが、障害者雇用では、働く方の体調や特性に合わせて無理のない形で働くことが重視されます。また、障害者雇用では「合理的配慮」は企業の義務であり、働きやすい職場づくりに企業が取り組んでいる点も大きな違いです。
配慮が必要な場面があるかを見極めよう
障害者雇用を検討するうえで大切なのは、「自分にとって、どんな場面で配慮が必要になるか」をあらかじめ整理しておくことです。
例えば、以下のような困りごとがある場合、障害者雇用のほうが働きやすい可能性があります。
- 長時間の勤務やフルタイム勤務が体力的に難しい。
- 人が多い環境や騒がしい職場が苦手。
- 通院や服薬のために定期的に時間を確保したい。
- 人とのやりとりに強いストレスを感じる。
こうした困りごとがある場合、障害者雇用では「合理的配慮」として、勤務時間の調整や静かな席の配属、通院への理解など、必要に応じたサポートを受けることができます。
一方で、「特に大きな配慮は必要ない」「フルタイムで幅広い業務に挑戦したい」といった希望がある方は、一般雇用も選択肢になります。
まずは、自分の体調や特性、生活リズムを見つめ直し、「どんな働き方なら無理なく続けられそうか」を考えてみましょう。
体調・通院頻度に応じた働き方を選ぶ
一般雇用では、決まった時間に出社し、フルタイムで継続的に働くことが前提とされています。そのため、体調に波がある方や、定期的な通院が必要な方にとっては、仕事との両立が難しいと感じる場面もあるかもしれません。
一方、障害者雇用では、週3日勤務や短時間勤務など、ライフスタイルや体調に応じた柔軟な働き方がしやすい環境が整っています。
例えば「午前中だけ働きたい」「週に数回通院の予定がある」といった事情がある場合でも、無理なく働けるスケジュールを組むことで、心身の安定を保ちながら就労を継続することができます。
将来的なキャリアで選ぶ
一般雇用では、幅広い業務に関わる機会が多く、昇進・昇格・異動などを通じてキャリアアップのチャンスも豊富にあります。自分の力をどんどん試していきたい方にとっては、成長の場として魅力的に感じられるかもしれません。
一方、障害者雇用では、業務がある程度限定されていたり、配慮を優先するあまり、キャリア形成の機会が少ないと感じることもあります。ただし近年では、正社員登用制度や昇給制度を整えている企業も増えており、「安定して働くこと」と「少しずつスキルを積むこと」を両立できる環境も広がりつつあります。
障害者雇用に向いている方の特徴とは?
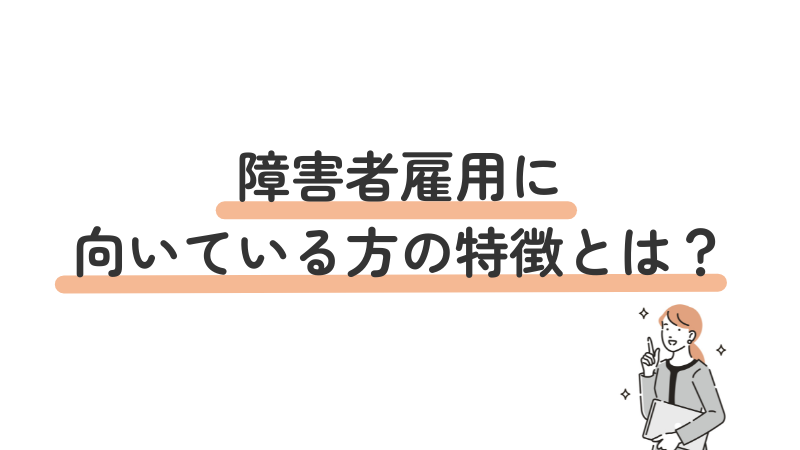
この章のポイント:障害者雇用に向いている方
- ● 体調の波があり、フルタイム勤務が難しい方
- ● 通院や苦手な業務など、具体的な配慮希望がある方
- ● 自分の障害特性や困りごとを理解している方
- ● 無理をせず、安定して長く働きたいと考えている方
ここでは、障害者雇用が向いていると考えられる方の代表的な特徴を4つ紹介します。
体調の波があり、フルタイム勤務が難しい方
特にうつ病や発達障害のある方は、日によって体調や集中力に大きな波があることも珍しくありません。「毎日フルタイムで働くのは不安」「週5日通うのは体力的に厳しい」と感じる方にとって、障害者雇用では、短時間勤務や週3日勤務からスタートできるので、無理のないペースで社会復帰を目指すことができます。
職場で配慮してほしいことが具体的にある方
「騒がしい職場がつらい」「通院のために定期的に休みを取りたい」「電話対応が苦手」など、働くうえでの困りごとや希望が明確にある方も、障害者雇用が向いています。
障害者雇用では、企業に対して「合理的配慮」を求めることが法的に認められており、本人の希望に基づいた柔軟な働き方を相談しやすい環境が整っています。無理をせず、自分に合った働き方を実現しやすいのが大きなメリットです。
自分の障害特性をある程度理解している方
「どんな場面で困るのか」「どんなサポートがあれば働きやすいのか」を自分なりに理解している方は、障害者雇用で力を発揮しやすい傾向があります。
自己理解が深いことで、企業や支援者とスムーズにコミュニケーションがとれるため、ミスマッチの少ない職場選びや、入社後の定着にもつながります。「自分に合った環境とは何か?」を一緒に考えてくれる支援者の力も借りながら、より働きやすい職場づくりができます。
再発を防ぎながら長く働きたいと考えている方
一度回復しても、無理をしたことで体調が悪化してしまった経験のある方にとって、働き続けることへの不安は大きいです。
障害者雇用では、本人のペースや状態に応じた働き方ができるよう、企業が短時間勤務や定期的な面談、業務の調整など、再発を防ぐためのサポートをしてくれるため、「無理せず長く働きたい」と考えている方にとっては、安心して就労を続けやすい制度です。
障害者雇用で働く方の体験談
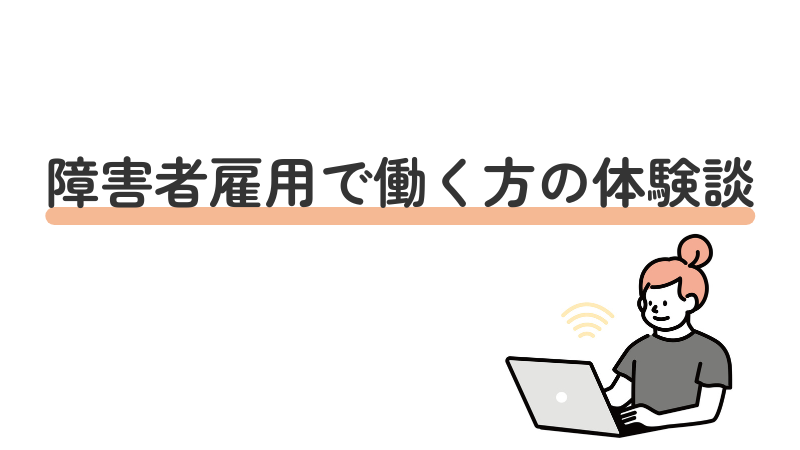
発達障害・うつ病
私は発達障害とうつ病があり、以前の一般雇用では人間関係や感覚過敏によるストレスで体調を崩し退職しました。主治医の勧めで就労移行支援を利用し、生活リズムやPCスキルの見直し、自己理解を深めたことで、自分に合った働き方が見えてきました。現在は障害者雇用枠で在宅勤務をしており、Webマーケティング業務に携わっています。通勤のストレスがない分、体調の波にも対応しやすく、自分のペースで働けるようになりました。また、障害者雇用という制度のもとで働くことで、定期的な通院や体調不良への理解があり、無理をしすぎずに業務を続けられていると感じます。業務の進め方やコミュニケーション方法についても相談しやすく、「配慮をお願いしても大丈夫なんだ」という安心感があります。
障害者雇用の求人はどこで探せる?
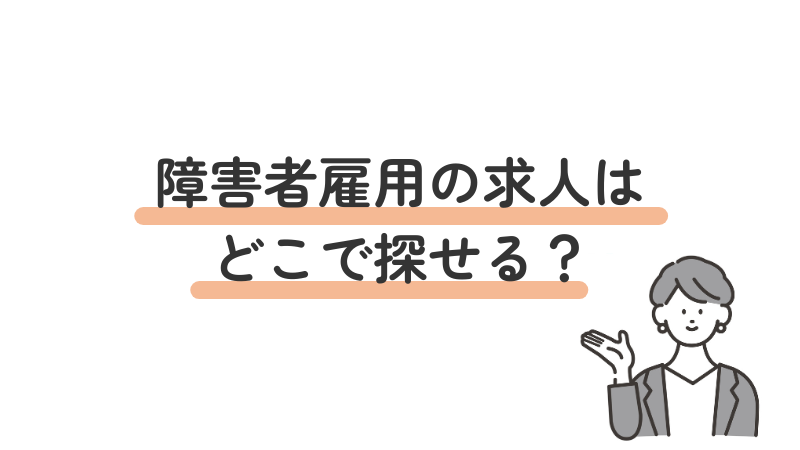
この章のポイント
- ● 障害者雇用の求人は「ハローワーク」「転職エージェント」「就労移行支援」で探せる
- ● ハローワークは公的機関で、障害者専門窓口なら配慮の相談もできる
- ● エージェントは非公開求人や条件交渉に強く、正社員を目指したい方におすすめ
- ● 就労移行支援では、訓練から求人紹介・面接同行・定着支援までサポートあり
「障害者雇用で働きたいけれど、どこで求人を探せばいいのかわからない」という方のために、障害者雇用を探すことができる代表的な3つの方法を紹介します。
ハローワークの障害者専門窓口を活用しよう
まず活用したいのが、全国のハローワークに設置されている「障害者専門窓口」です。専門の職員が常駐しており、障害の特性や体調に配慮した仕事探しをサポートしてくれます。
- 応募書類の書き方
- 面接での伝え方
- 合理的配慮の相談方法
など、一般窓口では聞きにくいことも丁寧に相談できるのが特徴です。通院や生活とのバランスを考慮した求人も紹介してもらえるため、はじめての方にもおすすめです。
障害者雇用に特化した転職エージェントとは?
最近では、障害者雇用に特化した民間の転職エージェントも増えてきました。これらのサービスでは、就労経験のある方を中心に、正社員や事務職などの求人を非公開で紹介していることが多くあります。
専門のキャリアアドバイザーが付き、希望や特性に合わせて求人を選んでもらえるほか、面接対策や企業への条件交渉も代行してもらえる点がメリットです。
「条件面をきちんと確認してから応募したい」「フルタイムでの転職を目指したい」といった方に向いています。
就労移行支援事業所からの紹介も
障害福祉サービスの一つである「就労移行支援事業所」でも、求人の紹介を受けることができます。就労移行支援では、通所しながら働く準備を整え、事業所のスタッフと一緒に自分に合った企業を探すというスタイルです。
例えば、
- 履歴書の添削
- 面接同行
- 企業への職場定着支援
といった支援もあり、「ブランクが長い」「就活に不安がある」という方にも手厚いサポートが期待できます。事業所によって得意とする職種や企業とのつながりが異なるため、見学や相談をしながら、自分に合う場所を選ぶと良いでしょう。
障害者雇用の働くサポートする支援機関
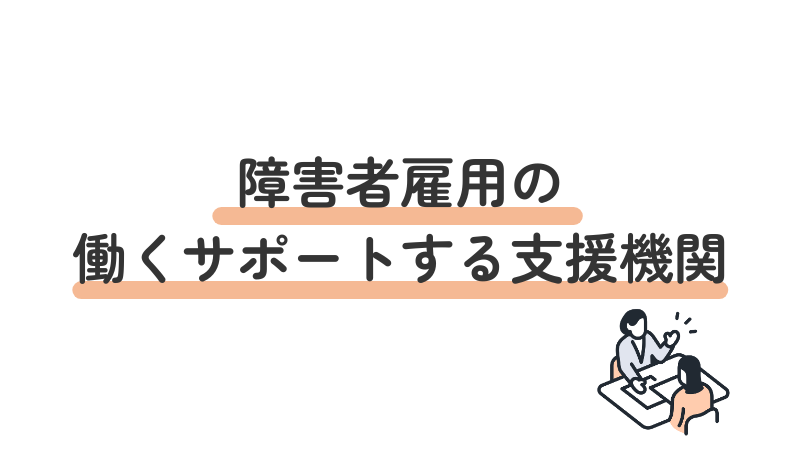
この章のポイント
- ● 障害者雇用には複数の支援機関があり、それぞれ役割が異なる
- ● ハローワークやエージェントは就職支援が中心
- ● 就労移行支援は、訓練から定着まで一貫してサポート
- ● 就業・生活支援センターでは、働くことと生活の両面を相談できる
障害者雇用を支える主な支援機関とその役割をわかりやすくご紹介します。
就労移行支援事業所とは?
就労移行支援事業所は、障害のある方が一般企業への就職を目指すためのトレーニングやサポートを提供する福祉サービスです。対象は、18歳以上65歳未満で、就労の意欲があり、一定の支援が必要と認められた方となります。
主な支援内容は以下のとおりです。
- ビジネスマナーやPCスキルなどの就労訓練
- 就職活動のサポート(履歴書作成・面接練習など)
- 職場実習の機会提供
- 就職後の職場定着支援
「自分に合った仕事を探したい」「働く準備がまだ整っていない」という方にとって、安心してステップを踏んでいける環境が整っています。
manabyの就労移行支援について
障害者雇用にはメリットもあれば、働き方や環境面に不安を感じることもあるかもしれません。
「本当に自分に合った職場があるのか」「体調や特性に合わせて働けるのか」という悩みをお持ちの方に向けて、就労移行支援manabyでは、一人ひとりのペースや状態に合わせたサポートを行っています。
例えば、次のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否については、お住まいの自治体により異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「自分は一般雇用でやっていけるのか、それとも障害者雇用を選ぶべきなのか…」「働くうえで配慮が必要だけど、どこまで相談していいのか分からない」「体調に波がある中で、フルタイム勤務が続けられるか不安」と障害者雇用を検討している方や、自分に合う働き方を見つけたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
障害者就業・生活支援センターとは?
障害者就業・生活支援センターは、障害のある方の「働く」と「暮らす」を総合的に支える公的な相談機関です。地域ごとに設置されており、誰でも無料で相談できます。
例えば、
- 職場での人間関係に悩んでいる
- 通院や生活リズムを保ちながら働きたい
- 就労移行支援やハローワークと連携したい
といった幅広い相談に対応してくれるため、「どこに相談していいかわからない」と迷ったときの窓口として非常に心強い存在です。
支援機関ごとの役割の違いとは?
障害者雇用に向けた支援機関にはさまざまな種類がありますが、「どのフェーズを支えるか」によって特徴が異なります。
- ハローワークや転職エージェントは、「できるだけ早く就職したい」「条件に合う企業を探したい」といった就職活動のサポートに強いのが特徴です。
- 一方で、就労移行支援や障害者就業・生活支援センターは、「長く安定して働けるようになりたい」「働く前に準備を整えたい」といった就労準備や定着支援にも対応しています。
どちらか一つを選ぶ必要はなく、自分の状況に合わせて併用するのがおすすめです。
以下の表に、代表的な支援機関の違いをまとめました。
| 支援機関名 | 主な役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| ハローワーク(障害者専門窓口) | 就職支援 | 公的機関で安心。求人数が多く相談も可能。 |
| 障害者専門の転職エージェント | 就職支援 | 正社員求人や条件交渉に強く、企業との調整もサポート。 |
| 就労移行支援事業所 | 就労準備〜就職〜定着までサポート | 訓練・面接練習・実習・職場定着まで一貫した支援が受けられる。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就労と生活の両立サポート | 生活面・職場調整の相談にも対応。どこに相談すべきかの案内も可能。 |
障害者雇用に関するよくある質問
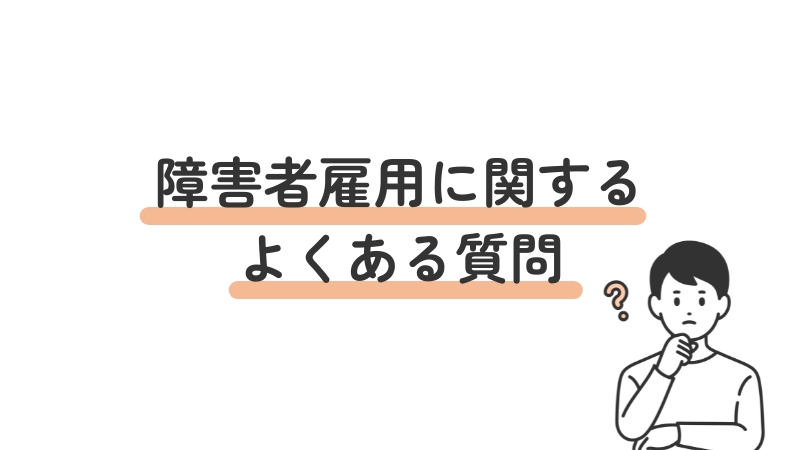
こでは、障害者雇用を検討するうえでよくある質問を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
障害者手帳がなくても障害者雇用は利用できますか?
基本的には、障害者雇用枠での応募には「障害者手帳の所持」が求められます。企業は法律上、手帳のある方を対象に採用枠を設けているためです。
ただし、企業によっては「取得予定の方」や「主治医の診断書がある方」を対象とした募集を行っているケースもあります。手帳を取得するか迷っている場合は、まずはハローワークや就労移行支援事業所に相談してみるとよいでしょう。
障害者雇用でも正社員になれますか?
障害者雇用でも正社員として働くことは可能です。近年は、長期的な雇用を前提に正社員で採用する企業も増えてきています。
ただし、最初は契約社員やアルバイトなどからスタートし、実績を積んで正社員登用されるケースも多いため、職場に慣れるステップとして段階的に働くのも一つの方法です。転職エージェントや支援機関を通じて、正社員登用制度のある企業を紹介してもらうこともできます。
障害者雇用でもキャリアアップは難しいですか?
障害者雇用でもキャリアアップは可能ですが、企業や業種によって差があります。中には昇進や異動が限定的で、単調な業務が中心となる職場もあります。自身の希望や適性に合わせて、将来的なキャリアビジョンを描ける企業を選ぶことが大切です。面接の際には「キャリアステップがどのようになっているか」を確認しておくと安心です。
障害者雇用から一般雇用に戻ることはできますか?
はい、可能です。障害者雇用で経験を積んだ後に、一般雇用に移行できます。「まずは体調に合わせて障害者雇用でスタートし、安定してきたら一般雇用へチャレンジする」という働き方は、無理のないキャリア形成としていいでしょう。
障害者雇用に応募するにはどうすればいいですか?
障害者雇用に応募するには、原則として「障害者手帳」を所持していることが必要です。
そのうえで、応募の方法としては以下のような選択肢があります。
- ハローワークの障害者専門窓口を利用する
- 障害者雇用に特化した転職エージェントに登録する
- 就労移行支援事業所から求人を紹介してもらう
これらの方法では、履歴書や職務経歴書の作成、面接対策のサポートも受けられるため、初めての就職・転職活動でも安心です。
「自分に合った働き方がわからない」「どこから始めればいいのか不安」という方も、まずは相談から始めることができます。
障害者雇用のメリット・デメリットを理解して、自分に合った働き方を見つけよう
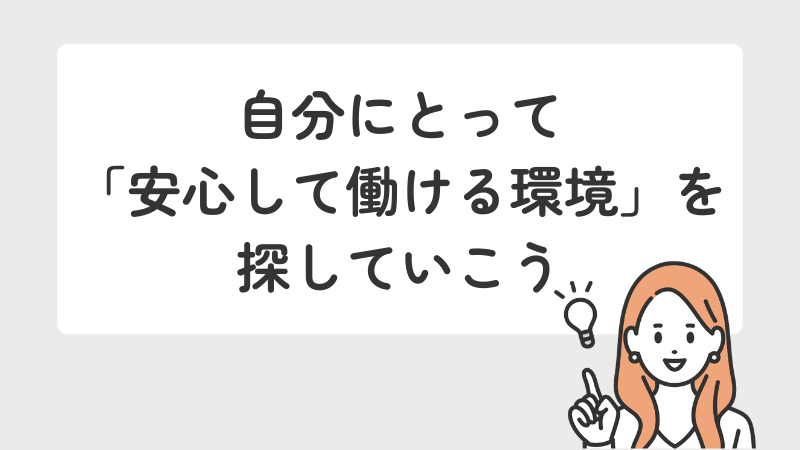
障害者雇用には、体調や障害特性に配慮した働き方ができる、合理的配慮を受けられるなどのメリットがあります。その一方で、収入や業務の幅、キャリアアップの面で不安を感じる方もいるのが現実です。
一方、一般雇用はフルタイム勤務が前提で、即戦力としての働きが求められる分、安定した収入やキャリア形成を重視する方に適している傾向があります。
以下の表は、障害者雇用と一般雇用を比較したものです。
| 項目 | 障害者雇用 | 一般雇用 |
|---|---|---|
| 勤務時間 | 週3日や短時間など、体調に合わせた働き方ができる | フルタイムが基本で、安定した出勤が前提 |
| 業務内容 | 特性に配慮して調整される。単純作業だけでなく、事務・IT・販売などもあり | 幅広い業務を任される。即戦力としての対応が求められる |
| 働くペース | 無理のないペースで取り組めるよう配慮される | 自己管理が求められ、周囲に合わせた働き方が必要 |
| 職場環境 | 音・光・人間関係などへの「合理的配慮」が相談しやすい | 配慮の有無は職場による |
| 人間関係 | 配属や接し方に配慮されることが多く、安心して働けるケースが多い | 配慮はないこともあり、ストレスを感じることも |
| 収入面 | 短時間勤務などにより収入が低くなる傾向も | フルタイムなら収入は高めだが、体調管理が重要 |
| キャリア形成 | ステップアップの機会が限られることもある | 昇進・転職など、キャリアの幅が広がりやすい |
| 向いている人 | 配慮を受けながら安定して働きたい人、再発予防を重視したい人 | フルタイムで働けて、キャリアアップを重視したい人 |
「どちらが良い・悪い」ということではなく、自分の状況や希望に合った働き方を選ぶことが大切です。
特に次のような視点で考えてみましょう。
- 毎日安定して働ける体力や体調があるか
- 通院や体調の波に配慮が必要か
- 長期的にキャリアをどう築いていきたいか
こうした視点をもとに、自分にとって「安心して長く働ける環境」を探していくことが、納得のいく就職につながります。
必要に応じて、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターなど、支援機関を活用も視野に入れてみてください。







