「うつ病かも?」と思ったら…仕事中に現れる症状と職場でとるべき行動とは

- うつ病とは?仕事や生活に影響を与える心の病気
- 仕事中に現れるうつ病のサインとは?
- 仕事に集中できず、ミスが目立つようになる
- 上司や同僚との関わりを避ける
- 清潔感や見た目への関心が薄れる
- 遅刻や欠勤が多くなる
- 体調が悪化する前にまず職場でできること
- 人事や上司に相談してみる
- 業務量や働き方の調整をお願いする
- 産業医との面談を申し込む
- 職場での対応だけで限界を感じたら、受診という選択肢も
- うつ病は精神科?心療内科?どこに相談すればいい?
- 受診したら会社にばれることはある?
- うつ病と診断されたら、仕事はどうすればいい?
- 仕事と治療の両立に向けて、働き方や業務内容を調整してもらう
- 休職して治療に専念する
- 働き方を見直して転職を考える
- 状況によっては退職も選択肢に
- うつ病で仕事を休職・退職する時に役立つお金の制度
- 傷病手当金
- 失業手当
- 自立支援医療制度
- 労災保険(労働災害補償保険)
- 生活保護
- うつ病かもと思ったら…仕事について相談できる機関
- 転職エージェント
- 就労移行支援
- manabyの就労移行支援について
- うつ病のサインに気づいたら、仕事を見直すタイミングかもしれません
最近、「気をつけているのにミスが増えた」「集中力が続かない」「会議中に内容が頭に入ってこない」など、仕事中にいつもと違う自分を感じることはありませんか?
それは、単なる疲れではなく、うつ病の初期症状かもしれません。
うつ病は、心のエネルギーが少しずつ削られていくことで発症する病気です。気づかないうちに、仕事のパフォーマンスや人間関係にじわじわと影響が出ることも少なくありません。
本記事では、仕事中に現れやすいうつ病の症状に注目しながら、「どんなサインがあるのか」「気づいたときにどうすればいいのか」を分かりやすく解説します。
さらに、うつ病で仕事が辛くなった時に使える支援制度や相談先も紹介しています。
この記事のまとめ
-
●
うつ病とは
気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったりといった体調不良が長く続き、日常生活や仕事に支障が出る心の病気 -
●
うつ病のサインに気づいたら…
限界を感じる前に業務を調節したり、産業医に相談する。病院に受診する場合は、精神科・心療内科へ。
うつ病とは?仕事や生活に影響を与える心の病気
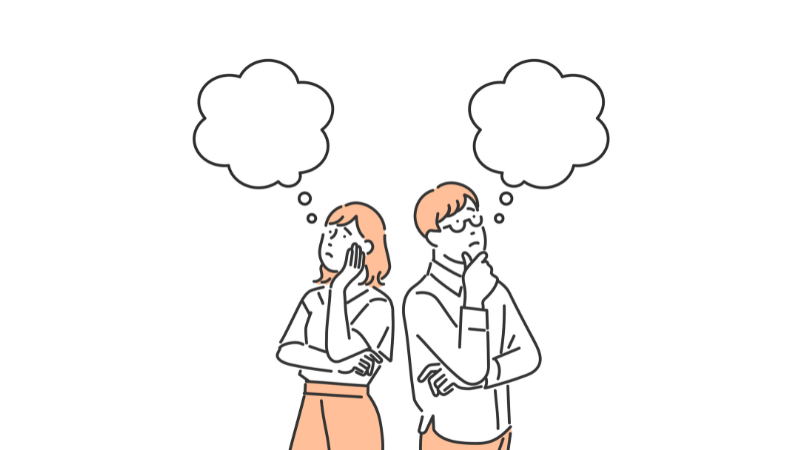
うつ病は、気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったりといった体調不良が長く続き、日常生活や仕事に支障が出る心の病気です。
一時的な「なんとなく憂うつ」「ちょっと疲れている」といった気分の落ち込みとは異なり、強いストレスなどをきっかけに脳の機能に変化が生じることで、感情や意欲、思考のコントロールが難しくなるのが特徴です。
症状は人によってさまざまで、軽度から重度まで幅があり、気づかないうちに進行してしまうこともあります。
うつ病の症状は多岐にわたり、個人によって異なりますが、一般的には以下のような症状が見られます。
| 症状 | 具体的な現れ方・特徴 |
|---|---|
| 睡眠問題 | 眠れない(不眠)、過眠になる |
| 体重の変化 | 体重が急激に増加または減少する |
| 倦怠感や意欲の低下 | 疲れやすく、何もやる気が出ない |
| 気分の落ち込み | 憂うつな気分が続く・悲観的になる |
| 物事に興味がなくなる | これまで好きだったことに興味がわかず、楽しむことができない |
| 感情が不安定 | イライラしやすい、怒りっぽくなる、不意に悲しくなる |
こうした症状が続くと、仕事を続けるのが辛くなったり、日常のことさえ億劫に感じるようになり、それでも無理をして働き続けると、ストレスが重なって症状が悪化してしまうこともあります。
仕事中に現れるうつ病のサインとは?
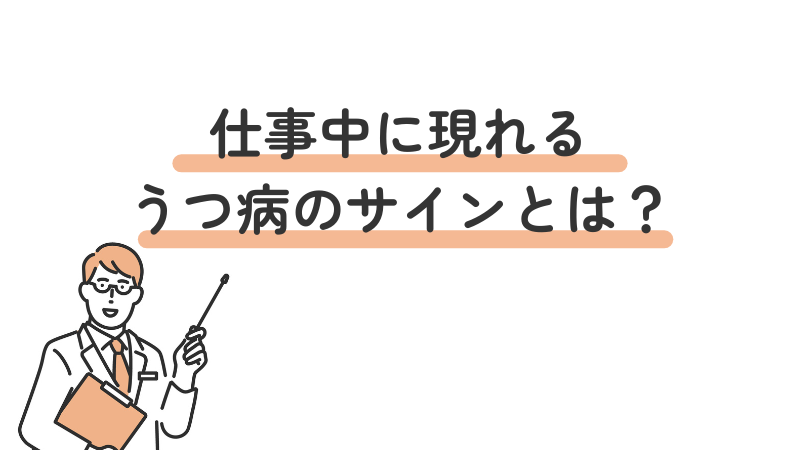
「最近、集中できない」「ちょっとしたミスが増えた」と感じることはありませんか?うつ病の初期には、気分の落ち込みだけでなく、仕事中のちょっとした変化として現れることもあります。「疲れているだけ」と見過ごされがちな変化も、実は心の不調のサインかもしれません。
ここでは、仕事中に見られる代表的なサインを4つご紹介します。
仕事に集中できず、ミスが目立つようになる
集中力の低下や注意力の散漫によって、仕事中にうっかりしたミスが増えてくることがあります。
例えば、「何度も見直しているのに誤字や脱字をしてしまう」「メールの宛先を間違える」「資料の数字を写し間違える」など、普段なら防げていたはずのミスが増えてくるのが特徴です。
これは、単なる不注意ではなく、脳の働きが低下し、思考や判断に影響が出ていることが原因です。
さらに、「会議や納期を忘れる」「優先順位をつけられず、仕事が進まない」といったスケジュールやタスク管理のミスが増えます。
こうしたミスが続くことで、「自分はダメだ」と過度に自己否定し、ストレスが増し、さらに症状がひどくなることも。
このような悪循環が続くと、心の不調がさらに深まり、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
上司や同僚との関わりを避ける
些細なことでイライラしたり、同僚や上司の言葉に敏感に反応してしまうことで、コミュニケーションが負担になり、周囲との関わりを避けるようになることがあります。
例えば、普段は気にならなかった同僚の会話に苛立ちを感じたり、上司の言葉を「責められている」と受け取ってしまい、必要以上に落ち込んでしまうことも。
その結果、以前は普通に会話していたのに、急に無口になったり、自分から話しかけることが減るなど、職場での人間関係がぎこちなくなってしまいます。
そして、孤立が続くと、ますます人と話すことが怖くなったり、「自分には居場所がない」と感じるようになり、さらに周囲との関わりを避けてしまう悪循環に陥ってしまいます。
清潔感や見た目への関心が薄れる
最近、「髪を整えるのが面倒」「何を着ていいか考えるのがしんどい」と感じることが増えていませんか?
朝の支度に時間がかかったり、最低限のメイクや着替えすら負担に感じるようになると、だんだんと見た目への関心が薄れていくことがあります。
最初は「今日はちょっと適当でいいや」という日があるだけだったのが、次第に身だしなみに気を配ることが少なくなり、以前のように鏡を見ることすら避けるようになることも。
「どうせ誰も見ていないし」「もうどうでもいい」といった気持ちが強くなると、服装の乱れや清潔感の低下が目立つようになり、周囲からの評価が下がるだけでなく、自信や意欲の低下にも繋がっていきます。
こうした状態が続くと、自分を責めたり、職場での視線が気になってしまい、さらに人と関わるのが億劫になってしまうこともあります。
これも、心のエネルギーが不足しているサインの1つです。
遅刻や欠勤が多くなる
「朝なかなか起きられない」「会社に行くのがつらい」と感じることが増えていませんか?
「無理に起きようとしても体が重く、気持ちがついてこない」そんな日が続くと、結果的に遅刻や欠勤が増えてしまうことがあります。
最初はたまの遅刻だったのが、次第に会社を休む日が増え、「欠勤が続いている…」と感じるようになる人も少なくありません。
遅刻や欠勤が続くことで「また迷惑をかけてしまった」「仕事に穴をあけた」と罪悪感を抱え、自分を責めてしまいます。
さらに、「自分がいなくても仕事は回っている」「必要とされていないのではないか」と思い込み、仕事への意欲や自信を失っていくことも。
そんな状態が続くと、「行かなきゃ」と思っていても、心と体がついてこなくなり、ますます出社が辛くなり、限界に気づけないまま無理を重ねてしまうことがあります。
遅刻や欠勤が多くなったと感じたら、「気のせい」「自分がだらしないだけ」と思い込まず、専門機関に相談してみることも大切です。
体調が悪化する前にまず職場でできること
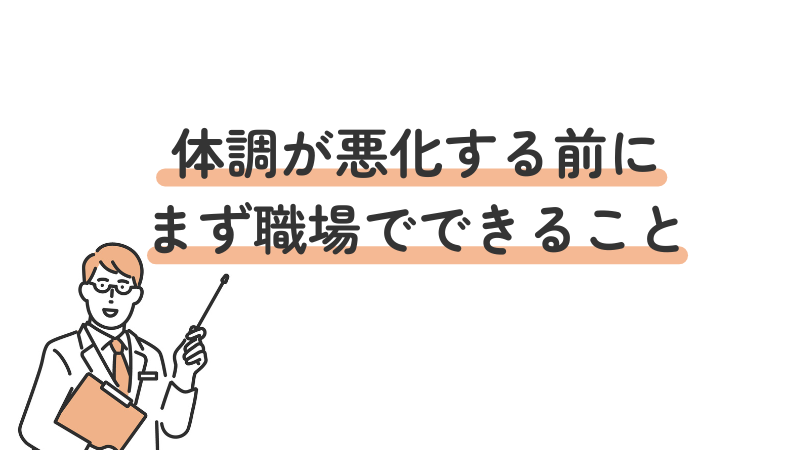
体調やメンタルに不調を感じていても、休職や退職の決断は簡単ではないものです。
「迷惑をかけるかも」「頑張らなきゃ」と思って、無理に仕事を続ける方も少なくありません。
ですが、限界を迎える前に職場でできることを知っておくことは、とても大切です。
この章では、うつ病かもしれないと感じたときに、会社でまずできる3つの行動をご紹介します。
人事や上司に相談してみる
「最近どうしても仕事がつらい」「気持ちが沈んで集中できない」など、心身の不調を感じている場合は、上司や人事担当者に相談してみましょう。
すぐに打ち明けるのは勇気がいるかもしれませんが、状況を職場に知ってもらうことで、無理のない働き方への調整や休職といった対応を取ってもらえる可能性があります。
話す内容に迷う場合は、体調の変化や仕事で困っていることをメモしておくと、伝えやすくなります。
業務量や働き方の調整をお願いする
「いつもの業務がこなせなくなってきた」「些細なミスが増えてきた」と感じるときは、業務量や働き方の見直しを検討してもらうのも大切です。
例えば、タスクの優先順位を整理してもらったり、残業を減らす、在宅勤務や時短勤務に切り替えるなど、心身の負担を軽減するための対応をしてもらえる場合があります。
「自分だけが甘えているのでは」と思うかもしれませんが、無理を続けて体調を崩してしまう前に、職場に伝えることは決してわがままではありません。
産業医との面談を申し込む
会社に産業医がいる場合は、心身の不調について専門的な立場からアドバイスを受けることができます。
「うまく眠れない」「食欲がない」「仕事への意欲が湧かない」といった症状も、産業医に相談することで、必要な対応や配慮の仕方、働き方の見直しなどについて助言をもらえる可能性があります。
また、産業医の意見をもとに、勤務時間の見直しや一時的な業務の軽減といった働き方の調整が行われたり、必要に応じて医療機関の受診を勧められることもあります。
面談を希望する場合は、人事や総務などの担当部署に相談すれば、日程を調整してもらえることが多いため、まずは気軽に申し出てみましょう。
職場での対応だけで限界を感じたら、受診という選択肢も
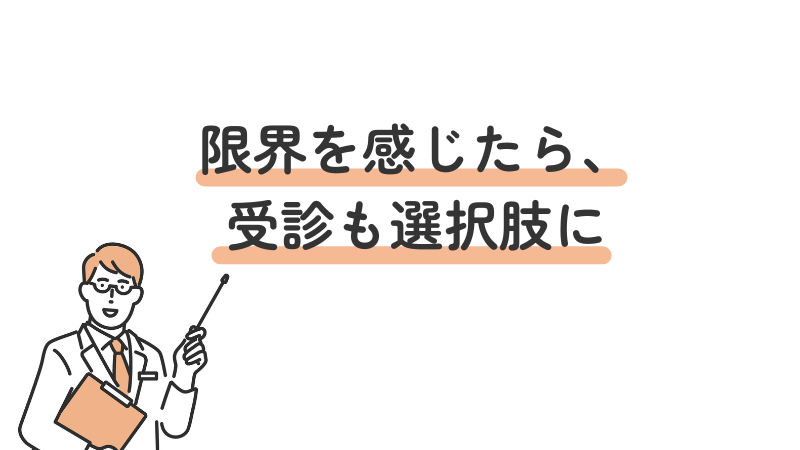
「もしかしたら、うつ病かも?」と感じても、「まだ大丈夫、もっと大変な人がいる」「こんなことで受診していいのかな」と迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。
うつ病は、誰にでも起こりうる心の不調です。「受診=重症」というわけではありません。
むしろ、早めに気づいて医療機関に繋がることで、症状の悪化を防ぎ、仕事との両立や生活の安定を図りやすくなります。
「なんとなく調子が悪い」「最近ずっと仕事が辛い」と感じる日が続いているなら、無理をせず、ひとまず専門家に相談してみることをおすすめします。
うつ病は精神科?心療内科?どこに相談すればいい?
「病院に行ったほうがいいのかな」と思っても、どこに相談すればよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
うつ病のような心の不調を感じたときは、精神科や心療内科などの医療機関が主な相談先となります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
- 精神科:うつ病・不安障害・発達障害など、心の病気全般に対応する専門的な診療科
- 心療内科:ストレスによる身体症状(例:胃痛、頭痛、不眠など)を主に扱う診療科
どちらを選んでも、うつ病の相談は可能です。初めての受診で迷ったら、「精神科」「心療内科」と表記されているクリニックを選べば安心です。
最近では、「メンタルクリニック」「メンタルヘルス科」など、受診しやすい名称の病院も増えています。
女性専用のクリニックや、オンライン相談に対応している医療機関もあるため、自分に合った方法を選びやすくなっています。
受診したら会社にばれることはある?
うつ病の症状で医療機関を受診したとしても、その事実が職場に自動的に知られることはありません。
精神科・心療内科を受診した記録は、個人のプライバシーとして守られており、勤務先や会社に情報が伝わることは基本的にありません。
また、健康保険証を使って受診しても、会社側が「どこで」「何の病気で」通院しているかを知ることはできません(例外として、産業医と連携する場合など、本人の同意があるときは情報共有されることがあります)
うつ病と診断されたら、仕事はどうすればいい?
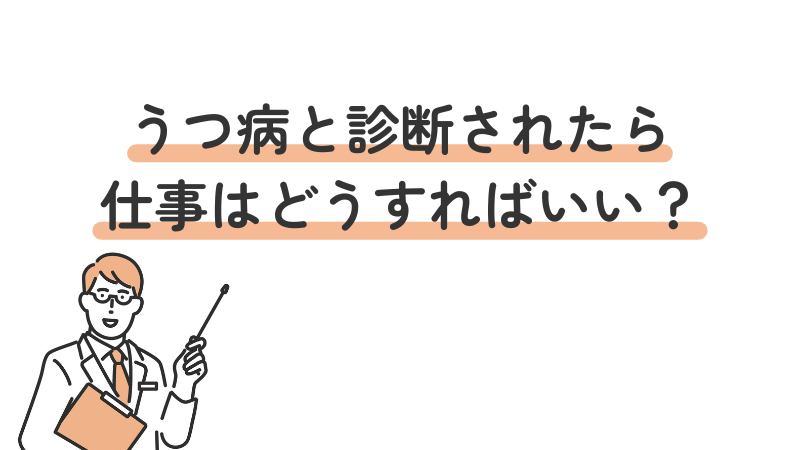
うつ病と診断された時、多くの方が「これから仕事をどうすればいいのか」と悩みます。
無理に頑張り続けるのではなく、自分の体調や気持ちに合わせて働き方を見直すことが大切です。ここでは、回復を目指すうえで考えたい4つの選択肢を紹介します。
仕事と治療の両立に向けて、働き方や業務内容を調整してもらう
いきなり休職や退職を選ばなくても、まずは働き方や業務内容の調整について、相談するという選択肢があります。
上司や人事担当者、産業医などに「最近体調が不安定でつらい」「集中力が続かない」などと率直に伝えることで、一時的な業務の見直しや、時短勤務・在宅勤務への切り替えといった対応によって、負担を減らす工夫ができる可能性もあります。
特に「今の仕事を完全に辞めるのはまだ迷っている」「まずは続けながら回復を目指したい」という方にとって、職場のサポートを受けながら働く選択肢を知っておくことは大切です。
休職して治療に専念する
「今はとにかくつらい」「何も手につかない」というときは、思い切って休むことも必要です。
会社員であれば、一定期間の休職制度を利用して治療に専念できます。
休職中は、傷病手当金などの支援制度を活用することで、収入面の不安を軽減しながら、職場復帰に向けた準備を進めることも可能です。
働き方を見直して転職を考える
今の職場の環境がどうしても合わない、配慮が得られないといった場合には、転職という選択肢もあります。
うつ病を抱えながらの転職は不安も大きいですが、障害者雇用や支援機関のサポートを利用することで、自分に合った働き方が見つかる可能性があります。
状況によっては退職も選択肢に
回復の見込みが立たない、職場復帰のイメージが持てないなど、状況によっては退職という選択も必要になることがあります。
無理をして心や体が壊れてしまう前に、「一度仕事から離れる」という判断も、自分を守るための選択肢です。
退職後の生活が不安な場合でも、失業手当や障害年金、生活保護などの制度があります。
うつ病で仕事を休職・退職する時に役立つお金の制度
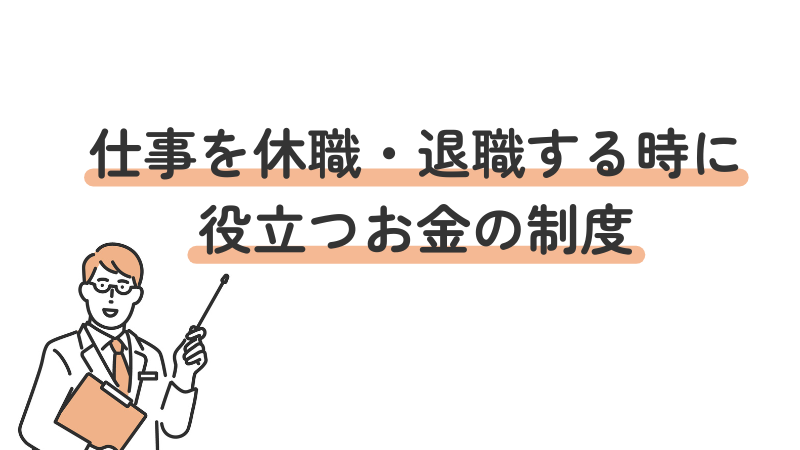
仕事が続けられなくなったら、生活はどうしたらいいの?」「収入がないのに、高い医療費は出せない…」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この章では、うつ病で仕事が続けられなくなった時に受けられる経済的な支援制度を5つ紹介します。
- 傷病手当金
- 失業手当
- 自立支援医療制度
- 労災保険(労働災害補償保険)
- 生活保護
傷病手当金
傷病手当金は、会社員や公務員の方が、うつ病などの病気やケガによって仕事を4日以上連続で休んだ場合に、給与の代わりとして健康保険から支給される制度です。
例えば、「うつ病でしばらく休職することになったけど、収入が心配…」というときに利用できます。支給額は給与の約3分の2で、最長1年6ヶ月間受け取れます。
この制度については、勤務先の人事や総務担当、もしくは加入している健康保険組合に相談してみましょう。
失業手当
失業手当(基本手当)は、雇用保険に加入していた方が離職した際に、次の仕事が見つかるまでの間、一定期間、生活を支えるために支給されるお金です。
うつ病などで「仕事を続けるのが難しくなり退職した」という場合も、一定の条件を満たせば受給できます。
まずは、お住まいの地域を管轄するハローワークに相談して、申請や必要書類について確認してみてください。
自立支援医療制度
自立支援医療制度(精神通院医療)は、うつ病をはじめとする精神疾患の治療にかかる通院医療費の自己負担を軽減してくれる制度です。
通常は3割負担の医療費が、原則1割負担になるため、長期的に治療が必要な方にとって大きな助けとなります。
この制度の申請や相談は、お住まいの市区町村の役所や福祉課で行うことができます。申請には医師の診断書が必要となるため、まずは主治医に相談しましょう。
労災保険(労働災害補償保険)
労災保険は、仕事による過度なストレスや長時間労働が原因でうつ病などを発症した場合に、医療費や休業中の収入を補償してくれる制度です。
「職場のストレスで心身が限界」「過労が原因でうつ病になった」など、明らかに業務との因果関係があるときに申請できます。
相談や申請は、労働基準監督署で行います。勤務先の人事や総務、社会保険労務士などに相談してみるのもおすすめです。
生活保護
生活保護は、うつ病の影響で働けず、生活費や医療費に困っている方を対象に、最低限の生活を保障してくれる制度です。
例えば、「働ける状態ではないけれど、収入もなく、貯金もほとんどない」という状況であれば、家賃や食費、医療費なども含めて支援が受けられる可能性があります。
生活保護の相談は、お住まいの市区町村の福祉事務所で行うことができます。申請には収入や資産の状況などを確認する手続きがありますので、不安なことがあれば事前に相談窓口で話を聞いてみましょう。
うつ病かもと思ったら…仕事について相談できる機関
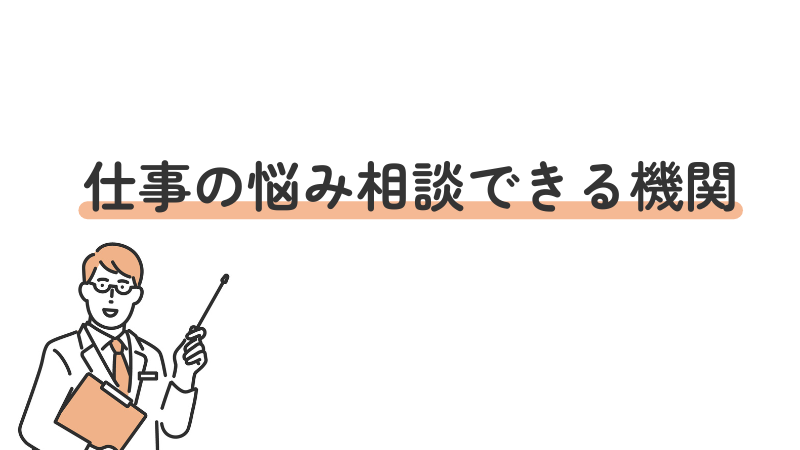
ここでは、うつ病かもと感じている方が安心して相談できる機関を3つ紹介します。
- ハローワーク
- 転職エージェント
- 就労移行支援
ハローワーク
ハローワークは、全国にある無料の公的な職業相談窓口です。
「仕事がつらい」「続ける自信がない」「休職や退職を考えているけれど、この先どうすればいいかわからない」といった不安に対して、求人の紹介や就職活動に関する相談をすることができます。
また、休職や退職後の生活が心配な方には、失業給付(雇用保険)の受け方や、再就職に向けたスキルアップ制度の紹介など、経済面や今後の方向性についても幅広くサポートしてもらえます。
関連: 厚生労働省「障害者に関する窓口」
転職エージェント
転職エージェントでは、現在の仕事が辛いことや、うつ病の症状についても踏まえた上で転職に関する相談や求人の紹介を受けることができます。
あなたの希望に合わせた働き方や職場環境について、具体的なアドバイスをもらえるのが特徴です。
また、自分1人では難しい応募書類の作成や面接対策、企業とのやり取りなども専任のアドバイザーがサポートしてくれます。
「転職したいけど何から始めればいいのか分からない」と感じている方にとっては、まず相談してみるだけでも、今の状況や気持ちを整理するきっかけになります。
就労移行支援
労移行支援とは、うつ病などの精神疾患を抱える方が、安心して就職に向けた準備を進められる福祉サービスです。
「職場のストレスで再発しないか心配」「まずは生活リズムを整えるところから始めたい」などといった気持ちに寄り添いながら、一人ひとりの体調や希望に合わせたサポートを受けることができます。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manaby(マナビー)では、うつ病をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方が自分らしく働くための支援を行っています。
1人ひとりの特性や不安に合わせた個別支援を大切にしており、「自分に合った働き方」を一緒に見つけていくことを重視しています。
例えば、以下のような支援を通じて、今の辛さを整理しながら、これからの働き方を一緒に考えていけます。
- 心身の状態を整えるための体調管理やストレス対処の練習
- eラーニングシステム「マナe」を活用したITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援あり
- 就職活動のサポート(履歴書作成・面接練習・求人の探し方)
- 就職後6か月間の定着支援
「今の仕事を続けるのがつらい」「辞めたいけど、この先が不安」とそんなお気持ちを抱えている方は、働き方を見つけ直すきっかけとして、ぜひ一度ご相談ください。
うつ病のサインに気づいたら、仕事を見直すタイミングかもしれません
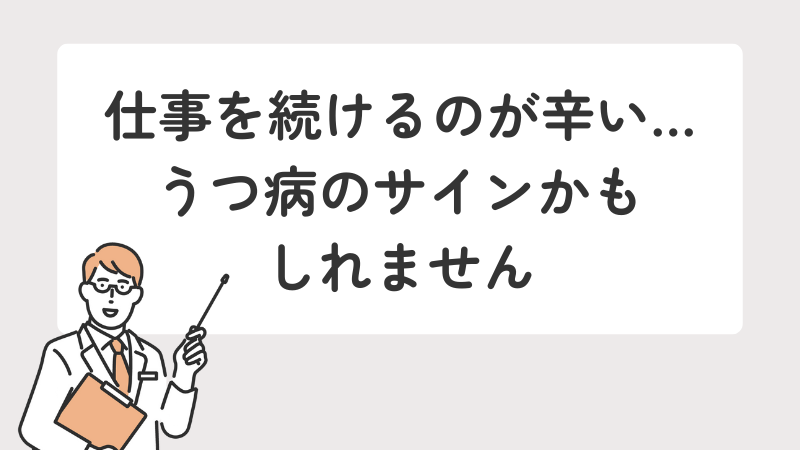
うつ病と診断されても、働き続けるという選択をしている方は少なくありません。
実際には、体調の変化や気持ちの浮き沈みを感じながらも、職場での仕事を続けるケースも多くあります。
無理なく働き続けるためには、治療を続けることに加えて、ストレスのサインに気づくこと、必要に応じて職場と業務内容を相談することが大切です。
時には、休職という選択をとることも、自分を守る手段のひとつになります。
また、「今の職場で働き続けること」だけが全てではありません。状況によっては、退職や転職を選ぶことも前向きな判断です。
いずれの場合も、傷病手当金や失業手当など、経済的な支えとなる制度があります。困ったときは、ひとりで抱え込まず、利用できる支援を活用しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。








