強迫性障害(強迫症)の方に向いている仕事とは?困りごとと仕事選びのコツ
の方に向いている仕事とは?.png)
- 強迫性障害(強迫症)とは?
- 強迫性障害(強迫症)の方が仕事で感じる困りごとは?
- 確認作業に気を取られて、本来やるべき作業に集中できない
- 上司や同僚との人間関係トラブル
- 急な予定変更や臨機応変に対応しなければならない
- 強迫性障害(強迫症)の方が働きやすい環境・働き方とは?
- 障害に理解があり、不安に寄り添ってくれる職場
- ルーティンワークで、急な予定変更が少ない
- 1人で進める作業が多い仕事
- 強迫性障害(強迫症)の方が向いている仕事
- 強迫性障害(強迫症)の方が仕事を始めるタイミングとは? 判断のポイント
- 症状が安定しているか
- 自分のストレスサインや対処法を理解できているか
- 強迫性障害(強迫症)の方が利用できる支援制度
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
- 障害年金
- 強迫性障害(強迫症)の方が仕事や生活のことを相談できる支援機関
- ハローワーク(障害者専門窓口)
- 障害者雇用専門転職エージェント
- 就労移行支援
- manabyの就労移行支援について
- 強迫性障害(強迫症)と向き合いながら、自分らしく仕事をするには
強迫性障害(強迫症)があると、「仕事はできるのか」「仕事を続けることができるのか」といった不安や悩みを感じることが少なくありません。
例えば、確認作業に時間がかかってしまったり、周囲と同じペースで作業を進めることにプレッシャーを感じたり、急な予定変更に対応できず戸惑うこともあります。こうした強迫性障害(強迫症)特有の困りごとは、仕事をするうえで大きな負担になりやすいものです。
しかし、環境や働き方を工夫することで、強迫性障害(強迫症)とうまく付き合いながら、自分らしい仕事のスタイルを見つけることは十分に可能です。
この記事では、強迫性障害(強迫症)のある方が仕事で直面しやすい困りごとや、働きやすい環境・働き方の特徴、向いている仕事の例を紹介しながら、仕事を始めるタイミングの見極め方や、利用できる支援制度・相談先についても分かりやすく解説していきます。
この記事のまとめ
-
●
強迫性障害(強迫症)とはどんな病気?
不安やこだわりで確認を繰り返してしまう病気 -
●
向いている仕事や働き方は?
データ入力などの事務作業・軽作業・在宅ワークなど
強迫性障害(強迫症)とは?
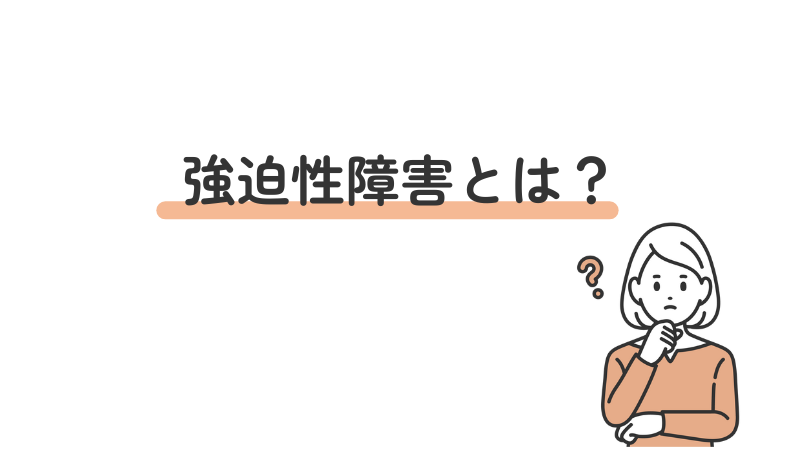
強迫性障害(強迫症)は、「何度も確認しないと気がすまない」「手を何度も洗ってしまう」といった不安やこだわりが強く表れる精神疾患です。
例えば、「鍵をかけ忘れたかもしれない」と不安になって何度も確認してしまったり、「手が汚れている気がする」と感じて何度も手を洗ってしまったりすることがあります。
「やりすぎかもしれない」「こんなことはおかしい」という自覚をしていても、不安を抑えるために繰り返さずにはいられないのが特徴です。
※強迫性障害は現在、診断基準の改訂により「強迫症」と呼ばれるようになっていますが、最新版「DSM-5-TR」以前の診断名である「強迫性障害」という表現も広く使われています。そのため、この記事では「強迫性障害(強迫症)」と表記して統一します。
強迫性障害(強迫症)の方が仕事で感じる困りごとは?
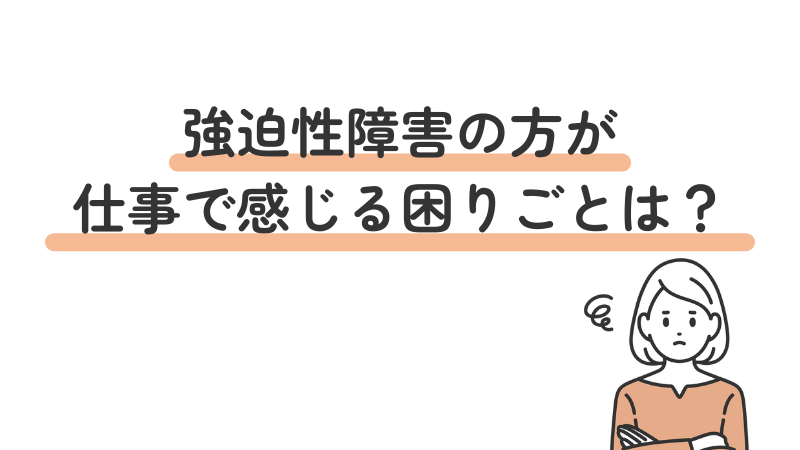
強迫性障害(強迫症)のある方は、仕事の場面でさまざまな困難を感じることがあります。
不安やこだわりの強さから、業務の進め方や人間関係、環境の変化への対応が難しくなることがあるためです。
ここでは、代表的な3つの困りごとをご紹介します。
確認作業に気を取られて、本来やるべき作業に集中できない
強迫性障害(強迫症)のある方は、「間違っていたらどうしよう」「汚れているかもしれない」といった強い不安が頭の中で繰り返されてしまい、目の前の仕事に集中できなくなることがあります。
例えば、資料の数字が合っているか何度も確認してしまい、数分で終わるはずの作業に30分以上かかってしまうことや、メールを送る前に文面を10回以上読み直して送信できなくなるといったことがあります。
周囲からは「慎重で丁寧」と思われる一方で、「作業が遅い」「まだ終わってないの?」と誤解されてしまうこともあり、プレッシャーや孤立感を抱きやすくなります。
「早く進めたい」「こんなに時間をかけたくない」と思っていても、不安を無視すると頭がいっぱいになってしまい、手が止まってしまうということも。
さらに、不安や確認への意識が強くなりすぎて、目の前の作業に意識を向けられず、集中できなくなることもあります。
「確認をやめる=大きなミスに繋がるのでは」という恐怖感が根底にあるため、意識的に確認をやめることも簡単ではありません。
その結果、予定通りに仕事が進まないことに自己嫌悪を感じたり、周囲の期待に応えられないストレスを強く感じてしまうことがあります。
上司や同僚との人間関係トラブル
強迫性障害(強迫症)の特性によって、ミスへの強い不安や自信のなさが影響し、上司や同僚との関係に悩むこともあります。
例えば、指摘を受けたことで極端に落ち込んでしまったり、確認作業や手順へのこだわりが強いために、「融通が利かない」「細かすぎる」といった誤解を受けてしまったりすることも少なくありません。
そのような積み重ねから、人と関わることそのものにストレスを感じやすくなり、必要以上に気を張って疲れてしまうこともあります。
結果として、距離を取りすぎる、孤立してしまうことにつながってしまいます。
急な予定変更や臨機応変に対応しなければならない
強迫性障害(強迫症)のある方は、決まった手順やルールが崩れることに対して強い不安を感じることがあります。
そのため、急なスケジュール変更や予期しない業務の割り込みなどがあると、気持ちの切り替えがうまくできず、混乱してしまうことも少なくありません。
また、「これで大丈夫か」と考えすぎてしまい、新しい対応に踏み出せなかったり、自分の中で整理がつかないまま焦りばかりが募ってしまったりするケースもあります。
こうしたことから、臨機応変な対応が求められる職場では、プレッシャーや精神的な負担を感じやすく、体調を崩すきっかけになります。
強迫性障害(強迫症)の方が働きやすい環境・働き方とは?
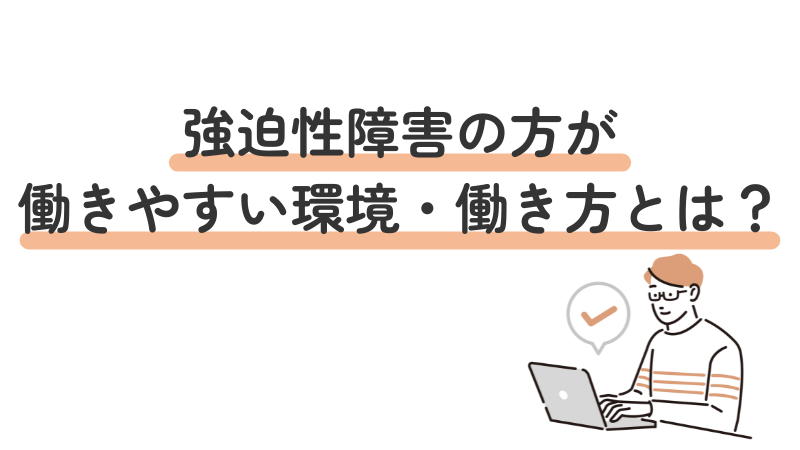
強迫性障害(強迫症)のある方が無理なく働くためには、症状の特性に配慮された職場環境や働き方の工夫がとても重要です。
環境や業務内容が合わない場合、症状に大きく影響を与えてしまうこともあるため、症状の特性に配慮された工夫やサポートがあるかどうかが、働きやすさを大きく左右します。
障害に理解があり、不安に寄り添ってくれる職場
強迫性障害(強迫症)のある方が安心して働き続けるためには、特性や体調への理解があり、必要な配慮を受けながら働ける職場環境を選ぶことが大切です。
その選択肢のひとつとして、「障害者雇用」や「特例子会社」での勤務があります。
- 障害者雇用:障害のある方が安心して働けるように、法律で定められた制度。企業には一定の割合で障害者を雇用する義務があります。
- 特例子会社:大手企業などが、障害のある方を継続的に雇用するために設立した、障害者雇用に特化した子会社のことです。
障害者雇用や特例子会社では、強迫性障害(強迫症)のある方が働きやすくなるよう、以下のような配慮がされることがあります。
職場で受けられる配慮の具体例
- 確認作業に時間をかけられるよう、業務の進め方を調整してくれる
- 業務手順やルールが明確にされ、急な変更が起こりにくいように配慮されている
- 定期的に体調や困りごとを相談できる面談やフォローがある
- 静かな場所や集中しやすい席を選べることがある
- コミュニケーションが少なめな作業を任せてもらえる
こうした環境が整っていることで、不安を感じる場面を減らしながら、自分のペースで働けるようになります。
ルーティンワークで、急な予定変更が少ない
強迫性障害(強迫症)のある方にとって、決まった手順やスケジュールで仕事を進められる環境は、安心して働くための大きな支えになります。
毎日業務内容が大きく変わったり、急に指示が追加されたりすると、頭の中が混乱してしまったり、不安が強くなって作業に集中できなくなることがあります。
そのため、あらかじめ決まった流れで作業ができるルーティンワークは、心の負担が少なく、強迫性障害の特性に向いている働き方です。
1人で進める作業が多い仕事
強迫性障害(強迫症)のある方の中には、周囲の目が気になったり、人と関わることで緊張や不安を感じやすい方もいます。
そうした場合、自分のペースで落ち着いて取り組める、または1人で進める作業が多い仕事は、安心して働きやすい選択肢のひとつです。
1人で進める業務であれば、周囲とのコミュニケーションに気を取られることが少なく、作業に集中しやすくなるというメリットがあります。
また、確認作業や手順へのこだわりがあっても、他人に急かされることが少ないため、自分の特性に合わせたリズムで仕事を進めやすくなります。
強迫性障害(強迫症)の方が向いている仕事
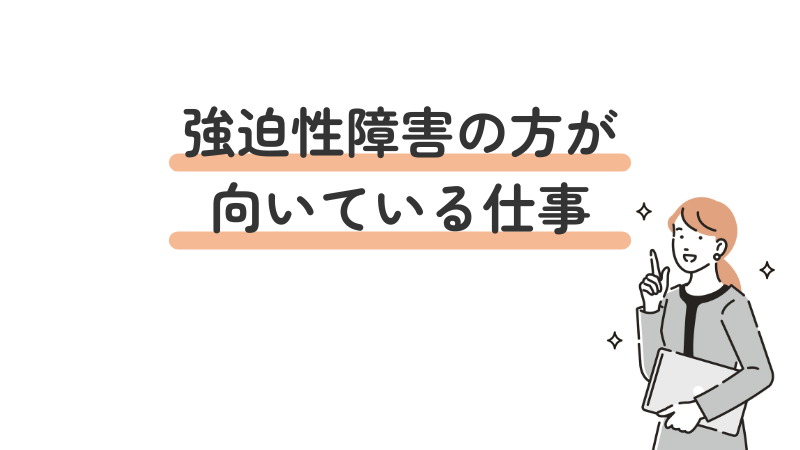
強迫性障害(強迫症)のある方は、「確認を何度もしてしまう」「決まった手順にこだわりがある」「急な変更に混乱してしまう」といった特性から、仕事選びに不安を感じることも多いかもしれません。
ですが、働き方や職場環境を工夫することで、無理なく働き続けることは十分に可能です。
| 仕事の例 | 特徴・理由 |
|---|---|
| データ入力、文字起こしなどの事務作業 | 静かな環境でルールに従って黙々と進められる |
| 清掃業務、備品管理などの施設管理系 | ルーティンワーク中心で、急な変更が少ない |
| 軽作業(シール貼り・検品・封入など) | 一定のペースで繰り返す作業が多く、集中しやすい |
| 在宅ワーク(Webライター・デザイナー・入力代行など) | 自分のペースで取り組め、人間関係や通勤のストレスが少ない |
| 図書館・資料室での整理、書類のスキャンや保管業務 | 整理整頓が求められ、静かな環境で集中しやすい |
これらの仕事は、急な判断や臨機応変な対応が少なく、手順や環境が安定していることが特徴です。
無理に自分を変えようとするよりも、自分の特性に合った職種や環境を選ぶことで、安心して長く働ける可能性が広がります。
強迫性障害(強迫症)の方が仕事を始めるタイミングとは? 判断のポイント
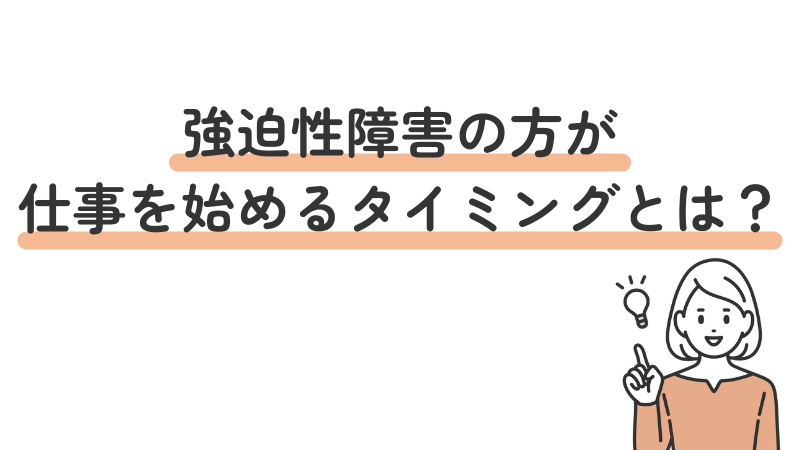
強迫性障害(強迫症)のある方が仕事を始めようと考える時、「今、本当に働き出して大丈夫なのか」という不安を感じるのでないでしょうか。
焦らず、自分の状態をしっかり見極めたうえでタイミングを判断することが大切です。
無理をしてスタートすると、負担が積み重なり、体調を崩してしまうリスクもあるため、次のようなポイントを参考にしながら、慎重にタイミングを考えていきましょう。
症状が安定しているか
まず大切なのは、強迫症状(確認行為や強い不安)がある程度落ち着いているかを確認することです。
「強い不安で手が止まってしまう」「確認に時間がかかりすぎて生活リズムが乱れる」といった状態が続いている場合は、もう少し回復を待った方がよいかもしれません。
目安としては以下のことが感じられるようになってきたら、仕事を考え始めるタイミングに入ってきたと言えます。
- 日常生活が大きな負担なく送れている
- ストレスのかかる場面でも、ある程度自分で対処できる
また、症状の安定については、主治医と相談しながら判断するのがおすすめです。主治医から復職について許可がもらえてから徐々に仕事をこなしていくことで無理なく続けられます。
また、定期的にカウンセリングを受けるなど、客観的な意見を取り入れることで、自分だけでは気づきにくい状態変化も把握しやすくなります。
自分のストレスサインや対処法を理解できているか
仕事を始めると、どんなに環境が整っていても、多少のストレスを感じる場面は避けられません。
そのため、自分がストレスを感じやすい状況や、体調が悪化するサインを理解できているかどうかも、大切な判断ポイントになります。
例えば、次のように自分なりのストレスのパターンに気づけているかを振り返ってみましょう。
- 確認作業を途中でやめると、強い不安に襲われて手が止まってしまう
- 汚れているかもしれないという感覚が頭から離れず、作業に集中できなくなる
- 「完璧にできたかどうか」が気になりすぎて、次の作業に進めなくなる
こうしたストレスのサインを把握できていると、自分にとって負担が大きい場面を予測したり、働き方を工夫するヒントになります。
また、ストレスを感じたときに簡単な対処行動(例:深呼吸をする、少し休憩を取るなど)を思い浮かべられるかどうかも、働き始めるタイミングを判断するポイントになります。
強迫性障害(強迫症)の方が利用できる支援制度
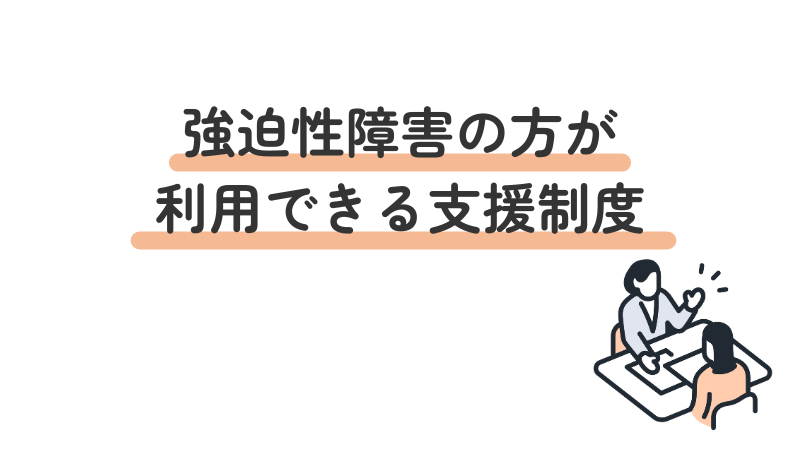
強迫性障害(強迫症)のある方が安心して働き続けるためには、生活面や就労面で利用できる支援制度を知っておくことも大切です。
症状によっては、働き方を工夫したり、治療を続けながら無理なく社会参加していくことが必要になるため、公的な制度を上手に活用することが心身の負担を軽減する助けになります。
ここでは、強迫性障害(強迫症)の方が仕事や生活に関して利用できる代表的な支援制度を3つご紹介します。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、強迫性障害(強迫症)などの精神疾患により通院治療が必要な方の医療費を軽減する制度です。
通常3割かかる医療費が、原則1割負担になります。
対象となるのは、診察、薬の処方、訪問看護、デイケアなどです。
利用には、医師の診断書を用意し、住んでいる市区町村の役所で申請する必要があります。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、強迫性障害(強迫症)を含む精神疾患がある方が取得できる手帳で、日常生活や就労面で必要な配慮を受けやすくするための制度です。
この手帳を持っていると、就職活動や仕事を続けるうえで支援や配慮を受けやすくなるメリットがあります。
例えば、障害者雇用枠での就職を目指す場合や、働くうえで必要な配慮を求める際に役立ちます。
また、税金の控除や交通機関の割引など、生活面で利用できる支援もあります。
取得には、医師の診断書などが必要です。
申請は、お住まいの市区町村の役所窓口で行います。詳しい手続きについては、各自治体にお問い合わせください。
障害年金
障害年金は、強迫性障害(強迫症)などの障害によって働くことや日常生活に支障がある場合に受け取れる公的な年金です。
症状が重く、就労が難しい、または働く上で大きな制限を受けている場合に支給対象となることがあります。
等級によって支給額は異なりますが、受給できれば生活の安定に役立つ支援となります。
申請は、年金事務所や市区町村の窓口で行います。
強迫性障害(強迫症)の方が仕事や生活のことを相談できる支援機関
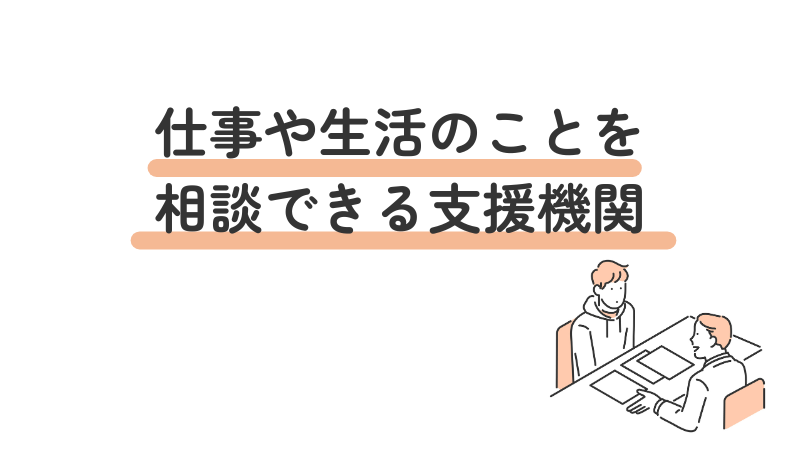
強迫性障害(強迫症)の方が仕事・生活のことを相談できる支援機関を紹介します。
ハローワーク(障害者専門窓口)
ハローワークには、障害のある方向けの「障害者専門窓口」が設置されているところがあります。
ここでは、強迫性障害(強迫症)を含む精神障害のある方でも、配慮を受けながら仕事探しのサポートを受けることができます。
担当者が障害特性をふまえて求人を紹介してくれるほか、次のような支援も受けることができます。
- 障害者雇用枠の求人紹介
- 面接対策(模擬面接や受け答えの練習)
- 履歴書・職務経歴書の作成アドバイス
- 仕事に必要なスキルや資格に関する相談
障害者雇用枠の求人も多数取り扱っているため、強迫性障害(強迫症)があっても、自分に合った働き方を一緒に考えてもらえる安心できる相談先の一つです。
障害者雇用専門転職エージェント
障害者雇用専門の転職エージェントは、障害のある方向けに特化した転職支援サービスです。
強迫性障害(強迫症)のある方でも、特性に配慮しながら求人を紹介してもらえるのが特徴です。
一般的な求人サイトとは違い、エージェントが間に入って企業と調整してくれるため、負担を減らしながら転職活動を進めることができます。
受けられるサポート例は次の通りです。
- 障害特性に配慮した求人の紹介
- キャリアカウンセリング(強み・希望に応じた仕事探し)
- 企業への応募書類(履歴書・職務経歴書)作成サポート
- 面接練習
- 企業との条件交渉・配慮事項の事前調整
- 就職後のフォローアップ支援
転職活動をサポートしてくれる方法の1つですが、長期的な支援を希望する場合は、他のサービスも合わせて検討すると安心です。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、働くための準備や就職活動のサポートを行う福祉サービスです。
強迫性障害(強迫症)のある方も利用でき、体調や特性に合わせたペースで、無理なく就職を目指すことができるのが特徴です。
転職エージェントが主に就職活動をサポートするのに対して、就労移行支援は、働くための準備段階から就職後のサポートまで、1人ひとりに合わせた支援を受けられる点が大きな違いです。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manabyでは、強迫性障害(強迫症)の方をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方が自分らしく働くための支援を行っています。
確認作業に時間がかかってしまう、不安や緊張で作業が進まない、体調や気分の波に不安を感じている方でも、1人ひとりの状態やペースに合わせた「個別支援」を大切にしており、「どんな働き方が自分に合っているか」を一緒に考えていくことを重視しています。
例えば、次のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否についてはお住まいの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「何度も確認をしてしまい作業が進まない」「予定が崩れると不安でいっぱいになる」「自分にできる仕事が本当にあるのか不安」と働くことへお悩みがある方はぜひ、お気軽にご相談ください。
強迫性障害(強迫症)と向き合いながら、自分らしく仕事をするには
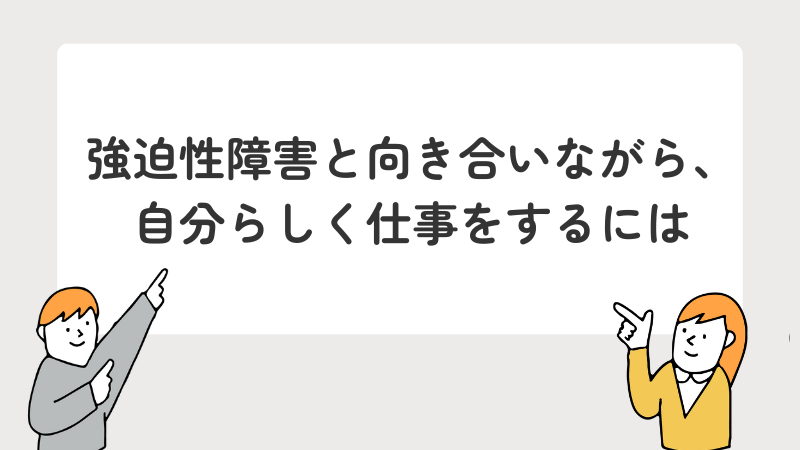
強迫性障害(強迫症)があると、仕事に向き合う中で不安や戸惑いを感じる場面も少なくありません。
確認作業に時間がかかったり、急な予定変更に対応できなかったり、周囲とのコミュニケーションに悩んだりすることは多いかもしれませんが、それは決して「甘え」でも「努力不足」でもありません。
そうした悩みを抱えながらも、少しずつ前に進んでいくためには、自分の特性を理解し、無理のないペースで働く方法を見つけることが大切です。
働き方を工夫したり、支援制度や相談先を上手に活用したりすることで、強迫性障害(強迫症)と向き合いながらも、自分らしく働くことは十分に可能です。
強迫性障害(強迫症)は再発しやすい病気です。症状が落ち着いているからといって完全に治っているわけではありません。主治医やカウンセラーとは定期的に繋がっていき、症状の再発・悪化を未然に防ぎながら、焦らず、比べず、自分に合った仕事のスタイルを探していきましょう。








