大人のASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴・原因・相談先まで解説
とは?特徴・原因・相談先まで解説.png)
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)とは?
- 発達障害とは?
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴と困りごと
- 対人関係の距離感や空気の読みづらさ
- 会話のズレや一方的な話し方などコミュニケーションのつまずき
- 予定通りに進まないことへのストレスや不安を感じやすい
- 自分なりのルールや手順に強いこだわりを持っている
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)の原因とは
- ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意注意欠如多動症)との違い
- うつ病などの二次障害からASD(自閉スペクトラム症)と気づくこともある
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)と仕事の向き合い方
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)の方が利用できる相談先
- お住まいの市町村の障害窓口
- 保健所・保健センター
- 仕事や生活面の不安を相談できる就労移行支援も
- manabyの就労移行支援について
- 大人のASD(自閉スペクトラム症)かもしれないと思ったら、まずは自分の困りごとを言語化しよう
「相手の気持ちが分からない」「柔軟な対応が苦手」といった困りごとはありませんか?
それは、発達障害の1つである「ASD(自閉スペクトラム症)」の特性が関係しているかもしれません。
ASD(自閉スペクトラム症)とは、対人関係やコミュニケーションの難しさ、特定の行動へのこだわりが特徴とされ、大人になってから気づくケースも少なくありません。
この記事では、大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴・原因・対処法や相談先について、分かりやすく解説します。
この記事のまとめ
-
●
大人のASDの特徴
ASD(自閉スペクトラム症)は、対人関係やコミュニケーションの難しさ、特定の行動へのこだわりが特徴です。大人になってから特性が顕著になることも多く、柔軟な対応が苦手でストレスを感じやすい傾向があります。 -
●
ASDかもと思ったら
まずは自分の困りごとを言語化することが重要です。これにより、相談しやすくなり、必要な支援を見つけやすくなります。
大人のASD(自閉スペクトラム症)とは?
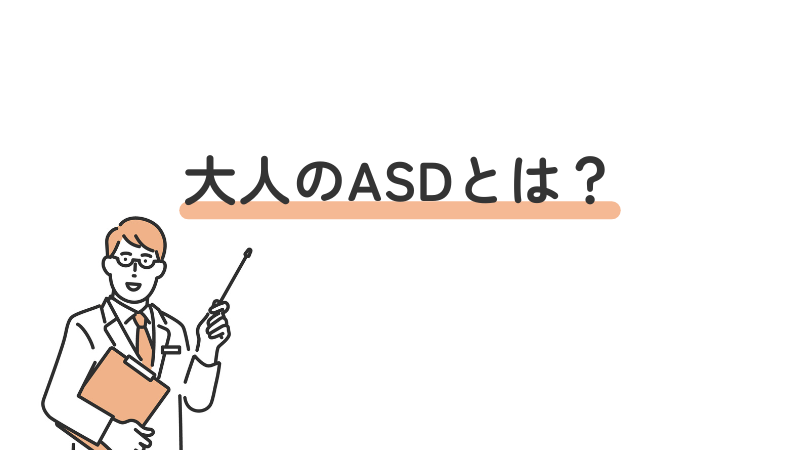
ASD(自閉スペクトラム症)の特性は幼少期から見られますが、子どもの頃には特性が目立たず、大人になって環境が大きく変わることをきっかけに、ASDの特性が顕著になることがあります。
例えば、他者との距離感の取り方が難しい、会話のテンポにうまく乗れない、急な予定変更に不安を感じやすいなどの特徴があります。
また、日常のルーティンが崩れると強いストレスを感じやすく、柔軟な対応が求められる場面では戸惑いや不安を抱きやすい傾向もあります。
こうした特徴は、幼少期には「ちょっとマイペース」くらいに受け取られていたとしても、社会人になって環境や役割が複雑になることで、一気に困りごととして現れることがあります。
発達障害とは?
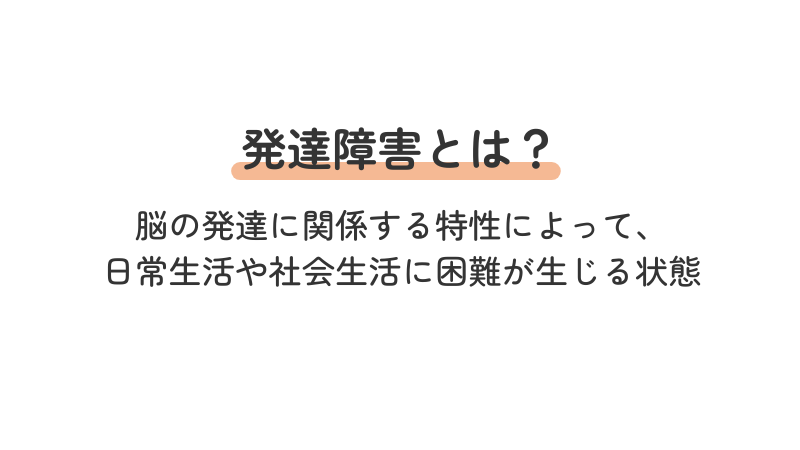
発達障害は、脳の発達に関係する特性によって、日常生活や社会生活に困難が生じる状態を指します。
幼少期から特徴があらわれることが多く、対人関係・コミュニケーション・感覚・行動・学習面などに独自の傾向が見られるのが特徴です。
大人になってから気づくケースもあり、「生きづらさ」の背景に発達障害が関係していることもあります。
代表的なものに、ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如・多動症)・LD(学習障害)などがあります。
大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴と困りごと
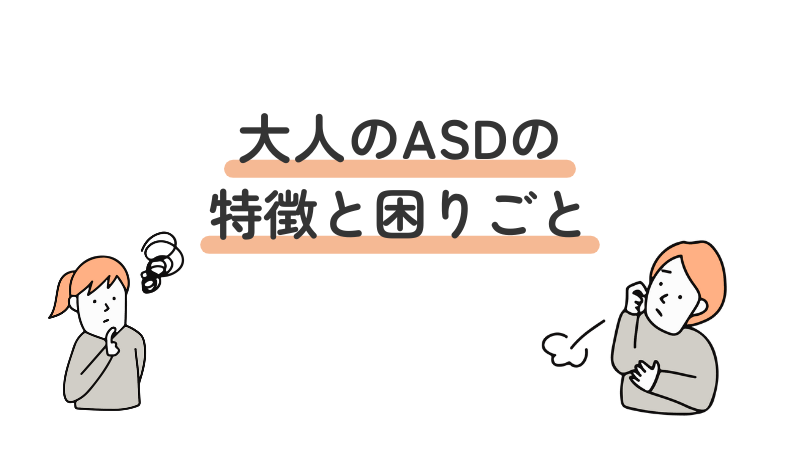
ASD(自閉スペクトラム症)のある方は、日常生活や職場の中で対人関係や環境の変化に関する困りごとを感じやすい傾向があります。
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)の主な特性とあわせて、実際にどのような場面で困りごととして現れやすいのかを具体的にご紹介します。
対人関係の距離感や空気の読みづらさ
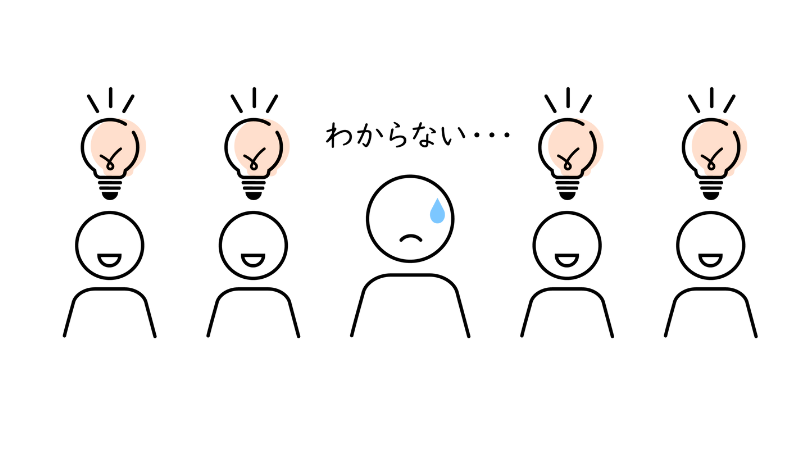
ASD(自閉スペクトラム症)の方に見られる特徴のひとつが、人との距離感のとり方が難しいことや、場の空気を読むのが苦手なことです。
例えば、周囲がなんとなく察して行動しているようなことや、表情・声のトーンなどの微妙な変化に気づきにくいことがあります。
職場で上司が明らかに忙しそうにしている時、まわりは「今は話しかけないほうがよさそう」と感じて行動を控えることがありますが、ASD(自閉スペクトラム症)の方にとってはそうした雰囲気を読み取るのが難しく、意図せず声をかけてしまうことがあります。
その結果、「空気が読めない」と思われたり、タイミングがずれて会話がかみ合わず、誤解や気まずさに繋がってしまいます。
会話のズレや一方的な話し方などコミュニケーションのつまずき

ASD(自閉スペクトラム症)の方には、言葉を文字どおりに受け取りやすい傾向があります。
そのため、相手がやんわり伝えようとしたつもりでも、文字どおりの意味で受け取ってしまい、戸惑うことがあります。
例えば、遊びに誘った時に「本当は行きたいけど忙しいからまた今度ね」と断られた際に「遊びたいと思っているなら明日は?明後日は?来週は?」と質問攻めにしてしまい、一歩引かれてしまうケースや「あとでやっておいて」と言われた時、「あとでっていつ?」と具体的なタイミングがわからず混乱してしまうケースがあります。
また、自分の興味のある話題になると、一方的に話しすぎてしまうことも。
電車が好きな方が、形式や路線について詳しく話していたら、相手がうなずいていたものの、実は内容についていけず困っていた…というような場面です。
さらに、冗談や比喩が伝わりにくいこともあります。
場の雰囲気がつかめず、「なんで笑ってるの?」「どういう意味だったの?」と戸惑うことも少なくありません。
こうしたコミュニケーション上のズレが積み重なることで、「話が通じない人」と誤解されてしまい、対人関係において辛さを感じる原因になることがあります。
予定通りに進まないことへのストレスや不安を感じやすい

ASD(自閉スペクトラム症)の方の中には、決まったスケジュールやルーティンが守られていると安心して行動しやすいという方が多くいます。
朝の準備や仕事の順番など「決まった流れ」があることで落ち着いて過ごせるという方も少なくありません。
反対に、予定の変更や想定外の出来事が起こると、不安が強くなりやすい傾向があります。
例えば、朝の会議が突然キャンセルになっただけでも、「このあとどう動けばいいのか」と戸惑い、不安から頭が真っ白になって、動けなくなってしまいます。
周囲にとっては小さな変化でも、本人にとっては大きなストレスに感じてしまいます。
自分なりのルールや手順に強いこだわりを持っている

ASD(自閉スペクトラム症)のある方の中には、「このやり方じゃないと落ち着かない」「この順番で進めたい」といった、自分なりのルールや手順に強いこだわりを持っている方もいます。
例えば、ファイル整理を自分の決まった順番で進めていたのに、上司から「順番は気にしなくていいから早く仕上げて」と言われて混乱してしまうことがあります。
自分なりのルールや手順へのこだわりが維持できると、気持ちが安定しますが、急なルール変更が多かったり、臨機応変な対応を求められると、戸惑いや混乱を感じてしまいます。
その結果、「柔軟に対応できない人」と誤解されてしまい、対人関係や仕事に影響が及ぶことがあります。
本人にとっては心の安定を保つために欠かせない手順であっても、周囲とのギャップがストレスの原因になります。
大人のASD(自閉スペクトラム症)の原因とは
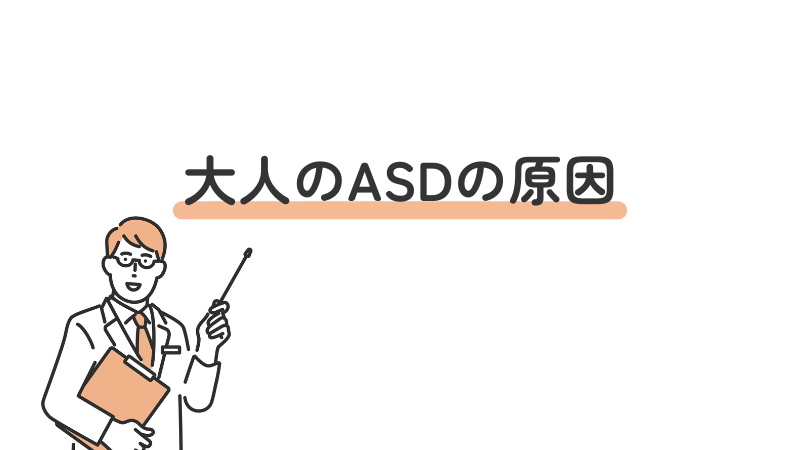
ASD(自閉スペクトラム症)の原因については、まだ完全には解明されていませんが、生まれつきの脳機能の働き方に違いがあることが関係していると考えられています。
「育て方が悪かったのでは?」「しつけが足りなかったのでは?」といった誤解を耳にすることもありますが、そうした環境的な要因が原因ではありません。
ASD(自閉スペクトラム症)は誰のせいでもなく、先天的な特性のひとつです。
だからこそ、「どうしてこうなったのか」と原因を探すよりも、「どう対処すれば安心して過ごせるのか」「どんな環境なら力を発揮できるのか」を考えていくことが大切です。
ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意注意欠如多動症)との違い
| 特徴 | ASD(自閉スペクトラム症) | ADHD(注意欠如多動症) |
|---|---|---|
| 主な特性 | コミュニケーションの苦手さ同じ行動をくり返すことが多い | 注意がそれやすいじっとしているのが苦手 |
| 人との関わり | 会話の間や表情から気持ちを読み取るのがむずかしい | おしゃべりが止まらなかったり、話を最後まで聞けなかったりすることがある |
| 興味・集中力 | 特定のことに強いこだわりがある | 興味のあることには集中できるが、すぐ気がそれてしまうことも多い |
| 感覚の特徴 | 音や光などにとても敏感、または鈍く感じることがある | まわりの刺激に反応しやすく、落ち着かないことがある |
| 困りごと | 柔軟に対応するのが苦手で、予定外のことに不安を感じやすい | 忘れ物や遅刻が多く、スケジュールを管理するのが苦手 |
ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)は、どちらも発達障害のひとつですが、それぞれに違った特徴があります。
ASD(自閉スペクトラム症)の方は、人とのやりとりや予定外の出来事に不安を感じやすく、決まったやり方やルールに沿って行動することで安心しやすい傾向があります。
一方でADHD(注意欠如多動症)の方は、注意がそれやすい、じっとしているのが難しい、といった落ち着きにくさを感じやすく、日常生活の中で集中力や計画性に課題を持つことがあります。
また中には、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の両方の特性を持っている方もいらっしゃいます。
そのため、自分がどちらに当てはまるかを一概に判断するのではなく、自分にはどんな特性があるのかを理解することが大切です。
うつ病などの二次障害からASD(自閉スペクトラム症)と気づくこともある

ASD(自閉スペクトラム症)のある方は、日常生活や人間関係の中でつまずきを感じやすい傾向があります。
そうした困りごとが積み重なることで、うつ病や不安障害などの「二次障害」を引き起こすことも珍しくありません。
例えば、職場でうまくコミュニケーションが取れなかったり、周囲の期待に応えるのが難しかったりすると、少しずつ自己評価が下がり、少しずつ心が疲れていってしまうことがあります。
その結果、精神科や心療内科を受診した際にうつ病などの診断とともにASD(自閉スペクトラム症)の可能性を指摘されるケースもあります。
大人のASD(自閉スペクトラム症)と仕事の向き合い方
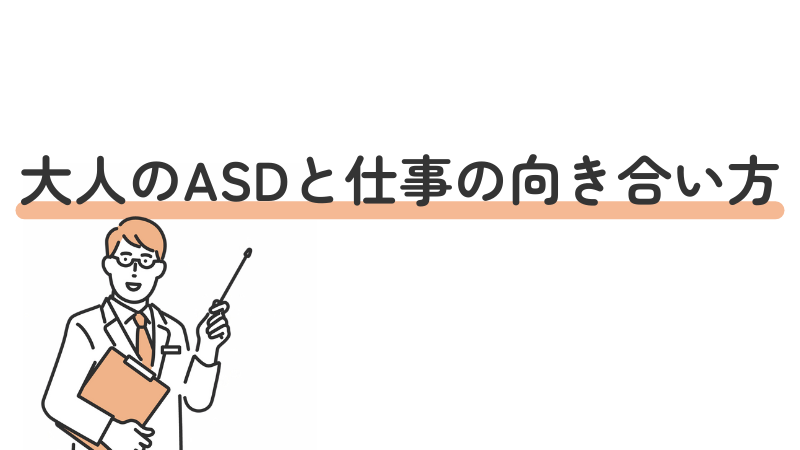
ASD(自閉スペクトラム症)のある方が、自分らしく働くためには、まず自分の特性を理解し、それに合った環境や工夫を見つけていくことが大切です。
苦手なことやストレスを感じやすい場面に気づくだけでも、仕事選びや働き方のヒントになります。
さらに、障害者雇用制度を活用することで、特性に応じた配慮を受けながら働ける環境を選ぶこともできます。
「どんな働き方が向いているのか」「どんなサポートがあれば安心できるのか」を考えることは、無理をせず、自分らしく働くための第一歩です。
大人のASD(自閉スペクトラム症)の方が利用できる相談先
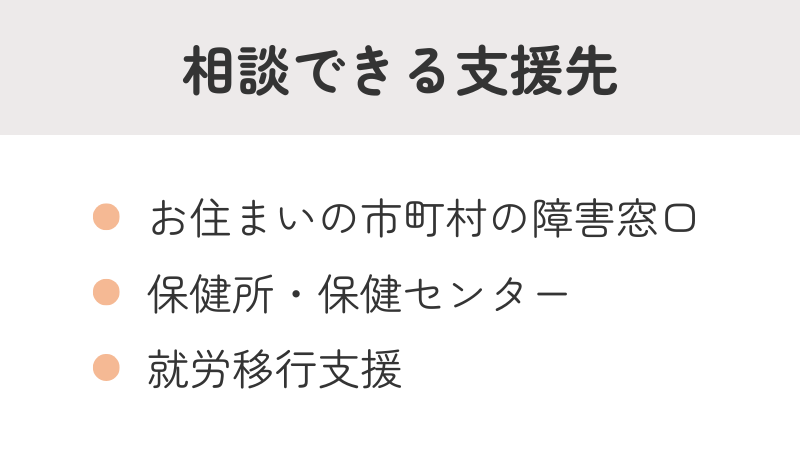
ASD(自閉スペクトラム症)の方が、相談できる場所はいくつかあります。ここでは代表的な相談先をご紹介します。
お住まいの市町村の障害窓口

市区町村にある障害福祉の窓口は、ASD(自閉スペクトラム症)のある方やそのご家族が無料で利用できる、身近な相談先のひとつです。
日常生活での困りごとや不安について話すことができ、必要な支援につながる情報を得ることができます。
相談できる内容の例
- ASDに関する基本的な説明
- 診断や療育に対応している医療機関の紹介
- 利用できる福祉サービスの案内
- 障害者手帳の申請について
- 支援制度や申請手続きに関する相談
どんな支援が受けられるのか分からないときも、まずは相談してみることで次の一歩につながります。
保健所・保健センター

保健所や保健センターでも、ASD(自閉スペクトラム症)に関する相談ができます。
場所によっては、臨床心理士や公認心理師、精神保健福祉士、社会福祉士など、心のケアや福祉に関する専門資格を持った職員が在籍していることがあります。
困りごとを一緒に整理しながら、状況に応じた支援先につないでくれるのが特徴です。
診断を受けた方はもちろん、これから診断を検討している方や、そのご家族も対象です。医療機関の紹介、心のサポート、地域の福祉サービスとの連携など、さまざまな面で相談ができます。
仕事や生活面の不安を相談できる就労移行支援も

ASD(自閉スペクトラム症)のある方の中には、仕事や日常生活に不安を感じている方も少なくありません。
そんな時には、就労移行支援を利用するという選択肢もあります。
就労移行支援では、働くための準備や生活のサポートを受けながら、自分に合った働き方を見つけることができます。
職業選びの相談やビジネスマナー、働くためのスキルを身につけるための訓練も用意されています。
さらに、生活リズムの整え方やストレスとの付き合い方、余暇の過ごし方など、日常生活全体についての相談も可能です。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manabyでは、ASD(自閉スペクトラム症)をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方がmanabyで訓練を受けながら、自分らしい働き方を見つけています。
気分の波や体調の変化に不安を感じている方でも、1人ひとりの状態やペースに合わせた「個別支援」を大切にしており、「どんな働き方が自分に合っているか」を一緒に考えていくことを重視しています。
例えば、以下のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることができます。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「急な予定変更が苦手」「曖昧な指示だと理解できない」など、1人ひとりの特性に寄り添いながら支援を行っています。
まずは相談だけでも大丈夫ですので、不安なことがあるときは気軽にお問い合わせください。
大人のASD(自閉スペクトラム症)かもしれないと思ったら、まずは自分の困りごとを言語化しよう
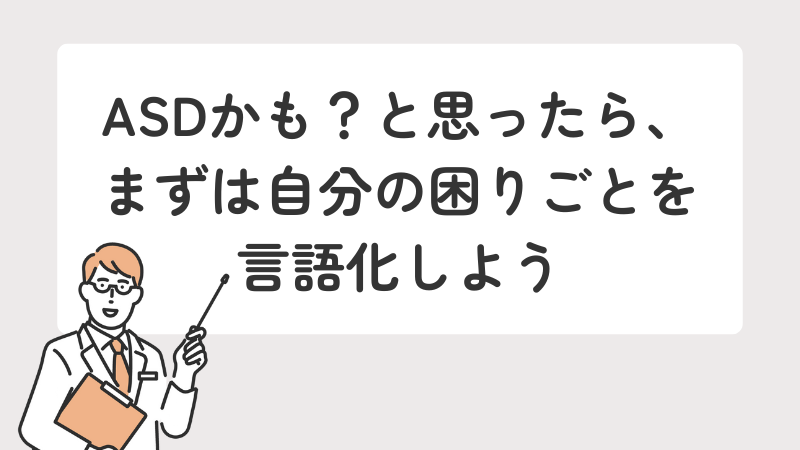
ASD(自閉スペクトラム症)かもしれないと感じたときは、まず「自分がどんなことで困っているのか」を言葉にしてみることが大切です。
困りごとを見つける方法
- どんな場面でつまずくことが多いか思い出す
- 何にストレスを感じやすいか振り返る
- こだわりが生活にどう影響しているかを整理する
- 日記やメモを使って困った場面を書き留める
- ネット上のセルフチェックを活用する
- 身近な人と情報を共有する
「なんとなく困っている」と感じているだけでは、まわりに理解されにくいこともあります。
具体的な困りごとを言葉にすることで、相談しやすくなったり、自分に合う支援を見つけやすくなったりします。
少しずつ、自分のペースで特性を理解していくことが大切です。
その積み重ねが、自分らしい過ごし方を見つける第一歩になっていきます。
必要に応じて専門機関に相談することも視野に入れつつ、無理せず取り組んでいきましょう!








