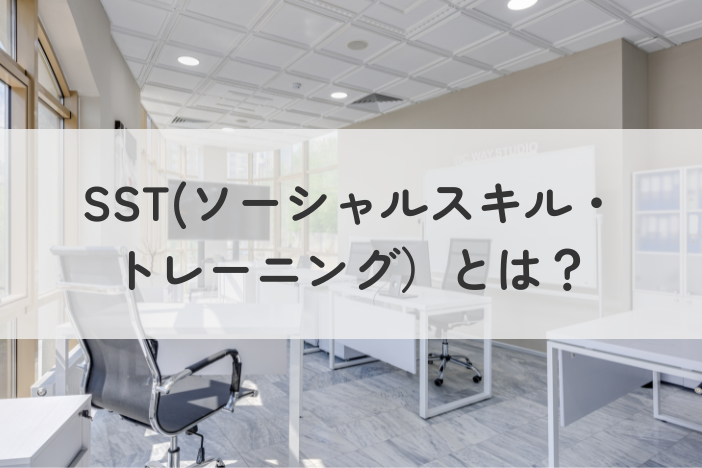大人の知的障害とは?特徴や困りごと、支援制度まで分かりやすく解説
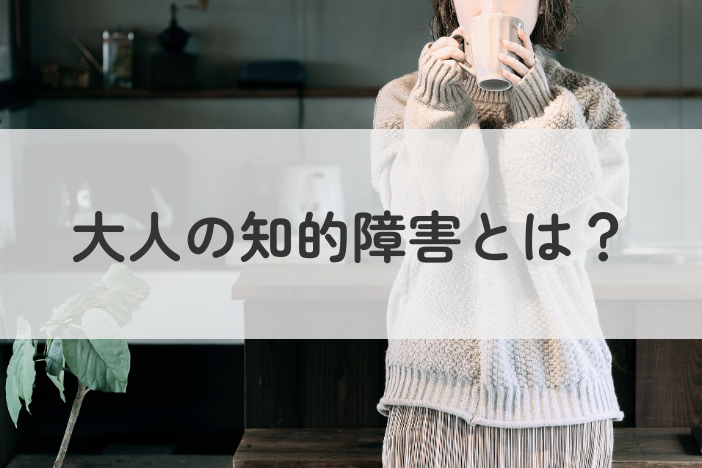
- 大人の知的障害とは?
- 大人の知的障害程度別の特徴
- 軽度
- 中度
- 重度
- 最重度
- 知的障害の原因
- 軽度知的障害と境界知能(グレーゾーン)の違いとは?
- 大人になってから知的障害と診断されることはある?
- うつ病や適応障害で受診したときに、実は知的障害があるとわかることも
- 知的障害と仕事の向き合い方
- 上司に相談して業務の見直しをお願いする
- 障害者雇用という選択肢も
- 知的障害の方が利用できる支援制度
- 自立支援医療制度(精神通院医療)
- 障害者手帳(療育手帳)
- 障害年金
- 知的障害の方が相談できる支援先
- 住んでいる市区町村の障害福祉課相談
- 保健所・保健センター
- 就職や仕事の悩みは就労移行支援でも相談できます
- manabyの就労移行支援について
- 大人の知的障害とは?特徴・困りごとの整理
同じミスを繰り返して怒られる、指示をちゃんと聞いたつもりなのに、うまく理解できず、また失敗してしまう。
そんな経験から、「なんでこんな簡単なこともできないんだろう」「努力が足りないのかな」と、自分を責め続けていませんか?
実は、子どもの頃から「勉強についていけない」「人と同じように行動するのが難しい」と感じていた方が、社会に出てから心が限界を迎え、通院をきっかけに大人になってから知的障害と気づくケースもあります。
この記事では、大人の知的障害について、その特徴や日常生活での困りごと、そして利用できる支援制度まで解説します。
この記事のまとめ
-
●
大人の知的障害とは?
知的障害は、知的機能や生活能力に困難がある状態です。発達期(18歳ごろまで)に現れますが、大人になってから仕事や人間関係でつまずき、初めて気づくことも少なくありません。 -
●
知的障害かも?と思ったら
「できない自分」を責めず、自分に合ったサポートや働き方を見つけることが大切です。
大人の知的障害とは?
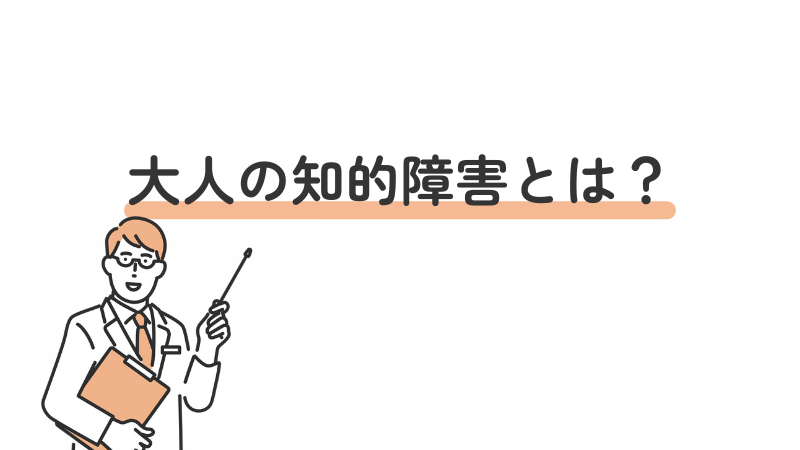
知的障害というと子どものころに診断されるイメージがあるかもしれませんが、大人になってから気づかれることもあります。
知的障害にはさまざまな定義がありますが、ここでは厚生労働省の基準をもとに紹介します。
厚生労働省では、知的障害を「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が出ており、なんらかの特別な支援が必要な状態」と定めています。
つまり、知的障害かどうかを判断するときには、
- 知的な能力にどのくらい困りごとがあるか(知的機能)
- 毎日の生活をどれくらい自分でこなせるか(生活能力)
この2つの視点で見ていきます。どちらも基準に当てはまる場合に「知的障害」と診断されることになります。
(参考:厚生労働省「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」)
知的機能とは、学習の理解度や考える力、判断力、問題を解決する力などのことです。
主にWISC(ウィスク)と呼ばれる知能検査を行い、IQ(知能指数)という数値で見ることが多くなっています。
生活能力のほうは、身の回りのことがどれくらいできるか、自分の気持ちを伝えられるか、道を覚えて移動できるか、仕事をこなせるかといった、日常生活に必要な力を見ていきます。
生活能力はVineland-II(ヴァインランド・ツー)という検査を用いて測定することが増えてきています。
最近では、「できないこと」だけを見るのではなく、「どんなサポートがあれば、その人らしく生活できるのか」といった視点で知的障害をとらえる考え方も広がっています。
周囲の理解やサポートによって、生きやすさがぐっと変わってくることもあります。
大人の知的障害程度別の特徴
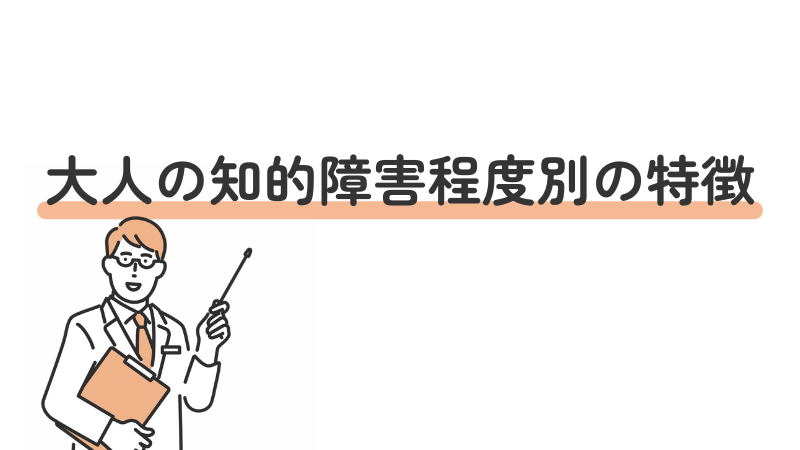
大人の知的障害がある方は、見た目だけではわかりにくいこともありますが、日常生活や仕事の中でさまざまな困りごとを抱えていることがあります。
ここでは、知的障害のある大人の方について、程度ごとの特徴をご紹介します。
軽度

軽度の知的障害がある方は、適切なサポートがあれば小学校レベルから中学校レベルくらいの学習を身につけることができます。
生活面では、金銭管理や食事、買い物などに少しの助けがあれば、一人で暮らすことも可能です。
読み書きや簡単な計算ができることが多く、ルールが決まっている仕事には向いています。
ただし、臨機応変に動くことや、複雑な人間関係がある環境では戸惑うことがあります。
また、ストレスを感じやすかったり、気持ちのコントロールが難しかったりする場面もあるため、心のサポートも大切です。
中度

中度の知的障害がある方は、身の回りのことを自分でできる場合もありますが、こまめな声かけや支援があるとスムーズに過ごせます。
簡単な会話はできますが、長い話や難しい内容は理解しづらいことがあります。
仕事では、決まった手順をくり返す作業など、内容がわかりやすい仕事であれば活躍できる可能性があります。
一人暮らしは難しい場合もありますが、グループホームなどの支援がある環境なら、自分のペースで生活していける方もいらっしゃいます。
人との関わりの中で困ることがあっても、周囲がやさしく関わり、わかりやすく伝えていくことで、安心して生活することができます。
重度

重度の知的障害がある方は、食事や着替え、入浴など、身の回りのことについて毎日のサポートが必要です。
ことばでのやりとりが難しく、気持ちを伝えるのに工夫が必要な場合もあります。
また、安全面の見守りが欠かせないことから、介助や介護の体制が整った場所で暮らしている方が多いです。
施設やグループホームでは、専門のスタッフが生活のサポートをしており、安心して過ごせる環境が整えられています。
最重度

最重度の知的障害がある方は、日常のすべての場面で介助や介護が必要です。
ことばでのコミュニケーションはとても難しく、表情や動きなどから気持ちを読み取るサポートが求められます。
また、体を動かすことや感覚の受け取り方にも制限があることが多く、リハビリや医療的なケアも含めた支援が必要になることもあります。
知的障害がある方が社会で生活していく中では、まわりの環境や働き方によってつまずきやすさが大きく変わります。
本人の努力だけでは乗り越えにくい場面もあるため、困りごとに気づいたときに適切なサポートや配慮が受けられるかどうかが、とても大切です。
その人に合った工夫や声かけがあることで、不安を減らし、安心して過ごせる場面が少しずつ増えていきます。
知的障害の原因
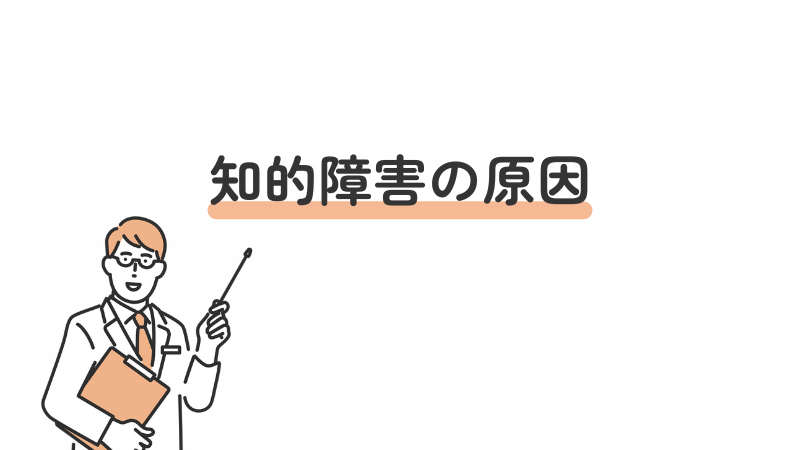
知的障害が起こる原因は、赤ちゃんが生まれる前・生まれるとき・生まれた後の3つの時期に分けて考えられます。
- 出生前の原因
赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいる間に、遺伝の問題や染色体の変化、風疹などの病気にかかることがあります。
また、お母さんが過剰な喫煙、過度なアルコールの摂取をすると、赤ちゃんに影響が出ることもあるのです。 - 周産期の原因
赤ちゃんが生まれるときに、早く生まれすぎたり、分娩の力で体に傷がついたりする場合があります。
そのほか、妊娠中の病気や出産時のトラブルも知的障害の原因になることがあるのです。 - 出生後の原因
赤ちゃんや子どものころに、十分な栄養が取れなかったり、心や体の成長に必要な関わりが少なかったりすると、発達に影響が出ることがあります。
さらに、脳の病気や感染症、けがなども原因に含まれます。
知的障害は原因がはっきりしないことも多く、複数の原因が重なっているケースも珍しくありません。
また、知的障害のもとになる変化が遺伝するかどうかは、まだはっきりとわかっていないのです。
軽度知的障害と境界知能(グレーゾーン)の違いとは?

軽度知的障害と境界知能(グレーゾーン)は、知能指数(IQ)の数値によって区別されます。
境界知能(グレーゾーン)はIQ70〜84にあたるとされ、軽度知的障害はIQ51〜70に該当します。
つまり、知的障害の中でも比較的IQが高いのが軽度知的障害で、その軽度知的障害よりもさらにIQが高いのが境界知能(グレーゾーン)という位置づけになります。
IQの平均は「100」とされており、どちらも平均より低めですが、社会の中で生活するうえで困りごとを感じやすいという共通点があります。
IQが70未満で、かつ日常生活に支障があると判断された場合は、「軽度知的障害」として療育手帳を取得し、福祉サービスに繋がる可能性があります。
一方で、境界知能(グレーゾーン)の方は診断や支援の対象になりにくいことも多く、困っていても制度に繋がりづらい現状があります。
ただし、自治体によっては支援の対象となることや、発達障害として相談できる場合もあります。
「軽度知的障害ではないから支援を受けられない」とあきらめず、困りごとがある場合は、早めに専門機関に相談することが大切です。
大人になってから知的障害と診断されることはある?
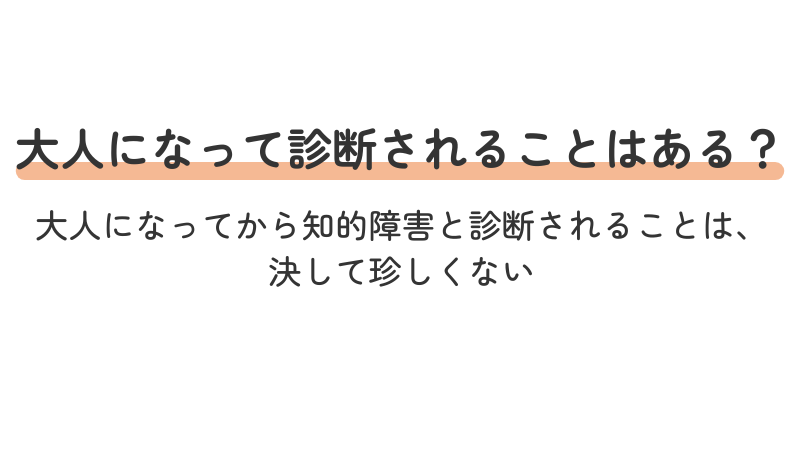
大人になってから知的障害と診断されることは、決して珍しくありません。
知的障害は本来、発達期(おおよそ18歳未満)に見つかることが多いですが、軽度の場合は幼少期や学齢期に気づかれにくく、そのまま大人になることがあります。
社会に出てから仕事で指示が理解しにくい、人とのやりとりが難しい、同じミスを何度も繰り返してしまうといった困りごとに直面し、初めて医療機関を受診したことで、はじめて知的障害と診断されるケースは珍しくありません。
うつ病や適応障害で受診したときに、実は知的障害があるとわかることも

うつ病や適応障害などの病気で病院に行ったことがきっかけで、知的障害があるかもしれないとわかることがあります。
もともとの困りごとに気づかず無理を重ねた結果、心身のバランスが崩れてしまうことも少なくありません。
診断が遅れると、本人の抱える困難さに周囲が気づけず、適切な支援を受けられないままになってしまうことがあります。
そのため、大人になっても「なぜか生きづらさを感じる」「できないことが多くてつらい」と思う場合は、専門機関や医療機関に相談することが大切です。
知的障害と仕事の向き合い方
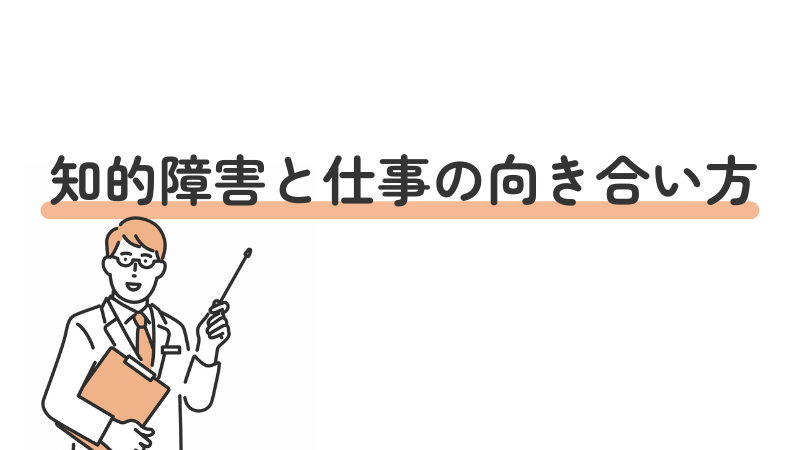
知的障害と診断されたり、その可能性を感じたりしたとき、「今の仕事を続けられるのかな」「自分に合った働き方はあるのかな」と不安に思う方も少なくありません。
これまで無理を重ねてきた方ほど、業務内容を調整したり、障害者雇用などの働き方を見直すことで、自分らしい働き方を見つけることができます。
ここでは、知的障害のある方が、無理なく働くためにできる工夫や選択肢についてご紹介します。
上司に相談して業務の見直しをお願いする

知的障害と向き合いながら働くには、まずは上司に相談し、自分に合った業務内容や働き方を一緒に考えていくことが大切です。
知的障害がある方が職場で直面しやすい課題には、指示の理解に時間がかかることや、同じミスを繰り返してしまうこと、仕事の要点がつかみにくくて周りと話しづらくなることなどが挙げられます。
こうした困りごとをひとりで抱え込まず、「自分にはこういう特性がある」と伝えたうえで業務の優先順位を整理してもらったり、負担が大きすぎる場合は業務量を調整してもらうことで、仕事がしやすくなったり、職場でのやり取りがスムーズになったりすることもあります。
相談の際は、「どんな場面で、どのように困っているのか」を具体的に伝えると、相手にも状況が伝わりやすくなります。
この時、必ずしも障害名を伝える必要はありません。
「指示を一度で理解するのが難しい」「複数のことを同時に頼まれると混乱してしまう」といったように、困っている内容にしぼって話すことでも十分です。
無理のない範囲で、「こうしてもらえると助かります」といった具体的な配慮の希望を伝えることが、働きやすい環境づくりに繋がります。
障害者雇用という選択肢も

障害者雇用という働き方も、自分に合った環境で仕事を続けるうえで有力な選択肢のひとつです。
障害の特性に合わせて業務内容を調整してもらえるだけでなく、安心して働けるよう支援体制が整っている職場が多いのも特徴です。
作業が細かく分かれている職場も多く、自分の得意なことを活かしやすい環境が整っています。
例えば、同じ作業を繰り返すことが得意な方には、その力を活かせる仕事を任せてもらえることもあります。
また、職場によっては、コミュニケーションをサポートする担当者がいたり、業務の進め方について相談できる窓口が設けられていたりと、不安やストレスを抱え込みにくい工夫もされています。
知的障害の方が利用できる支援制度
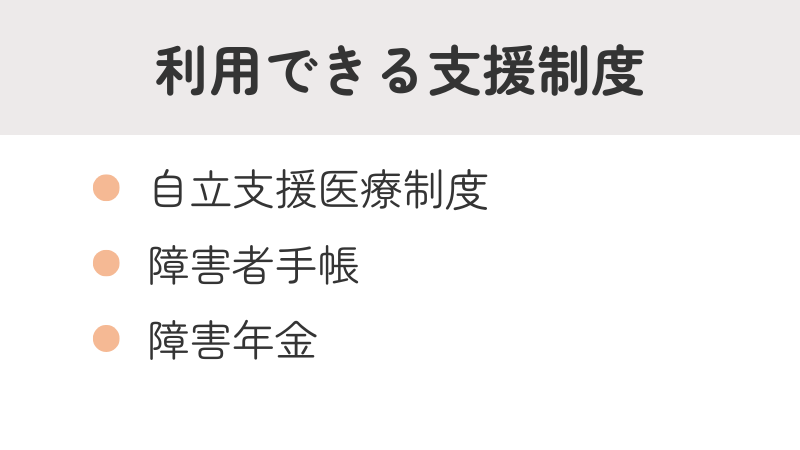
知的障害のある方が、生活や就労の中で感じる困りごとをサポートするために、利用できる支援制度がいくつかあります。
ここでは、その中から代表的な制度を3つご紹介します。
自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度は、知的障害を含む精神障害のある方が医療サービスを受けやすくするための制度です。
医療費の自己負担が基本3割から1割に軽くなる仕組みになっており、通院による精神疾患の治療などが対象となります。
知的障害がある方の中には、継続的な医療サポートが必要な方も多いため、経済的な理由で治療を受けられないことがないように配慮されています。
利用するには、お住まいの市区町村の福祉課や保健所での申請が必要です。
障害者手帳(療育手帳)

障害者手帳は、障害のある方がさまざまな支援を受けやすくするための大切な証明書です。
知的障害のある方には「療育手帳」が交付され、障害の程度によってA(重度)・B(中軽度)などの区分がされます。
療育手帳を持っていると、公共交通の割引や税の軽減、福祉サービスの利用などの支援が受けられるようになります。
申請は市区町村の福祉課や保健センターで行います。
手帳を使って受けられる支援の内容は自治体によって違うことがあるため、事前に確認しておくと安心です。
更新が必要な場合もあるので、期限も忘れずにチェックしておきましょう。
障害年金
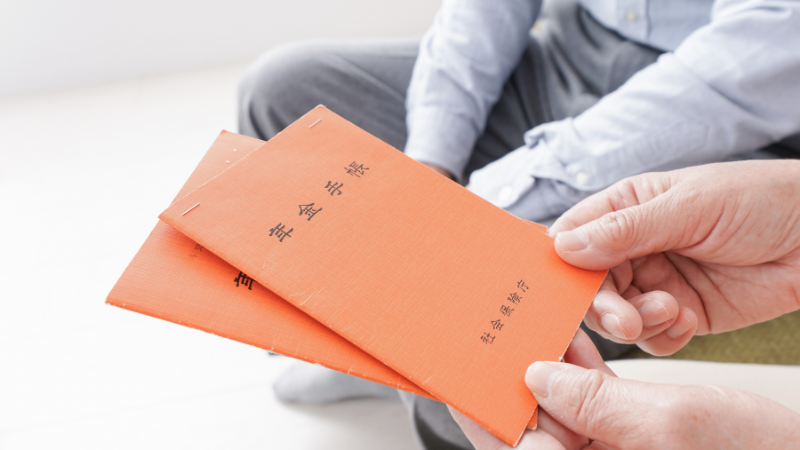
障害年金は、知的障害を含む障害のある方が安定した暮らしを続けるための経済的な支援制度です。日常生活や社会参加を支える役割もあり、とても大切な制度のひとつです。
障害年金には次の2種類があります。
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方、20歳未満(まだ年金に加入していない段階)だった方、または60歳以上65歳未満で日本に住んでいた方が対象
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金や共済年金に加入していた会社員や公務員などが対象
それぞれ障害の程度や働いていたときの収入によって支給額が決まります。
申請には、医師の診断書や所定の手続きが必要です。
提出先は日本年金機構で、手続きのタイミングや書類の不備などによって、支給までに時間がかかることもあります。
不安がある場合は、専門の相談員や社会保険労務士に相談してみるのがおすすめです。
知的障害の方が相談できる支援先
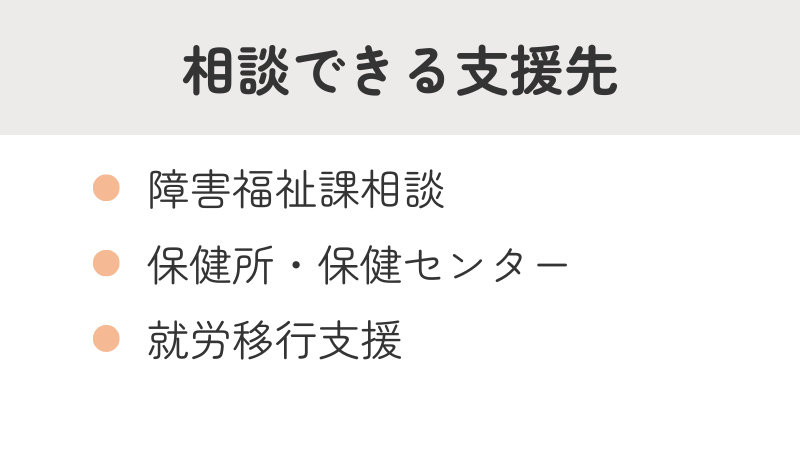
知的障害のある方が、不安や悩みを抱えたときに相談できる場所をご紹介します。
住んでいる市区町村の障害福祉課相談

住んでいる地域の障害福祉課は、知的障害のある方にとって身近な相談窓口のひとつです。
具体的には、以下のような手続きや相談に対応しています。
- 療育手帳の取得
- 自立支援医療制度の申請
- 障害年金に関する手続き
その他にも、障害者総合支援法に基づいた生活サポートの紹介や、日常生活に関する悩みごとの相談も可能です。
相談は無料で、個別の状況に応じた対応をしてくれるので、どんなことでもまずは話してみるのがおすすめです。
また、地域によっては定期的に相談会や制度の説明会が開かれていることもあり、制度について詳しく知りたい時や、似た立場の人と話してみたい時にも役立ちます。
保健所・保健センター

保健所や保健センターは、医療や健康の面から生活を支える相談窓口のひとつです。
福祉サービスや医療機関の紹介もしてもらえるため、「どの制度を使えばいいのか分からない」「どこに相談すればいいか迷っている」という困りごとに対応をしています。
また保健師や精神保健福祉士などの専門家がいるため、支援制度のことだけでなく、日々の不安や体調面のことまで幅広く相談できるのが特徴です。
必要に応じて、関係機関と連携しながら支援計画を立ててくれることもあるため、ひとりで悩まずにまずは話をしてみることが大切です。
就職や仕事の悩みは就労移行支援でも相談できます

仕事に関する相談は、就労移行支援も頼れる存在です。就職活動の準備や、職場での人間関係の不安、働くことへの自信のなさなど、就労に関する悩みに寄り添いながら支援を行っています。
履歴書の書き方や面接練習といった基本的な就職準備はもちろん、作業トレーニングやビジネスマナーの練習も行いながら、少しずつ「働く力」を身につけていくことができます。
就職後も、職場に定着できるようフォローを続けてくれるのが就労移行支援の特徴です。安心して長く働きたいと考えている方にとって、大きな支えになります。
manabyの就労移行支援について
就労移行支援manabyでは、知的障害をはじめ、精神障害や発達障害、難病のある方が自分のペースに合わせて働く力を身につけながら、「自分らしい働き方」を見つけることができます。
manabyでは1人ひとりの状態やペースに合わせた個別支援を行っているため、「どんな働き方が自分に合っているのか」を一緒に考えることができます。
例えば、以下のような支援を通じて、無理なく安心して就職の準備を進めることが可能です。
- eラーニングシステム「マナe」を活用した学習サポート
- Webデザインやプログラミングなど、ITスキルの習得
- 通所が難しい方への在宅支援や柔軟なスケジュール調整
※在宅訓練の利用可否ついてはお住いの自治体によって異なります - 就職活動のサポートや、就職後6か月間の定着支援 など
「仕事の指示がうまく理解できない」「ミスが多くて職場に居づらくなる」といった不安に対しても、1人ひとりに合わせて丁寧に対応しています。
相談だけでも大丈夫ですので、まずは気軽にお問い合わせください。不安なことがあるときは、一緒に解決の糸口を探していきましょう。
大人の知的障害とは?特徴・困りごとの整理
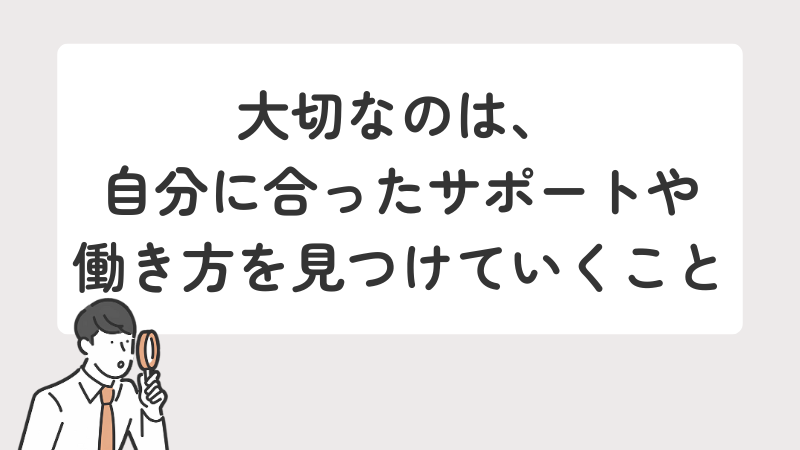
知的障害は、大人になってから診断されることもあり、その特性や困りごとは人によって違います。
情報の理解や整理が難しかったり、仕事や人との関わりの中で戸惑いやすかったりといった特徴があり、こうした困りごとは見た目には分かりにくくまわりから理解されにくいこともあります。
大切なのは、「できない自分を責める」ことではなく、自分に合ったサポートや働き方を見つけていくことです。
無理にまわりと同じペースで頑張ろうとせず、自分らしいやり方で「できること」を一つずつ積み重ねていくことが、自信や安心に繋がります。
もし不安や困りごとを抱えているなら、福祉の相談窓口や医療機関に話をしてみるのもひとつの方法です。
ひとりで抱え込まず、必要な支えを受けながら、「できること」を活かせる環境を見つけていきましょう。